unbanked株式会社(東証スタンダード:8746)は、2025年10月10日開催の取締役会において、株式交付の手法を用いて株式会社まーるを子会社化することを決議しました 。このM&Aは、unbankedが既存の金地金事業とノンバンク事業に加え、成長著しい高級腕時計を中心としたブランド品リユース市場へ本格参入するための戦略的な一手です 。本記事では、M&Aアドバイザーの視点から、この案件の核心である企業価値評価(バリュエーション)と株式交付比率の算定に焦点を当て、その妥当性と戦略的意義を専門的に解説します。
M&Aのスキームと戦略的背景
簡易株式交付による子会社化
本件は、unbankedを株式交付親会社、まーる社を株式交付子会社とする株式交付というスキームが用いられます 。具体的には、unbankedがまーる社の発行済株式100株のうち51株を取得する対価として、unbankedの新規発行株式をまーる社の株主に割り当てます 。これにより、unbankedは現金の支出を伴わずに(キャッシュアウトを抑制し)、まーる社を連結子会社としてグループに迎え入れることができます 。また、本件は株主総会の承認を必要としない簡易株式交付の手続きで行われる予定であり、機動的な経営判断がなされたことが窺えます 。
unbankedの戦略的意図:収益源の多様化
unbankedグループは、金地金事業とノンバンク事業を主軸としてきましたが、かねてより収益源の多様化と成長分野への進出を重要な経営課題として認識していました 。
近年、高級腕時計を中心とするブランド品リユース市場は、価格の透明性や国際的な流動性の高さを背景に国内外で拡大を続けており、持続的な成長が見込まれる魅力的な市場です 。この成長市場へ参入するにあたり、unbankedは最適なパートナーとしてまーる社を選定しました 。
まーる社は、委託販売を基本とするビジネスモデルにより、在庫リスクを極小化しつつ、設立からわずか数年で売上高を約80億円まで急拡大させるなど、著しい成長を遂げています 。unbankedは、まーる社が持つ以下の強みを高く評価しました。
- 専門性: 高級腕時計の真贋判定や査定に関する独自のノウハウ 。
- 顧客基盤: 富裕層を中心とした安定的な個人顧客 。
- 成長性: 都心での実績を基盤とした関西エリアへの展開や海外販路の拡大余地 。
- シナジー: unbankedグループの既存事業との早期シナジー実現可能性 。 これらの強固な事業基盤をグループに取り込むことで、新たな収益の柱を構築し、中長期的な企業価値の向上を目指すことが本M&Aの最大の目的です 。
企業価値評価(バリュエーション)の深掘り
株式交付においては、対価が現金ではなく株式であるため、両社の企業価値を公正に評価し、妥当な株式交付比率を算定することが極めて重要です。これは、既存の株主の利益を保護するために不可欠なプロセスです。
本件では、公平性・妥当性を確保するため、両社から独立した第三者算定機関である永田町リーガルアドバイザー株式会社が起用され、株式価値の算定が行われました 。
株式交付親会社 unbankedの価値算定:「市場株価法」
上場企業であるunbankedの株価算定には、市場株価法が採用されました 。これは、市場における株価が投資家の集合的な判断を反映したものであり、企業の価値を示す客観的な指標であるという考え方に基づく、最も一般的な評価手法です。
算定にあたっては、取締役会決議日の前営業日である2025年10月9日を基準日とし、基準日の終値のほか、直近1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の各期間における終値の単純平均値が用いられています 。これにより、短期的な株価の乱高下による影響を排し、より安定した企業価値を捉えようとする意図が見られます。
- 算定結果: 1株あたり 384円 〜 528円
株式交付子会社 まーるの価値算定:各評価手法からの考察
非上場企業であるまーる社の価値算定は、市場株価が存在しないため、より多角的なアプローチが求められます。本件で実際に採用されたDCF法を中心に、M&A実務で用いられる他の評価手法も交えながら、その妥当性を検証します。
評価手法① DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法
本件の算定で採用されたのがDCF法です 。これは、企業が将来生み出すと予測されるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率(資本コスト)で現在価値に割り引いて企業価値を算出する手法です。企業の将来性や収益力を直接的に評価に反映できるため、まーる社のような急成長中の企業の評価に適しています。算定の基礎となったのは、まーる社が策定した事業計画です 。
- 成長予測: 2026年5月期には営業利益約3.3億円を見込み、その後2030年5月期まで年率10%程度の成長を想定 。
- 長期的な前提: 長期的には国内市場の成熟を鑑み、成長率は段階的に低下し、最終的には名目GDP成長率程度に収斂するとの現実的な前提が置かれています 。これらの将来予測に基づき、算定機関は以下の評価レンジを算出しました。
- 採用手法: DCF法
- 算定結果: 1株あたり 20,123,719円 〜 24,595,657円
まーる社の発行済株式総数は100株であるため 、株式価値の総額(時価総額)は約20.1億円〜24.6億円と評価されたことになります。
評価手法③ 類似比較法(EBITDAマルチプル法)
もう一つの代表的な手法が類似比較法です。これは、事業内容や規模が類似する上場企業の株価が、利益や純資産の何倍で評価されているか(マルチプル)を分析し、対象会社の評価に適用する手法です。リユース業界の上場企業(例:コメ兵ホールディングス、バリュエンスホールディングス等)のEV/EBITDAマルチプル(企業価値がEBITDAの何倍かを示す指標)が、仮に8倍〜12倍のレンジで取引されていると仮定します。
まーる社の2025年5月期の営業利益は約203百万円であり 、EBITDAを仮に210百万円と推定します。これを基に企業価値(EV)を試算すると、約16.8億円(210百万円 × 8倍)〜 約25.2億円(210百万円 × 12倍)となります。
この試算結果は、DCF法による算定結果(約20.1億円〜24.6億円)と非常に近いレンジに着地します。このことは、第三者算定機関が採用したDCF法における将来計画や割引率といったパラメータの設定が、市場参加者の視点から見ても妥当な水準であったことを裏付ける有力な根拠となります。
株式交付比率の妥当性と今後の展望
- 算定結果: まーる社株式1株に対し、unbanked株式 38,113.10株 〜 64,051.19株
- unbankedとまーる社株主との間の慎重な協議の結果、最終的に合意された株式交付比率は以下の通りです。
- 合意比率: まーる社株式1株に対し、unbanked株式 43,859.39株
この比率は、第三者算定機関が提示した算定レンジの範囲内にあり、客観的かつ公正な交渉を経て決定されたものであると判断できます。
なお、この株式交付によりunbankedの潜在的な発行済株式総数は19.74%増加(希薄化)する見込みです 。既存株主にとっては一時的な希薄化となりますが、これを上回るまーる社の事業成長とシナジー効果を実現することが、経営陣に課せられた責務となります。
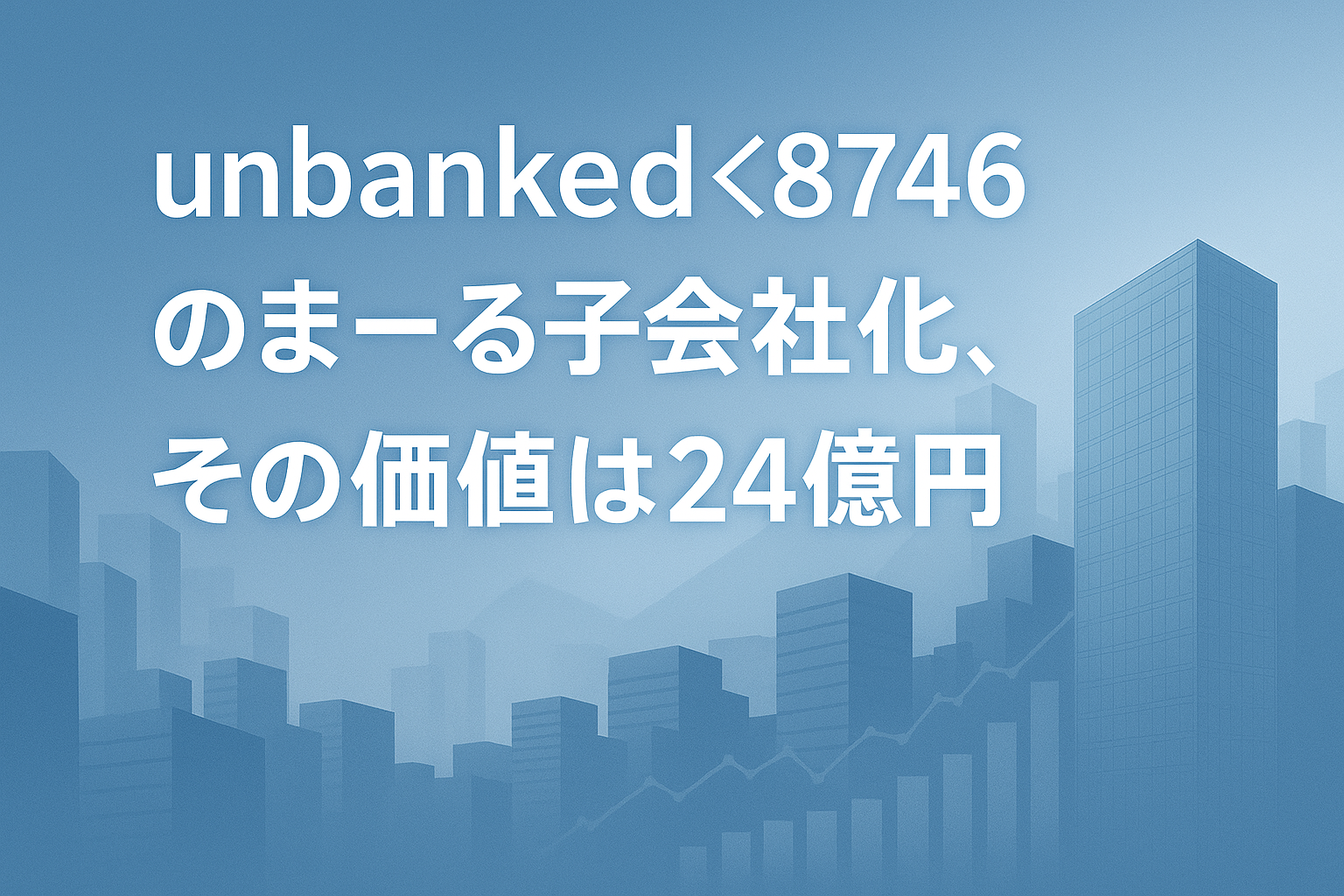



















コメント