M&A(企業の合併・買収)の世界において、企業の価値を測る作業、すなわち「企業価値評価(バリュエーション)」は、その成否を分ける最も重要なプロセスの一つです。買い手は適正な価格で買収し投資を成功させるために、売り手は自社の価値を正当に評価され、次なるステージへ進むために、客観的かつ合理的な価値の算定を求めます。
その複雑な評価実務の中で、国際的な共通言語として、また企業の「真の収益力」を測る指標として、圧倒的な存在感を放っているのが EBITDA(イービットディーエー) です。
しかし、このEBITDAは、その利便性の高さゆえに多くの誤解を生み、時として投資判断の「陥穽(かんせい)=ワナ」ともなり得ます。
本記事では、EBITDAとは一体何なのか、なぜM&A実務でこれほどまでに重用されるのか、その計算方法から、企業価値評価における具体的な活用法(EV/EBITDA倍率)、そしてEBITDAだけを見ていては見落としてしまう重大なリスクまで、そのすべてを法務・会計・税務の観点を踏まえ、論理的かつ網羅的に解説いたします。
1. EBITDAとは何か? – M&Aにおける「物差し」の正体
まず、EBITDAの定義とその本質から解き明かしていきましょう。
1-1. EBITDAの定義と示すもの
EBITDAとは、Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization の頭文字を取った略語です。
日本語では一般的に「利払前・税引前・減価償却前利益」と訳されます。
その名の通り、企業の利益から以下の項目を**差し引く前(あるいは足し戻した)状態の利益水準を示します。
- I (Interest): 支払利息(および受取利息)
- T (Taxes): 法人税等
- D (Depreciation): 有形固定資産の減価償却費(例:建物、機械装置)
- A (Amortization): 無形固定資産の償却費(例:のれん、ソフトウェア、特許権)
なぜ、わざわざこれらの項目を利益から除外(あるいは足し戻す)のでしょうか。それは、EBITDAが「企業が本業の事業活動から生み出す、キャッシュベースに近い収益力」を測ることを目的としているからです。
特に「D(減価償却費)」と「A(償却費)」は、会計上は費用として計上されますが、実際の現金の支出を伴わない費用(非現金支出費用)です。これらを利益に足し戻すことで、より「手元に残るキャッシュ」に近い概念の利益を算出できる、という考え方が根底にあります。
1-2. EBITDAの計算式:実務と理論
EBITDAには、実は世界共通で「これ」と定められた厳格な会計基準上の計算式が存在するわけではありません。しかし、M&Aの実務上、最も一般的に用いられる計算式は以下のものです。
【実務上の最頻出計算式】
EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却費(及びその他の無形固定資産償却費)
日本の会計基準における「営業利益」は、すでに利息(営業外費用)や税金(法人税等)が引かれる前の利益であるため、ここに非現金支出費用である減価償却費(D)と無形固定資産償却費(A)を足し戻すだけで、簡便的にEBITDAを算出できます。
※実務上、無形固定資産償却費が重要でない場合は、さらに簡便的に 営業利益 + 減価償却費 だけで計算するケースも散見されます。
一方で、より原則的な計算方法として、当期純利益(あるいは税引前当期純利益)から遡って計算する方法もあります。
【原則的な計算式(一例)】
EBITDA = 税引前当期純利益 + 支払利息 + 減価償却費 + 無形固定資産償却費
(※この場合、支払利息だけでなく受取利息も考慮し「純支払利息」を用いる方がより厳密です)
どちらの計算式を用いるかは、評価の目的や比較対象企業との前提を揃えるために、専門家が状況に応じて判断します。
1-3. 混同しやすい類似指標との違い
EBITDAの理解を深めるため、よく似た指標との違いを明確にしておきましょう。
- EBIT (イービット)
Earnings Before Interest and Taxesの略で、「利払前・税引前利益」を指します。- 計算式は
営業利益とほぼ同義か、税引前当期純利益 + 純支払利息で計算されます。 - EBITDAとの最大の違いは、減価償却費を足し戻さない(=費用として考慮する)点です。
- EBITDAが「投資(減価償却)の影響を除いた」収益力を見るのに対し、EBITは「投資の影響を反映した」事業利益を見る指標と言えます。
- 営業キャッシュ・フロー (Operating Cash Flow: OCF)
- キャッシュ・フロー計算書に記載される数値で、「企業が本業で稼いだ実際の現金の増減」を示します。
- EBITDAとの違いは、EBITDAが考慮しない「(売掛金・買掛金・在庫などの)運転資本の増減」や「法人税等の実際の支払額」をOCFは考慮する点です。
- EBITDAはあくまで「利益」の概念であり、キャッシュ・フロー計算書上の「キャッシュ・フロー」そのものではない、という点が重要です。
- フリー・キャッシュ・フロー (Free Cash Flow: FCF)
- 企業が事業活動から生み出したキャッシュ(OCF)から、事業維持・成長に必要な設備投資(CAPEX)を差し引いた、「企業が自由に(株主や債権者に)分配できるキャッシュ」を指します。
- EBITDAはFCFの「大元の源泉」の近似値とはなりますが、EBITDAから税金、運転資本増減、設備投資を差し引かないとFCFにはなりません。
2. なぜEBITDAはM&A実務で重宝されるのか (メリット)
EBITDAがM&Aや企業価値評価の現場で「共通言語」として多用される最大の理由は、それが「比較可能性の高さ」という極めて強力なメリットを持つからです。M&Aでは、異なる背景を持つ複数の企業を、同じ土俵で比較検討する必要があります。EBITDAは、その比較を妨げる「ノイズ」を排除する機能を持っています。
メリット①:減価償却という「会計方針」の影響を排除できる
企業の営業利益は、減価償却費の計上方法によって大きく変動します。
- 設備投資のタイミング: 例えば、大規模な設備投資を行った直後の企業は減価償却費が大きくなり、営業利益は見かけ上、圧迫されます。逆に投資が一巡した企業は減価償却費が減り、営業利益が大きく見えがちです。
- 会計処理の違い: 減価償却の方法として、毎年一定額を償却する「定額法」を採用するか、初期に多く償却する「定率法」を採用するか。あるいは、資産の耐用年数を何年に設定するか。これらは経営者の会計方針によって選択可能であり、企業間で異なります。
A社(積極投資・定率法)とB社(投資抑制・定額法)があった場合、営業利益だけを比較しても、どちらが本源的に儲ける力があるのか正しく判断できません。EBITDAは、この減価償却費を足し戻すことで、こうした会計方針や投資サイクルの違いに左右されない、事業本来の収益力を比較可能にします。
メリット②:財務構成(金利負担)という「資本政策」の影響を排除できる
企業が事業を行うための資金をどう調達しているか(資本政策)も、企業ごとに異なります。
- C社: ほとんど借入をせず、自己資本中心で堅実に経営している(支払利息は少ない)
- D社: 積極的に銀行借入や社債発行を行い、レバレッジを効かせて事業を拡大している(支払利息は多い)
この2社の経常利益(営業利益から支払利息等を引いたもの)を比較しても、事業そのものの優劣は判断できません。EBITDAは、利息(Interest)を考慮しないことで、「どのように資金を調達したか」という財務活動の影響を排除し、「事業そのものがどれだけ稼いでいるか」という点にフォーカスして比較することを可能にします。
メリット③:税率という「国・地域」の影響を排除できる
M&Aが国境を越える「クロスボーダーM&A」の場合、このメリットは絶大な効果を発揮します。
- 日本企業: 法人税率 約30%
- シンガポール企業: 法人税率 約17%
- タックスヘイブン所在企業: 法人税率 0%
当然ながら、税引後の当期純利益を比較しても、まったく意味がありません。EBITDAは、税金(Taxes)の影響を排除することで、異なる税制下にある企業同士の収益性をフラットに比較することを可能にします。
[Image illustrating comparison between companies using EBITDA]
3. EBITDAの死角と投資上のワナ (デメリット・留意点)
EBITDAはその利便性から「万能の指標」と誤解されがちですが、M&Aのプロフェッショナルは、その「死角」を常に強く意識しています。メリットの裏返しが、そのまま重大なデメリット(投資のワナ)となるのです。
ワナ①:設備投資(CAPEX)の負担を完全に無視する
EBITDA最大のメリットである「減価償却費の排除」は、同時に最大のデメリットを生み出します。
- EBITDAは、事業を維持・成長させるために**将来必要となる「再投資(設備投資=CAPEX)」のコストを一切反映しません。
- 特に、製造業、建設業、運輸業、インフラ産業といった、常に巨額の設備投資が必要となる資本集約型(Capital Intensive)のビジネスにおいて、EBITDAだけを見ることは極めて危険です。
- 「EBITDAは潤沢に黒字だが、毎年の設備投資を差し引くと、手元のキャッシュ(FCF)は真っ赤」という企業は現実に存在します。このような企業を高値で買収した場合、買収後も継続的な追加投資(資金流出)に苦しむことになります。
ワナ②:運転資本(Working Capital)の増減を無視する
EBITDAは利益ベースの指標であり、実際の「現金の動き」を正確に反映するわけではありません。
- 運転資本とは、事業を回していく上で必要な短期的な資金(具体的には
売掛金 + 在庫 - 買掛金)を指します。 - 例えば、売上が急拡大している企業では、EBITDAも大きく伸びているように見えます。しかし、その実態が「売掛金の回収が滞っている」あるいは「過剰な在庫を抱えている」場合、EBITDAは良くても、会社には現金が残っていません(いわゆる黒字倒産のリスク)。
- EBITDAだけを見て「キャッシュリッチな会社だ」と判断するのは早計であり、必ず運転資本の状況(B/S=貸借対照表の分析)と合わせて確認する必要があります。
ワナ③:金利・税金の「実際の支払い」を無視する
EBITDAは「支払う前」の利益概念です。しかし、企業が存続するためには、当然ながら利息(Interest)も税金(Taxes)も実際に支払わなければなりません。
- 特に、多額の借入金を抱える高レバレッジの企業の場合、EBITDAが大きくても、そこから多額の金利が差し引かれ、最終的に株主に残る利益はごくわずか、というケースがあります。
- EBITDAは「事業の稼ぐ力」を示しますが、「(買収後に)株主が享受できるリターン」を直接示すものではない点に、細心の注意が必要です。
ワナ④:最も重要な「正常収益力」のワナ(正常化調整)
M&A実務において、決算書(P/L=損益計算書)に記載された営業利益から単純計算したEBITDAを、そのまま評価に用いることは絶対にありません。 なぜなら、その数値は企業の「真の収益力=正常収益力」を表していない可能性が非常に高いからです。
M&Aアドバイザーは、EBITDAを算出する前段階として、必ず「正常化調整(Normalization)」という厳密な分析作業を行います。
- ① 非経常的な損益の除外:
- その期にたまたま発生した一時的な損益(例:固定資産の売却益、役員の高額な退職金、災害損失、訴訟関連費用など)は、将来の継続的な収益力とは関係ないため、加算または減算して排除します。
- ② オーナー固有の費用の調整(中小企業M&Aで特に重要):
- オーナー経営者が、個人の裁量で支出している費用を精査します。
- 例:実態に見合わない過大な役員報酬(あるいは逆に過小な役員報酬)、プライベートと混同した交際費や車両費、節税目的で加入している生命保険料(簿外の解約返戻金にも注意)など。
- これらを「買い手が引き継いだ場合(=第三者の経営になった場合)に、合理的に発生するであろう水準」に修正します。
M&Aで用いるEBITDAとは、この「正常化後EBITDA」を指します。この作業を怠ると、企業の価値を著しく過大(あるいは過小)に評価してしまう致命的なミスにつながります。
4. M&A価格算定の核心「EV/EBITDA倍率」を使いこなす
EBITDAは、それ単体で使われるよりも、むしろ「EV/EBITDA倍率(マルチプル)」という形で企業価値評価(バリュエーション)に用いられることが本領です。
4-1. EV/EBITDA倍率(マルチプル)とは?
読み方は「イーブイ・イービットディーエーばいりつ」または「イービットディーエー・マルチプル」などと呼ばれます。これは、企業のEV(Enterprise Value:企業価値)が、その企業のEBITDAの何年分に相当するかを示す指標です。
【EV/EBITDA倍率の簡易的な解釈】
「その企業を丸ごと買収した場合、その企業が稼ぎ出す本業のキャッシュベースの利益(EBITDA)で、およそ何年で買収費用(EV)を回収できるか」という投資回収期間の目安を示します。
一般的に、この倍率が低いほど、その企業は割安であると判断されます。
4-2. EV(企業価値)の計算方法
ここで言う「EV(企業価値)」は、M&Aの買収総額に近い概念です。一般的に以下の式で計算されます。
【EVの計算式】
EV = 株式時価総額(=株価 × 発行済株式数) + 純有利子負債
※ 純有利子負債 = 有利子負債(借入金や社債など) - 現預金
(※非上場企業の場合は「株式時価総額」の代わりに「株式価値」を用います)
なぜこの式になるのでしょうか。
企業を「丸ごと買う」とは、株主から全株式を取得する(=株式価値を支払う)と同時に、その会社が抱えている銀行などからの借金(純有利子負債)も実質的に引き継ぐ(=買い手が将来返済する責任を負う)ことを意味します。したがって、買い手にとっての実質的な買収総コストは、この2つの合計額(=EV)である、という考え方に基づいています。
4-3. 企業価値評価(バリュエーション)での使い方
M&A実務では、このEV/EBITDA倍率を用いて、評価対象企業の価値を算定する「類似会社比準法」という手法が多用されます。
これは、市場(株式市場)が類似の企業をどのように評価しているかを参考に、対象企業の価値を推し量る手法です。
【類似会社比準法のステップ】
- 評価対象企業と、事業内容、規模、成長性、リスクなどが類似する上場企業を複数社選定します。
- 選定した類似上場企業群の「EV/EBITDA倍率」をそれぞれ計算し、その平均値や中央値(ノイズを除去するため中央値が好まれる)を算出します。(例:類似企業のEV/EBITDA倍率の中央値が 8.0倍 だったと仮定)
- 評価対象企業の「正常化後EBITDA」を算出します。(例:精査の結果、3億円 だったと仮定)
- 対象企業のEBITDAに、類似企業の倍率を乗じて、対象企業のEV(企業価値)を試算します。
対象企業のEV = 3億円(正常化後EBITDA) × 8.0倍 = 24億円- 最後に、試算されたEVから、対象企業が実際に抱える純有利子負債を差し引いて、株式価値(=M&Aの売買価格の基準)を算出します。
- (例:対象企業の純有利子負債が 4億円 あった場合)
対象企業の株式価値 = 24億円(EV) - 4億円(純有利子負債) = 20億円
このように、EBITDAは企業価値を算定する上で、極めて実践的かつ重要な役割を担っています。
4-4. EV/EBITDA倍率の目安と業種差
「EV/EBITDA倍率の平均は8倍~10倍」といった解説を見かけることがありますが、この数値を鵜呑みにすることは非常に危険です。倍率は、業種や企業の成長ステージ、市場環境によって全く異なります。
- 倍率が高くなる(例:10倍超)業種:
- IT・SaaS、ソフトウェア、製薬、バイオなど。
- 理由:将来の成長期待(グロース)が非常に高く、かつ、ビジネスモデルとして多額の設備投資(CAPEX)を必要としない(=EBITDAがキャッシュ・フローに近い)ため、高い倍率が許容されます。
- 倍率が低くなる(例:4倍~7倍)業種:
- 製造業、建設業、小売業、運輸業など。
- 理由:成長が安定的(マチュア)である一方、前述の「ワナ①」で触れた通り、事業維持・更新のための設備投資(CAPEX)負担が重いため。EBITDAから多額の投資が差し引かれることを市場が織り込み、倍率は低く抑えられる傾向にあります。
中堅・中小企業M&Aにおける倍率
上場企業同士のM&Aと異なり、非上場の中堅・中小企業のM&Aにおいては、一般的に上場企業よりも低いEV/EBITDA倍率(例:4倍~7倍程度)が適用される傾向にあります。これは、上場企業と比較した場合の以下のような固有のリスクが、評価額のディスカウント(割引)要因として考慮されるためです。
- 流動性の欠如: 売りたい時にすぐに売れない(非流動性)リスク。
- 規模の小ささ: 事業基盤の脆弱性、リソースの限定性。
- オーナー依存度: 特定の経営者の手腕や人脈に依存しているリスク。
- 内部管理体制: 大企業に比べたガバナンスやコンプライアンス体制の未整備。
(※参考情報にあるような業界別平均倍率(例:全業種平均5.4倍、建設業4.4倍)は、あくまで過去の統計データであり、個別の企業の成長性や独自性、買収のシナジー効果によって、実際の取引倍率はこれを大きく上回ることも、下回ることもあります。)
5. EBITDAを改善し、企業価値(評価額)を高める方法
M&Aによる売却(イグジット)をお考えの経営者にとって、EBITDAの向上は、企業価値(=売却価格)の向上に直結します。前述の通り、株式価値 = (正常化後EBITDA × EV/EBITDA倍率) – 純有利子負債 です。
EBITDAが1,000万円改善すれば、仮に6倍の倍率が適用される場合、企業価値(EV)は6,000万円向上し、それはほぼそのまま株式価値(売却価格)の向上に跳ね返ってきます。
EBITDA(≒ 営業利益 + 減価償却費)を改善するには、実質的に「営業利益をいかに増やすか」が鍵となります。
- 売上高の向上:
- 既存顧客への深掘り、アップセル・クロスセルの徹底。
- 新規顧客の開拓、マーケティング戦略の見直し。
- 価格戦略の見直しによる客単価の向上。
- 売上原価の低減:
- 仕入先の集約や交渉によるコストダウン。
- 製造プロセスの見直し、歩留まりの改善による効率化。
- 在庫管理の徹底による廃棄ロスや評価損の削減。
- 販売管理費の削減:
- 業務プロセスのデジタル化(DX)による間接人件費の効率化。
- 広告宣伝費や交際費などの費用対効果の厳格な見直し。
- (ただし、将来の成長に必要な研究開発費やマーケティング投資まで削ると、逆効果になるため注意が必要です。)
- 「正常化」を意識した経営:
- これは特にオーナー経営者に重要な視点です。
- 平時から、会社の経費とオーナー個人の経費を明確に分離し、公私混同な支出を厳しく律すること。
- 将来のM&Aの際に「これは一時的な費用(非経常費用)だ」「これはオーナーの個人的な経費だ」と明確に説明(正常化)できるようにしておくことが、正常化後EBITDAを最大化し、評価額を高めることに直結します。
6. おわりに – EBITDAと賢く付き合うために
EBITDAは、その優れた比較可能性から、M&Aや企業価値評価、投資分析の世界において、今や欠くことのできない非常に有用かつ強力な「共通言語」です。しかし、本記事で詳述した通り、EBITDAは企業の「一つの側面」を切り取った指標に過ぎません。
EBITDAの数値だけを盲信し、その背景にあるビジネスの実態(継続的な設備投資の必要性、運転資本の効率性、財務レバレッジのリスク、そして正常化調整の妥当性)の分析を怠れば、必ず手痛い失敗を招きます。プロフェッショナルなM&Aとは、EBITDAという便利な羅針盤を使いこなしつつも、それだけに頼るのではなく、キャッシュ・フロー(FCF)の精査、貸借対照表(B/S)の健全性、事業計画の蓋然性(がいぜんせい)、そして法務・税務デューデリジェンス(専門家による詳細調査)といった、あらゆる角度からの多角的な分析を組み合わせて、初めて合理的な意思決定が可能となる世界です。
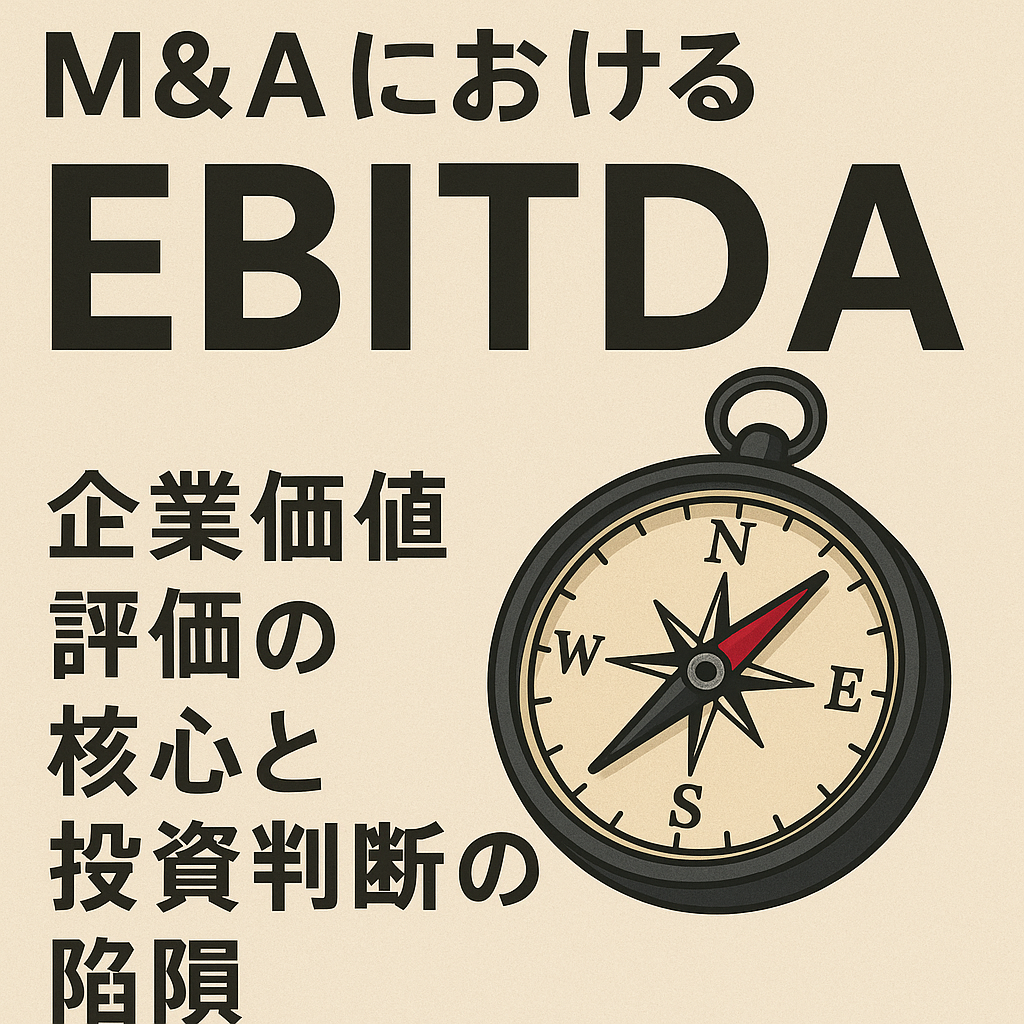



















コメント