第1章:なぜM&A仲介に「業法」が存在しないのか
M&A仲介という、極めて高額かつ専門的な知見を要する取引に、なぜ直接的な業法が存在しないのでしょうか。この問いに答えるためには、「業法」の概念と、M&A仲介に他の法律を適用することの困難性を理解する必要がございます。
1.1. 「業法」の理念と不動産仲介との比較
「業法」とは、特定の事業分野において、国民の生命、身体、財産を保護し、あるいは公共の利益を確保する目的で、事業者の参入要件や業務遂行上の行為を規律する法律の総称でございます。例えば、弁護士法、公認会計士法、そして不動産取引を規律する宅地建物取引業法(宅建業法)がその典型例です。宅建業法は、専門知識を持たない一般消費者が不測の損害を被ることのないよう、免許制度による参入規制、重要事項説明の義務化、誇大広告の禁止など、厳格なルールを定めております。
これに対し、中小企業のM&Aは、簿外債務、労務問題、許認可の承継など、不動産取引とは比較にならぬほど複雑かつ多岐にわたるリスクを内包します。にもかかわらず、これを専門に扱う仲介業には、宅建業法のような包括的な業法は存在いたしません。
この規制の空白を象徴するのが、不動産を保有する会社の「株式」を売買する場合、宅建業法の適用を受けないという事実です。これは、現行法制が「モノ(不動産)」の取引を規律の対象とする一方で、「事業体(会社)」そのものの取引を想定してこなかった歴史的経緯の表れと申せましょう。
1.2. 金融商品取引法(金商法)適用の限界
次に、非公開会社の株式も金商法上の「有価証券」に該当することから、その仲介行為が金商法の規制対象となるか、という論点がございます。この議論は長きにわたり専門家の間で交わされてまいりましたが、結論として、中小企業のM&A仲介に金商法を直接適用することは困難である、という見解が実務上、定着しております。その理由は、主に以下の三点に集約されます。
- 取引の性質: 金商法が主たる保護対象とするのは、不特定多数の投資家が参加する資本市場での「投資」活動です。一方、中小企業のM&Aは、特定の当事者間で「事業そのもの」を移転させることを目的とした相対取引であり、その本質は「経営権の移転」であって、有価証券投資とは性格を異にする、と解されております。
- 規制手法の実効性: 仮に株式譲渡のみを金商法の規制対象としても、会社分割や事業譲渡といった、株式の移動を伴わないスキームを用いることで、規制を回避することが可能です。取引の一部分のみを規律しても、制度全体の実効性を担保することが難しいのです。
- 過剰な規制コスト: 金商法が定める第一種金融商品取引業者の登録要件(厳格な財務基盤、コンプライアンス体制の構築義務等)は、中小M&Aを主たる業務とする仲介会社にとって、過度に重い負担となり、かえって円滑な事業承継を阻害する可能性が懸念されました。
これらの理由から、M&A仲介は金商法の直接的な網の掛からぬ領域として、今日まで存続してきたのでございます。
第2章:現代版「中小M&Aガイドライン」の役割と実効性
業法による直接的な規制が存在しない一方で、近年のM&A市場の健全化を促しているのが、中小企業庁が主導する「中小M&Aガイドライン」と、それに連動する「M&A支援機関登録制度」でございます。
2.1. ソフトロー・アプローチが選択された背景
国が直ちに業法を制定せず、まずガイドラインという手法を選択した背景には、自由主義経済における謙抑的な姿勢と、「立法事実*の慎重な見極めがあったと推察されます。業法という強力な規制は、国民の経済活動の自由(憲法第22条第1項)に対する重大な制約となります。そのためには、規制を正当化するだけの客観的かつ明白な事実、すなわち「M&A仲介を野放しにすることによる社会的弊害」が、国民的コンセンサスとして確立している必要がございます。
M&A仲介は比較的新しい業態であり、その功罪に関する社会通念が十分に熟成していない段階で拙速な規制を導入することは、市場を不必要に萎縮させるリスクを伴います。そこで、まずは業界の自律的な取り組みを促し、その実態を注意深く見守るという、理性的かつ戦略的な政策判断がなされたものと考えられます。
2.2. 「中小M&Aガイドライン」が示す行動規範
「中小M&Aガイドライン(第2版)」は、M&A専門業者が遵守すべき行動規範を具体的に示しております。これらは法律ではございませんが、健全な実務の標準(デファクトスタンダード)として極めて重要な意味を持ちます。特に以下の項目は、仲介業者の根源的な責務として強調されています。
- 誠実義務と利益相反の管理: 依頼者の利益を最優先する義務を明確にし、特に売手と買手の双方から報酬を得る「両手仲介」において想定される利益相反(例:取引の成立を急ぐあまり、一方に不利な条件を看過する等)の適切な開示と管理を求めています。
- 手数料体系の透明化: 成功報酬の算定基準であるレーマン方式を含め、手数料が発生するタイミングや算定根拠を事前に明瞭に説明することを義務付けています。
- 情報開示と専門的知見の活用: デューデリジェンス(買収監査)の重要性を説き、依頼者に対して潜在的なリスクを十分に説明し、必要に応じて他の専門家(弁護士、公認会計士等)の活用を促すことを求めています。
2.3. M&A支援機関登録制度という実効性担保の仕組み
ガイドラインの実効性を担保しているのが「M&A支援機関登録制度」です。この制度に登録された仲介業者は、ガイドラインの遵守を公に誓約します。そして、違反が認められた場合には、登録が取り消されるという措置が講じられます。
2024年4月に株式会社M&A DXが登録を取り消された事案は、この制度が単なる形式ではないことを業界に強く印象付けました。中小企業庁の公表によれば、同社はガイドラインが定める複数の事項において遵守状況が不十分であったと認定されております。
法的な罰則ではないものの、登録取消の事実は公にされ、企業の信用の根幹を揺るがす深刻なレピュテーション・ダメージにつながります。これは、M&A仲介業者にとって、事実上の強力な規律として機能していると評価できましょう。
第3章:2026年新資格制度がもたらす変革
こうしたソフトローによる規律の流れは、2026年からの導入が予定される新たな民間資格制度によって、次の段階へと進むことが見込まれます。
3.1. 新資格制度の目的と想定される制度設計
この資格制度の真の目的は、単に知識レベルを測ること以上に、業界全体の質の底上げと、実務家の倫理観の向上にあると考えられます。宅建士のような強力な「業務独占」(資格がなければ業務を行えない)ではなく、当面は「名称独占」(資格がなければ特定の名称を名乗れない)に近い形での運用が想定されますが、その影響は決して小さくありません。
想定される制度設計としては、以下のようなものが考えられます。
- 試験科目: 法務、財務、税務、企業価値評価(バリュエーション)、M&Aプロセス管理など、実務に不可欠な知識を網羅的に問うもの。
- 倫理規定: 利益相反の管理や守秘義務など、高い職業倫理を定めた規程の遵守。
- 継続的専門研修: 資格取得後も、法改正や最新実務に関する継続的な学習を義務付けることで、専門性の維持・向上を図るもの。
3.2. 海外事例との比較と、日本市場へのインパクト
米国の多くの州では、M&Aブローカー(Business Broker)が証券ブローカーライセンスや不動産ブローカーライセンスの取得を義務付けられるなど、公的な規制下に置かれております。日本の新資格制度は、これらとは異なり民間主導で始まりますが、将来的には公的なお墨付きを得て、その権威性を高めていく可能性もございます。この制度が定着すれば、M&Aを検討する経営者が支援機関を選ぶ際に、「有資格者が在籍しているか」という点が、信頼性を判断する重要な指標となります。結果として、資格を持たない事業者は淘汰されるか、あるいは資格取得を余儀なくされ、業界全体の水準が徐々に引き上げられていく、という緩やかでありながらも確実な変革がもたらされることでしょう。
さらに重要なのは、この制度がM&A実務に携わる「個人」のトレーサビリティ(追跡可能性)を格段に向上させる点です。問題が発生した際に、組織の責任だけでなく、担当した個人の責任も問いやすくなり、一人ひとりの実務家がより強い責任意識を持つことを促す効果が期待されます。
第4章:健全な市場発展のために M&A仲介業者がすべきこと
M&A仲介業は、法制度の過渡期にあり、いわば業界全体の自律性と倫理観が、国や社会から試されている状況にございます。現在のソフトローによる規律は、業界に対する「最後の信頼」であり、成長への機会とも捉えることができます。この期待に応え、健全な市場の発展に貢献するために、M&A仲介業者は今、以下の取り組みを真摯に実行すべきでございます。
- コンプライアンス体制の抜本的強化: 中小M&Aガイドラインを「最低基準」と位置づけ、それ以上の水準の社内規程を整備・運用すること。特に利益相反管理については、形式的な開示にとどまらず、実質的に依頼者の利益が損なわれることのないよう、厳格なプロセスを構築すべきです。
- 情報開示の徹底と透明性の確保: 提供するサービスの範囲と限界、手数料体系、想定されるリスクについて、契約締結前に、いかなる誤解も生じさせないレベルで、丁寧に説明する責務がございます。
- 人材育成への投資: 法務・財務・税務等の専門知識はもとより、何よりも高い職業倫理観を備えた人材の育成に、組織として最大限の資源を投下することが不可欠です。
そして、M&Aをご検討される経営者の皆様におかれましても、仲介業者を選定される際には、手数料の安さや耳障りの良い言葉だけでなく、その業者がいかにガイドラインの精神を理解し、誠実な情報開示とプロセスを実践しているか、という本質的な観点から、厳しい目でご判断いただくことが肝要です。
M&Aは、企業の未来、そして従業員やその家族の人生を左右する極めて重大な経営判断でございます。その神聖な場に携わる者として、我々M&Aの専門家は、自らの社会的責任の重さを深く自覚し、不断の自己研鑽に努めなければなりません。業界全体がその使命を果たした先にこそ、真に信頼される市場の未来が拓かれるものと、固く信じております。
プライマリーアドバイザリー株式会社 代表取締役 内野 哲
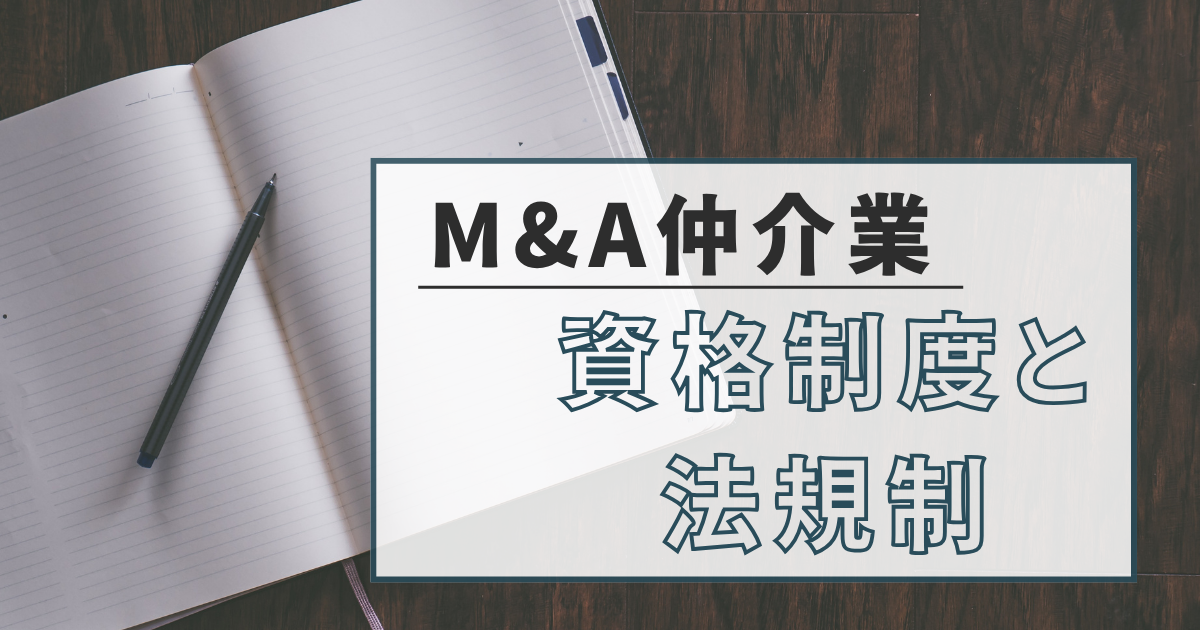




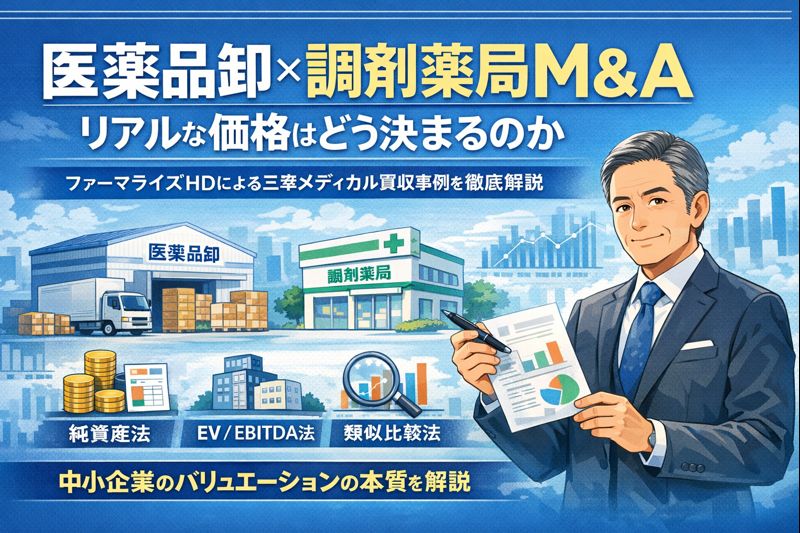


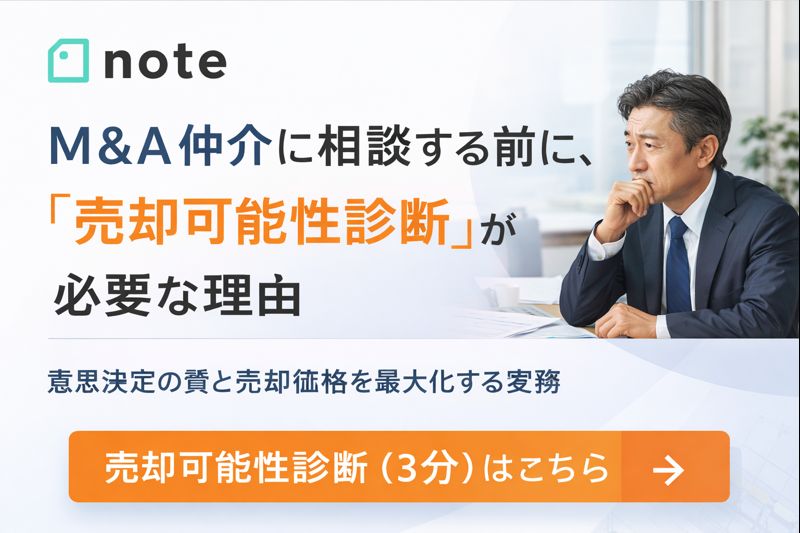


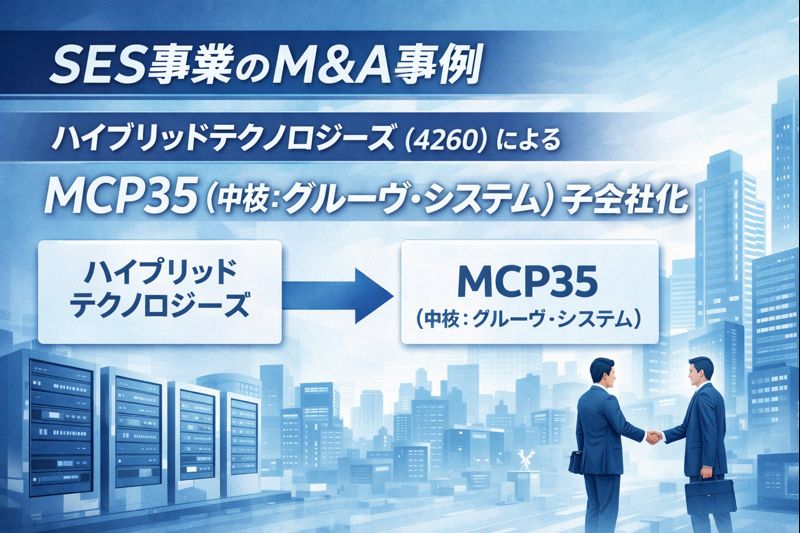






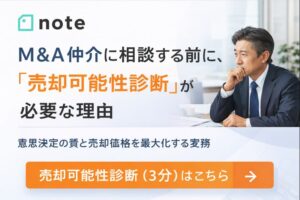

コメント