事業の出口はIPO(証券取引所に上場)だけではありません。買い手企業へ売却するM&Aイグジットは、上場に比べて早く・確率が高く・条件を設計しやすい選択肢になり得ます。本稿は、経営者が今日から準備できる実務を、専門用語の解説付きで整理します。
目次
1. 会社の価値は、要は今後どれだけ現金を生むかで決まります。
- EBITDA(イービッタ:営業利益+減価償却。事業の“現金創出力”の近似)
- ARR(エーアールアール:年間経常収益)
- FCF(フリーキャッシュフロー:税引後の営業キャッシュから投資などを差し引いた“自由に使えるお金”)
これらの水準と伸び方が価値の中心です。さらに運転資本(売掛金や在庫など日々の運転に要る資金)や負債に近い項目(未払い賞与や前受金など、実質的に債務として扱われやすいもの)も、買収価格の精算で効いてきます。
2. IPOとM&Aの違い
- IPO:資金調達力と知名度が上がる一方、四半期開示や内部統制のコストが恒常的に発生。株式市場の評価に業績が左右されやすい。
- M&A:買い手の販売網・ブランド・採用力を“借りられる”。シナジー(足し算以上の効果)が見込めれば、単独上場より高い価格が付くこともある。
シナジー:統合により売上増やコスト減が生まれる効果。
例)買い手の営業網にあなたの商材を載せ、短期間で販売拡大。
3. 買い手が本当に見ているKPI
3-1. 収益性と安定性
- 粗利率(売上から原価を引いた利益率。プロダクトの強さを示す)
- 解約率(サブスクの流出度合い。低いほど安定)
- NRR(ネット・レベニュー・リテンション:既存顧客内での増減。100%超なら“売らなくても伸びる”)
3-2. 成長の質
- LTV/CAC(顧客生涯価値 ÷ 新規獲得コスト。3倍超が目安)
- 顧客集中度(上位顧客依存の高さ。偏りが大きいと評価が下がる)
- ROIC(投下資本利益率。投じた資本に対してどれだけ稼げるか)
目安例:NRR110%・粗利80%・LTV/CAC3倍以上なら、EBITDA倍率(会社をEBITDAの何倍で買うか)も上振れしやすい。
4. 「価格×仕組み」で取り切る:実務の肝
M&Aは表示価格だけでなく、精算・補償・将来対価の設計で、実質受取額が変わります。
4-1. 価格の出し方(二方式)
- 完了勘定:クロージング時点の現金・有利子負債・NWCを確定し、EV(企業価値。事業全体の価値)から株式価値を逆算。 NWCターゲット:妥当な運転資本水準の合意値。ここが低いと、クロージングで受取額が削られやすい。
- ロックドボックス:基準日以降の資金流出を禁止し、基準日BSで価格固定。 安定成長の売り手に有利。日々の精算が少なく交渉がシンプル。
4-2. 将来対価の使い方
- アーンアウト:一定のKPI達成で後払いを受け取る仕組み。 留意点:KPIの定義、会計方針の固定、親会社内取引のルール化を契約に明記。恣意的操作を防ぐ。
4-3. リスク分担
- R&W(表明保証):財務・税務・労務・個人情報・反社など“問題は無い”と約束する条項。
- エスクロー:買い手が一部代金を預け、問題発覚時の補償に充てる。 設計ポイント:金額、期間、免責額(小さな不備は請求不可)を価格水準と連動させる。
4-4. 人の設計
- ノンコンピート:売り手が同一領域で一定期間ビジネスしない約束。
- リテンション:主要人材への残留報酬(現金・RSU等)。 人材が価値の源泉なら不可欠。のれん(買収時に生じる無形価値)の減損リスクを下げる。
5. 会計・税務・法務の要点だけ
- スキーム選択
- 株式譲渡:会社“丸ごと”。契約移管が簡便。スピード重視。
- 事業譲渡:資産・契約を選んで移す。柔軟だが手続が多い。消費税がかかる場合も。
- のれんの扱い
- 日本税務は通常5年償却可能。IFRSは償却せず減損テスト。買い手の税メリットは価格原資になる。
- デットライク項目
- 未払い賞与、退職給付、返金リスク、長期前受け、未払税金、未消化ポイント等。EV控除で実質価格が下がり得る。
- 個人情報・情報セキュリティ
- ISMS/PMS(情報保護の仕組み)やインシデント対応を整備。重大事故は価格調整の対象。
- 知財・ソフトウェア
- コードの帰属、FOSS(オープンソース)遵守、外部SDKのライセンス。クラウドのSLA(サービス品質保証)とDR(障害時復旧)も確認。
6. 「売れるBS」「死なないCF」をつくるチェックリスト
- 月次決算を5営業日で締める
- 科目棚卸(仮払・仮受・役員貸付など)を整理し、回収不能は引当
- NWCの12か月推移を見える化し、NWCターゲット案を準備
- 粗利の低い商材・案件を縮小し、粗利率を引き上げ
- 価格改定とプラン設計でARPU(顧客単価)最適化
- 解約理由を定量化し、NRRを110%超へ
- LTV/CACを常時モニタ(3倍超を狙う)
- クラウド原価は予約割引/RI/SPで最適化
- データルーム雛形、CIM(買い手向け説明資料)アウトラインを作成
- 労務・委託・競業避止などの契約を合法・最新化
CIM:事業内容、財務、KPI、組織、リスク、成長戦略をまとめた情報パッケージ。買い手検討の基礎資料。
7. 最適な“時期”の見つけ方
- 2〜3四半期連続でKPIが過去最高
- 受注残やパイプラインの可視性が高い
- 組織が引き継ぎ可能な状態
この条件が整ったら、ティーザー→NDA→CIM→Q&A→LoIの流れを複数社同時に走らせ、競争環境をつくる。
LoI:買付意向書。価格帯や主要条件を記した非拘束の文書。複数本を並べると条件が引き上がりやすい。
8. ミニ事例(数値は仮)
- 売上5億円、営業利益5,000万円、減価償却1,000万円 → EBITDA 6,000万円
- 粗利82%、NRR112%、解約月1.2%、LTV/CAC=4.1倍
- 想定EVはEBITDAの8〜11倍。
- 条件設計:ロックドボックス、ノンコンピート3年、主要人材にリテンション24か月、アーンアウトはARR成長とEBITDAの二本立て。
→ 表示価格を変えずとも、実質受取が20〜30%増になる設計は現実的。
9. よくある質問
Q1. 赤字でも売れる?
A. 売れます。技術、顧客基盤、チームが強く、NRRや成長が高ければ、アーンアウトで価格の溝を埋められます。
Q2. 従業員への開示はいつ?
A. 通常はLoI後〜最終契約直前。リーク防止とリテンション設計が先です。
Q3. アドバイザーは必要?
A. 価格より**“仕組み”の設計が差になります。精算・補償・アーンアウト・人の設計を一気通貫**で回せる伴走者の期待値は高い。
10. 今日からのアクション(90日計画)
- 0〜30日:月次早締め、科目棚卸、NWC分析、主要契約の棚卸
- 31〜60日:価格改定テスト、解約要因の施策化、クラウド原価の見直し
- 61〜90日:データルーム整備、CIMドラフト、バイヤーリスト作成、ティーザー配布準備
用語ミニ辞典(本文の復習用)
- EBITDA:営業利益+減価償却。現金創出力の目安
- ARR:年換算サブスク売上
- FCF:自由に使える現金の増減
- NWC(運転資本):日々の運転に必要な資金。売掛金+在庫−買掛金 など
- EV:企業価値。株式価値+有利子負債−現金
- 完了勘定:クロージング時点のBSを使って価格を精算
- ロックドボックス:基準日以降の資金流出禁止で価格固定
- アーンアウト:将来KPI達成で後払いが発生
- R&W:表明保証。問題が無いことの約束
- エスクロー:代金の一部留保口座
- ノンコンピート:競業避止
- リテンション:残留報酬(現金・株式など)
- NRR:既存顧客売上の純維持・拡大率
- LTV/CAC:顧客価値と獲得コストの比
- CIM:買い手向け情報資料
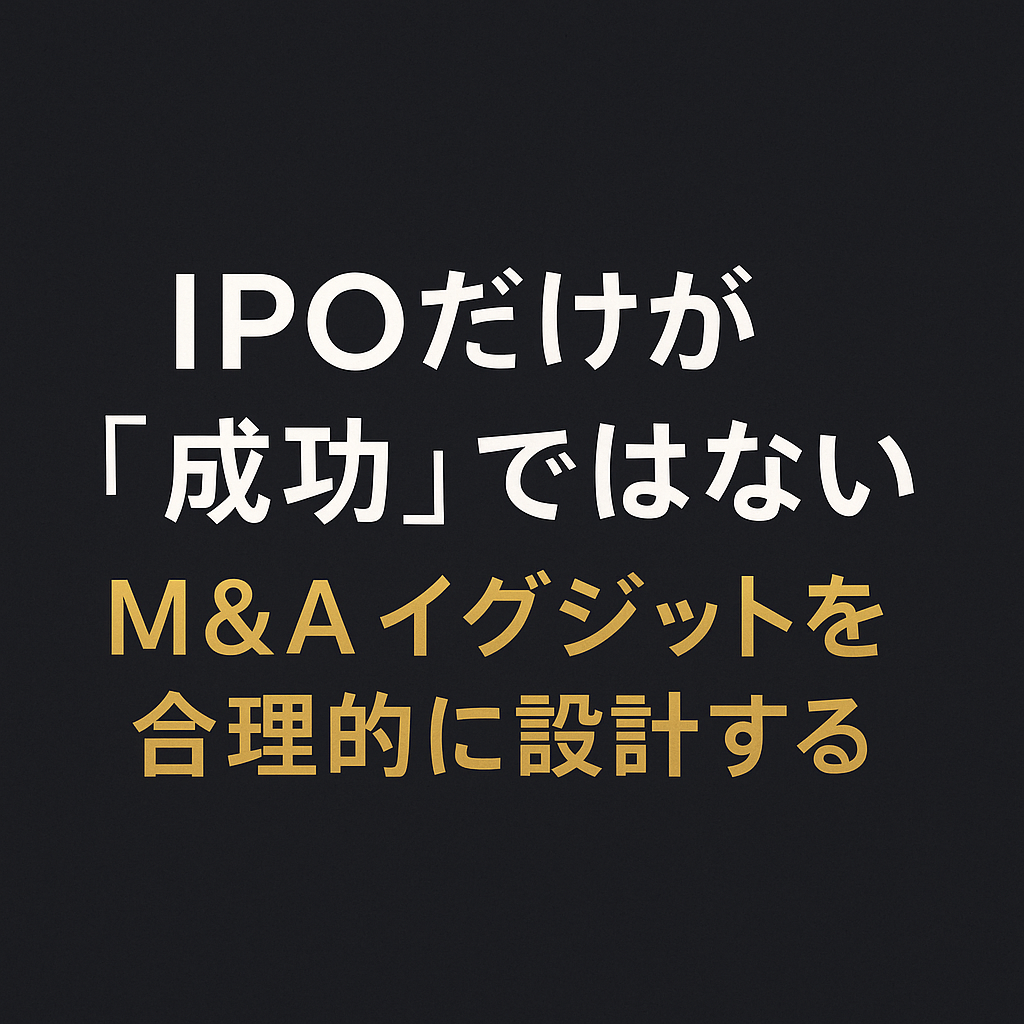



















コメント