ビジョナルはThinkingsの何に140億円を投じたのか?
2025年7月23日、HR Tech業界にインパクトを与えるM&Aが公表されました。転職プラットフォーム「ビズリーチ」を運営するビジョナルが、採用管理システム(ATS)「sonar ATS」を手がけるThinkingsを140.1億円で完全子会社化するという発表です。本件は、単なる事業規模の拡大に留まらず、日本のSaaS(Software as a Service)市場におけるM&A戦略、とりわけ企業価値評価(バリュエーション)の観点から非常に多くの示唆を含んでいます。
本稿では、この案件をバリュエーションという切り口で多角的に分析し、140.1億円という取得価額に込められた戦略的意図と、織り込まれたシナジー効果の正体を解き明かしていきます。
① 案件概要:HR Techの覇権を目指す戦略的布石
まず、本M&Aの構造と戦略的背景を整理します。
- 買収側: ビジョナル株式会社(東証プライム:4194)
- 実質的な買収主体は、中核子会社である株式会社ビズリーチ。
- 「ビズリーチ」や、人材活用プラットフォーム「HRMOS(ハーモス)」シリーズを展開。特に中小・中堅企業層に強固な顧客基盤を持つ。
- 被買収側: Thinkings株式会社
- 大手企業向け採用管理システム(ATS)「sonar ATS」を提供。
- 2020年設立ながら、2024年7月期には売上高19.8億円、営業利益5,300万円を計上する急成長SaaS企業。

- 取得価額: 140億1,000万円
- スキーム: 株式取得による完全子会社化
戦略的意義
ビジョナルは、本買収の目的を「中小・中堅企業から大企業までを対象にした採用管理サービスのマーケットリーダーとしての地位を固める」こと、そして「自社サービスとの機能連携やクロスセルによる事業拡大」にあると説明しています。これは、以下の2つの側面から極めて合理的な戦略と言えます。
- 顧客セグメントの補完: ビジョナルの「HRMOS」が主戦場とする中小・中堅企業市場に対し、Thinkingsの「sonar ATS」は大手企業市場に強みを持ちます。この統合により、両社は互いの弱点を補完し、あらゆる企業規模のニーズに対応可能な、包括的なHRソリューションプロバイダーへと進化します。これは、プロダクトのラインナップを拡充する上で、最も効果的かつ迅速な手段です。
- クロスセルの機会創出: 本件における最大の妙味は、クロスセルによる売上シナジーにあります。ビジョナルが持つ広範な顧客ネットワークに対し「sonar ATS」を、逆にThinkingsの顧客基盤である大手企業に対し「HRMOS」シリーズの他のプロダクト(タレントマネジメント等)を相互に販売することが可能になります。これにより、顧客獲得コスト(CAC)を抑えつつ、顧客生涯価値(LTV)を最大化するという、SaaSビジネスの王道を突き進むことができます。
この戦略的背景を念頭に置いた上で、次章では、本案件の核心である「140.1億円」という買収価格の妥当性を、複数のバリュエーション手法を用いて解剖していきます。
② バリュエーション手法の解説:140.1億円という価格の多角的分析
企業価値評価は、対象企業の「スタンドアロン価値(単独での価値)」に、買収によって生まれる「シナジー価値」を加算して買収価格を導出するプロセスです。ここでは代表的な4つの手法を用い、Thinkingsの価値を分析します。
1. 純資産法(コスト・アプローチ):下限値としての意味合い
- 手法の解説 純資産法は、企業の貸借対照表(B/S)上の純資産(資産-負債)を基に価値を算出する手法です。帳簿上の数値をそのまま使う簿価純資産法と、資産・負債を時価に評価し直す時価純資産法があります。企業の「解散価値」とも言え、M&Aにおいては、評価額の下限値として参考にされることが一般的です。
- 本件への適用と分析 公表されているThinkingsの純資産は2億7,700万円です。買収価格140.1億円と比較すると、実に50倍以上の乖離があります。これは、純資産法がソフトウェア、顧客基盤(導入実績2,300社)、ブランドといった、SaaS企業にとって最も重要な無形資産の価値を全く反映できないためです。したがって、Thinkingsのような高成長テクノロジー企業の評価において、純資産法は議論の出発点にすらなり得ないことが明確に分かります。この乖離こそが、未来の収益力に対する期待の大きさを物語っています。
2. 年買法(マーケット・アプローチの簡便法):適用限界の露呈
- 手法の解説 年買法(年倍法とも)は、主に中小企業のM&Aで慣習的に用いられる評価手法です。「時価純資産 + 営業利益 × 数年分(一般的に3~5年)」という簡便な計算式で算出されます。この「営業利益の数年分」は、のれん(超過収益力)の対価と見なされます。
- 本件への適用と分析 この計算式を本件に当てはめてみましょう。Thinkingsの営業利益は5,300万円です。仮に純資産を時価評価しても簿価(2.77億円)と大差ないと仮定し、買収価格から逆算してみます。
- のれん相当額:140.1億円 – 2.77億円 ≒ 137.3億円
- 営業利益の倍率:137.3億円 ÷ 0.53億円 ≒ 約259倍
営業利益の「259年分」という結果は、常識的な範囲(3~5年)を遥かに逸脱しており、年買法が本件のような高成長SaaS企業の評価には全く適さないことを示しています。年買法は、事業の成長が比較的安定した成熟企業の評価を前提としており、将来の爆発的な成長ポテンシャルや、業界構造を変えうる戦略的価値を織り込むことが構造的に不可能なのです。
3. EBITDAマルチプル法(マーケット・アプローチ):SaaS評価の「現実」
- 手法の解説 EBITDAマルチプル法は、類似の上場企業やM&A事例を参考に、「EV(企業価値)がEBITDA(税引前利益+支払利息+減価償却費)の何倍か」という倍率(マルチプル)を算出し、対象企業の価値を評価する手法です。金利水準や税率、減価償却方法の違いを排除して比較できるため、グローバルなM&Aで標準的に用いられます。
- 本件への適用と分析 ThinkingsのEBITDAを推定します。SaaS企業は自社開発ソフトウェアなどの無形資産償却が大きいため、営業利益にこれを加算する必要があります。仮に減価償却費を3,000万円と仮定すると、EBITDAは営業利益5,300万円+3,000万円=8,300万円と推定されます。 この場合、EV/EBITDA倍率は、
- EV/EBITDA倍率:140.1億円 ÷ 0.83億円 ≒ 約169倍

この169倍という数値も、一般的な製造業や小売業(10倍前後)と比較すれば異常な高水準です。しかし、ここで思考を停止してはなりません。SaaS企業の評価では、利益がまだ出ていない、あるいは投資先行で赤字の企業も多いため、別の指標が重視されます。それがARR(Annual Recurring Revenue:年間経常収益)です。
Thinkingsの売上高19.8億円の大半が、リカーリング(継続課金)型のARRであると仮定します。すると、ARRマルチプルという指標で評価できます。
- ARRマルチプル:140.1億円 ÷ 19.8億円 ≒ 7.1倍
ARRマルチプル7.1倍という水準は、上場SaaS企業の市況や、ThinkingsのARR成長率、解約率(チャーンレート)、市場の潜在性などを考慮すれば、十分に議論の俎上に載る値です。特に、年間数十パーセントの高い成長を続けているSaaS企業であれば、ARRの7倍~10倍、あるいはそれ以上の評価がなされるケースも珍しくありません。
つまり、ビジョナルはThinkingsの現在の利益(EBITDA)ではなく、将来の収益基盤である「質の高いARR」とその「高い成長性」に対して、140.1億円という価値を見出していると解釈するのが最も合理的です。
4. DCF法(インカム・アプローチ):未来のストーリーを数値化する技術
- 手法の解説 DCF(Discounted Cash Flow)法は、企業が将来創出するフリー・キャッシュフロー(FCF)を、事業のリスクなどを反映した割引率(WACC:加重平均資本コスト)で現在価値に割り引くことで、事業価値を算出する評価手法です。将来の事業計画に大きく依存しますが、企業の固有の価値や成長性を最も理論的に反映できるとされています。
- 本件への適用と分析 140.1億円という評価額をDCF法で正当化するためには、どのような事業計画(未来のストーリー)が必要となるかを逆算的に思考することが有効です。
- FCFの成長ストーリー: ビジョナルは、Thinkingsが自社グループに加わることで、以下のようなキャッシュフロー成長を実現できると見込んでいるはずです。
- 短期(1~3年): 積極的な統合投資・マーケティング投資により、FCFは低水準かマイナスで推移。
- 中期(4~10年): クロスセル戦略が本格的に奏功し、ARRが年率30~40%といった高い成長を遂げる。同時に、規模の経済が働き、営業利益率も向上し始める。
- 長期(11年目以降): 安定成長期に入り、市場リーダーとして高い営業利益率(例:25%以上)を維持し、巨額の安定したFCFを創出し続ける。
- FCFの成長ストーリー: ビジョナルは、Thinkingsが自社グループに加わることで、以下のようなキャッシュフロー成長を実現できると見込んでいるはずです。
この野心的な成長ストーリーを、具体的な数値計画に落とし込み、適切な割引率(例えば、8~10%)で割り引いた結果が、140.1億円という現在価値に合致した、と考えることができます。DCF法は、まさにこの「シナジーを含んだ未来の成功シナリオ」を定量的に評価するためのフレームワークなのです。
結論
今回のビジョナルによるThinkingsの買収は、目先の利益指標だけでは到底測れない、典型的な「成長戦略型M&A」です。140.1億円という買収価格は、以下の要素を織り込んだ、極めて戦略的な意思決定の結果であると結論付けられます。
- 評価の主軸は「ARR」とその成長性: 利益や純資産ではなく、将来の安定収益の源泉であるARRと、その高い成長ポテンシャルが評価の核となっています。
- 巨大なシナジー価値の織り込み: 買収価格には、ビジョナルグループのリソースを活用することで初めて生まれる、40億円超と推定される巨大なシナジー価値が含まれています。
- 未来の事業計画へのベット: DCF法の観点からは、この買収はThinkings単独では成し得ない、両社の統合によって実現される「飛躍的な成長ストーリー」に対する明確な投資です。
―この記事の監修者―
プライマリーアドバイザリー株式会社
代表取締役 内野 哲
一般社団法人 金融財政事情研究会 M&Aシニアエキスパート/東証プライム上場企業グループ会社代表取締役社長を経てM&Aアドバイザリー事業創業/自己勘定投資会社にて投資業/企業価値評価、M&Aスキーム設計に精通
[→無料相談・お問い合わせはこちら]

代表電話:03-5050-5175
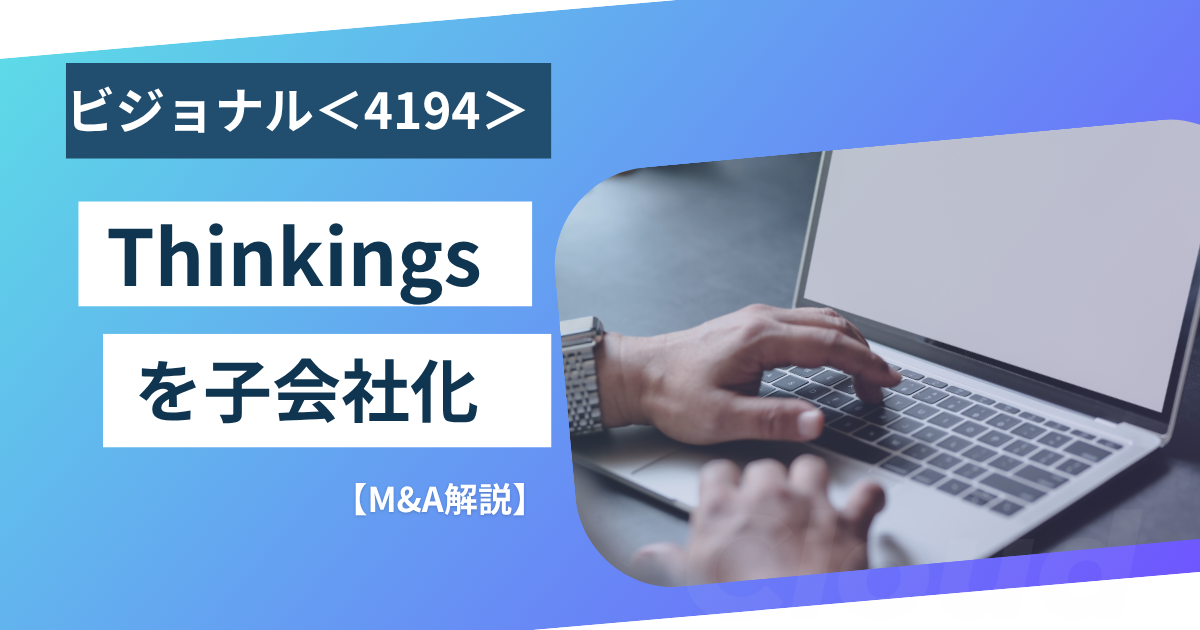



















コメント