「代表取締役であるご主人が、昨日、突然倒れられて…」。 これはアドバイザーとして仕事をする中で、残念ながら幾度となくお聞きしてきた言葉です。一家の大黒柱であり、会社の顔であったオーナー社長の急逝は、ご遺族にとって計り知れない悲しみであると同時に、会社の未来を揺るがす重大な経営課題の始まりでもあります。
残されたご家族、特に経営に直接関与してこられなかった奥様やお子様は、悲しみに暮れる間もなく、複雑で難解な問題に直面します。それは、「会社の経営をどうするのか」「従業員の生活はどうなるのか」、そして「非上場である自社株式をどう扱えばよいのか」という問いです。
本記事では、このような困難な状況に直面された方々に向けて、具体的な手順を解説します。特に、多くの方が見落としがちな「株価算定(バリュエーション)」の重要性に焦点を当て、ご家族と会社にとって最善の未来を選択するための一助となることを目指します。
第1章:オーナー社長の急逝、煩雑な手続き内容と手順
オーナー社長が亡くなられた瞬間、会社は法的に「代表取締役不在」の状態に陥ります。対外的な契約や銀行取引など、重要な意思決定がすべて停滞するリスクに晒されます。同時に、ご遺族は相続という、これまた複雑な手続きを開始しなければなりません。
1-1. 株式の相続と「経営権の空白」
ご主人が保有されていた株式は、民法の規定に従い、相続人の皆様の「準共有」状態となります。つまり、遺産分割協議が完了するまで、特定の誰かが単独で議決権を行使することはできません。この「経営権の空白」期間は、会社の事業価値を日々毀損させていく可能性があります。
【最初にやるべきこと】
- 相続人の確定: 戸籍謄本等を取り寄せ、法的に誰が相続人であるかを確定させます。
- 臨時株主総会の開催: 相続人全員の同意のもと、株主総会を開催し、暫定的な代表取締役を選任します。これにより、当面の会社経営を安定させることが急務です。
- 遺産分割協議: 誰が株式を相続するのかを、相続人全員で協議し、合意形成を図ります。「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・捺印することで、株式の帰属が正式に決定します。
1-2. 非上場株式が「争続」の火種となる理由
不動産や預貯金と異なり、非上場株式は3つの点で極めて扱いにくい資産です。
- 分割が困難: 「A株式を長男に3分の2、次男に3分の1」といった物理的な分割はできません。誰か一人が代表して相続するか、あるいは売却して現金化し、その現金を分割する必要があります。
- 価値が不明確: 上場株式のように市場価格が存在しないため、その価値を巡って相続人間で見解が対立しがちです。
- 換金性が低い: 買い手を見つけるのが難しく、すぐに現金化できないため、納税資金の確保に窮するケースが少なくありません。
これらの特性が、相続を「争続」へと発展させる大きな要因(参照:非上場株主紛争について )となります。
1-3. 株式の名義変更(名義書換)
遺産分割協議が完了し、株式を誰が相続するかが決定したら、次に行うべきは「株式の名義変更(名義書換)」です。これは、会社の株主名簿上の株主名を被相続人(故人)から相続人へ書き換える手続きであり、会社に対して正式に株主としての権利を主張するための対抗要件となります。この手続きを怠ると、配当金の受領や株主総会での議決権行使ができないなど、重大な不利益を被る可能性があります。
手続きの相手方や難易度は、株式が「非上場」か「上場」かによって大きく異なります。
A. 非上場株式の名義変更(最重要)
非上場株式の場合、手続きの窓口は証券会社ではなく、株式を発行している会社自身となります。これが手続きを複雑となる第一のポイントです。
【手続きの基本ステップ】
窓口の確認と連絡:
まずは株式を発行している会社(故人が経営していた会社)の担当部署(通常は総務部など)に連絡を取ります。
盲点: 定款で「株主名簿管理人(通常は信託銀行など)」が定められている場合があります。その場合は、その信託銀行が手続きの窓口となるため、最初に必ず定款を確認するか、会社に問い合わせる必要があります。
必要書類の準備と提出:
一般的に、以下の書類の提出を求められます。会社所定の書式がある場合が多いため、必ず事前に取り寄せましょう。
- 株式名義書換請求書(会社所定様式)
- 遺産分割協議書の原本(相続人全員の実印が押印されたもの)
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(通常は発行後3ヶ月または6ヶ月以内のもの)
- 株券(※株券発行会社の場合のみ。紛失している場合は別途手続きが必要)
【戦略的論点】非上場株式特有の「壁」
譲渡制限の存在: 日本の非上場会社の株式は、そのほとんどが定款で「譲渡制限株式」とされています。相続による取得は、この譲渡制限の対象外であるため、会社の承認なく名義書換が可能です。しかし、その株式を将来第三者に売却(M&A)しようとする際には、会社の承認が必要になるという点をここで認識しておくことが極めて重要です。
会社側の協力度合い: 手続きの相手が「身内」である会社そのものであるため、他の株主(例:故人の兄弟など)との関係性によっては、手続きがスムーズに進まないリスクもゼロではありません。必要書類の案内を意図的に遅らせる、些細な不備を指摘して受け付けないなど、非協力的な対応を取られるケースも想定されます。このような事態は、まさに専門家が介入すべき領域です。
B. 上場株式の名義変更(比較参考)
上場株式の場合は、手続きが定型化されています。
窓口: 被相続人が口座を開設していた証券会社となります。
手続き: 証券会社に相続が発生した旨を連絡すると、「相続手続依頼書」などの必要書類一式が送られてきます。遺産分割協議書や戸籍謄本など、指示された書類を提出することで、被相続人の口座から相続人の口座へ株式が振り替えられます。非上場株式に比べて、手続きは遥かにスムーズに進みます。
この比較からも分かる通り、非上場株式の相続は、手続きの各段階において、個別性が高く、潜在的な紛争リスクを内包しているのです。単なる事務手続きと軽視せず、慎重に進める必要があります。
第2章:「相続税評価額」と「M&A時価」の決定的な価格差の違い
非上場株式の扱いで最も重要な論点が、その「価値」です。そして、多くの方が最初の罠にはまるのが、この価値には目的の異なる2つの評価額が存在するという事実です。それは「相続税の計算に使われる株価」と「M&Aで実際に会社を売却できる株価」であり、両者は全くの別物です。この違いを理解することが、ご家族の資産を守り、会社の未来を正しく選択するための第一歩となります。
2-1. 相続税を計算するための「相続税評価額」
相続税評価額は、あくまで相続税や贈与税を計算するために、国税庁が定めた画一的なルールに基づいて算出される価格です。その目的は「課税の公平性」であり、会社の真の事業価値を反映するものではありません。評価方式は、会社の規模(大会社・中会社・小会社)に応じて、主に以下の方法が用いられます。
① 類似業種比準価額方式
事業内容が類似する上場企業の株価を基に、「配当」「利益」「純資産」の3つの要素を比較して株価を計算する方法です。主に、規模の大きな会社で適用されます。これは、いわば「同業他社の成績を参考にした評価」と言えるでしょう。
株価 = 類似業種の上場会社の株価 × (aA+bB+cC) ÷ 3 × 斟酌率
(A,B,C:自社の配当・利益・純資産, a,b,c:類似業種の配当・利益・純資産)
※斟酌率は会社の規模に応じて異なり、大会社の場合は0.7、中会社の場合は0.6、小会社の場合は0.5とされています。
② 純資産価額方式
会社の総資産から負債を差し引いた「純資産」を、発行済株式数で割って株価を計算する方法です。帳簿上の数値を相続税評価額ベースに修正して計算します。これは、仮に会社を今解散した場合に株主に残る価値、すなわち「解散価値」に近い考え方です。
株価 = 発行済株式数相続税評価額による純資産額
③ 配当還元方式
過去の配当実績を基に、株価を評価する方法です。主に、経営への影響力が限定的な少数株主が株式を相続した場合などに用いられます。利益を内部留保し、配当を少なく抑えているオーナー企業では、株価が極めて低く計算される傾向があります。これらの方法で算出された相続税評価額を基に、相続人は納税額を確定させ、申告・納税(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)を行います。しかし、この評価額をもって「自社の価値」と結論付けてしまうのは、極めて危険な判断です。
2-2. 納税の期限と資金対策:『10ヶ月の壁』と3つの選択肢
相続税評価額に基づき納税額が算出された後、ご遺族の前に立ちはだかるのが「納税」という現実的な課題です。ここには厳格なルールと、知らなければ大きな損をする可能性がある制度が存在します。
(1) 絶対厳守のルール:10ヶ月以内の現金一括納付
まず、全ての相続人が理解すべき大原則は以下の通りです。
- 申告・納税期限: 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
- 納付方法: 原則として現金一括納付
この「10ヶ月」というタイムリミットは、遺産分割協議をまとめ、株式の価値を評価し、会社の将来を決定するという一連のプロセスに、強烈な時間的プレッシャーを与えます。特に、相続財産の大部分が換金性の低い非上場株式である場合、「納税資金をどう準備するか」は極めて深刻な問題となります。
(2) 現金納付が困難な場合の選択肢と、その「罠」
現金一括納付が難しい場合に備え、国は救済制度を設けていますが、その利用には慎重な判断が必要です。
| 制度 | 概要 | メリット | デメリット・戦略的注意点 |
| 延納 | 相続税を年賦(分割払い)で納める制度 | 当面の資金繰りを緩和できる | ・高い利子税がかかる ・担保の提供が必要 ・あくまで支払いの先延ばしであり、負債総額が減るわけではない |
| 物納 | 現金の代わりに、不動産や株式などの財産そのもので税金を納める制度 | 現金がなくても納税が可能 | ・許可要件が非常に厳しく、最終手段と位置づけられる ・非上場株式で物納する場合、その収納価額(国の評価額)は「相続税評価額」となる。M&A時価(本来の価値)が相続税評価額を大きく上回る場合、極めて大きな財産価値を失うことになる。 |
【非上場株式の物納がもたらす致命的な損失】
本記事で繰り返し強調している通り、多くの場合、M&A時価 ≫ 相続税評価額です。 例えば、M&Aで売却すれば3億円の価値が付く可能性のある株式を、納税のために物納したとします。その際の国の収納価額は、相続税評価額である1億円になってしまうかもしれません。これは、差額の2億円という莫大な機会損失をご遺族が受け入れることに他なりません。納税資金の確保という短期的な問題解決のために、会社の真の価値を捨て去る選択は、絶対に避けるべきです。
(3) 事業承継時の特例:事業承継税制
ご親族が事業を引き継ぐ場合には、極めて強力な制度があります。
- 制度概要: 後継者(相続人)が、相続等により取得した自社の株式(議決権の3分の2まで)にかかる相続税の全額について、納税が猶予されます。さらに、後継者が死亡した場合など一定の要件を満たすと、猶予されていた相続税が免除されます。
- メリット: 実質的に相続税の負担なく、自社株式を次世代に引き継ぐことが可能です。
- デメリット:
- 適用要件や手続きが非常に複雑で、専門家の支援が不可欠。
- 承継後5年間は、後継者が代表を継続し、雇用の8割を維持するなどの制約がある。
- 定期的に都道府県への報告義務がある。
この制度は親族内承継を強力に後押ししますが、経営上の制約も伴うため、会社の将来像や後継者の意思を慎重に吟味した上で活用を判断すべきです。
2-3. 会社の真の価値を映す「M&Aにおける企業価値(時価)」
M&Aにおける企業価値(一般に「時価」と呼ばれる)は、税金計算のためではなく、「買い手が、その会社をいくらで買いたいか」という観点で評価されます。評価の尺度は、過去の実績や現在の資産だけでなく、「その会社が将来どれだけのキャッシュを生み出す能力があるか」という未来への期待値が中心となります。
代表的な評価アプローチは以下の3つです。
① インカム・アプローチ(DCF法など)
将来、会社が生み出すと予測されるフリー・キャッシュフロー(FCF)を、事業のリスクなどを反映した割引率(WACC)で現在価値に割り戻して企業価値を算出する方法です。
- フリー・キャッシュフロー (FCF): 会社が本業で稼いだ現金から、事業維持に必要な投資を差し引いた、自由に使える現金の流れ。
- 割引率 (WACC): 株主資本コストと負債コストを加重平均したもので、事業の不確実性(リスク)を反映します。
DCF法は、会社の将来性や独自の強み(技術力、ブランド、顧客基盤など)を最も反映できる評価方法であり、M&Aの実務で最も重視されるアプローチの一つです。
② マーケット・アプローチ(類似会社比較法、類似取引比較法など)
評価対象の会社と事業内容や規模が類似する上場企業の株価や、過去のM&A事例を参考に、企業価値を類推する方法です。 例えば、類似企業の企業価値がEBITDA(税引前利益+減価償却費)の何倍(マルチプル)で評価されているかを分析し、その倍率を自社のEBITDAに乗じて価値を算出します。 客観性が高く、市場の動向を反映しやすいというメリットがあります。
企業価値 = 自社のEBITDA × 類似企業のマルチプル (企業価値/EBITDA倍率)
③ コスト・アプローチ(修正純資産法など)
貸借対照表(B/S)上の資産・負債を、帳簿価額から時価に修正して純資産を再計算し、それを企業価値とする方法です。例えば、含み損益のある土地や有価証券を時価で評価し直します。 このアプローチは、将来の収益力よりも、保有する純資産に着目した評価方法であり、特に資産管理会社や、事業の継続が難しい場合の清算価値を算定する際に参照されます。
2-4. なぜ「2つの株価」の違いが重要なのか?
結論から言えば、多くの場合、M&Aにおける時価は、相続税評価額を大きく上回ります。
- 評価の視点: 相続税評価は「過去・現在」のルール上の評価、M&A時価は「未来」の収益力を含めた評価です。
- のれん(営業権): M&Aでは、帳簿に載らない無形資産(ブランド力、技術力、顧客網、従業員の能力など)が「のれん」として高く評価されますが、相続税評価ではほとんど考慮されません。
- シナジー効果: 買い手企業は、自社との統合によって生まれる新たな価値(シナジー)を見込んで買収価格を提示します。これも相続税評価にはない概念です。
もし、相続税評価額を自社の価値と信じ込み、その価格で安易に第三者へ売却したり、特定の相続人が他の相続人から買い取ったりすれば、本来得られたはずの何倍もの価値を失うことになりかねません。これは、ご家族にとって取り返しのつかない経済的損失です。
第3章:会社の未来を決める3つの戦略的選択肢
非上場株式を相続したご家族が取り得る選択肢は、大きく分けて3つです。どの選択肢が最適かは、ご家族の状況、会社の状況、そして皆様の想いによって異なります。それぞれのメリット・デメリットを冷静に比較検討することが不可欠です。
| 選択肢 | メリット | デメリット | こんな方におすすめ |
| 1. 親族内承継 (事業を続ける) | ・創業家の理念や文化を守れる ・従業員の雇用を維持しやすい ・所有と経営の一致を継続できる | ・後継者に経営能力と強い意志が必要 ・後継者以外の相続人との公平性担保が難しい ・個人保証の引き継ぎという重い負担 | 経営に意欲と能力のある後継者が親族内にいて、他の相続人もその方針に同意している場合。 |
| 2. 第三者承継 (M&Aで売却) | ・創業者利益を実現し、ご家族の資産を最大化できる ・後継者不在問題を解決できる ・会社の更なる成長を資本力のある他社に託せる ・個人保証から解放される ・従業員の雇用や取引先との関係を維持できる | ・希望の条件(価格、雇用維持等)に合う買い手が見つかるとは限らない ・創業家の理念が薄れる可能性がある ・情報漏洩のリスク管理が必要 | 親族内に後継者がいない場合。会社の成長を最優先に考えたい場合。相続税の納税資金やご自身の老後資金を確保したい場合。 |
| 3. 廃業・清算 (会社をたたむ) | ・経営の責任から完全に解放される ・ご自身のタイミングで決断できる | ・従業員は全員解雇となる ・取引先に多大な迷惑がかかる ・資産を現金化できても、負債が残るリスクがある ・会社の持つ技術やブランドが消滅する | 債務超過で事業継続が困難な場合。買い手が見つからず、他に選択肢がない場合の最終手段。 |
多くの場合、オーナー社長が心血を注いで育て上げた会社を、ご自身の代でたたむという選択は避けたいと考えるのが自然な感情でしょう。また、経営経験のない方が突然事業を引き継ぐことの困難さを考慮すると、会社の成長と従業員の生活、そしてご家族の利益を鼎立させる現実的かつ有力な選択肢として「M&Aによる第三者承継」が浮上してきます。
第4章:M&Aを決断した場合の成功へのロードマップ
M&Aは、単に会社を高く売ればよいというものではありません。従業員の雇用、取引先との関係、そして創業者が築き上げた文化を、いかにして最良の相手に引き継いでもらうかという、極めて繊細なプロセスです。専門家であるM&Aアドバイザーと共に行動することが、成功の絶対条件と言えます。
ステップ1: 信頼できるM&Aアドバイザーの選定
最初の、そして最も重要なステップです。M&Aアドバイザーは、ご家族の仲介人として、企業価値評価から買い手候補の選定、交渉、契約締結まで、全てのプロセスをナビゲートします。
ステップ2: 企業価値評価(バリュエーション)と戦略立案
M&Aアドバイザーと共に、第2章で解説したDCF法やマルチプル法など、複数のアプローチを用いて詳細な企業価値を算定します。これは、交渉の出発点となるだけでなく、会社の強み・弱みを客観的に分析し、どのような買い手候補にアピールできるかを考える「M&A戦略」の基盤となります。
ステップ3: 買い手候補へのアプローチ
M&Aアドバイザーは、会社の強みや将来性を最も高く評価してくれるであろう買い手候補のリスト(ロングリスト)を作成します。その後、ご家族と協議の上で有力候補を絞り込み(ショートリスト)、まずは会社名が特定されない形にまとめた資料(ノンネームシート)で打診を開始します。この段階での情報管理は極めて重要です。
ステップ4: 交渉と基本合意
関心を示した候補先と秘密保持契約(NDA)を締結し、より詳細な企業情報(インフォメーション・メモランダム)を開示します。その後、経営者同士の面談を経て、買い手から買収価格や条件を記載した「意向表明書(LOI)」が提示されます。条件交渉を行い、双方が大筋で合意に至れば、「基本合意書(MOU)」を締結します。
ステップ 5: デューデリジェンス(DD)と最終契約
基本合意後、買い手は公認会計士や弁護士などの専門家を起用し、売り手企業の財務・法務・税務・事業内容などを詳細に調査します。これをデューデリジェンス(DD)と呼びます。DDで重大な問題が発見されなければ、最終的な売買条件を確定させ、「株式譲渡契約書(SPA)」を締結します。
ステップ 6: クロージング
SPAで定められた日に、株式の譲渡と売買代金の決済を実行します。この日をもって、会社の所有権は正式に買い手へ移転し、M&Aのプロセスは完了となります。
最後に
オーナー社長の急逝という事態は、ご遺族にとっても、会社にとっても、筆舌に尽くしがたい危機です。しかし、その危機の中で立ち止まり、悲しみにくれるだけでは、大切な会社と従業員、そしてご家族自身の未来を守ることはできません。正しい知識を身につけ、信頼できる専門家をパートナーとして選ぶことで、この危機を乗り越え、むしろ会社がより大きく飛躍し、ご家族が経済的な安定と心の平穏を得るための「機会」とすることも可能です。その鍵を握るのが、本記事で繰り返し強調した「株価の正しい理解」です。相続税申告という目先の課題に追われ、「相続税評価額」という一面的な価値判断に囚われてしまうと、本来会社が持つ未来の価値を見過ごしてしまいます。
私たちは、M&Aのプロフェッショナルとして、数多くの事業承継をお手伝いしてまいりました。その経験から断言できるのは、早期にご相談いただくほど、選択肢は広がり、より良い未来を描く可能性が高まるということです。
「何から手をつけて良いかわからない」
「まずは自社の本当の価値を知りたい」
「相続人間の話し合いを円滑に進めたい」
どのようなお悩みでも結構です。突然の出来事に途方に暮れている今だからこそ、まずは現状を客観的に把握し、進むべき道の選択肢を整理することから始めてみませんか。
私たちは、単なる仲介者ではありません。ご家族の皆様に寄り添い、創業者の想いを尊重しながら、会社と関わるすべての人々にとって最善の未来を共に構想するパートナーです。初回のご相談は無料にて承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
―この記事の監修者―
プライマリーアドバイザリー株式会社
代表取締役 内野 哲
一般社団法人 金融財政事情研究会 M&Aシニアエキスパート/東証プライム上場企業グループ会社代表取締役社長を経てM&Aアドバイザリー事業創業/自己勘定投資会社にて投資業/企業価値評価、M&Aスキーム設計に精通
[→無料相談・お問い合わせはこちら]

代表電話:03-5050-5175
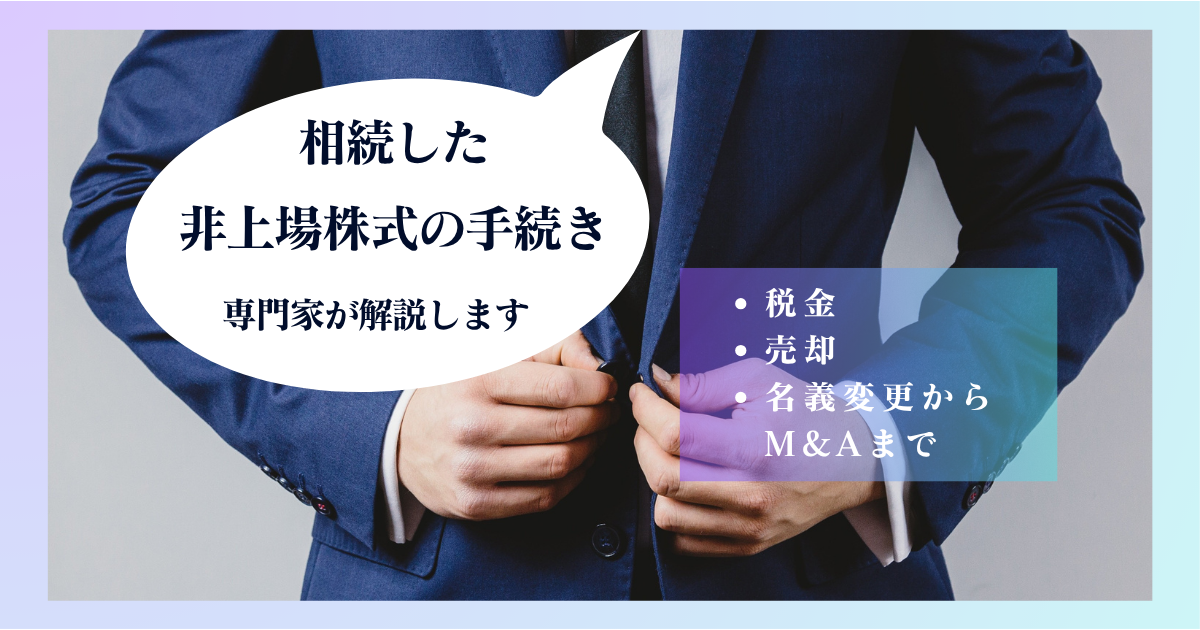



















コメント