2025年10月9日、リユース大手の株式会社トレジャー・ファクトリーが、無人店舗型ドレスレンタルサービス「Empty Dressy」の事業取得を発表しました。
◆ トレジャー・ファクトリーはなぜこの事業を選んだのか
トレジャー・ファクトリーは、既に「cariru」というブランドでファッションレンタル事業を展開しています。一方、買収対象の「Empty Dressy」は、「無人店舗型」というユニークなビジネスモデルを特徴としています。
今回の事業取得の目的は、プレスリリースからも明らかですが、主に以下の2点が考えられます。
- 既存事業とのシナジー創出:
- サービス拡充: 「cariru」のオンライン完結型サービスに加え、「Empty Dressy」の「試着して、その場で持ち帰れる」というオフラインの強みを取り込むことで、顧客体験価値を向上させます。
- クロスセル: 両サービスの顧客基盤を相互に活用し、売上の増加を狙います。
- オペレーション効率化: 在庫管理や物流、メンテナンスといったレンタル事業のバックヤード業務を統合し、コスト削減を図ります。
- 新規ビジネスモデルの獲得:
- 無人店舗運営ノウハウ: 今後の人手不足が深刻化する中で、省人化・効率化を実現する無人店舗の運営ノウハウは、他事業への横展開も可能な貴重な経営資源となり得ます。
- 新たな市場への足掛かり: ドレスレンタルというニッチながらも安定した需要が見込める市場で、独自のポジションを確立します。
◆ 純資産法(年買法)から見る評価
年買法による企業価値 = 時価純資産 + のれん(営業利益 × N年分)
この「N年」は、業界や企業の安定性、将来性によって変動しますが、一般的には3年〜5年が一つの目安とされています。
今回の事業譲渡では、対象事業の純資産額は公表されていません。しかし、レンタル用のドレスや内装設備などが資産として計上されていると考えられますが、事業規模から勘案して、ここでは仮にその額が限定的であったと仮定し、取得価額の大部分が「のれん」であると想定して逆算してみましょう。
- のれん(営業権) ≒ 取得価額 4,800万円
- 営業利益 = 1,300万円
この場合、トレジャー・ファクトリーが評価した「のれん」は、営業利益の何年分に相当するのでしょうか。
N年=営業利益のれん=13,000,000円48,000,000円≈3.69年
営業利益の約3.7年分。この数字は、一般的なM&Aにおける「3年〜5年」という目安の範囲内に収まっています。
このことから、年買法というシンプルな評価軸で見ても、今回の取得価額4,800万円は、市場の相場観から大きく逸脱しない、合理的な水準であると推察できます。特に、無人店舗というビジネスモデルの独自性や今後の拡張性を考慮すれば、買い手にとって十分に妥当な判断であったと言えるでしょう。
◆ EBITDAマルチプル法:簡易的かつ実務的な評価手法
DCF法が精緻である一方、多くの仮説を必要とするため、客観性に欠ける側面もあります。そこで、より簡易的で実務的によく用いられるのがEBITDAマルチプル法です。
EBITDAとは、「利払前・税引前・減価償却前利益」のことであり、金利水準や税率、減価償却方法といった会計方針の違いに影響されにくい、企業の「本源的な収益力」を示す指標とされています。
EBITDA = 営業利益 + 減価償却費
EBITDAマルチプル法では、このEBITDAに、類似企業や類似のM&A取引から導き出される**倍率(マルチプル)**を乗じることで事業価値を算出します。
事業価値 = EBITDA × マルチプル(倍率)
今回のケースで試算してみる
対象事業の減価償却費は不明ですが、無人店舗の設備投資などを考慮し、仮に年間200万円と設定してみましょう。
- EBITDA = 営業利益 1,300万円 + 減価償却費 200万円 = 1,500万円
このEBITDAを用いて、取得価額4,800万円からマルチプルを逆算します。
マルチプル=EBITDA事業価値=15,000,000円4,800,0000円=3.2倍
「3.2倍」というマルチプルは、対象事業の成長性やリスクをどのように反映しているのでしょうか。一般的に、成熟産業の小規模事業であれば3〜5倍、成長性の高いIT関連事業などでは10倍を超えることも珍しくありません。
この事業は、レンタルサービスという安定した側面と、無人店舗という成長・拡張性のポテンシャルを併せ持っています。3.2倍という倍率は、事業規模の小ささやニッチな市場であることを考慮すると、比較的堅実で妥当な評価であると見ることができます。買い手としては、今後のシナジーによって実質的なEBITDAを向上させることで、この投資の回収を早めることができると考えているでしょう。
◆ マーケット・アプローチ(類似比較法)の応用
視点を変えて、買い手であるトレジャー・ファクトリー自身の市場評価を参考にしてみましょう。これは、M&Aの価格の妥当性を測る上で、非常に興味深い示唆を与えてくれます。
仮に、本稿執筆時点のトレジャー・ファクトリー(3093)の市場評価が以下のようであったとします。(※数値は解説のための仮定です)
- PER: 15.0倍
- PBR: 2.5倍
- EV/EBITDA倍率: 8.0倍
これらの数値は、株式市場がトレジャー・ファクトリーの事業内容や成長性を高く評価していることを示しています。特にEV/EBITDA倍率が8.0倍である会社が、マルチプル3.2倍の事業を買収するということは、「割安な投資」と見ることができます。もちろん、事業規模やリスクが全く異なるため、単純比較はできません。しかし、自社が市場から受け入れている評価基準(マルチプル8.0倍)よりも低い倍率で、かつ将来のシナジーが見込める事業を取得することは、既存株主の価値向上(企業価値の増大)に繋がると経営陣が判断した、と解釈することができます。
このように、マーケット・アプローチは、直接的な比較対象がない場合でも、買い手自身の立ち位置を客観的に見ることで、M&Aの意思決定の合理性を説明する一つの根拠となり得るのです。
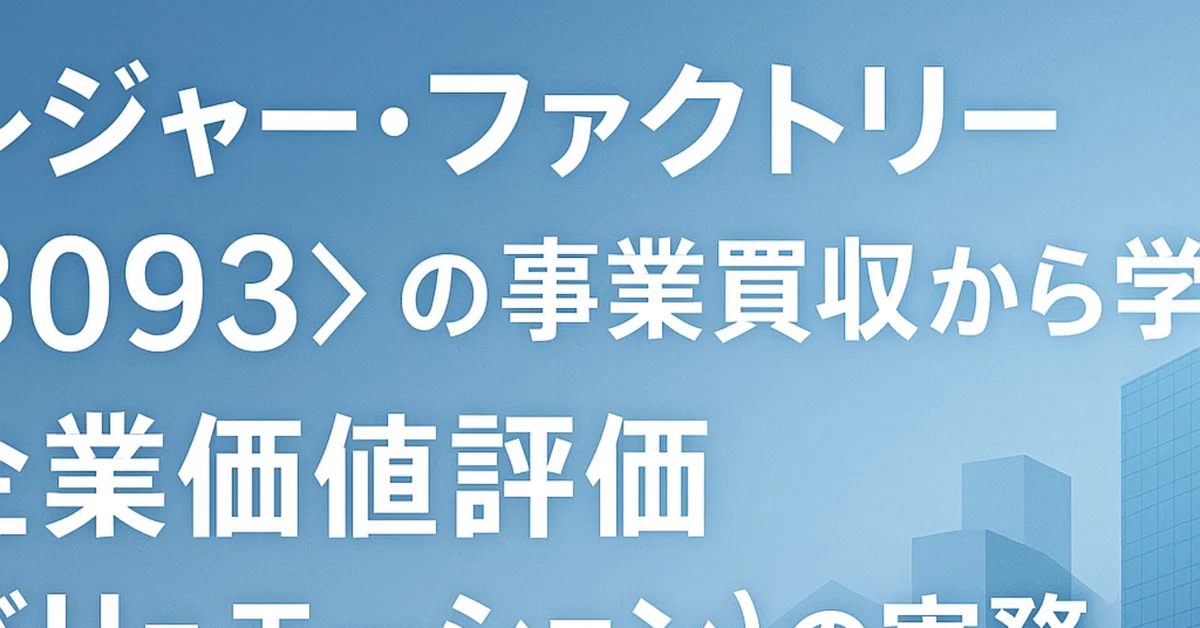

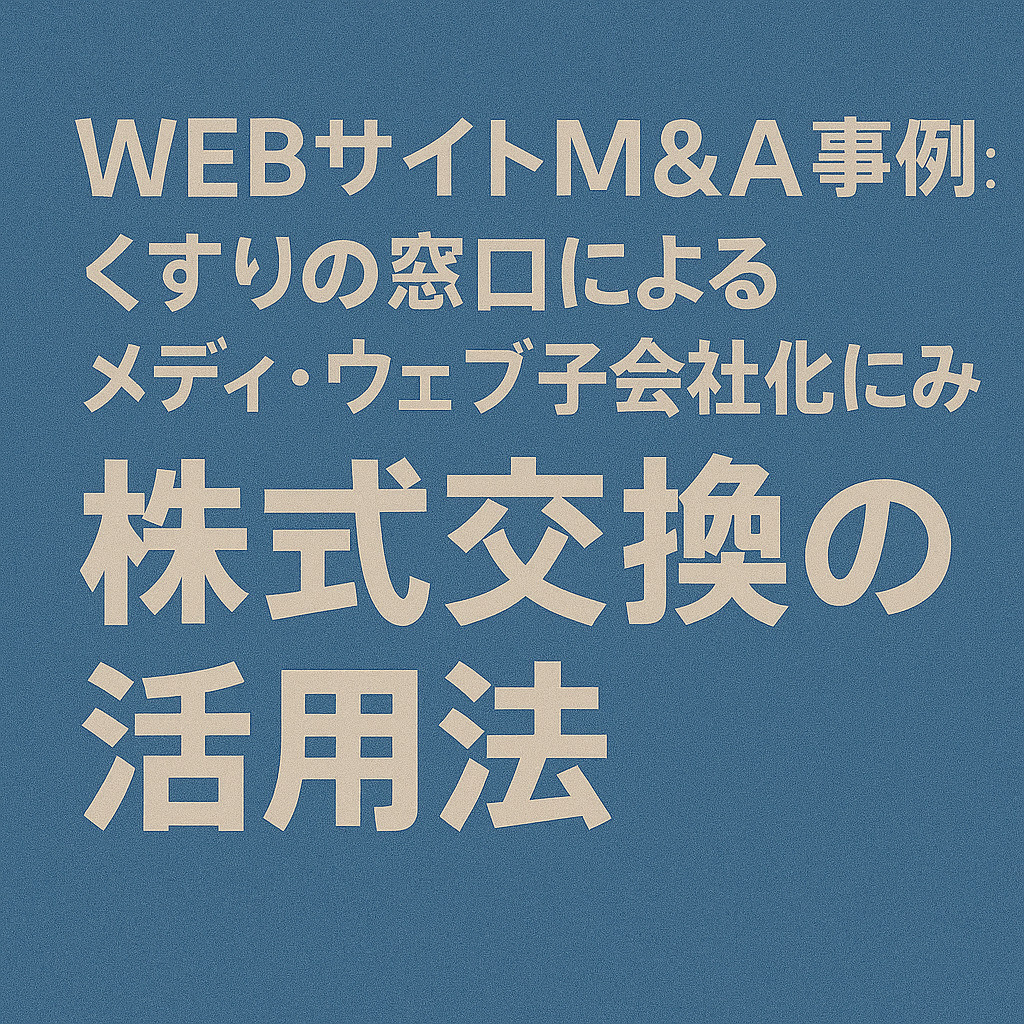
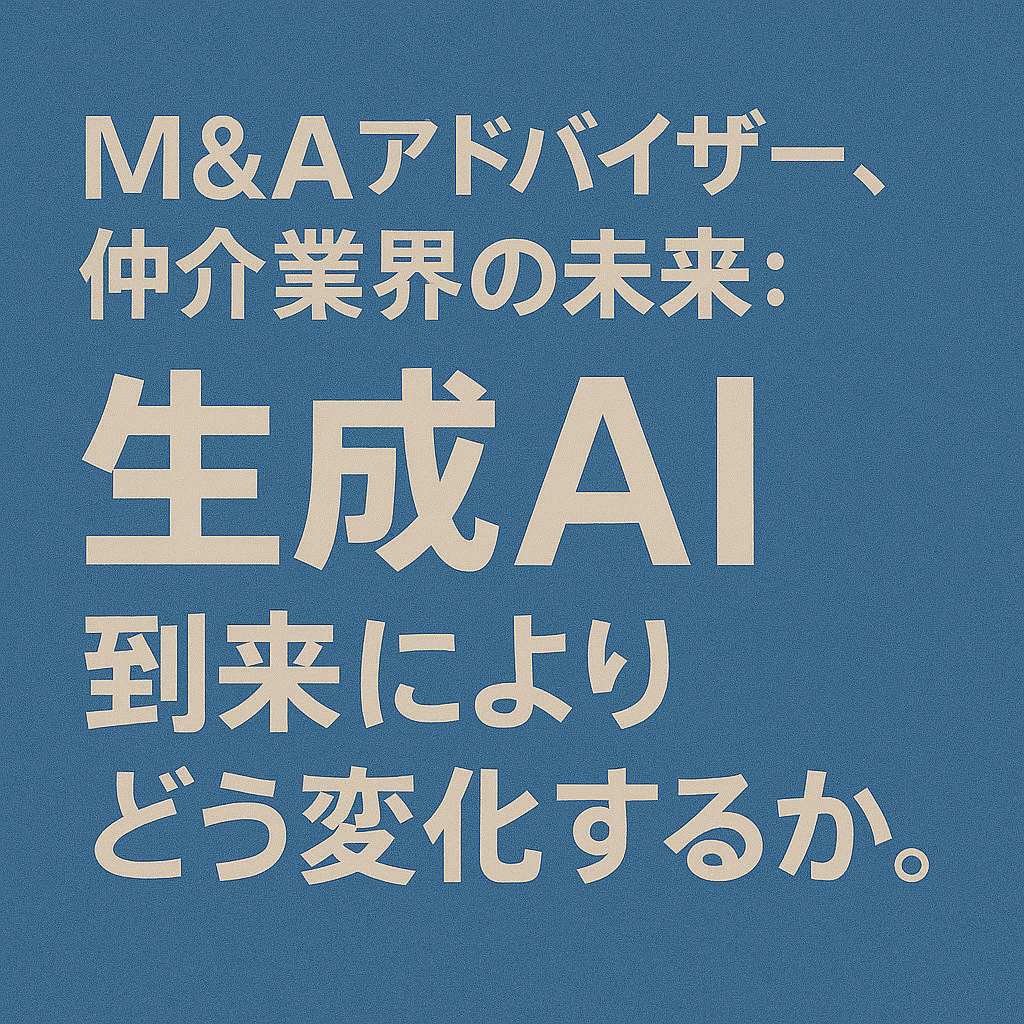
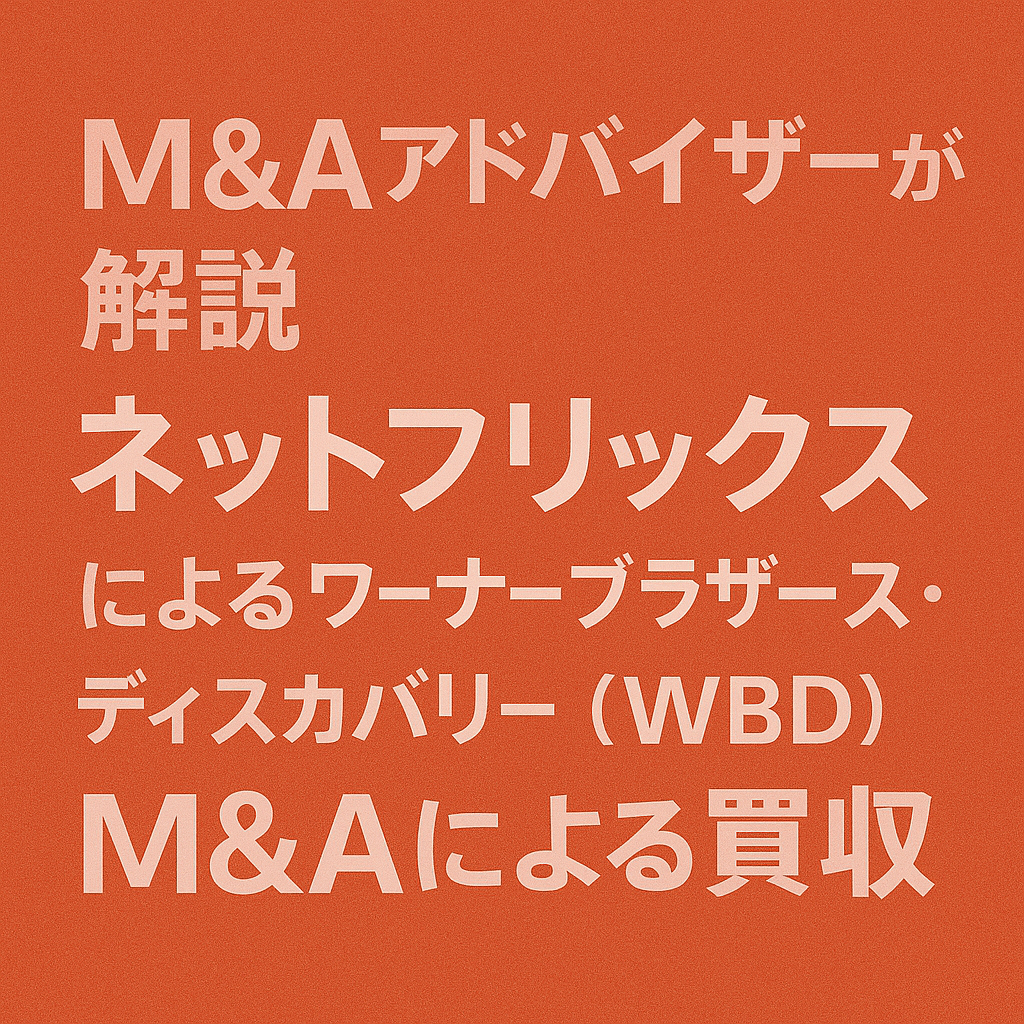
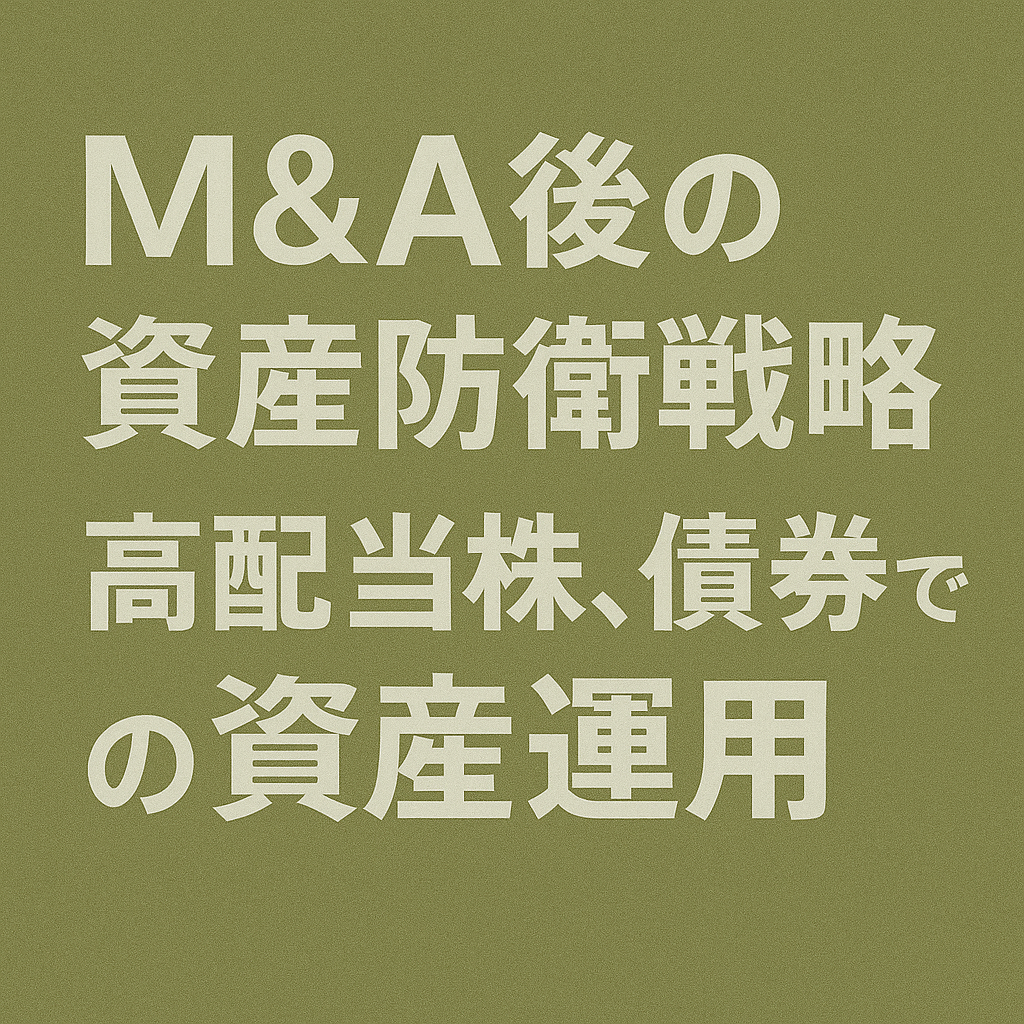
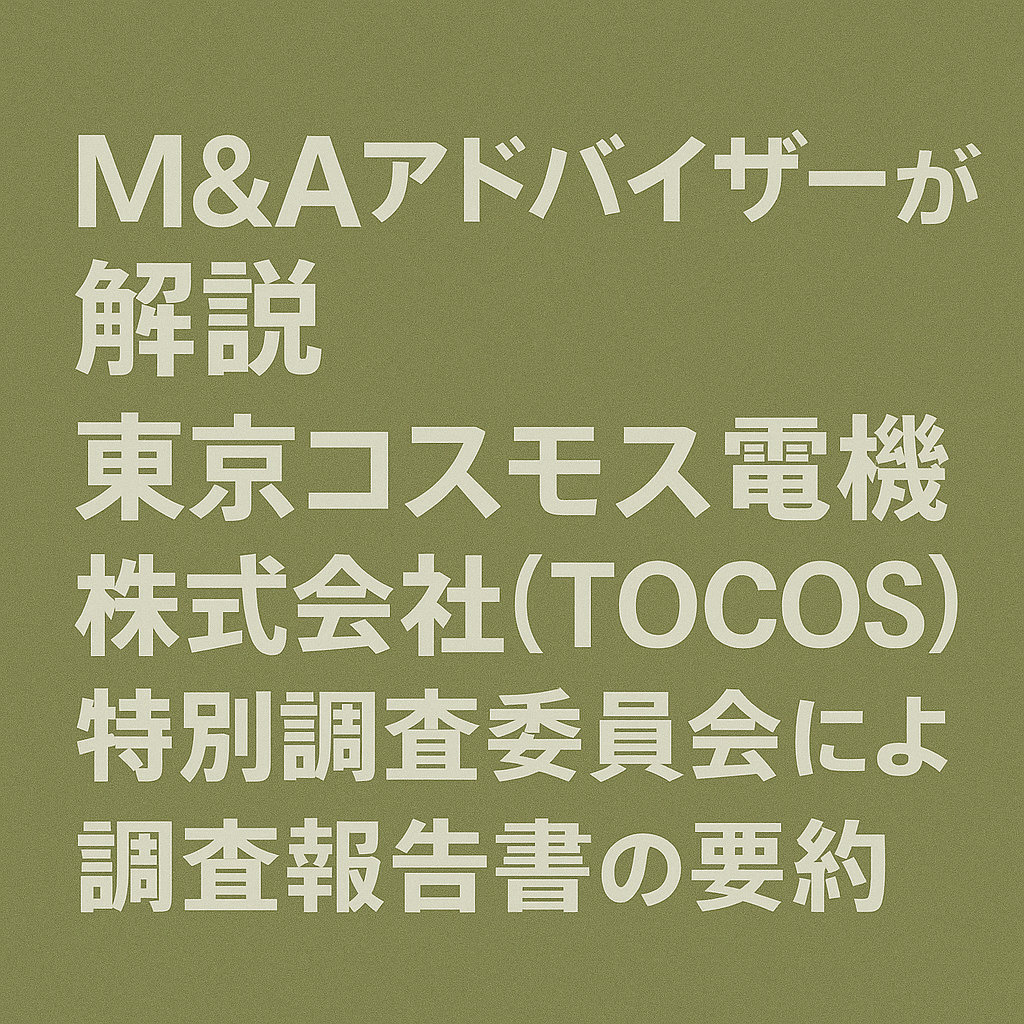
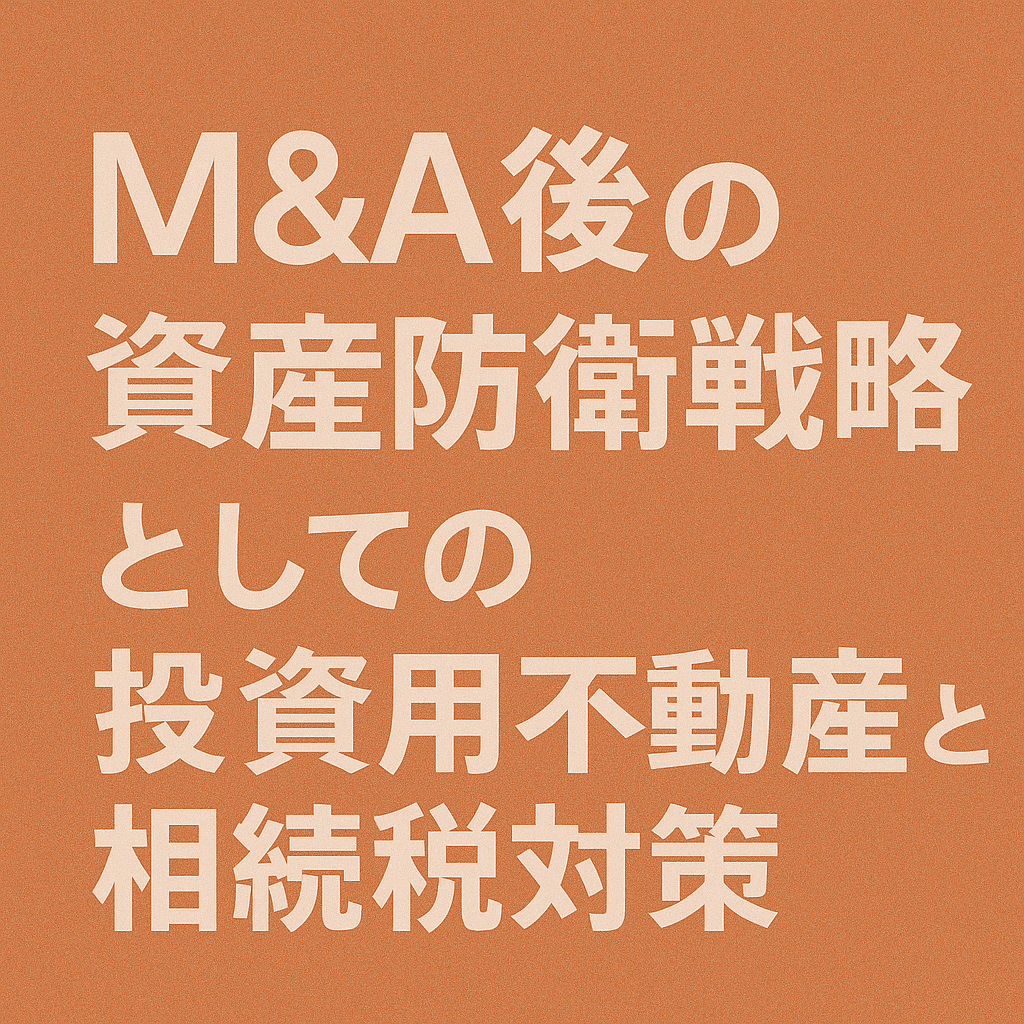
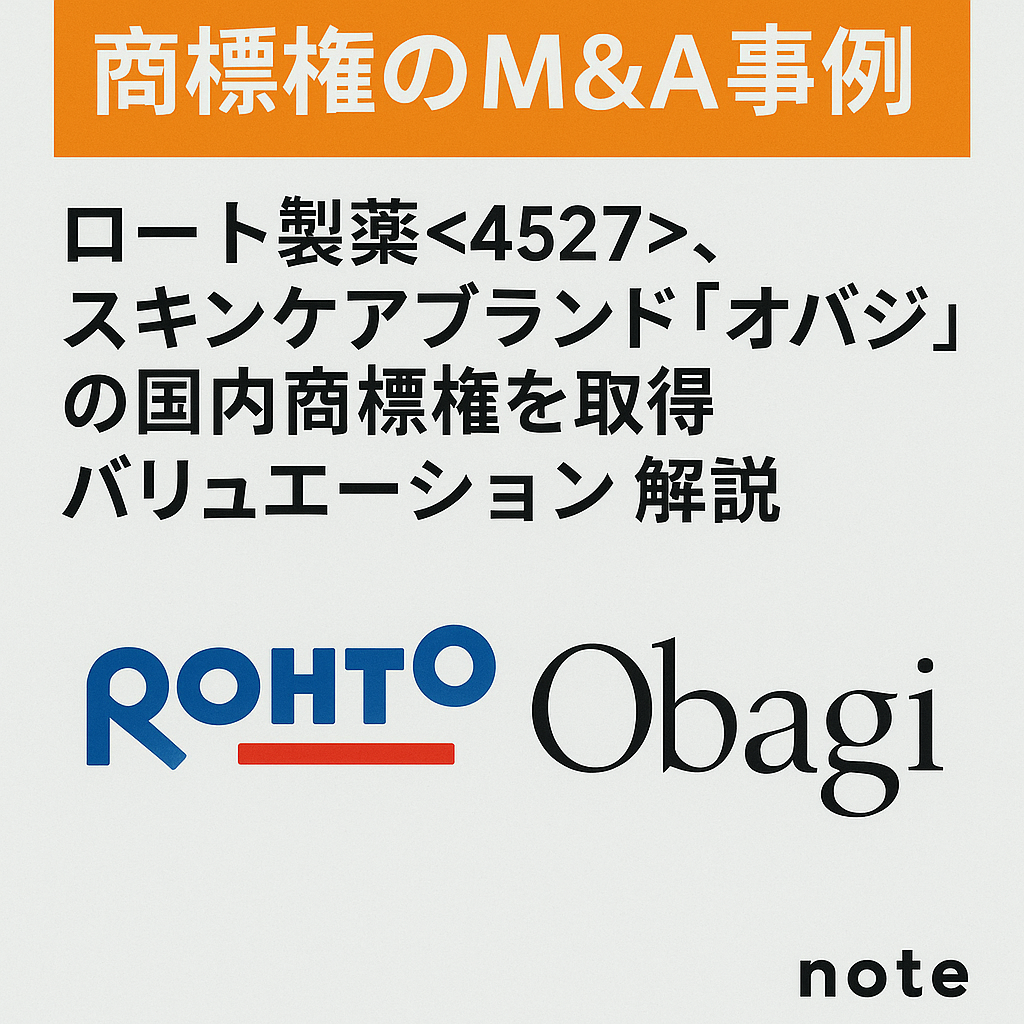
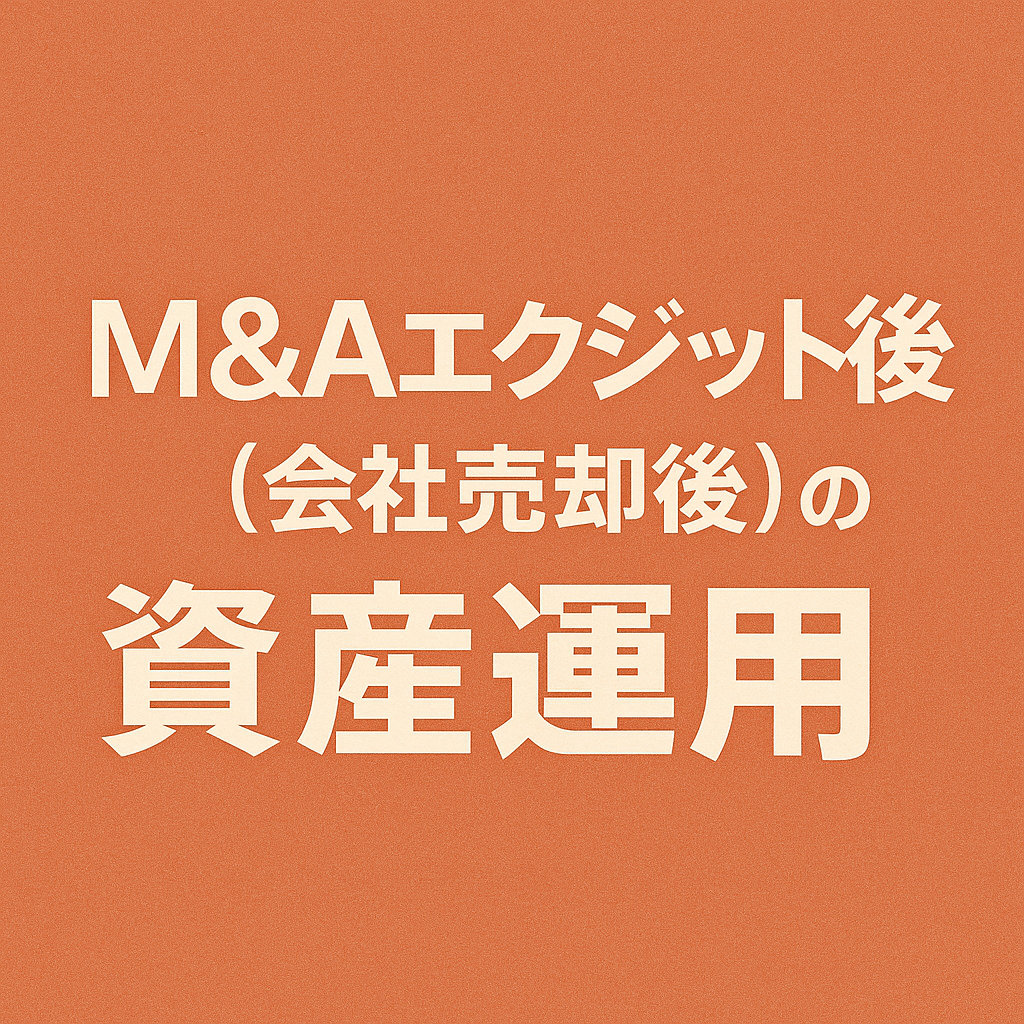
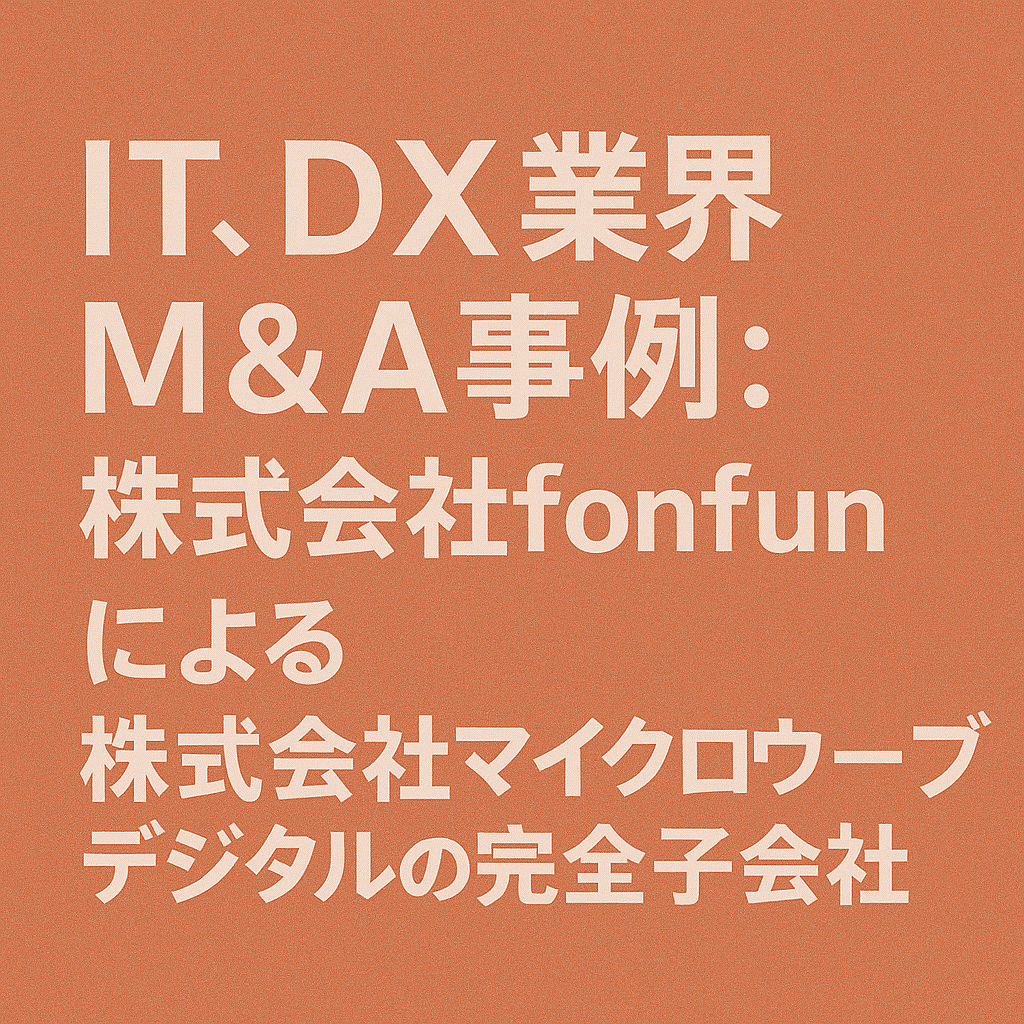

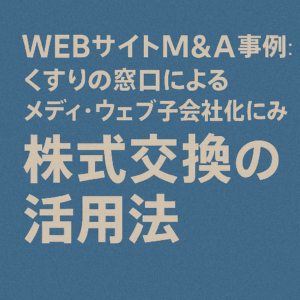
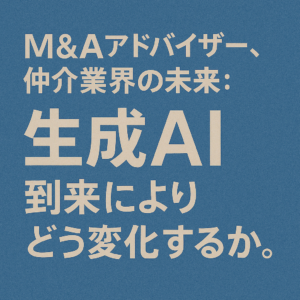
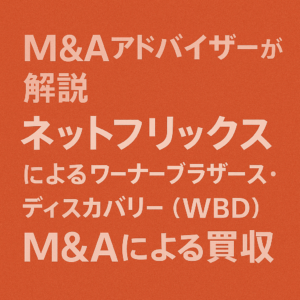
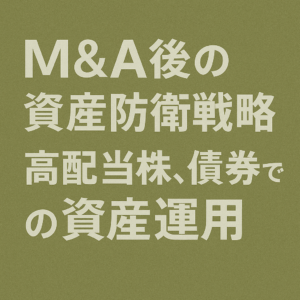
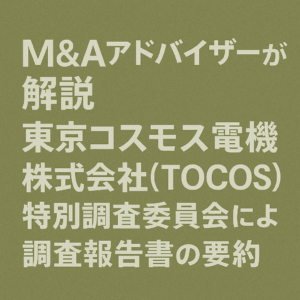
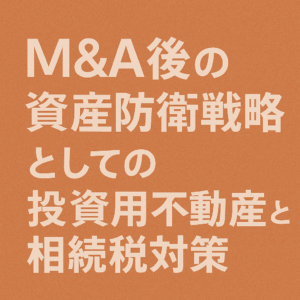
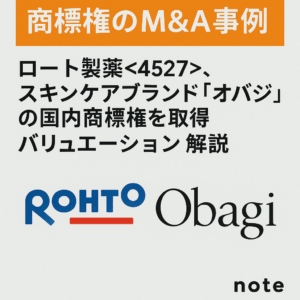
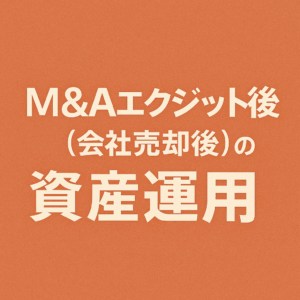
コメント