2025年10月30日、大和ハウス工業株式会社が住友電設株式会社(証券コード: 1949)に対する公開買付け(TOB)の開始を発表しました 。本件は、大和ハウス工業が住友電設を完全子会社化することを目的としたものであり、その買付価格は1株あたり9,760円と設定されています 。この取引は、単に上場企業が非公開化されるというだけでなく、対象会社の親会社(住友電気工業株式会社、所有割合50.66%)との複雑な利害関係を調整し、少数株主の利益を最大化するための精緻なスキームと価格交渉が展開された、M&A実務における注目すべき事例です 。
本記事では、M&Aアドバイザーの視点から、特に「株価算定(バリュエーション)」と「スキームの妥当性」に焦点を当てて詳細に解説いたします。
案件の概要とスキーム
本件は、大和ハウス工業が住友電設の少数株主(所有割合49.34%)が保有する株式をTOBにより取得し、その後、株式併合(いわゆるスクイーズアウト)を行うことで、住友電設を完全子会社化する「二段階買収」の手法を採用しています 。ここまでは一般的なM&Aの手法ですが、本件の最大の特徴は、対象会社の親会社である住友電気工業(以下、住友電工)の処遇にあります。
- ステップ1(TOB): 住友電工は、その保有株式(50.66%)について、大和ハウス工業との間で「不応募契約」を締結しており、TOBには応募しません 。
- ステップ2(TOB後): スクイーズアウト(株式併合)が完了し、株主が大和ハウス工業と住友電工のみとなった後、住友電設自身が住友電工から株式を取得します(=自己株式取得) 。
この一見複雑なスキームこそが、本件の核心である「二段階価格設定」を可能にする鍵となっています。
【本件の核心】二段階価格設定(9,760円 vs 6,877円)のロジック
本件では、株式を売却する株主の属性によって、適用される価格が異なります。
- 少数株主向け(TOB価格): 1株 9,760円
- 親会社・住友電工向け(自己株式取得価格): 1株 6,877
なぜ、このような価格差が設けられたのでしょうか。それは、税務メリットの活用とその配分にあります。
専門用語解説:みなし配当と益金不算入
- みなし配当:会社法上の剰余金配当ではありませんが、法人が自己株式を取得する際、その取得対価が株主の当初の出資額(資本金等の額)を上回る場合、その超過部分は税務上「配当」とみなされます 。これを「みなし配当」と呼びます。
- 益金不算入規定:法人が他の法人から配当(みなし配当を含む)を受け取った場合、二重課税を排除する目的で、その配当金の全部または一部を税務上の利益(益金)に算入しない(=課税されない)制度があります 。特に、100%(あるいは完全支配関係)子会社からの配当は全額が益金不算入となります。
価格算定の仕組み
本件のスキームでは、住友電工は株式譲渡(TOB)ではなく、自己株式取得に応じます。これにより、住友電工が受け取る対価(6,877円/株)の一部に「みなし配当」が発生し、その部分に「益金不算入規定」が適用される見込みです 。結果として、通常の株式譲渡益(売却益全体に課税)よりも税負担が軽減される可能性が高いのです。
公開買付者(大和ハウス工業)は、この税務メリットに着目しました。開示資料によれば、この2つの価格は、以下の等式が成り立つように逆算して設定されています 。
(A)もし住友電工がTOB(9,760円)に応じた場合の税引後手取り額
=
(B)住友電工が自己株式取得(6,877円)に応じ、益金不算入規定の適用を受けた場合の税引後手取り額
このスキームが持つ重要な意義
この設計により、住友電工にとっては、どちらの価格(9,760円または6,877円)で売却しても、最終的な経済的実質(税引後の手取り額)は変わらないことになります 。一方で、買収者である大和ハウス工業から見れば、買収総額の約半分(住友電工持分)を、名目上低い価格(6,877円)で取得できることになります。その結果として生じた買収余力(バジェット)を、すべて少数株主向けのTOB価格(9,760円)に上乗せ・還元することが可能となりました 。
これは、親会社(住友電工)が得られるはずだった税務メリットを、少数株主と公正にシェア(共有)することで、少数株主の利益最大化を図った、極めて高度で洗練されたディール・ストラクチャリングと言えます。
バリュエーション(株価算定)の徹底分析
では、この結果設定されたTOB価格 9,760円は、バリュエーションの観点から妥当なのでしょうか。本件では、公平性を期すために、3つの異なる算定機関(ファイナンシャル・アドバイザー)がそれぞれ独立して株価算定を行っています。
- 公開買付者(大和ハウス)側: みずほ証券
- 対象者(住友電設)側: 野村證券
- 対象者の特別委員会側: 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
各社が採用した主要な算定手法と、その結果(1株あたり価値のレンジ)は以下の通りです。
| 算定機関 | 算定手法 | 算定結果(1株あたり) |
| みずほ証券 | 市場株価基準法 | 6,471円 ~ 7,620円 |
| 類似企業比較法 | 5,393円 ~ 6,867円 | |
| DCF法 | 6,612円 ~ 8,692円 | |
| 野村證券 | 市場株価平均法 | 6,471円 ~ 7,620円 |
| 類似会社比較法 | 4,555円 ~ 7,914円 | |
| DCF法 | 7,262円 ~ 8,675円 | |
| 三菱UFJ証券 | 市場株価分析 | 6,471円 ~ 7,620円 |
| 類似企業比較分析 | 5,180円 ~ 9,191円 | |
| DCF分析 | 7,271円 ~ 9,026円 |
専門用語解説:3つの算定手法
- 市場株価法: 対象者が上場している場合、その市場株価(直近終値や過去1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の平均値)を基準とする、客観性の高い手法です 。
- 類似会社比較法(マルチプル法): 事業内容が似ている他の上場企業の株価が、その会社の利益(PER)や純資産(PBR)、EBITDA(EV/EBITDAマルチプル)の何倍で評価されているかを分析し、対象者に当てはめる手法です 。
- DCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)法: 企業が将来(事業計画に基づき)生み出すと予測されるフリー・キャッシュ・フローを、リスクを反映した割引率で現在価値に割り戻して企業価値を算出する、M&Aで最も重視される手法の一つです 。
TOB価格 9,760円の評価
上記の表から読み取れる最も重要な事実は、最終的なTOB価格である 9,760円 が、3社すべての、すべての算定手法における上限値(Highest Value)すらも大幅に上回っている点です 。例えば、企業の本源的価値を反映しやすいとされるDCF法の上限値は、最も高い三菱UFJモルガン・スタンレー証券の評価でも 9,026円 です 。これを 700円以上も上回る 9,760円という価格は、事業計画上の価値に加え、以下の2つの価値が相当額上乗せされた結果であると分析できます。
- シナジー(相乗効果): 大和ハウスグループとなることで期待される事業拡大(データセンター、半導体工場、海外事業など)の価値 。
- コントロール・プレミアム: 会社の経営権(支配権)を取得するための対価(上乗せ幅)。
また、プレミアム(株価への上乗せ幅)の観点では、以下のようになっています4。
- 公表前日(10/29)終値比: +28.08%
- 過去1ヶ月平均比: +41.16%
- 過去3ヶ月平均比: +43.45%
- 過去6ヶ月平均比: +50.83%
特に過去6ヶ月平均株価に対するプレミアム(+50.83%)は、同種案件の中央値(50.07% )を上回る水準であり 、少数株主に対して十分な売却プレミアムが提供されたと評価できます。
価格交渉の軌跡と特別委員会の役割
この 9,760円という価格は、最初から提示されたものではありません。本件の開示資料は、TOB価格が決定するまでの生々しい交渉の軌跡を、異例なほど詳細に記載しています 。
- 当初提案(9/12): 8,287円(配当なし前提)
- 2回目提案(9/25): 8,287円(中間配当あり前提)
- 3回目提案(10/1): 8,847円
- 4回目提案(10/10): 8,929円
- 5回目提案(10/20): 9,283円
- 最終提案(10/24): 9,760円
この6回にわたる交渉プロセスで中心的な役割を果たしたのが、住友電設が設置した「特別委員会」(独立社外取締役3名、独立社外監査役1名で構成)です 。特別委員会は、少数株主の利益を代弁する機関として、「当初の提案価格は本源的価値に照らして不十分である」との立場から、住友電設の好調な足元の業績(上方修正の可能性 )やM&Aによるシナジー価値を根拠に、大和ハウス工業に対して粘り強く価格の引き上げを要請しました 。
最終的に、当初提案から約18%もの価格上昇(8,287円 → 9,760円)を勝ち取っており 、これは経済産業省の「公正なM&Aの在り方に関する指針」が求める手続きの公正性(アームズ・レングスな交渉)が、実効性をもって機能した好事例と言えます。
アドバイザリー体制と報酬体系の論点
最後に、本件の公正性を担保する「縁の下の力持ち」であるアドバイザーの体制、特にその報酬体系について触れておきます。これはM&A実務において非常に重要な論点です。
- 対象者(住友電設)のFA(野村證券): 報酬に成功報酬を含む 。
- 特別委員会のFA(三菱UFJ証券): 報酬に成功報酬を含まない 。
- 対象者のLA(アンダーソン・毛利・友常): 報酬は時間単位のみで、成功報酬を含まない 。
一般に、M&Aアドバイザーの報酬が「成功報酬型」である場合、取引を成立させること自体がインセンティブとなり、価格交渉などで少数株主の利益よりもディールの成立を優先してしまうのではないか、という利益相反の懸念が指摘されます。
本件では、対象者のFAは成功報酬型である一方、少数株主の利益を直接的に擁護する立場にある特別委員会のFAとリーガル・アドバイザー(LA)の報酬体系から成功報酬が排除されています 。
これは、特別委員会のアドバイザーが取引の成否に経済的に左右されることなく、純粋に「価格の妥当性」と「手続きの公正性」のみを追求できる独立した立場を確保するための、極めて重要な設計です。
結論
大和ハウス工業による住友電設のTOBは、単に高プレミアムな案件というだけでなく、その背後にM&A実務の粋が詰まっています。
- 精緻なスキーム設計: 親会社の税務メリットを少数株主に還元する「二段階価格設定」 。
- 重厚な公正性担保措置: 3つの算定機関の起用と、独立した特別委員会の強力な交渉力 。
- 独立性への配慮: 特別委員会アドバイザーの報酬体系から成功報酬を排除する徹底した利益相反管理 。
これらの要素が組み合わさった結果として提示されたTOB価格 9,760円は、算定レンジを大幅に上回り、かつ粘り強い交渉を経たものであり、少数株主にとって非常に魅力的かつ公正な売却機会を提供するものとして、高く評価できます。
本件は、親会社が関与する上場子会社の非公開化(MBO/TOB)において、少数株主の利益をいかに保護し、最大化するかを示す一つの理想的なモデルケースとして、今後のM&A実務に大きな示唆を与えるものとなるでしょう。
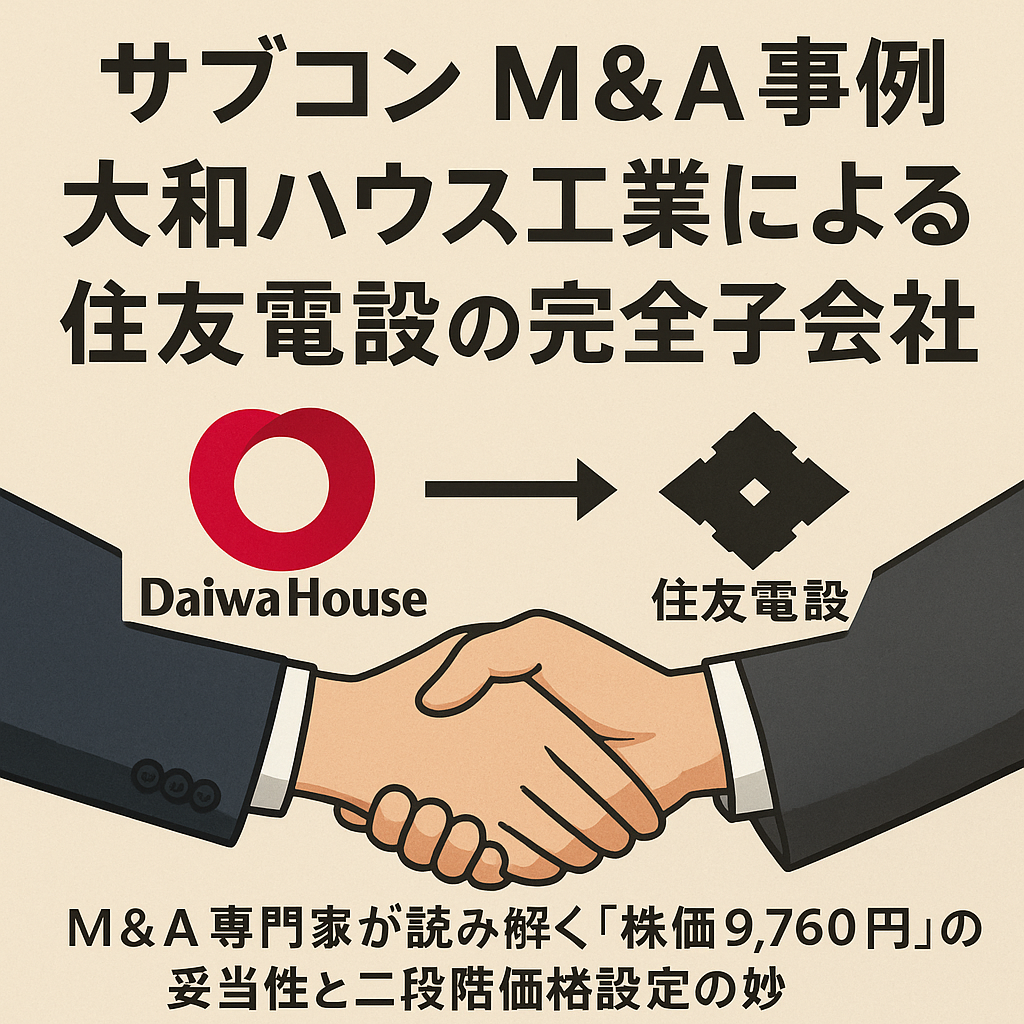



















コメント