2025年11月、ITエンジニア支援市場で注目すべきM&A(企業の合併・買収)が公表されました。フリーランスエンジニアのマッチングサービスを展開するTWOSTONE&Sons(以下、T&S社)が、システムエンジニアリングサービス(SES)を手掛けるFAM(以下、FAM社)を子会社化するという発表です。
M&Aアドバイザーの視点から、このディール(取引)を「バリュエーション」と「スキーム」という2つの主要な軸で深掘りし、その戦略的意義と実務的な論点を、専門用語の解説を交えながら詳細に解説いたします。
1. M&Aの背景:なぜ「今」、T&S社はFAM社を選んだのか
M&Aの分析は、常に「Why(なぜ)」から始まります。本件の核心は、現代の日本経済、特にIT業界における最大の経営課題である「高度IT人材の確保」にあります。
- T&S社(買手)の戦略: 同社の中核事業は「フリーランスエンジニアと企業のマッチング」です。これは、企業がプロジェクト単位で即戦力人材を求めるニーズに応えるものです。しかし、このビジネスモデルは「登録するエンジニアの数と質」に大きく依存します。市場が拡大すればするほど、競合他社との人材獲得競争が激化します。
- FAM社(売手)の強み: 一方、FAM社はSES(ITエンジニアを顧客企業に常駐させるサービス)を営みつつ、特に「エンジニア未経験者の採用・育成」に独自のノウハウを持つとされています。
この組み合わせが意味するものは明確です。T&S社は、「即戦力(フリーランス)」に加えて、「育成途上(FAM社の正社員エンジニア)」という新たな人材パイプラインを手に入れることができます。
FAM社が持つ「育成ノウハウ」は、T&S社のプラットフォームと融合することで、未経験者をフリーランスとして活躍できるレベルまで引き上げる「教育機能」として昇華される可能性があります。これは、自社で人材の「供給源」を持つことに他ならず、極めて強力なシナジー(相乗効果)と言えます。
2. M&Aの核心:「企業価値評価(バリュエーション)」の技術
M&Aにおいて最も重要なプロセスの一つが、対象企業の「値決め」、すなわちバリュエーションです。これは「買手」と「売手」が、客観的な根拠に基づき、双方が納得できる「取引価格」のレンジ(範囲)を探る作業です。
(1) バリュエーションの3つのアプローチ
企業の価値を測る手法は、大きく以下の3つに分類されます。専門家は、どれか1つに依存するのではなく、複数の手法を組み合わせて多角的に価値を分析します。
① インカム・アプローチ(Income Approach)
将来その企業が生み出すであろうキャッシュフロー(現金)や利益に着目し、それを「現在価値」に割り引いて評価する手法です。理論的に最も正当化されやすいアプローチです。
- 代表的手法:DCF法 (Discounted Cash Flow)
- 企業の将来の事業計画に基づき、将来のフリー・キャッシュフロー(FCF)を予測します。
- そのFCFを、WACC(加重平均資本コスト)と呼ばれる割引率で「現在」まで割り引いて、事業価値(EV)を算出します。
- WACC (ワック) とは: 企業が事業を運営するために調達する「株主資本(自己資本)」と「負債(他人資本)」にかかるコストを加重平均したものです。M&Aの文脈では、買収対象のリスクを反映した「期待収益率」として機能します。
② マーケット・アプローチ(Market Approach)
評価対象の企業と「類似する上場企業」や「類似するM&A取引」と比較して、相対的な価値を評価する手法です。市場の客観的な評価を反映しやすいのが特徴です。
- 代表的手法:類似会社比較法 (Comps / Multiples)
- 上場している類似企業(本件であれば、他のSES企業やIT人材派遣企業)を複数選びます。
- それらの企業の株価が「利益(PER)」や「EBITDA(EV/EBITDA倍率)」の何倍で取引されているかを分析し、その「倍率(マルチプル)」をFAM社の財務数値に適用します。
- EBITDA (イービットディーエー) とは: 営業利益に、減価償却費(実際のキャッシュ支出を伴わない費用)を加えたもので、企業が本業で稼ぐ「現金創出力」を測る指標として多用されます。
③ コスト・アプローチ(Cost Approach)
企業の「純資産(資産から負債を引いたもの)」に着目する手法です。いわば、その企業を「今、解散させたらいくら残るか」という清算価値的な側面から評価します。
- 代表的手法:簿価純資産法 / 時価純資産法
- 貸借対照表(B/S)上の純資産をベースにします。
- ただし、M&Aの実務では、B/Sに記載の「簿価」ではなく、土地や有価証券などを「時価」で評価し直した「時価純資産」を基準とすることが一般的です。
(2) FAM社のケース:公表情報から読み解くバリュエーション
今回のディールで公表されている情報を整理してみましょう。
- FAM社の財務(2024年10月期)
- 売上高:4億8900万円
- 営業利益:2800万円
- 純資産:4800万円
- 取引価額
- 取得価額:1億3700万円(これで株式80%を取得)

ここから、FAM社全体の「100%の株式価値」を逆算してみます。
FAM社の100%株式価値(推計): 1億3700万円 ÷ 80% = 約1億7125万円
T&S社は、FAM社全体を「約1億7100万円」の価値と評価したと推察できます。では、この「1億7100万円」は、前述のバリュエーション手法に照らしてどう評価できるでしょうか。
① コスト・アプローチ(純資産)との比較
- FAM社の純資産:4800万円
- 推計された株式価値:1億7125万円
- PBR(株価純資産倍率)に類似する倍率: 1億7125万円 ÷ 4800万円 = 約3.57倍
これは、解散価値(純資産)の約3.6倍の価格で取引されたことを意味します。この「差額」こそが、M&Aの核心である「のれん」の源泉です。
② インカム/マーケット・アプローチ(利益)との比較
- FAM社の営業利益(EBITに近い):2800万円
- 営業利益倍率(EV/EBIT倍率の簡易計算): 1億7125万円 ÷ 2800万円 = 約6.1倍 (※厳密には株式価値と事業価値(EV)は異なりますが、ここでは中小企業M&Aで多用される簡易的な倍率として計算します)
SES業界やIT人材関連のM&Aにおいて、営業利益の6倍程度という水準は、市況や企業の成長性にもよりますが、十分に合理的(むしろ堅実)な範囲内にあると筆者は評価します。
(3) M&Aで最も重要な概念:「のれん(Goodwill)」とは
バリュエーション分析で最も重要な示唆は、「のれん」の存在です。
のれん(Goodwill)とは: 買収対価が、買収される企業の「時価純資産」を上回る部分(超過額)を指します。 これは、帳簿には載らない「超過収益力」や「無形の資産価値」に対する対価です。
今回のケースで「のれん」の概算額を計算してみましょう。
「のれん」の概算: 推計株式価値(1億7125万円) – 純資産(4800万円) = 約1億2325万円
T&S社は、FAM社の「帳簿上の価値(4800万円)」に、約1億2300万円もの「無形の価値」を上乗せして支払ったことになります。この「のれん」の正体こそが、FAM社が持つ「未経験者を採用・育成する独自ノウハウ」「既存の顧客基盤」「優秀なエンジニア従業員」そして何より、T&S社の事業と組み合わさることで生まれる「シナジー(将来の収益拡大)」への期待です。
M&Aは、単に過去の実績(純資産)を買うのではなく、未来の可能性(のれん)に投資する行為なのです。
3. プロが注目する「M&Aスキーム」の巧みさ
本件は、その「買い方(スキーム)」においても非常に洗練された設計がなされています。
公表されたスキーム:
- 2025年12月25日: FAM社の株式80%を取得(対価:1億3700万円)
- 2025年12月26日: 残る20%を「株式交換」で取得し、完全子会社化
この「2段階取得(Two-Step Acquisition)」、特に2段階目で「株式交換」という手法を用いている点が、実務家としての注目ポイントです。
(1) 「株式交換(Kabushiki Kokan)」とは
株式交換とは: 買収(親)会社が、対象(子)会社の株主から、その保有する株式を「現金」ではなく「自社(親会社)の株式」を対価として交付(交換)し、買い取る手法です。 これにより、子会社を100%(完全)子会社化することが可能になります。
(2) なぜこのスキームが選ばれたのか?
この80%(現金) + 20%(株式交換)というスキームには、買手と売手の双方にとって非常に合理的な理由があります。
① 売手(FAM社オーナー)側のメリット
- 税制上の優遇(課税の繰延べ): これが最大の理由の一つと推察されます。通常、株式を売却して現金を得ると、その売却益(譲渡益)に対して約20%のキャピタルゲイン税が課税されます。 しかし、一定の要件(組織再編税制)を満たす「適格株式交換」の場合、FAM社オーナーは、対価として「T&S社の株式」を受け取る限り、売却益への課税が将来T&S社の株式を売却する時まで繰り延べられます。売手にとって、手取り額を最大化する上で極めて有利な手法です。
- 買手(T&S社)の成長への参加: FAM社オーナーは、売却後も「T&S社の株主」として、両社が一体となって生み出すシナジー(企業価値の向上)の恩恵を引き続き享受できます。これは、売却後も経営にコミットする際の強力なインセンティブ(動機付け)となります。
② 買手(T&S社)側のメリット
- 現金支出(キャッシュアウト)の抑制: 100%を現金で買収する場合、推計1億7100万円の現金が必要でした。しかし、本スキームでは、まず1億3700万円(80%)の支出で経営権(コントロール)を確保し、残りの20%は自社の株式(現金支出なし)で取得できます。 上場企業とはいえ、手元流動性を確保しつつ大型のM&Aを遂行する上で、株式交換は非常に有効な手段です。
- 完全子会社化(100%支配)の実現: 80%の取得(子会社化)で経営権は握れますが、20%の少数株主が残ると、将来の迅速な経営判断(例:T&S社との合併)において、少数株主保護の手続きが煩雑になる可能性があります。 株式交換を用いて最初から100%(完全)子会社化することで、T&S社はFAM社をグループの一部として完全に一体化させ、シナジーの創出をスピーディに進めることができます。
このように、本件のスキームは、売手の税務メリットとインセンティブを考慮しつつ、買手のキャッシュ負担と経営の自由度を両立させる、非常に実務的かつ合理的な設計と言えます。
4. 結論:未来の価値に投資する、洗練された戦略的M&A
TWOSTONE&SonsによるFAMの子会社化は、単なる企業の買収劇ではありません。
- バリュエーションの観点: FAM社の純資産(4800万円)に対し、100%換算で約1億7100万円という評価額が提示されました。この差額(のれん)約1億2300万円は、FAM社が持つ「エンジニアの育成ノウハウ」という無形の資産と、T&S社との「シナジー」に対する明確な投資です。
- スキームの観点: 「80%現金 + 20%株式交換」という2段階取得は、売手オーナーの税務メリットとインセンティブに配慮しつつ、買手のキャッシュアウトを抑え、完全なグループ一体化を迅速に実現する、極めて洗練された手法です。
本件は、IT業界における人材獲得競争の激化を背景に、M&Aがいかに企業の構造的な課題を解決し、未来の成長ドライバーを「買う」ための有効な戦略ツールであるかを鮮やかに示しています。M&Aは、その価格(バリュエーション)と手法(スキーム)にこそ、経営者の戦略とビジョンが最も色濃く反映されるのです。






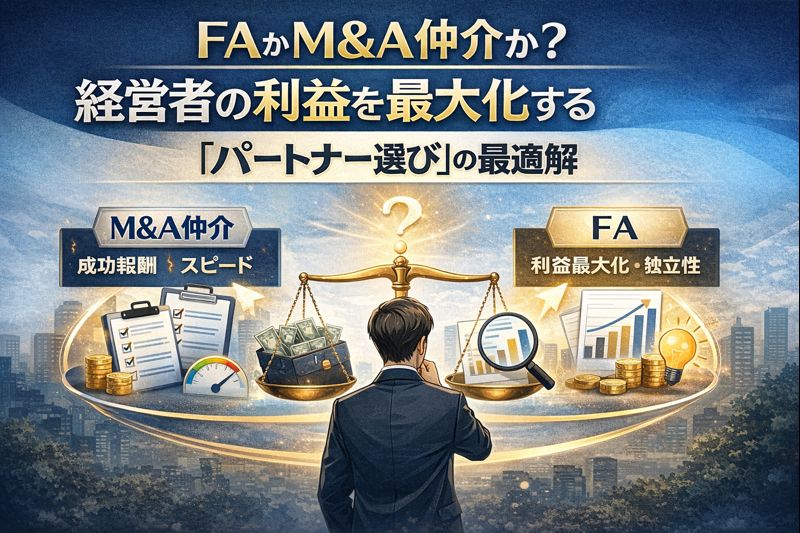
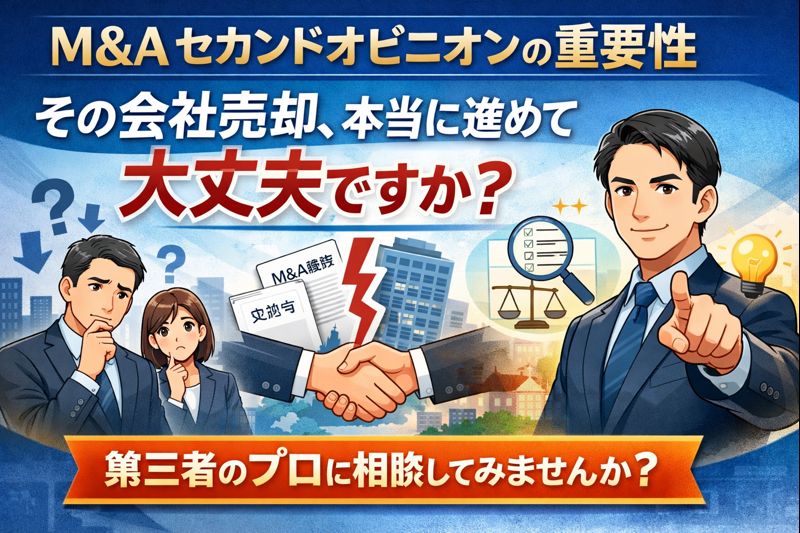

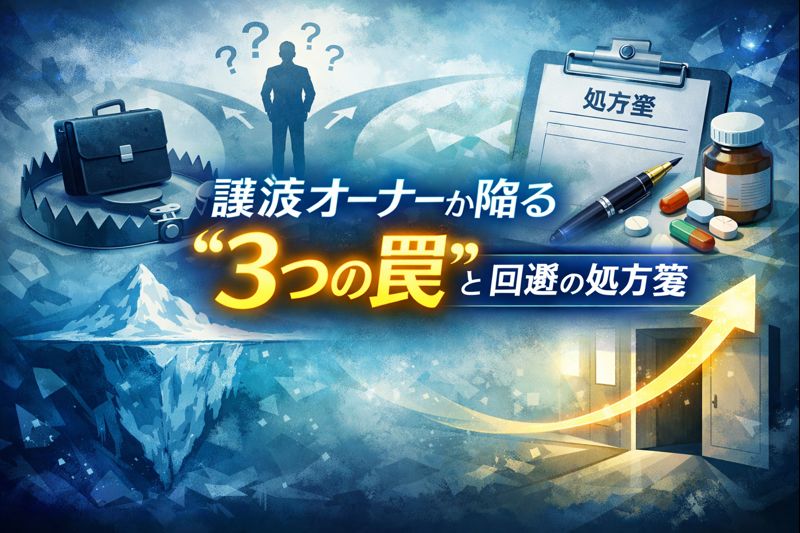

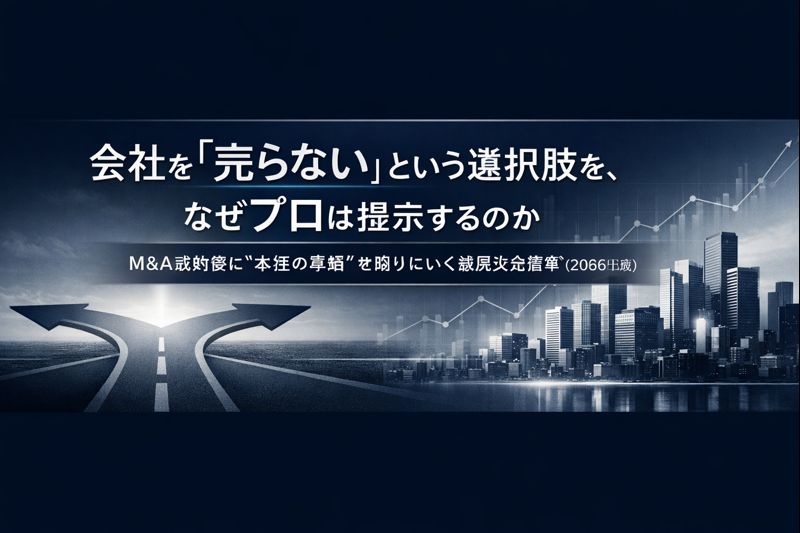


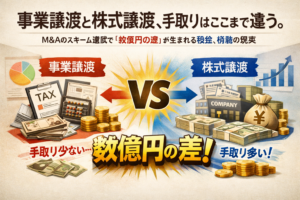

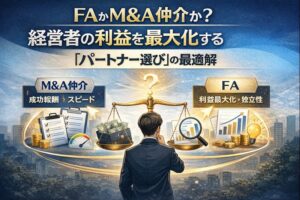


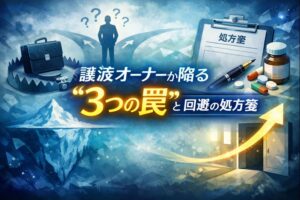
コメント