M&Aの現場において、多くのオーナー様が最初に抱かれる疑問は「私の会社はいくらで売れるのか?」という点です。しかし、我々アドバイザーやプロの投資家(プライベート・エクイティ・ファンド等)は、少し異なる角度から問いを立てます。「この会社が生み出す将来のキャッシュフローは、現在価値に直すといくらか?」。
M&Aにおけるバリュエーションとは、単なる電卓計算ではありません。買い手がその会社を手に入れた後に描く「未来のストーリー」を数値化したものです。本稿では、簿記上の数字だけでは見えない「企業価値の正体」を解き明かしていきます。
第1章:バリュエーションの3つの基本地図
まず、専門家が用いる評価手法の全体像を整理しましょう。これらは「地図」のようなもので、どのルートで山頂(適正価格)を目指すかによって使い分けます。
1. コストアプローチ(純資産法)
企業の保有する資産(土地、建物、現金など)から負債を引いた「純資産」を価値とする方法です。
- 中小企業の実務: 多くのオーナー様にとって馴染み深いのがこの手法です。「修正簿価純資産法」として、時価修正した純資産に営業権(のれん)を数年分足して算出するケースが日本の中小M&Aでは一般的です。
- プロの視点: 実は、我々はこの手法を単独ではほとんど重視しません。なぜなら、「工場がいくらで売れるか」よりも「その工場でいくら稼げるか」に興味があるからです。解散価値としては参考になりますが、継続企業の価値(ゴーイング・コンサーン)を表すには不十分です。
2. マーケットアプローチ(マルチプル法)
上場している類似企業や、過去の類似取引事例と比較して価値を決める方法です。
- 実務の王道: 最も納得感があり、頻繁に使われるのが「EBITDAマルチプル法」です。
- プロの視点: 「この業界ならEBITDAの3倍〜5倍が相場」といった相場観(マルチプル)を用います。客観性が高く、交渉のメインツールとなります。
3. インカムアプローチ(DCF法)
将来生み出すキャッシュフローを、リスクに応じた割引率で現在の価値に割り引いて計算する方法です。
- 理論的支柱: ファイナンス理論において最も正統な手法です。
- プロの視点: 投資銀行やファンドが最も重視するのがこれです。「事業計画」の確度と「リスク」を精緻に織り込むためです。
第2章:実務の共通言語「EBITDA」と「マルチプル」
プロの投資家と対話する際、避けて通れないのがEBITDA(イービットディーエー)です。
なぜ「営業利益」ではなく「EBITDA」なのか?
EBITDA(利払い・税引き・償却前利益)は、簡単に言えば「会社が事業活動で稼ぎ出す、キャッシュベースの本業の儲け」です。
計算式:
EBITDA=営業利益+減価償却費
会計上の「営業利益」は、設備投資の多寡(減価償却費)によって大きく変動してしまいます。多額の設備投資をした年は利益が減りますが、実際の現金を稼ぐ力(キャッシュフロー創出力)が落ちたわけではありません。 国や会計基準、設備投資方針の違いを排除し、「純粋な稼ぐ力」を比較するために、プロは必ずEBITDAを見ます。
マルチプルの魔法:EV/EBITDA倍率
「御社の価値はEBITDAの5倍です」と言われたとき、それは何を意味するのでしょうか? これは、「買収にかかったコスト(EV:事業価値)を、その会社の稼ぎ(EBITDA)で回収するのに何年かかるか」という指標です。
- マルチプルが高い(8倍以上など): 「高成長が見込める」「リスクが低い」「非常に希少な技術がある」ため、回収に時間がかかっても欲しい。
- マルチプルが低い(3〜4倍など): 「斜陽産業である」「競争が激しい」「特定のオーナーに依存している」ため、早期に回収しないと危険。
一般的に、中小企業のM&Aでは3倍〜5倍程度、中堅・上場企業レベルや成長IT企業では8倍〜15倍以上つくこともあります。この「倍率の差」こそが、買い手が感じている「期待とリスク」の差なのです。
第3章:プロ投資家の脳内~DCF法とIRRの深淵~
ここからが本稿の核心です。なぜプロの投資家(PEファンドなど)は、DCF法を重視し、時にオーナー様が思うよりもシビアな価格を提示するのでしょうか。
1. 時間は金なり(Time Value of Money)
DCF法(Discounted Cash Flow)の基本思想は、「今日の1億円は、10年後の1億円よりも価値がある」というものです。 10年後に確実に1億円もらえる権利があったとして、それを今日いくらで買うか? もしリスクがゼロなら9000万円で買うかもしれませんが、もしその会社が倒産するリスクがあれば、5000万円、あるいは3000万円でしか買わないでしょう。この「将来の現金を、リスクに応じて割り引いて現在の価値にする」計算こそがDCFです。
2. 投資家の規律:IRR(内部収益率)
プロの投資家は、出資者(年金基金や機関投資家)からお金を預かっています。彼らには「最低でも年利20%のリターンを出す」といった目標(ハードルレート)があります。これがIRR(Internal Rate of Return)の目線です。
例えば、ある会社を10億円で買収する場合、彼らの頭の中では以下のようなシミュレーションが瞬時に行われます。
- 5年後にこの会社を売却(Exit)する時、恐らく20億円で売れるだろう。
- その間のキャッシュフローと合わせると、年利(IRR)は25%になる。
- 「よし、合格ラインだ。10億円で入札しよう」
逆に言えば*「年利20%を達成できないような高値では、絶対に入札できない」という厳格な規律があります。これが、感性や「なんとなくの相場」で動く個人投資家との決定的な違いです。
3. 割引率(WACC)という名の「恐怖指数」
DCF法で計算する際、将来の利益を割り引くためのレートをWACC(加重平均資本コスト)と呼びます。 難しい数式は割愛しますが、要点は一つです。 「買い手が感じるリスクが高ければ高いほど、割引率は高くなり、現在の企業価値は下がる」ということです。
- 社長がいないと回らない会社
- 大口取引先1社に依存している会社
- 法務コンプライアンスが未整備な会社
これらは全て「リスク」とみなされ、割引率を跳ね上げます。結果として、どんなに足元の利益が出ていても、バリュエーションは低くなります。
第4章:中小企業M&Aにおける「ノーマライズ(正常化)」の魔術
実務において、バリュエーションを劇的に変えるテクニックがあります。それが「修正EBITDA(ノーマライズドEBITDA)」の算出です。中小企業、特にオーナー企業では、会計上の利益が実態よりも低く出ていることが多々あります。これらを「M&A後の姿」に合わせて修正します。
- 役員報酬の修正: オーナー社長が年間5,000万円の報酬を取っているが、後任の雇われ社長なら1,500万円で済む場合。差額の3,500万円は利益として加算できます。
- 私的経費の排除: 高級外車、過度な接待交際費、家族従業員への給与など、事業に直接関係のない経費。これらも全て利益(EBITDA)に足し戻します。
- 一時費用の排除: 突発的な修繕費や退職金など。
この「磨き上げ」作業を行うことで、決算書上の営業利益が1億円でも、実力値(修正EBITDA)は2億円になることも珍しくありません。マルチプルが5倍だとすれば、これだけで企業価値は5億円も跳ね上がります。 売り手のアドバイザーとして最も腕が鳴るのは、この「隠れた価値」を論理的に証明し、買い手に認めさせる瞬間です。
第5章:プロが教える「バリュエーションを高める」ための処方箋
M &Aは「結婚」に例えられますが、準備に関しては「就職活動」や「アスリートの肉体改造」に近いです。高く評価されるためには、買い手(投資家)が見ているスコアボードを意識する必要があります。
1. 「誰でも回せる仕組み」を作る(組織の非属人化)
特定の職人や社長個人のカリスマ性で持っている会社は、買い手にとってリスクの塊です。「社長がいなくなったら価値ゼロ」と判断されれば、DCFの割引率は極大化します。マニュアル化、権限委譲を進めることは、直接的にバリュエーション向上につながります。
2. 「質」の高い利益にする(ストックビジネス化)
同じ1億円の利益でも、単発の請負工事で稼ぐ1億円と、毎月の保守契約(サブスクリプション)で稼ぐ1億円では、後者の方が圧倒的に高く評価されます(マルチプルが高くなります)。将来の予測可能性が高いからです。
3. コンプライアンスと会計の透明化
簿外債務の可能性や、未払い残業代のリスクは、最終価格からの減額要因(ディスカウント)になります。月次決算の早期化や労務管理の適正化は、守りのようでいて、実は最強の「価格防衛策」です。
第6章:M&Aスキームによる価値の違い
最後に、スキーム(手法)による受取額の違いにも触れておきましょう。
- 株式譲渡: 最も一般的です。会社そのものを株主が変わる形で引き継ぎます。売り手(個人)への課税は約20%(分離課税)で済むため、手取り額(ネットキャッシュ)が最大化しやすいメリットがあります。
- 事業譲渡: 会社の中の特定の事業だけを売ります。会社(法人)にお金が入るため、法人税(約30%〜)がかかります。さらに、そのお金を個人オーナーが配当などで受け取る際に再度課税されるため、税務上の効率は株式譲渡に劣るケースが多いです。しかし、簿外債務のリスクを切り離せるため、買い手が好む場合があります。
プロのアドバイザーは、「表面的な売却価格」ではなく、「税引後の手取り額」が最大になるスキームを提案します。
おわりに:バリュエーションは「対話」である
ここまで、ロジックと数字の話をしてきましたが、最後に一つだけ、実務家として大切なことをお伝えします。
バリュエーション算定書(Valuation Report)に出る数字は、あくまで「理論値」であり「出発点」です。 実際のM&Aの成約価格は、「売り手の想い」と「買い手の夢」が交差する点で決まります。どんなにDCF法で低い数字が出ても、買い手が「この技術と自社の販路を組み合わせれば、世界が獲れる(シナジー効果)」と確信すれば、相場を遥かに超えるプレミアム価格が提示されることがあります。これを「戦略的価値」と呼びます。
【Next Step】
貴社の決算書(直近3期分)をもとに、簡易的ながらプロの視点で「修正EBITDA」を算出し、現実的なバリュエーションレンジと、価値向上のための具体的なポイントを診断させていただきましょうか?
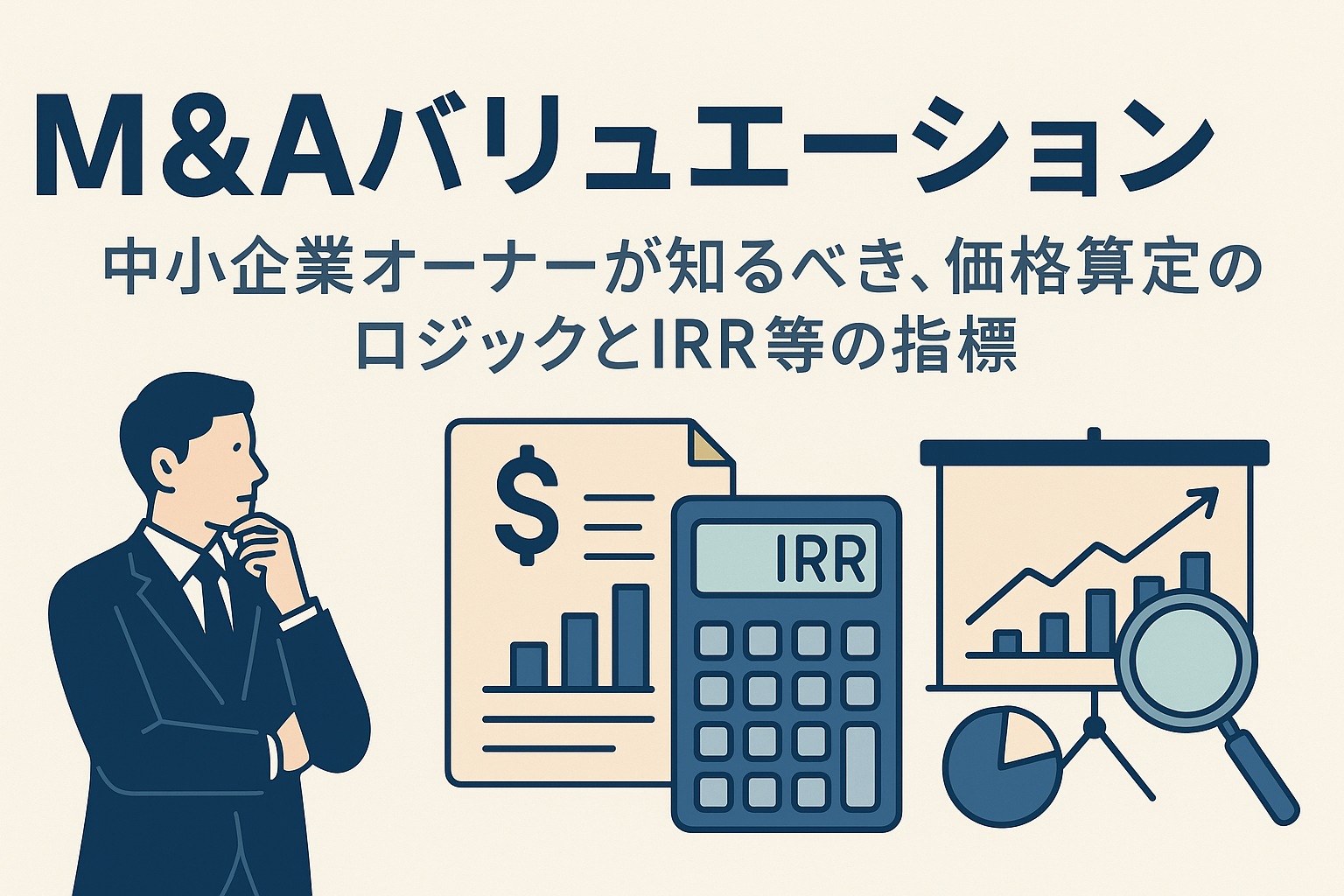




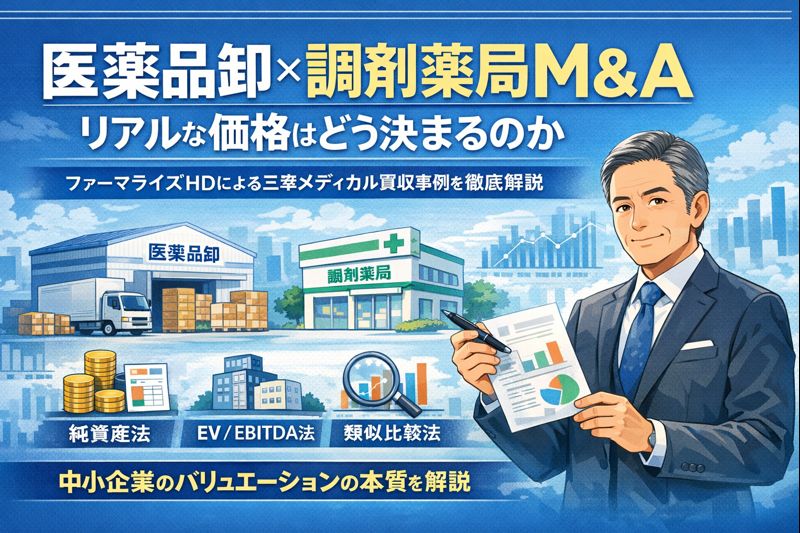


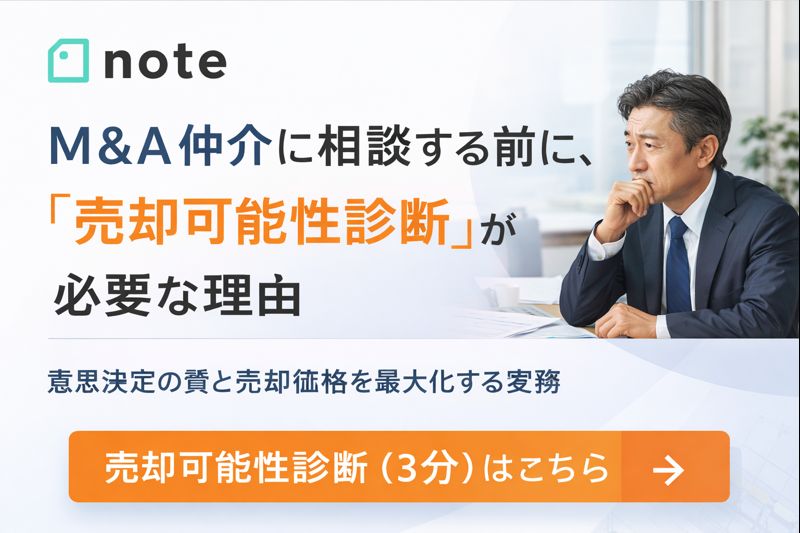


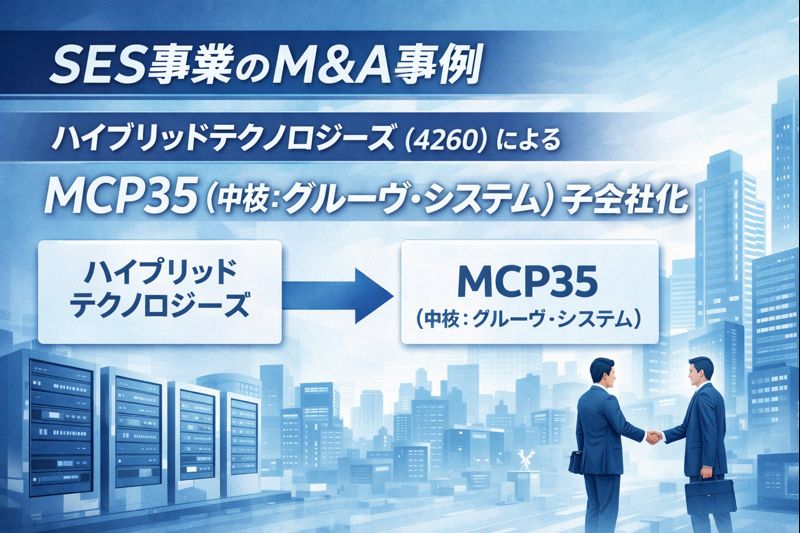






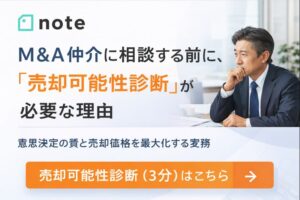

コメント