「節税」の成功が、M&Aの「失敗」を招くパラドックス
多くのオーナー経営者様にとって、決算期の最大の関心事は「いかに利益を圧縮し、税金を減らすか」であったはずです。しかし、会社売却(Exit)を決断された瞬間から、その「節税脳」を完全にリセットしていただく必要があります。
なぜなら、通常の経営とM&Aとでは、ゴールの計算式が真逆だからです。
過度な節税は、M&Aにおける評価指標である利益(EBITDA)を毀損させます。手元の300万円の税金を惜しむあまり、数億円単位の「企業価値」をドブに捨てる可能性があります。
本稿では、M&A実務の最前線で使われるバリュエーションのロジックに基づき、PL(損益計算書)とBS(貸借対照表)をいかに「翻訳」し直すべきか、法務・税務の観点から解説します。
第1章:バリュエーションの基本構造と「税効果」の罠
まずは、企業価値がどのように算出されるか、その基本式をご覧ください。
株式価値 = 正常収益力 × EV/EBITDA倍率 + ネットキャッシュ
ここには、実務家だけが知る「税効果(Tax Effect)の二重構造」が存在します。
- 左辺(事業価値)は「税引前」で勝負する:EBITDA(金利・税金・償却前利益)には税金が含まれていません。ここでは「税金を払ってでも利益を出す」ことが、マルチプル(倍率)の効果で価値を5倍〜10倍に跳ね上がらせます。
- 右辺(実質現預金)は「税引後」で評価される:一方で、会社に残る現金や換金可能な資産(ネットキャッシュ)は、換金時にかかる税金を差し引いた「税引後(After-tax)」で厳しく評価されます。
この「PLはアクセル(税引前)」、「BSはブレーキ(税引後)」という感覚を持つことが、テクニカルな準備の第一歩です。
第2章:PL(損益計算書)の適正化 ~EBITDAを「あるべき姿」に戻す~
買い手が見るのは、表面上の当期純利益ではなく、「正常収益力(Normalized EBITDA)」です。節税のために歪められた利益を、本来の実力値に修正(Add-back)していく作業が不可欠です。
1. 節税保険・オペレーティングリースの処理
「全額損金」「半額損金」の保険料や、航空機・足場等のリース料は、M&Aにおいては純粋な事業コストではなく「オーナーの貯蓄行動」とみなされます。
- テクニック: これらの支払額を営業利益に足し戻します。例えば、年間2,000万円の保険料を経費処理している場合、これを利益に戻すだけで、マルチプル8倍なら1億6,000万円の企業価値向上に直結します。
2. 役員報酬と私的経費(Private Expenses)の厳格な峻別
オーナー企業特有の「経費」は、買い手(特に上場企業やファンド)が最も厳しく精査するポイントです。
- 役員関連コスト: 相場より著しく高い役員報酬、実態の伴わない親族への給与、過剰な社宅家賃。
- 個人的経費: 事業関連性の薄い高級外車の減価償却費、ゴルフ会員権の年会費、家族旅行を兼ねた出張費、個人的な飲食費。 これらをDD(買収監査)で指摘されてから認めるのではなく、売却の前々期あたりから自ら排除し、「このPLは修正なしでそのまま実力値です」と言える状態を作ることが、最も高いプレミアム(信用代)を生みます。
第3章:BS(貸借対照表)のスリム化 ~資産の「税引後価値」を知る~
BSは筋肉質であるべきですが、ここで「税効果」の論点が重要になります。不要な資産を持っていても、それは額面通りには評価されません。
1. 非事業用資産(Non-operating Assets)の処分と税コスト
ハワイのコンドミニアム、事業に関係のない上場株式、ゴルフ会員権などは、EBITDAを生み出さないため、別途時価評価して株式価値に加算されます。
- 重要論点(税効果): 買い手は、将来その資産を処分する際の税コストを懸念します。例えば、含み益がある不動産を時価1億円で評価しても、売却時に3,000万円の法人税がかかるなら、企業価値への加算額は7,000万円(税引後)と見積もられるのが実務の常識です。
- テクニック: 可能であれば、M&A前に会社からオーナー個人へ適正時価で譲渡(現金化)しておくことで、BSをキャッシュ(現預金)に変えておく方が、ディスカウント議論を回避でき、評価が明瞭になります。
2. 在庫(棚卸資産)と仕入管理の透明化
在庫は資産ですが、回転していない在庫は「損失の予備軍」です。
- 長期滞留在庫: 1年以上動いていない在庫は、DDにおいて評価減(価値ゼロ)とされ、さらに廃棄費用までマイナスされる可能性があります。事前に廃棄損を出してでも処理し、BSをクリーンにしてください。
- 仕入価格のエビデンス: 原材料価格の変動を適切に管理できているか、「仕入価格推移表」を整備することは、将来の収益性を証明する強力な武器になります。
第4章:労務・法務リスクの排除 ~簿外債務という「時限爆弾」~
M&Aにおいて、価格交渉以前に「ディールブレイク(破談)」を引き起こす最大の要因は、労務を中心としたコンプライアンス違反です。これらは「簿外債務(隠れた借金)」として扱われます。
1. 未払い残業代の完全清算
「管理職扱いだから」「固定残業代込みだから」という独自の解釈は、M&Aの場では通用しません。
- リスク: 過去3年分(法改正により延長傾向)の未払い残業代は、潜在的な債務として株式価値から「1円単位」で控除されます。従業員の労務監査を行い、未払いがあれば支給し、クリーンな状態にしてから売却プロセスに入ってください。
2. 社会保険料の適正化
パート・アルバイトの社会保険加入漏れは、年金事務所の調査が入れば過去2年に遡って徴収されます。これは買い手にとって「買収後に被る損害」そのものです。
- 対策: 加入要件を満たす従業員は全員加入させるか、労働時間を調整するなど、法的にクリアな運用体制を構築します。
3. 法務トラブルと「人のリスク」の履歴管理
- 退職者・退任役員: 過去に喧嘩別れした人物はいませんか? 退職時に「債権債務がないことの確認書」や「秘密保持誓約書」を取得していますか? これがないと、売却発表後に不当解雇などを訴えられるリスク(偶発債務)とみなされます。
- 訴訟・事故履歴: 過去の訴訟、労働災害、死亡事故などの履歴は隠さず整理します。「弁護士によるリスク評価書(意見書)」を添付し、「解決済みであり、再発防止策も運用されている」ことを論理的に示せれば、リスクは「管理された事実」へと変わります。
おわりに:経営者の「最終決算」を美しく飾るために
M&Aにおける企業価値評価は、電卓上の計算だけでは決まりません。
「この会社はリスクが管理され、収益力が正しく可視化されている」という情報の質が、買い手の安心感を生み、それが最終的な価格(プレミアム)に転嫁されます。
「PLは税引前で大胆に、BSは税引後で保守的に」
この鉄則を理解し、適切な「磨き上げ」を行うことで、貴社の企業価値は数億円、場合によっては数十億円変わるポテンシャルを秘めています。貴社がこれまで積み上げてきた歴史が、正当に、そして高く評価されることを心より願っております。
用語解説(Expert Note)
税効果(Tax Effect): 会計上の利益と税務上の所得のズレや、資産の含み益に対する将来の課税関係を財務諸表に反映させること。M&Aでは「資産を売ったら税金がかかるので、その分価値を割り引く」という文脈で使われることが多い。、その会社が本来持っている実力値としての利益。
EBITDA(イービットディーエー): 税引前利益に、支払利息と減価償却費を足し戻した利益指標。「国による税率や金利の違い」「設備投資の方針」を除外した、事業そのものの稼ぐ力を表す。
正常収益力(Normalized Earnings): 一過性の要因(災害損失や記念配当)や、オーナー私的経費などを排除し、新しい買い手が経営した場合に見込まれる「実力値としての利益」。
ネットキャッシュ(Net Cash): 手元の現預金から、有利子負債(借入金)を引いたもの。M&Aでは、これに加えて非事業用資産(の税引後現金化価値)を加算して計算することがある。





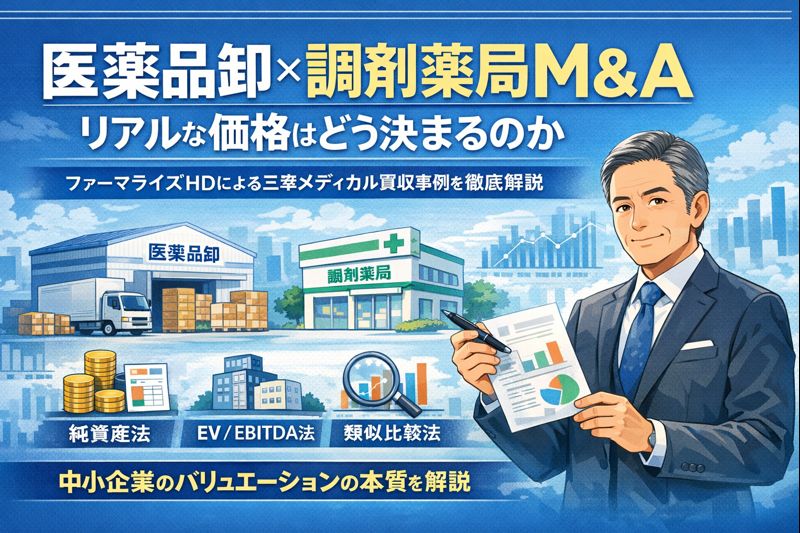


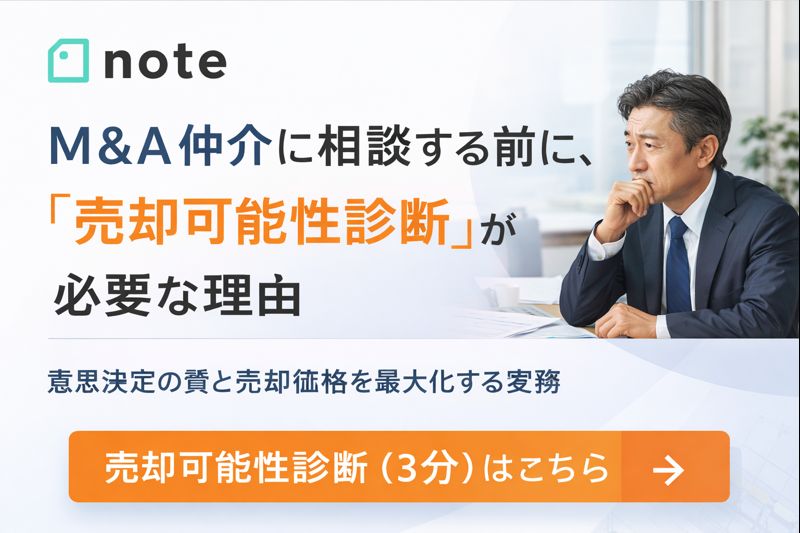


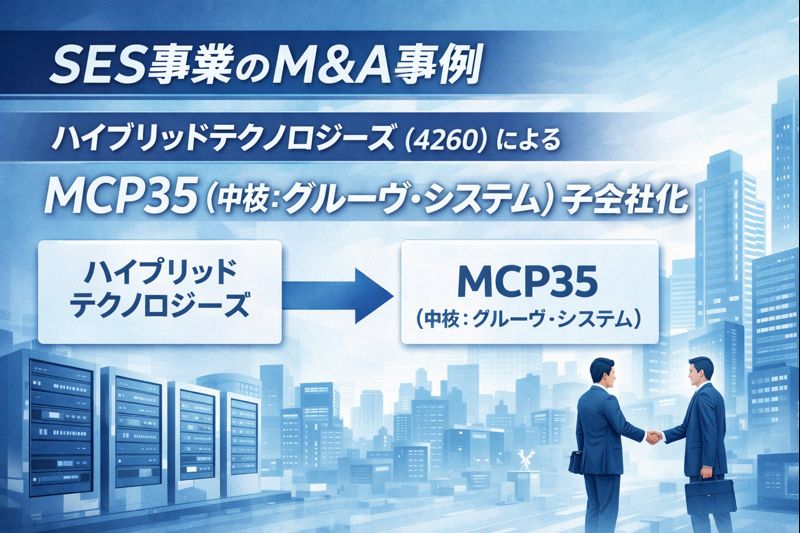






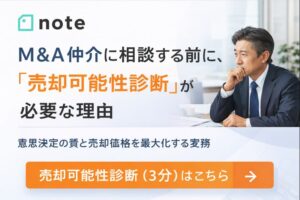

コメント