M&A(企業の合併・買収)は、企業の成長戦略を実現する有力な手段の一つです。しかし、華々しい成功の裏には、その何倍もの「失敗」が隠されています。ディール(取引)の成立はゴールではなく、スタートラインに過ぎません。本当の失敗は、ディールが成立した「後」に発覚することがほとんどです。本記事ではM&Aアドバイザーとしての知見に基づき、M&Aがなぜ失敗するのか、その構造的な要因を、法務・会計・税務、そして実務家の視点から深く掘り下げます。
私たちが目の当たりにしてきた数々の事例、特に「失敗の本質」に焦点を当てることで、M&Aを検討されている経営者やご担当者様が、将来直面しうるリスクを回避するための一助となれば幸いです。
1. M&Aにおける「失敗」の定義:なぜディール成立後に悲劇は起こるのか
一般的に「M&Aの失敗」と聞くと、交渉が決裂し、ディールが成立しなかったケースを想像されるかもしれません。しかし、私たち実務家が「失敗」と呼ぶのは、主にM&Aが成立した後に、当初期待した効果が得られない事態を指します。ディールが成立した瞬間は、買い手も売り手も高揚感に包まれます。しかし、本当の試練はそこから始まります。私たちが定義する「M&Aの失敗」には、主に以下の4つの類型があります。
1-1. 戦略(ストラテジー)の失敗:シナジー効果の不発
最も多い失敗が、期待した*シナジー効果(相乗効果)が発揮されず、投資対効果(ROI)が著しく未達となるケースです。シナジーとは、「1 + 1」が「2」ではなく、「3」にも「4」にもなることを期待するもので、M&Aの醍醐味とも言えます。
- シナジーの例:
- 販売網の相互活用(クロスセル)
- 重複部門(バックオフィスなど)の統合によるコスト削減
- 技術やノウハウの融合による新製品開発
しかし、このシナジーの「読み」が甘いことが非常に多いのです。「買収すれば、きっとうまくいくはずだ」という希望的観測や、競合に勝ちたいという焦りが、客観的な分析を妨げます。結果として、投資額を回収できず、M&Aは「高値掴み」の烙印を押されます。
1-2. 評価(バリュエーション)の失敗:「のれん」の減損
M&Aの失敗が会計数値として最も明確に表れるのが、「のれん」の減損損失の計上です。
【専門用語解説:のれん(Goodwill)】 「のれん」とは、M&Aの際に支払った「買収価額」が、買収対象企業の「時価純資産額(資産から負債を引いた価値)」を上回った場合の差額を指します。これは、対象企業のブランド力、技術力、顧客基盤といった「目に見えない資産(無形資産)」の価値であり、買い手の「将来この企業はこれだけ稼いでくれるはずだ」という期待値の表れでもあります。
会計上、この「のれん」は資産として計上されますが、買収後の業績が計画通りに進まず、「投資額の回収が見込めない」と判断された場合、その価値を引き下げなければなりません。これが「減損損失」です。巨額の減損損失は、M&Aが失敗であったことを明確に示すと同時に、企業の純利益を圧迫し、時には株価急落や経営陣の退陣にもつながる深刻な事態を引き起こします。
1-3. 精査(デューデリジェンス)の失敗:買収後の不祥事発覚
買収後に、買収対象企業の不祥事や、隠れていた巨額の負債(簿外債務や偶発債務)が発覚するケースも、典型的な失敗です。
【専門用語解説:デューデリジェンス(Due Diligence)】 略して「DD(ディーディー)」と呼ばれます。M&Aの買い手が、対象企業の価値やリスクを精査するために行う詳細調査のことです。財務・税務・法務・人事・ビジネスなど、あらゆる側面から専門家(会計士、弁護士、コンサルタント)が調査を行います。
DDはM&Aプロセスにおいて極めて重要ですが、万能ではありません。
- 時間的制約: 競合との入札合戦(オークション)では、DDに十分な時間をかけられないことがあります。
- 情報開示の限界: 売り手が意図的に情報を隠したり、そもそも売り手自身がリスクを把握していなかったりするケースもあります。
DDの不備によって、法令違反、訴訟リスク、環境汚染問題などを見落とすと、買収後に予期せぬ巨額の損失や、深刻なブランドイメージの失墜を招くことになります。
1-4. 統合(PMI)の失敗:中核人材の流出
M&Aの成否を最終的に決定づけるのは、PMI(Post Merger Integration:M&A成立後の統合プロセス)です。しかし、このPMIの失敗が原因で、事業継続に深刻な影響が出ることがあります。
最も顕著なのが、中核を担うキーパーソンや優秀な従業員の流出です。 M&Aにおいて、従業員は「自分たちの会社はどうなるのか」「待遇は変わるのではないか」と強い不安を感じています。特に、独自の技術やノウハウ、顧客との強固な関係を持つキーパーソンが、買収後の混乱や企業文化の違い(カルチャー・クラッシュ)に嫌気がさして退職してしまうと、買い手が期待していた「目に見えない資産」そのものが失われ、M&Aは「抜け殻」を買ったことになりかねません。
2. M&A失敗事例から学ぶ「5つの教訓」
机上の理論だけでは伝わらない「失敗の本質」を、世界と日本で実際に起きた有名なM&A失敗事例から学んでいきましょう。
失敗事例 1:【巨額減損】東芝 × ウェスチングハウス(米国)
(失敗要因:高値掴み、DDの限界、PMI(ガバナンス)不全)
- 背景: 2006年、東芝は原子力事業をグローバルに拡大するため、米国の原子力大手ウェスチングハウス(WH)を、競合を大幅に上回る約54億ドル(当時のレートで約6,200億円)で買収しました。
- 失敗の経緯: 当初から「高値掴み」が指摘されていましたが、2011年の東日本大震災による世界的な原子力事業の見直しと、WH内部での巨額のコスト超過(不適切な会計処理とも指摘)が発覚。東芝はWHの企業価値を維持できなくなり、2017年3月期にはWH関連だけで7,000億円を超える巨額の減損損失を計上。最終的に東芝本体の経営危機を招きました。
- 教訓: この事例は、M&Aの失敗要因が複合的に絡み合った典型例です。①競合に勝つための高値掴み(バリュエーションの失敗)、②買収対象の複雑な工事コスト管理や内部統制のリスクを完全に見抜けなかった**(DDの限界)、③買収後のWHを適切に管理・統制(ガバナンス)できなかった(PMIの失敗)。これら全てが、ひとつの巨大な失敗に繋がりました。
失敗事例 2:【シナジー不発】パナソニック × 三洋電機(日本)
(失敗要因:戦略の失敗、シナジーの過大評価)
- 背景: 2009年、パナソニックは「リチウムイオン電池」と「太陽電池」事業の強化を狙い、三洋電機を約8,000億円(段階的な取得を含む総額)で買収し、完全子会社化しました。
- 失敗の経緯: 最大の目的であった電池事業において、両社の技術的な強み(パナの安全性技術、三洋の高容量技術)の融合は容易ではなく、市場環境も韓国・中国メーカーの猛追により急速に悪化。さらに、テレビ事業など重複する赤字事業の整理にも追われました。結果として、期待したシナジーは発揮できず、買収からわずか2年後の2012年3月期に、三洋電機関連で約2,500億円もの巨額の「のれん」減損を計上しました。
- 教訓: M&Aにおける「戦略」の重要性を示す事例です。「電池事業を強化する」という方向性は正しくとも、「なぜ三洋でなければならないのか」「買収後にどうやって融合させるのか」というシナジー創出の具体的なロードマップ(戦略)が甘かったと言わざるを得ません。技術や文化が異なる企業同士を融合させるPMIの難しさも浮き彫りになりました。
失敗事例 3:【DDの失敗】LIXIL × Joyou(中国・ドイツ)
(失敗要因:DDの不備、買収後の不正会計発覚)
- 背景: LIXIL(当時はLIXILグループ)は、グローバル化戦略の一環として、2011年にイタリアの建材メーカー、2013年にドイツの水栓金具大手グローエを買収しました。
- 失敗の経緯: 問題は、グローエが買収する以前から保有していた中国の子会社「Joyou(中宇)」で起きました。LIXILによるグローエ買収後、Joyouにおいて長年にわたる大規模な不正会計(売上の水増しなど)が行われていたことが発覚。LIXILは、グローエ買収時のDDでこの不正を見抜けませんでした(正確には、グローエ側もJoyouの実態を完全には把握していなかったとされます)。この結果、LIXILは2015年3月期にJoyou関連で600億円を超える巨額損失を計上する事態となりました。
- 教訓: これは「DDの失敗」、特にクロスボーダーM&A(国境を越えたM&A)におけるリスクを象徴する事例です。DDは、直接の買収対象(グローエ)だけでなく、その子会社、孫会社に至るまで徹底的に行う必要があります。特に、会計基準やガバナンスの透明性が異なる新興国の企業が関連する場合、そのリスクは飛躍的に高まるという教訓です。
失敗事例 4:【異文化リスク】第一三共 × ランバクシー(インド)
(失敗要因:DDの失敗、異文化・法規制リスク)
- 背景: 2008年、日本の大手製薬会社である第一三共は、新興国市場への進出と後発医薬品(ジェネリック)事業の獲得を目指し、インドの後発薬大手ランバクシーを約4,900億円で買収しました。
- 失敗の経緯: 買収直後から、ランバクシーの主力工場において、米国のFDA(食品医薬品局)が定める品質基準(cGMP)に関する深刻な違反が発覚。製品の製造・出荷停止処分を受け、米国市場から事実上締め出されました。第一三共は、DDの段階でこの重大な問題を把握しきれていませんでした。品質問題への対応に追われ、巨額の和解金支払いも発生。期待したシナジーは得られず、最終的に2014年、ランバクシーを別企業に実質的に売却。累計で約4,500億円の損失を計上したとされています。
- 教訓: クロスボーダーM&Aにおける「法規制リスク」と「品質管理文化の違い」を見誤った事例です。特に製薬業界のような規制産業では、コンプライアンス(法令遵守)に関するDDは、財務諸表の数字以上に重要です。また、「問題ない」とする現地経営陣の言葉を鵜呑みにせず、自らの目で厳格にチェックする体制の必要性を示しました。
失敗事例 5:【戦略の失敗】マイクロソフト × ノキア(米国・フィンランド)
(失敗要因:戦略の失敗、市場調査の不足)
- 背景: 2014年、マイクロソフト(MS)は、当時苦境にあえいでいたフィンランドの携帯電話大手ノキアのデバイス・サービス部門を約72億ドル(約7,400億円)で買収しました。目的は、自社のOS「Windows Phone」を搭載したスマートフォンを普及させ、アップル(iOS)とグーグル(Android)が支配する市場に割って入ることでした。
- 失敗の経緯: しかし、時すでに遅しでした。市場はiOSとAndroidの「二強」によって完全に寡占されており、Windows Phoneが入り込む余地は残っていませんでした。買収後もノキアのシェア下落は止まらず、MSのスマホ事業は全く浮上しませんでした。結果、買収からわずか1年後の2015年、MSは買収額72億ドルを上回る76億ドルの巨額減損を計上。事実上、買収の「全損」を意味し、多くの人員削減も伴いました。
- 教訓: M&Aによって「市場の変化」に逆らおうとした「戦略(ストラテジー)の失敗」の典型です。ノキアという「ハードウェア」を手に入れても、消費者が求める「エコシステム(アプリやサービスの生態系)」でiOSやAndroidに勝てなければ意味がありませんでした。競合調査やマーケティング調査が不十分だった、あるいは、自社の戦略に固執しすぎた結果と言えるでしょう。
3. M&A失敗の深層分析:アドバイザーが語る「陥穽」
失敗事例からもわかるように、M&Aの失敗は複数の要因が絡み合って発生します。ここでは、実務家として特に「危険」と感じる2つのプロセス(バリュエーションとDD)について、その深層を解説します。
3-1. バリュエーション(企業価値評価)の罠:なぜ「高値掴み」は起きるのか
M&Aの価格交渉の土台となるのが「バリュエーション(企業価値評価)」です。私たちは、対象企業が将来生み出すキャッシュフローを予測し、それを現在の価値に割り引くDCF法(Discounted Cash Flow法)などを駆使して、理論的な企業価値を算定します。しかし、このプロセスには大きな「罠」が潜んでいます。
罠1:将来事業計画の「作文」 DCF法の根幹となる「将来事業計画」は、誰が作るのでしょうか? 多くの場合、買収対象企業の経営陣、あるいは買収を推進したい買い手側の担当部署です。そこには「M&Aを成立させたい」というバイアスがかかり、極めて楽観的な(バラ色な)事業計画が描かれがちです。私たちアドバイザーは、その計画の妥当性を厳しく精査しますが、未来を正確に予測することは誰にもできません。
罠2:シナジーの「過大評価」と「二重計上」 「この買収が実現すれば、これだけのシナジーが生まれるはずだ」——。この期待がバリュエーションを歪ませます。買い手は、自らが生み出すはずのシナジー価値まで含めて、高い買収価格を提示してしまうことがあります。 さらに厄介なのは、売り手側も「あなた(買い手)と組めば、これだけの価値が生まれるのだから、その分も価格に反映してほしい」と主張することです。これが「シナジーの二重計上」であり、冷静な価格交渉を困難にします。
罠3:オークション(入札)による「焦り」 優良な案件には、複数の買い手候補が群がります。入札形式(オークション)になると、「競合にだけは負けたくない」「このディールを逃したら次はない」という経営陣の焦り(いわゆるディール・フィーバー)が、アドバイザーの冷静な「高値掴みですよ」という進言を押し切ってしまうことがあります。東芝のWH買収がこの典型でした。
3-2. デューデリジェンス(DD)の限界:なぜリスクは見落とされるのか
「徹底的にDDをやれば、リスクは見抜けるはずだ」と思われるかもしれません。しかし、DDには構造的な「限界」があります。
限界1:時間の制約 M&Aのプロセスは、非常にタイトなスケジュールで進みます。特にオークション案件では、DDに割ける期間は数週間程度ということも珍しくありません。膨大な資料を精査し、現地調査を行い、経営陣にインタビューする……。この短期間で、隠されたすべてのリスクを発見することは物理的に不可能です。
限界2:情報の非対称性 当然ながら、対象企業の内部情報に最も精通しているのは「売り手」です。買い手は、売り手から開示された情報(VDR: Virtual Data Roomと呼ばれる電子開示システム)に基づいて調査を行うしかありません。 悪意のある売り手は不利な情報を隠すかもしれませんし、悪意がなくとも「自社にとってのリスク」を正しく認識していない場合もあります。LIXILのJoyouの事例のように、「子会社のリスク」は、親会社ですら把握していないことがあるのです。
限界3:見えにくいリスク(人事・法務) 財務諸表に表れる数字(財務DD)は比較的精査しやすいですが、「人」と「コンプライアンス」のリスクは見抜きにくいのが実情です。
- 人事DD: 「このキーパーソンが辞めたら、事業は回らなくなる」という属人的なリスク。
- 法務DD: 「現時点では問題になっていないが、潜在的な訴訟リスクや法令違反(例えば、サービス残業の常態化やハラスメント)」など。
第一三共がランバクシーの品質問題を見抜けなかったように、これらの「見えにくいリスク」が、買収後に牙を剥くのです。
4. M&Aスキーム(手法)選択の失敗と法的・税務的「陥穽(かんせい)」
M&Aの「手法」をどう選ぶか。これもアドバイザーの重要な仕事です。手法(スキーム)には、主に以下のものがあります。
- 株式譲渡: 会社の株式を丸ごと買い取り、経営権を取得する。最も一般的な手法。
- 事業譲渡: 会社の「特定の事業」だけを切り出して買い取る。
- 会社分割: 会社を分割し、その事業を別会社に移す(組織再編)。
- 株式交換・株式移転: 自社の株式を対価として、相手の会社を100%子会社化する(組織再編)。
どのスキームを選ぶかは、買収の目的、法務・税務上の影響を考慮して、パズルのように組み立てます。しかし、この選択を誤ると、予期せぬ失敗を招きます。
失敗例1:株式譲渡の「丸ごと引き受け」リスク 最もシンプルな「株式譲渡」は、会社を丸ごと買うため、買い手はその会社の「全ての資産と負債」を引き継ぎます。もしDDで簿外債務や訴訟リスクを見落としていれば、それらも「丸ごと」引き受けることになります。
失敗例2:事業譲渡の「許認可・契約」リスク 「リスクのある負債は引き継ぎたくない」と考え、「事業譲渡」で優良な事業だけを買い取る戦略は有効です。しかし、ここにも罠があります。 事業に必要な「許認可」は、原則として買い手が「再取得」しなければなりません。また、従業員との「雇用契約」や、取引先との「契約」も、個別に「同意」を得て巻き直す必要があります。 もし、キーマンが転籍に同意しなかったり、重要な取引先が「買い手が変わるなら取引しない」となったりすれば、事業そのものが成り立たなくなるリスクがあります。
失敗例3:予期せぬ「税務リスク」 M&Aスキームは、税務と密接に関連します。例えば、組織再編(会社分割や合併)において、一定の要件(適格要件)を満たさない「非適格」な再編と税務当局に判断された場合、巨額の「繰越欠損金(将来の税金を減らせる資産)」が使えなくなったり、予期せぬ「みなし配当課税」が発生したりすることがあります。 アドバイザーや税理士の検討不足が、ディール成立後に巨額の税金として跳ね返ってくるのです。
5. 最大の難関「PMI(買収後の統合プロセス)」の失敗
M&Aは「結婚」によく例えられます。ディール成立(クロージング)は「結婚式」に過ぎません。本当に重要なのは、その後の「結婚生活(=PMI)」です。私たちが関与するディールの多くで、PMIの失敗がM&A失敗の最大の要因となっています。
5-1. 「企業文化(カルチャー)」の衝突
「人」と「組織」の統合は、M&Aで最も困難な作業です。特に、歴史ある大企業と、スピード感のあるベンチャー企業が統合するようなケースでは、あらゆる面で衝突が起こります。
- 意思決定プロセス: 「稟議(りんぎ)とハンコ」の文化と、「まず実行(Do First)」の文化。
- 評価制度・報酬: 年功序列と成果主義。
- コミュニケーション: 「阿吽(あうん)の呼吸」を求める文化と、徹底的に言語化・マニュアル化する文化。
これらの違いを放置すると、従業員は疲弊し、優秀な人材から見切りをつけて辞めていきます。
5-2. キーマンの流出と「リテンション」の失敗
買い手が最も恐れるのが、買収対象企業の「キーマン」(創業者、トップエンジニア、トップセールス)の流出です。彼らを引き留めるために、私たちは「リテンション・プラン」(引き留め策)を設計します。 例えば、一定期間の雇用を保証したり、成功報酬(アーンアウト条項など)を設けたりします。しかし、金銭的な手当てだけでは、人の心は繋ぎ止められません。 買収後に「リスペクト(尊敬)」が感じられない、あるいは「自由な裁量が奪われた」と感じれば、彼らは簡単に競合他社に移ってしまいます。
5-3. 「100日プラン」の不在と統合の遅延
「PMIはディールが終わってから考えれば良い」——この考えが最も危険です。 M&Aの成功には、ディールが成立した「Day 1(初日)」から、いかにスムーズに統合プロセスを開始できるかがかかっています。私たちは通常、M&Aの交渉中から「PMIチーム」を組成し、Day 1から最低100日間で何を達成すべきか(例:経営理念の共有、基幹システムの統合方針決定、重複部門の整理など)を定めた「100日プラン(Day 1 Plan)」を策定します。 この準備が不足していると、統合は後手に回り、現場は混乱し、シナジーなど到底望めない状態に陥ります。
6. M&Aの失敗を防ぐための「5つの処方箋」
これまで数多くの失敗を解説してきましたが、M&Aは依然として、企業が非連続な成長を遂げるための最も強力な戦略オプションの一つです。 では、どうすれば失敗の確率を下げ、成功に近づけるのでしょうか。M&Aアドバイザーとしての実務的な処方箋を5つ提示します。
処方箋1:「Why(なぜ買うのか)」を研ぎ澄まし、「買わない勇気」を持つ
M&Aの実行自体が目的化(ディール・ドリブン)してはいけません。
- 「なぜ、自社でゼロから立ち上げる(オーガニック)のではなく、M&Aなのか?」
- 「その買収によって、自社の中核戦略はどう強化されるのか?」 この「Why」を、経営陣が自らの言葉で語れるまで徹底的に議論してください。 そして、M&Aの目的と戦略(自社の「買収戦略(Acquisition Strategy)」)に合致しない案件や、DDの結果リスクが高すぎると判断した案件は、たとえどれだけ時間をかけて交渉していても、「買わない(降りる)勇気」を持つことが最も重要です。
処方箋2:信頼できる「専門家(FA・弁護士・会計士)」を選定する
M&Aは、法務・会計・税務・ビジネスが複雑に絡み合う「総合格闘技」です。それぞれの分野で最高水準の知見を持つ専門家のサポートは不可欠です。 特に、売り手と買い手の双方から手数料を得る「仲介」ではなく、買い手(あるいは売り手)の利益を最大化するためにのみ動く「FA(フィナンシャル・アドバイザー)」(私たちのような投資銀行が担います)を選定することが重要です。 また、弁護士や会計士も、M&A(特にクロスボーダーや組織再編)の実績が豊富な専門家チームを選ぶべきです。
処方箋3:「疑義的」なデューデリジェンス(DD)を徹底する
DDは「性悪説」に立つべきです。「売り手が何か隠しているかもしれない」「この計画には穴があるかもしれない」という「疑義的(Skeptical)」な視点で、徹底的にリスクを洗い出してください。 コストを惜しんでDDを簡略化することは、将来の巨額損失のリスクを抱え込むことと同義です。特に、財務・法務・人事・ITシステム、そしてクロスボーダー案件では現地の法規制やコンプライアンスのDDは絶対に省略してはいけません。
処方箋4:「客観的」なバリュエーションを維持し、シナジーを「厳しく」見る
オークションの熱気や、「これを逃したら次はない」という焦りに流されてはいけません。 FAが算出した客観的なバリュエーション(企業価値)を常に意識し、自社が許容できる「上限価格(Walk-away Price)」をあらかじめ厳格に定めておくべきです。 また、シナジー効果は、「誰が、いつまでに、どうやって達成するのか」を具体的に計画に落とし込み、その実現可能性を厳しく評価した上で、バリュエーションに反映させる必要があります。
処方箋5:「Day 1」から始まるPMIを、M&A交渉と「同時」に設計する
M&Aの成功はPMIで決まります。そして、PMIはディールのクロージング(成立)と同時に始まるものです。 私たちは、最終契約の交渉と並行して、PMI専門のチームを立ち上げ、「100日プラン」を策定することを強く推奨します。新しい経営体制、従業員へのコミュニケーションプラン、企業文化の融合プログラムなど、買収初日からロケットスタートを切るための準備を、M&T交渉中に完了させておくのです。
7. 結論:M&Aの成功は「失敗の回避」から始まる
M&Aは、時間とリソースを買い、企業の成長を一気に加速させる可能性を秘めた、強力な経営戦略です。 しかし、そのプロセスは無数の「失敗の罠」に満ちています。本記事で解説したように、失敗の要因は、戦略、評価(バリュエーション)、精査(DD)、手法(スキーム)、そして統合(PMI)という、M&Aのあらゆるプロセスに潜んでいます。
M&Aの成功確率を高める唯一の方法は、これらの「失敗の本質」を深く理解し、学び、一つひとつのリスクを潰していく地道な作業以外にありません。M&Aは「買って終わり」ではなく、「買ってからが始まり」です。この記事が、皆様のM&A戦略を成功に導くための一助となれば、これに勝る喜びはありません。
よくある質問(FAQ)
Q1. M&Aが失敗する最も一般的な原因は何ですか?
A1. 一つだけ挙げるのは困難ですが、実務家としては「PMI(買収後の統合プロセス)の失敗」が最も多く、かつ深刻な結果を招くと感じています。たとえDDやバリュエーションが完璧でも、買収後に企業文化が衝突し、キーマンが流出してしまえば、シナジーは生まれず、M&Aは失敗に終わります。また、その前段階として「戦略の不在(なぜ買うのかが曖昧)」が、その後のすべての失敗の引き金になることも多いです。
Q2. M&Aの失敗事例には、どのようなものがありますか?
A2. 本文で詳しく解説した通り、国内外で多くの事例があります。海外では、マイクロソフトによるノキア買収(戦略の失敗)、国内では東芝によるウェスチングハウス買収(高値掴み・DD・ガバナンスの失敗)、パナソニックによる三洋電機買収(シナジー不発)、LIXILのJoyou問題(DDの失敗)、第一三共によるランバクシー買収(DD・異文化リスク)などが有名です。これら全てが「のれんの巨額減損」という形で会計的な失敗としても表面化しています。
Q3. M&Aで失敗しないためには、どのような対策がありますか?
A3. 本記事の「6. M&Aの失敗を防ぐための5つの処方箋」に集約されます。
- M&Aの目的(Why)を明確にし、「買わない勇気」を持つこと。
- 信頼できるM&A専門家(FA、弁護士、会計士)を選定すること。
- 「疑義的」な視点でデューデリジェンス(DD)を徹底すること。
- オークションの熱に浮かされず、客観的な企業価値評価(バリュエーション)を維持すること。
- M&Aの交渉段階から、PMI(買収後の統合)計画を並行して策定すること。 これら5つの対策を、高いレベルで実行することが不可欠です。
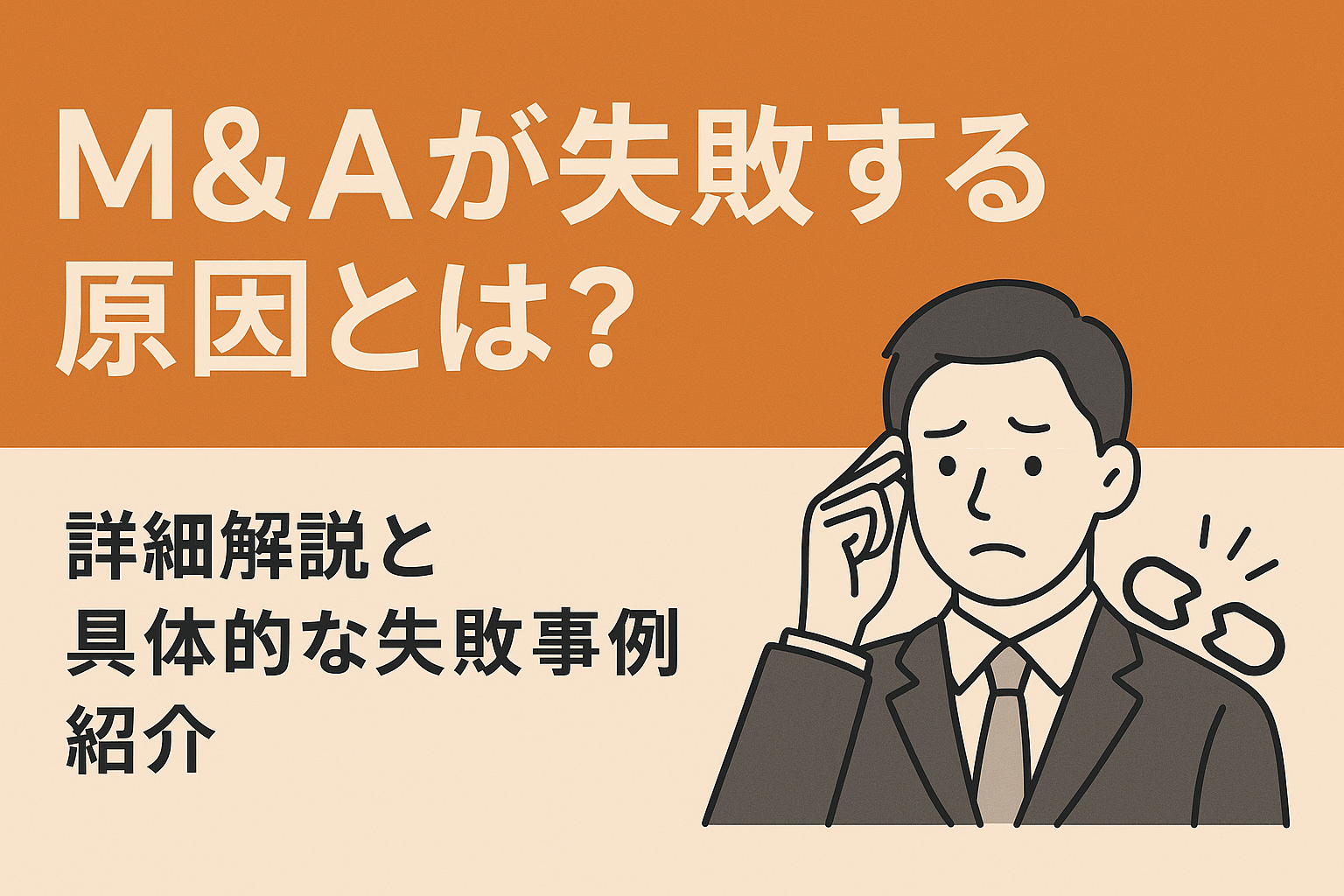

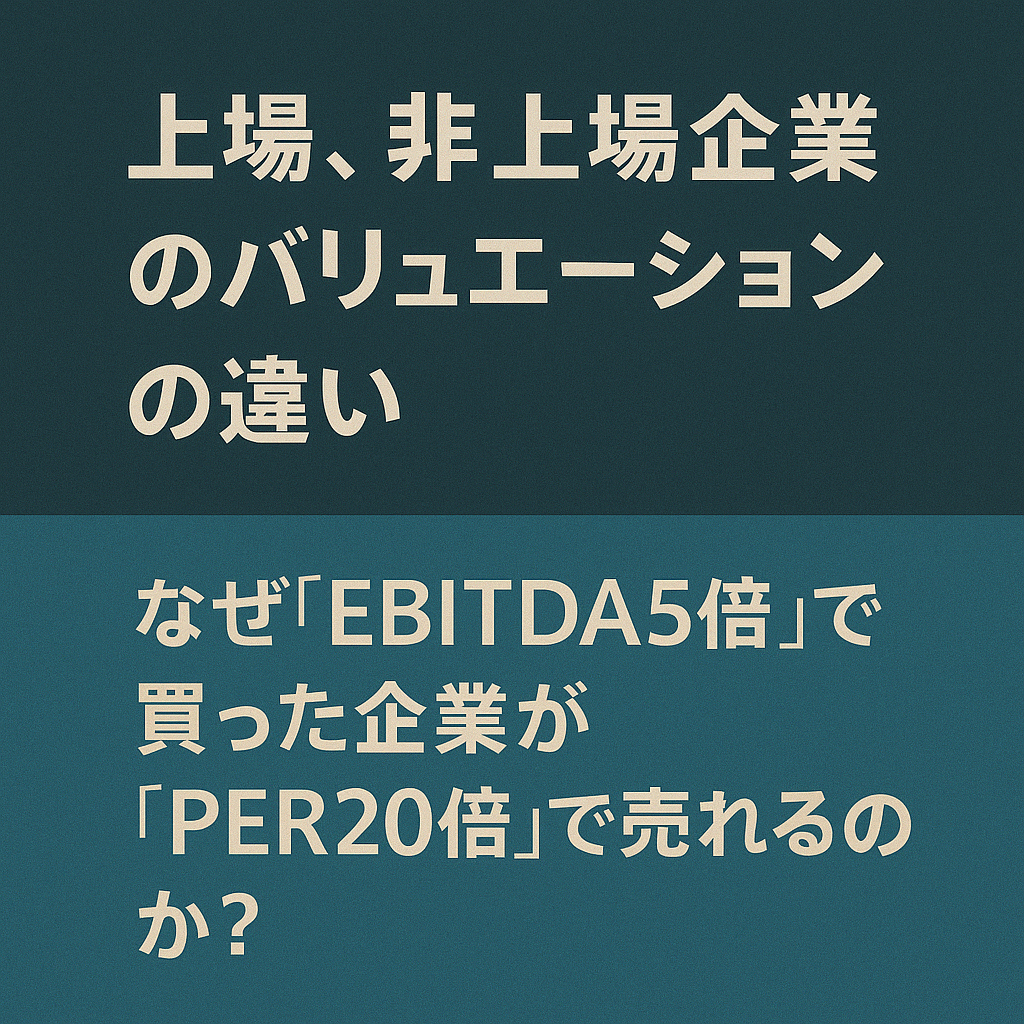
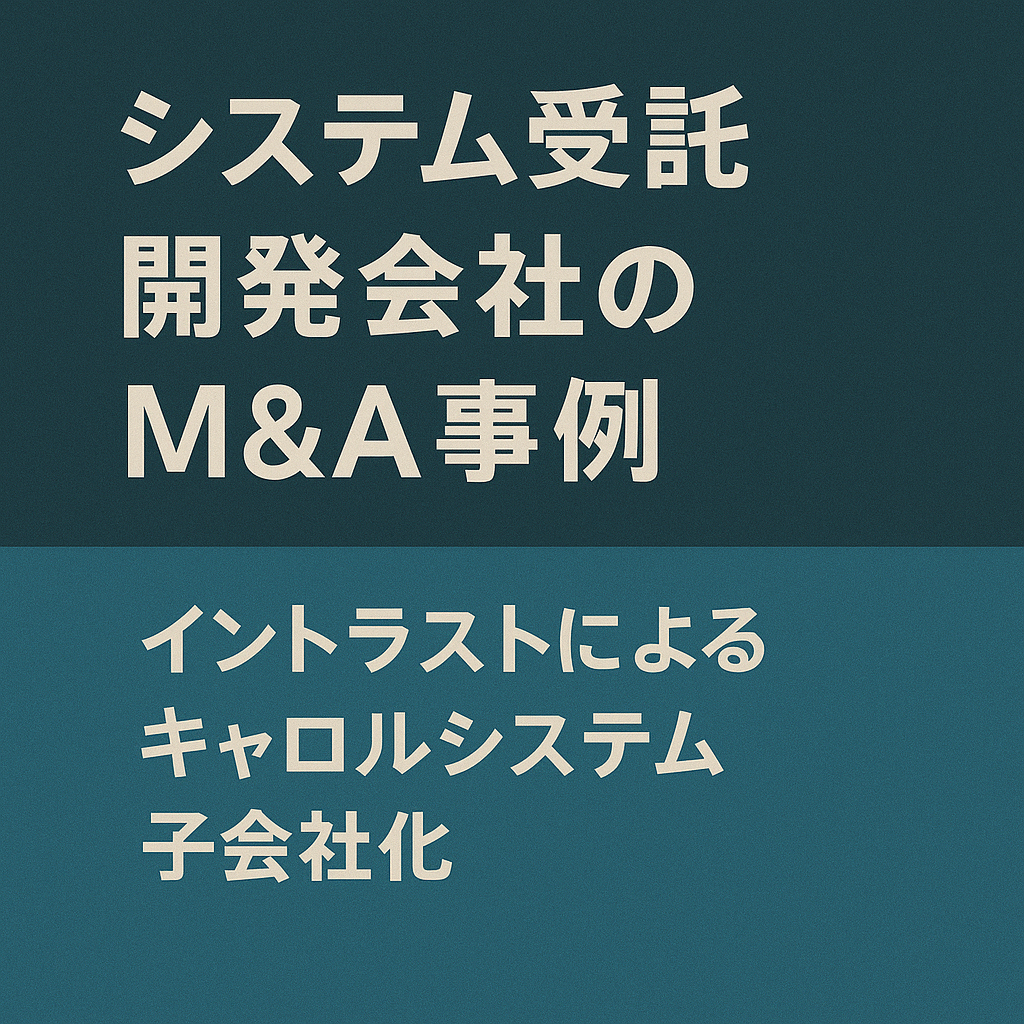
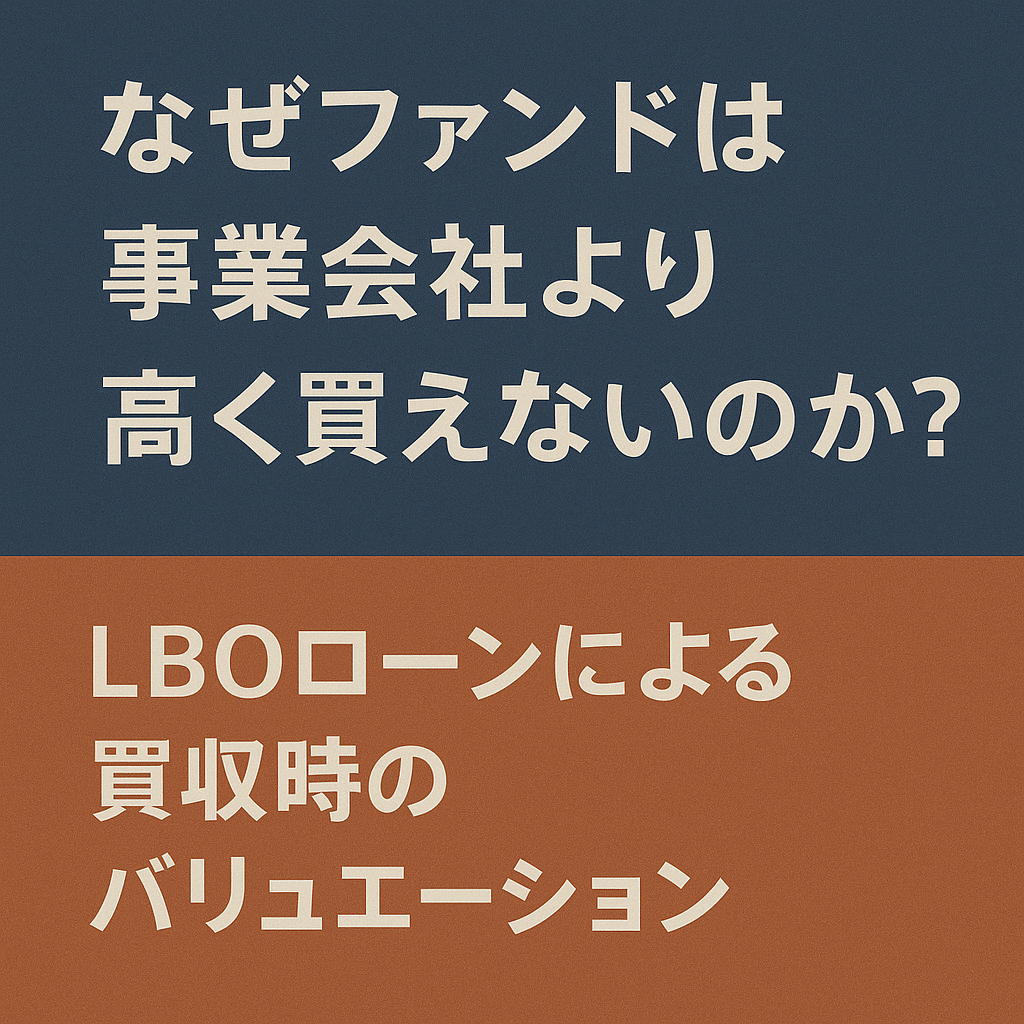
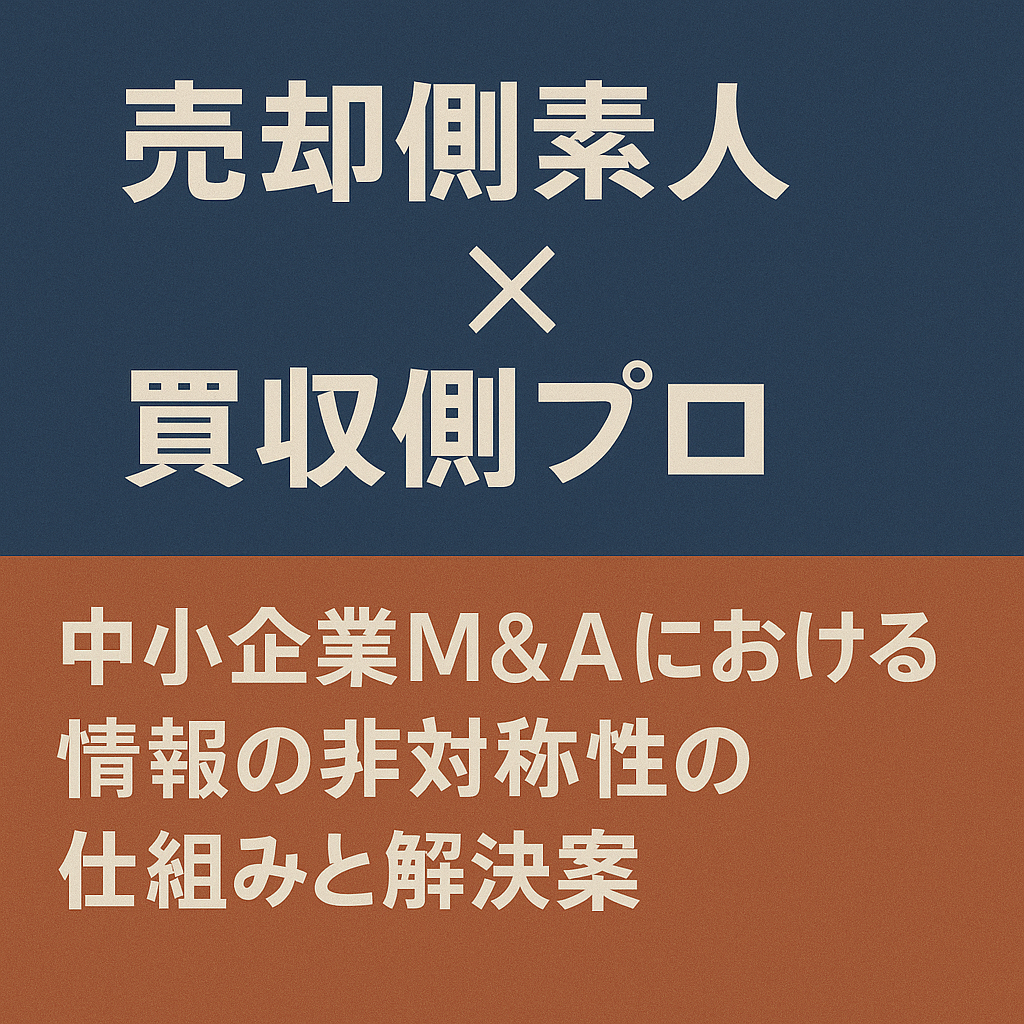

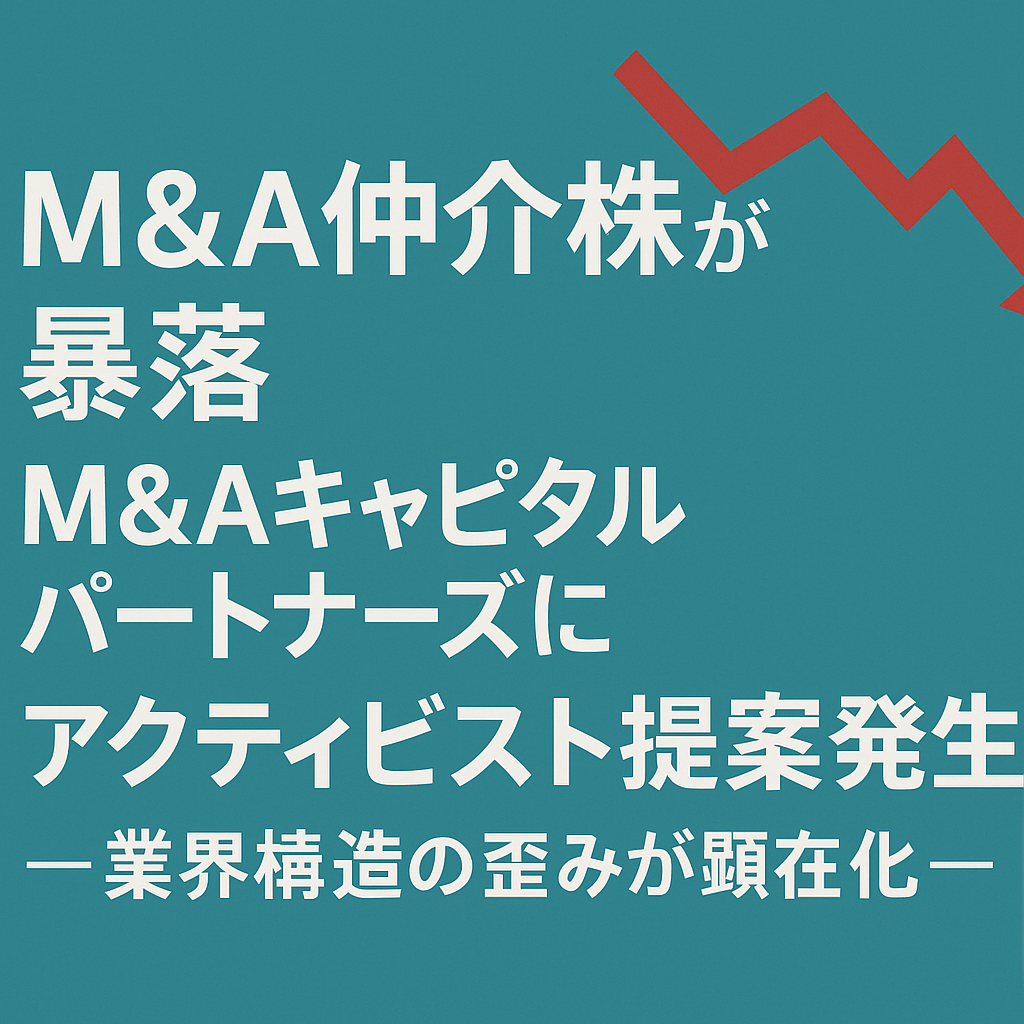


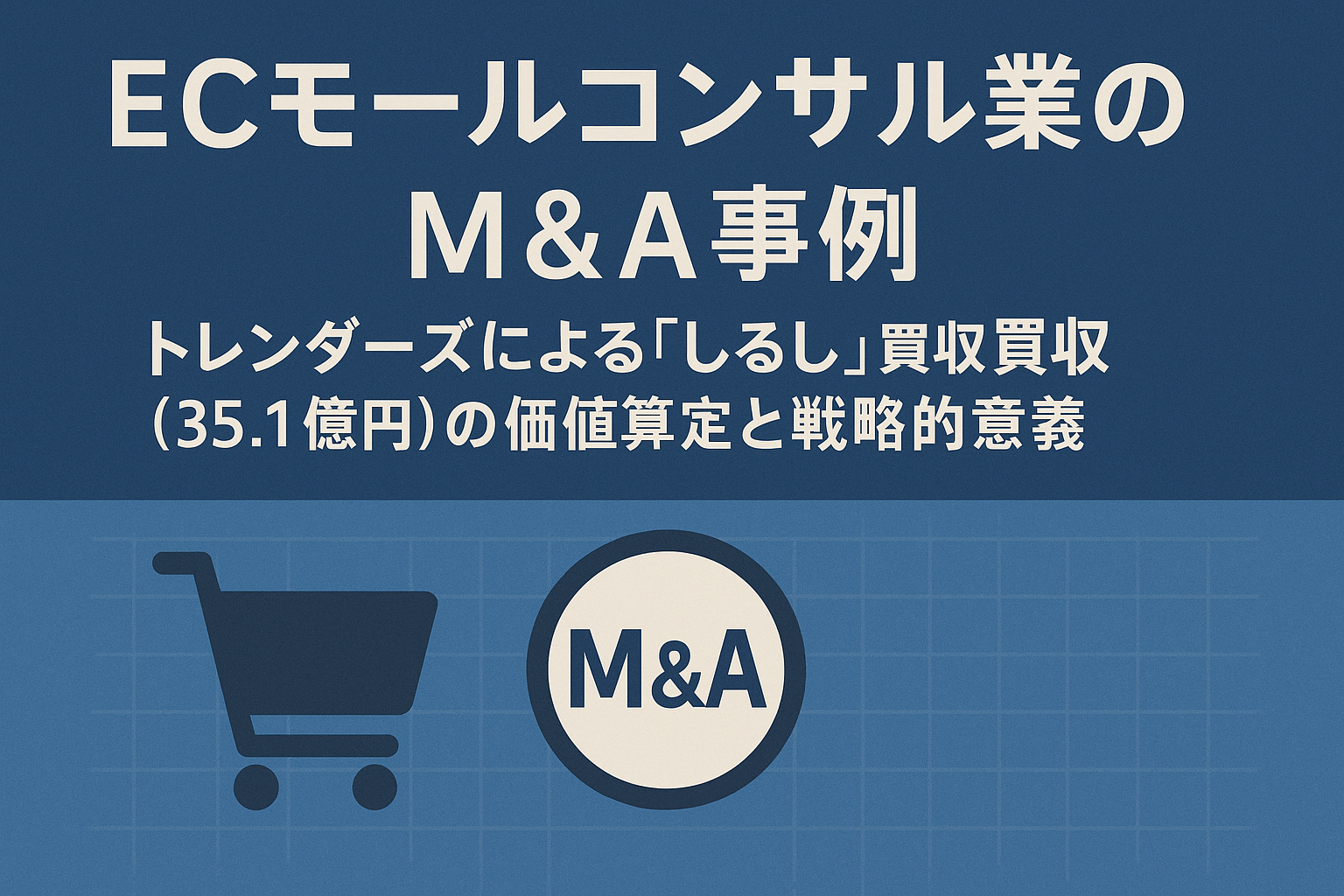

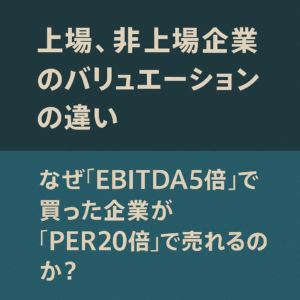
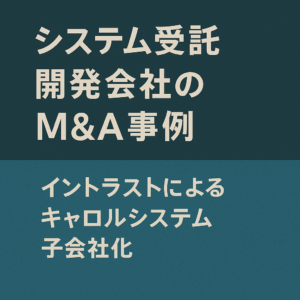
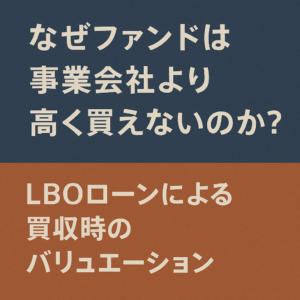

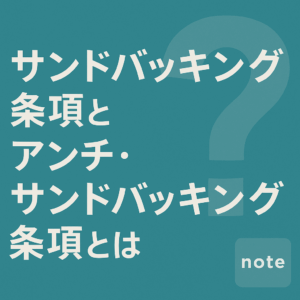
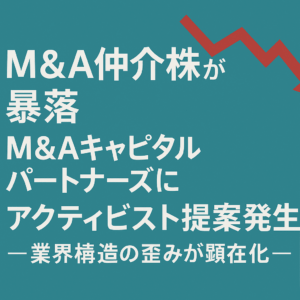


コメント