多くのM&A仲介会社や銀行の担当者は、オーナー様にこう囁きます。
「社長、御社のEBITDA(償却前営業利益)は1億円ですから、相場の5倍を掛けて、企業価値は5億円です。これに現預金を足しましょう。」
非常に分かりやすく、耳触りの良い言葉です。しかし、ここに大きな落とし穴があります。
果たして、「最先端のSaaS(ソフトウェア)企業」と「老舗の運送会社」が、同じ利益額だからといって、同じ倍率(マルチプル)で評価されるべきでしょうか?
答えは、断じて「No」です。
我々プロは、画一的な倍率ではなく、「その利益の質」と「事業継続に必要な再投資額(CAPEX)」、そして「資産の実在性」を精緻に見極めます。ここからは、その具体的なロジックを紐解いていきます。
第1章:業界によって「マルチプル(倍率)」が劇的に異なる理由
「EBITDA×5倍」というのは、あくまで全産業をならした平均値に過ぎません。プロの世界では、業界の成長性、収益の安定性、そして資本効率によって、適正なマルチプルは3倍にもなれば、15倍にもなります。
1. 高マルチプルがつく業界(IT、ヘルスケア、SaaS等)
- 目安:EBITDA 10倍 ~ 20倍以上
- 理由: これらの業界は、市場シェアや一度システムを構築すれば、追加のコストをあまりかけずに売上を増やせます(限界利益率が高い)。また、サブスクリプションモデルであれば将来の収益が約束されています。
- プロの視点: 「現在の利益」よりも「将来の成長スピード」を買うため、現在の利益が小さくても、驚くような高値がつきます。これを「5倍」で売ることは、安く買い叩かれている事を認識せねばなりません。
2. 低マルチプルとなる業界(建設、印刷、一部の製造業等)
- 目安:EBITDA 3倍 ~ 5倍
- 理由: 成長率がGDP並みかそれ以下であり、売上を増やすためには多額の設備投資や人員増加が必要です。競争も激しく、利益率が圧迫されやすい構造にあります。
- プロの視点: リスクが高く、投資回収に時間がかかるため、高い倍率は許容できません。
3. プロが見る「利益の質」
同じ1億円の利益でも、以下の二社では評価が全く異なります。
- A社: 特定の大口顧客1社からの受注で1億円稼いでいる。
- B社: 1,000社の小口顧客からの継続契約で1億円稼いでいる。
仲介会社の簡易算定ではどちらも同じ価値になりますが、プロはA社を「リスクが高い」と判断しマルチプルを引き下げ(ディスカウント)、B社には「安定性が高い」としてプレミアム(加算)を乗せます。
第2章:純資産評価の落とし穴~「時価」と「稼ぐ力」の乖離~
中小企業M&A、特に「コストアプローチ(純資産法)」を用いる際、多くの誤解が生じるのが「資産の評価」です。
「うちは資産(設備や車両、不動産)をたくさん持っているから、純資産価値が高いはずだ」という考え方は、時として裏目に出ます。
プロ投資家は、貸借対照表(BS)の数字をそのまま信じません。「その資産が将来のキャッシュフローを生むのか、それとも食いつぶすのか」という視点でBSを再構築します。
事例1:運送・物流会社における「車両」のパラドックス
運送会社のBSには、多数のトラックが資産計上されています。簿価(帳簿上の価値)が残っていれば純資産は厚く見えます。
- 仲介的な視点: 「車両の時価評価額を純資産に足しましょう」
- プロ投資家の視点(CAPEXの考慮):ここで重要なのがCAPEX(Capital Expenditure:設備投資)の概念です。トラックは走れば走るほど劣化します。もし保有車両の多くが走行距離50万キロを超えており、数年以内に買い替えが必要だとしたらどうでしょうか?買い手からすれば、「会社を買った直後に、数億円の車両購入費(維持更新投資)が出ていく」ことになります。この場合、プロは表面的な時価が高くても、「将来発生する設備更新コスト(Future CAPEX)」を企業価値からマイナス(デットライクアイテムとして控除)して評価します。「資産がある」ことが、逆に「将来の現金流出の予兆」とみなされるのです。これを無視して高値で売却しようとすると、DD(デューデリジェンス)の段階で必ず破談になります。
事例2:不動産賃貸業・ホテル業における「含み益」の罠
歴史ある企業では、安く買った土地の時価が上がり、多額の含み益を持っているケースがあります。
- 仲介的な視点: 「土地の含み益が5億円あるので、株価に5億円上乗せします」
- プロ投資家の視点(税務と利回りの考慮):不動産は「持っているだけ」では価値を生みません。もしその不動産が事業に使われており、売却できない(換金性がない)場合、その含み益は「絵に描いた餅」です。さらに、もし事業を清算して不動産を売るとしても、法人税(約30-34%)がかかります。プロは、純資産に含み益を足す際、「繰延税金負債(将来払う税金)」として約30%~40%を控除して評価します。これを考慮せずに提示された価格は、買い手にとって「高すぎる」と映ります。また、不動産価値が高すぎて、そこから生み出される利益(家賃やホテル収益)の利回り(NOI利回り)が極端に低い場合、「資産としての価値」はあっても「事業としての価値」は低いと判断され、買い手がつきにくくなる現象(アセット・ヘヴィのディスカウント)が起きます。
第3章:EBITDAではなく「フリー・キャッシュ・フロー」を見よ
ここが、本稿で最もお伝えしたい「核心」です。
なぜプロはEBITDAを見るのか。それは「簡易的なキャッシュフローの代用指標」だからです。しかし、より厳密な投資判断においては、EBITDAから「事業を維持するためにどうしても必要な投資(メンテナンスCAPEX)」を引いた、真のフリー・キャッシュ・フロー(FCF)を見ます。
真の実力値(FCF)の計算式:
FCF = EBITDA – 運転資本増減 – 維持更新設備投資(Maintenance Capex)
設備集約型産業(製造業・運送業など)の悲劇
例えば、EBITDAが1億円の製造業があるとします。
しかし、古い機械を動かし続けるために、毎年8,000万円の修繕や買い替え投資が必要だとしたらどうでしょう?
- 表面上のEBITDA: 1億円
- 手元に残る現金(FCF): 2,000万円(1億円 – 8,000万円)
この会社を「EBITDA 5倍」の5億円で買う投資家はいません。実質2,000万円しか手元に残らないのであれば、回収に25年もかかってしまうからです。この場合、バリュエーションはFCFを基準に算定され、EBITDA倍率で見れば1倍~2倍程度になるのが適正となります。逆に、追加投資がほとんど不要なIT企業であれば、EBITDAのほとんどがFCFになるため、高い倍率が正当化されます。
「見かけの利益」ではなく、「投資後に手元に残る現金」こそが価値の源泉なのです。
第4章:プロ投資家との交渉術~「ノーマライズ」の攻防~
では、売り手オーナーはどうすれば良いのでしょうか?
プロの買い手(ファンドや上場企業)はシビアですが、合理的であれば話を聞く耳を持っています。重要なのは、自社の数値を「実態に合わせて正しく修正(ノーマライズ)して提示すること」です。
1. 過剰なCAPEXの修正
もし直近で「将来のための先行投資(大型倉庫の建設など)」を行い、一時的に支出が増えている場合、それは「維持更新コスト」ではなく「成長投資」であると説明し、FCFのマイナス要因から除外するよう交渉します。
2. 役員報酬・節税経費の足し戻し
中小企業特有の「節税のための経費(保険、高級車、過度な交際費)」や「オーナーへの高額報酬」は、M&A後には不要になるコストです。これらを明確にリストアップし、「これらは本来、利益(EBITDA)の一部です」と証明することで、基礎となる利益額を適正に引き上げます。
3. 「のれん」の源泉を言語化する
単に「利益が出ている」だけでなく、その利益が「他社が模倣困難な強み(技術、特許、強固な顧客基盤)」から来ていることを証明できれば、マルチプルの倍率自体を引き上げることが可能です。これを「マルチプル・エクスパンション」と呼びます。
結び:バリュエーションは「計算」ではなく「意思」である
M&Aにおける企業価値評価は、電卓を叩けば誰でも同じ答えが出るような単純なものではありません。
- 業界特有の商習慣とリスク
- 保有資産の将来キャッシュフロー創出力
- 設備投資の必要性
これらを深く洞察し、論理的に組み立てられたバリュエーションこそが、プロの投資家を納得させ、適正かつ最大限の価格を引き出す唯一の武器となります。
「相場はEBITDAの5倍」という言葉は、あくまで「入り口の目安」に過ぎません。





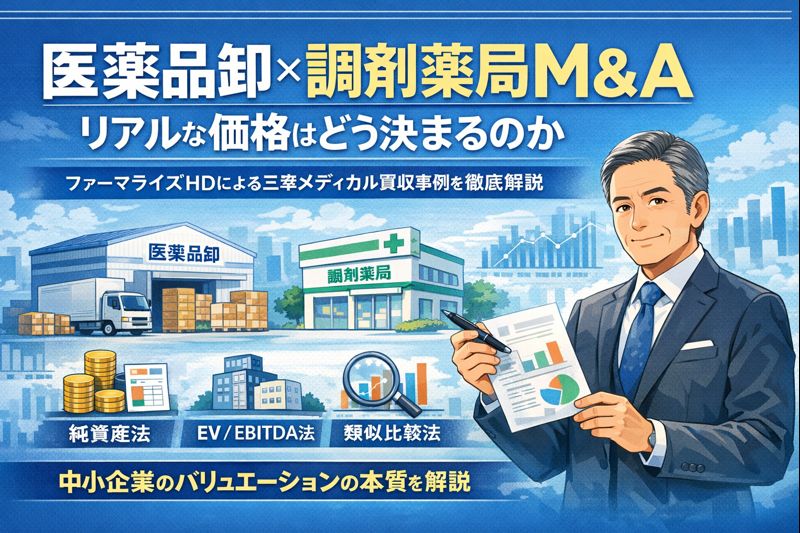


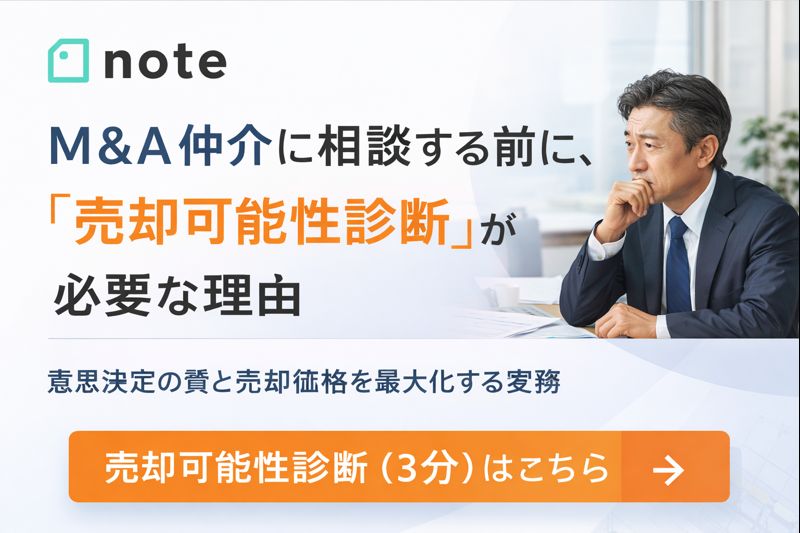


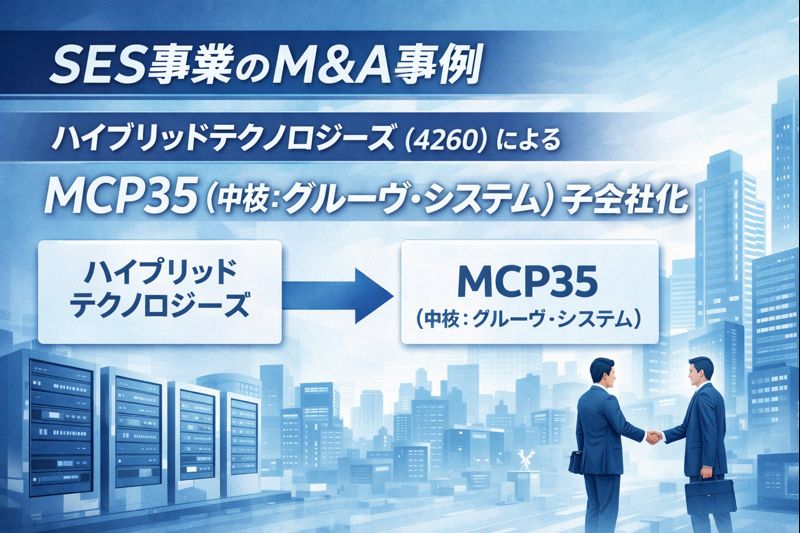






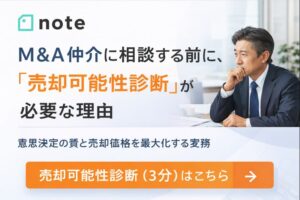

コメント