M&A(企業の合併・買収)アドバイザリーの現場において、私たちが最も注力する論点の一つが「人」の引継ぎです。M&Aは単なる資産や株式の売買ではなく、事業、そしてそれを支える「人」と「文化」の戦略的統合プロセスに他なりません。特にオーナー経営者や特定の役員が事業の中核を担ってきた企業においては、その「キーマン」の去就が、M&Aの成否、ひいては買収価格(バリュエーション)の妥当性そのものを左右します。
この重要な「人」の引継ぎを契約上担保する仕組みが、M&Aにおける「ロックアップ(Lock-up)」条項、一般に「キーマン条項」と呼ばれるものです。
本稿では、M&Aの実務家として、このキーマン条項(ロックアップ)がなぜ必要なのか、その具体的な内容、期間設定、違反した場合のリスク、そして私たちアドバイザーの報酬との関連性について、法務・会計・実務の観点から網羅的に解説いたします。
1. M&AとIPO:「ロックアップ」の根本的な違い
まず、読者の皆様の混乱を避けるため、二種類の「ロックアップ」を明確に区別するところから始めます。主に解説されているのは、IPO(新規株式公開)におけるロックアップです。
- IPOのロックアップ:
- 目的: 株式市場への上場後、株価の急激な変動(特に下落)を防ぐこと。
- 対象: 創業者や役員、ベンチャーキャピタルなどの既存株主。
- 内容: 上場後、一定期間(例:90日、180日など)、保有する株式を市場で売却することを禁止するルール(制度ロックアップ、任意ロックアップ)。
これに対し、本稿で中心的に扱うM&Aにおけるロックアップ(キーマン条項)は、その目的も内容も全く異なります。
- M&Aのロックアップ(キーマン条項):
- 目的: M&A成立後、事業の円滑な引継ぎと企業価値の維持・向上(PMIの成功)を図ること。
- 対象: 売り手企業のオーナー経営者や、事業継続に不可欠な特定の役員・従業員(=キーマン)。
- 内容: M&A成立後も、一定期間、会社に残り、経営や事業運営に参画することを契約によって義務付けるもの。
IPOのロックアップが「株式の売却禁止(=市場からの退出制限)」であるのに対し、M&Aのロックアップは「経営への参画継続(=会社からの退出制限)」を意味します。本稿では、後者のM&Aにおけるキーマン条項について詳述します。
2. なぜM&Aでロックアップ(キーマン条項)が必要なのか
買い手企業(Buy-side)が、売り手企業(Sell-side)のオーナー経営者に対し、なぜM&A後も会社に残ることを要求するのでしょうか。それは、企業の価値が、貸借対照表(B/S)に記載される有形資産だけで構成されているわけではないからです。私たちが企業の価値評価(バリュエーション)を行う際、その価値の源泉の多くが「無形資産」にあると判断します。そして、その無形資産の多くは、特定の「キーマン」に紐付いています。
🔹 買い手(Buy-side)側の論理:無形資産の実現
- PMI(Post Merger Integration:M&A後の統合プロセス)の円滑化: M&Aの成否はPMIで決まると言っても過言ではありません。キーマンには、新体制へ移行するまでの間、羅針盤としての役割が期待されます。業務プロセス、組織文化、暗黙知となっているノウハウなど、目に見えない経営資源を買い手へ円滑に引き継ぐ責任者が不可欠です。
- 企業価値(のれん)の維持・実現: M&Aの買収価格には、対象企業の純資産を超える「のれん(超過収益力)」が含まれます。この「のれん」の正体こそ、キーマンが長年かけて築き上げた以下のような無形資産です。
- 主要な顧客や仕入先との強固な信頼関係
- 中核となる技術・ノウハウ(特に属人性の高いもの)
- 組織を牽引するリーダーシップと企業文化
- 業界内での人脈やブランドイメージ キーマンがM&Aと同時に退任すれば、これらの無形資産は急速に毀損し、買い手が期待したシナジーや収益力(=のれん代)を実現できなくなるリスクが極めて高くなります。バリュエーションは、キーマンの残留を前提として算出されているケースが殆どです。
- 主要なステークホルダーの離反防止: 「あの社長が残るのであれば、取引(あるいは勤務)を継続しよう」という安心感は、顧客、仕入先、そして何より優秀な従業員の流出を防ぐ上で極めて重要です。キーマンの残留は、周囲への最も強力なメッセージとなります。
- 偶発債務・リスク管理: M&Aに際しては、法務・財務デューデリジェンス(DD)を徹底的に行いますが、それでも発見しきれない過去の商習慣や潜在的なリスク(簿外債務、将来の訴訟リスクなど)が存在し得ます。万が一、買収後にそうした問題が発覚した場合、経緯を最もよく知るキーマンに対応してもらう必要があります。
🔹 売り手(Sell-side)側のメリット
一方、売り手であるオーナー経営者にとっても、ロックアップを受け入れることには戦略的なメリットがあります。
- ディール(取引)の成立可能性の向上: 買い手の最大の懸念(=キーマン退任による価値毀損)を払拭することで、M&Aの交渉をスムーズに進め、取引成立の確度を高めることができます。
- 売却価格(バリュエーション)の最大化: キーマンが残留し、事業の円滑な引継ぎにコミットすることは、買い手にとってのリスク低減要因です。リスクが低いと判断されれば、より高い企業価値評価(=売却価格)を引き出す強力な交渉材料となります。
- アーンアウト(Earn-out)条項との連動: ロックアップは、しばしばアーンアウト条項と組み合わせて設計されます。【専門用語解説】アーンアウト(Earn-out)条項: M&Aの実行時点では対価の一部のみを支払い、将来、対象企業が一定の業績目標(EBITDAや売上高など)を達成した場合に、売り手に対して追加の対価を支払う仕組みです。売り手はロックアップ期間中も経営に関与し、業績目標を達成することで、M&A実行時以上の売却益を得るチャンスがあります。これは、キーマンのモチベーションを維持しつつ、買い手にとっては「期待した業績が実現した場合にのみ追加対価を払う」という合理的なリスク分担の方法です。
3. ロックアップ(キーマン条項)の厳格なルール:契約実務
キーマン条項は、最終契約書である株式譲渡契約書(SPA: Stock Purchase Agreement)または関連する付属契約書(雇用契約書、顧問契約書など)において、極めて具体的に規定されます。曖昧な定めは、将来の紛争の火種となります。
🔹 対象者(Key Person)
誰を拘束するのかを特定します。通常は代表取締役であるオーナー経営者ですが、事業の核が特定の技術者(CTO)や営業責任者にある場合、その人物も対象に含めるよう買い手から要求されることがあります。
🔹 ロックアップ期間(Duration)
実務上、最も交渉が難航する論点の一つです。期間は、事業の属人性や引継ぎの難易度によって異なります。
- 一般的な目安: 添付資料(契約ウォッチ様)では「3年ほどが一般的」とされていますが、これは一つの目安です。実務上の感覚では、1年~3年の範囲で設定されるケースが多いです。
- 事業特性による調整:
- 6ヶ月~1年程度: オペレーションが標準化されており、キーマンへの依存度が比較的低い事業。
- 2年~3年: 属人性の高い事業(例:特定のコンサルティング、職人的な技術、キーマンの人脈に依存した営業が中心の事業)。
- 長期化の弊害: 3年を超えるような長期のロックアップは、キーマンのモチベーション維持が困難になるほか、後述する法的な問題(職業選択の自由の過度な制約)を生じさせる可能性があるため、慎重な検討が必要です。
🔹 役職・権限(Position & Authority)
M&A後、キーマンがどのような立場で残るのかを明確にします。
- 例: 代表取締役(そのまま)、取締役(権限を一部委譲)、顧問、アドバイザー、フェローなど。
- 権限の明確化: 買い手から派遣される新役員との権限分掌(レポートライン、決裁権限など)を明確に定義することが、後の混乱を避けるために不可欠です。売り手オーナーが「名誉職」として残るのか、引き続き一定の「実権」を持って事業を牽引するのか、その設計がPMIの鍵となります。
🔹 報酬(Compensation)
ロックアップ期間中の報酬体系も重要な契約事項です。
- 形態: 役員報酬、顧問料、あるいは前述のアーンアウトによるインセンティブ報酬。
- 水準: M&A前の報酬水準、M&A後の職責、買い手企業の報酬体系などを総合的に勘案して決定されます。
🔹 競業避止義務(Non-Compete)
ロックアップ条項と必ずセットで規定されるのが競業避止義務です。
【専門用語解説】競業避止義務(Non-Compete): 売り手(キーマン)が、ロックアップ期間中および期間終了後の一定期間、売却した事業と競合する事業を自ら行ったり、競合他社に協力したりすることを禁止する義務です。
これは、買い手がM&Aで取得した「のれん(事業価値)」を、売り手自身によって毀損されることを防ぐための重要な防衛策です。ロックアップ期間中はもちろん、ロックアップが終了した後(例:終了後1~3年間)、どの地域で(地理的範囲)、どの事業分野を(事業範囲)禁止するのかを、法的に有効な範囲で具体的に定めます。
4. ロックアップ(キーマン条項)が解除・破棄される条件
ロックアップは永久に続くものではなく、契約で定められた一定の条件に基づき終了または解除されます。
- 期間の満了: 契約で定められたロックアップ期間(例:2年間)が経過すれば、キーマンの拘束は自動的に終了します。
- 当事者間の合意解除: 期間中であっても、引継ぎが想定より早く完了したと買い手が判断した場合など、買い手とキーマンが双方合意の上で、ロックアップを早期に解除することがあります。
- キーマンのやむを得ない事由: キーマンの死亡、あるいは業務遂行が物理的に不可能となるような重大な疾病や障害を負った場合は、ロックアップ義務は免除されるのが一般的です。
- 買い手側の契約違反(Breach of Contract): 以下のように、買い手側が契約上の重要な義務を履行しない場合、キーマンはロックアップ義務の解除を主張できる可能性があります。
- 合意した報酬(役員報酬や顧問料)が正当な理由なく支払われない場合。
- キーマンの役職を不当に解任したり、合意した権限や職務内容を不合理に変更・剥奪したりした場合(これは「擬制解雇」に近い概念と見なされることがあります)。
- チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項: これは実務上、売り手側が挿入を試みる重要な条項です。【専門用語解説】チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項: M&Aで自社を買収した買い手企業が、さらに別の第三者に買収された場合(=経営権が再度変更された場合)、キーマンは当初合意した相手(買い手)とは異なる株主の下で働くことになります。この場合、キーマンがロックアップ義務を解除し、退任を選択できる権利を定めるものです。
5. ロックアップ違反のリスク:法的なペナルティ
万が一、キーマンが正当な理由なくロックアップ(残留義務)や競業避止義務に違反した場合(例:突然退職して競合他社を立ち上げた場合)、買い手は契約に基づき法的措置を講じることが可能です。
- 損害賠償請求(Damages): 買い手は、キーマンの離脱によって被った損害(売上減少、取引先の流出、代替人材の採用・育成コストなど)の賠償を請求できます。しかし、実務上、違反行為と損害額との因果関係を立証することは非常に困難な場合があります。
- 違約金(Liquidated Damages): 損害額の立証困難性を回避するため、あらかじめ契約書に「ロックアップ条項または競業避止義務に違反した場合、キーマンは買い手に対し違約金として金X円を支払う」と定めておく方法です。ただし、金額が過度に高額である場合、公序良俗(民法90条)や職業選択の自由(憲法22条)の観点から、裁判所で無効または減額されるリスクがあります。
- 差止請求(Injunction): 競業避止義務違反の場合、競合行為そのものを差し止めるよう裁判所に請求することが可能です。
- 株式対価の減額またはクローバック(Clawback): 実務上、最も実効性が高い措置の一つです。ロックアップ違反を条件として、M&A対価の一部(特にアーンアウトや、分割払いにしている対価)の支払いを停止したり、あるいは一度支払った対価の一部を返還させたりする(=クローバック)条項を設けます。これはキーマンにとって強力な牽制となります。
6. 結論:ロックアップは「未来への戦略的な約束」
M&Aにおけるロックアップ(キーマン条項)は、単にキーマンを会社に「縛り付ける」ためのものではありません。それは、売り手が人生をかけて築き上げてきた事業という「バトン」を、買い手という次の走者へ確実に渡し、その価値をさらに高めていくための、新旧経営者間の「戦略的な約束」です。
その設計には、法的な厳密さだけでなく、人間の心理、事業の実態、そしてM&A後のビジョンへの深い共感が不可欠です。私たちM&Aアドバイザーは、この最も繊細かつ重要な「約束」の設計を通じて、M&Aの真の成功(=PMIの成功)を支援しています。
本稿が、M&Aを検討される経営者の皆様、また実務に携わる方々にとって、ロックアップ条項の重要性をご理解いただく一助となれば幸いです。
M&Aの具体的なスキームやバリュエーション、ロックアップ条項の設計に関してさらに詳しいご相談がございましたら、お気軽にお声がけください。
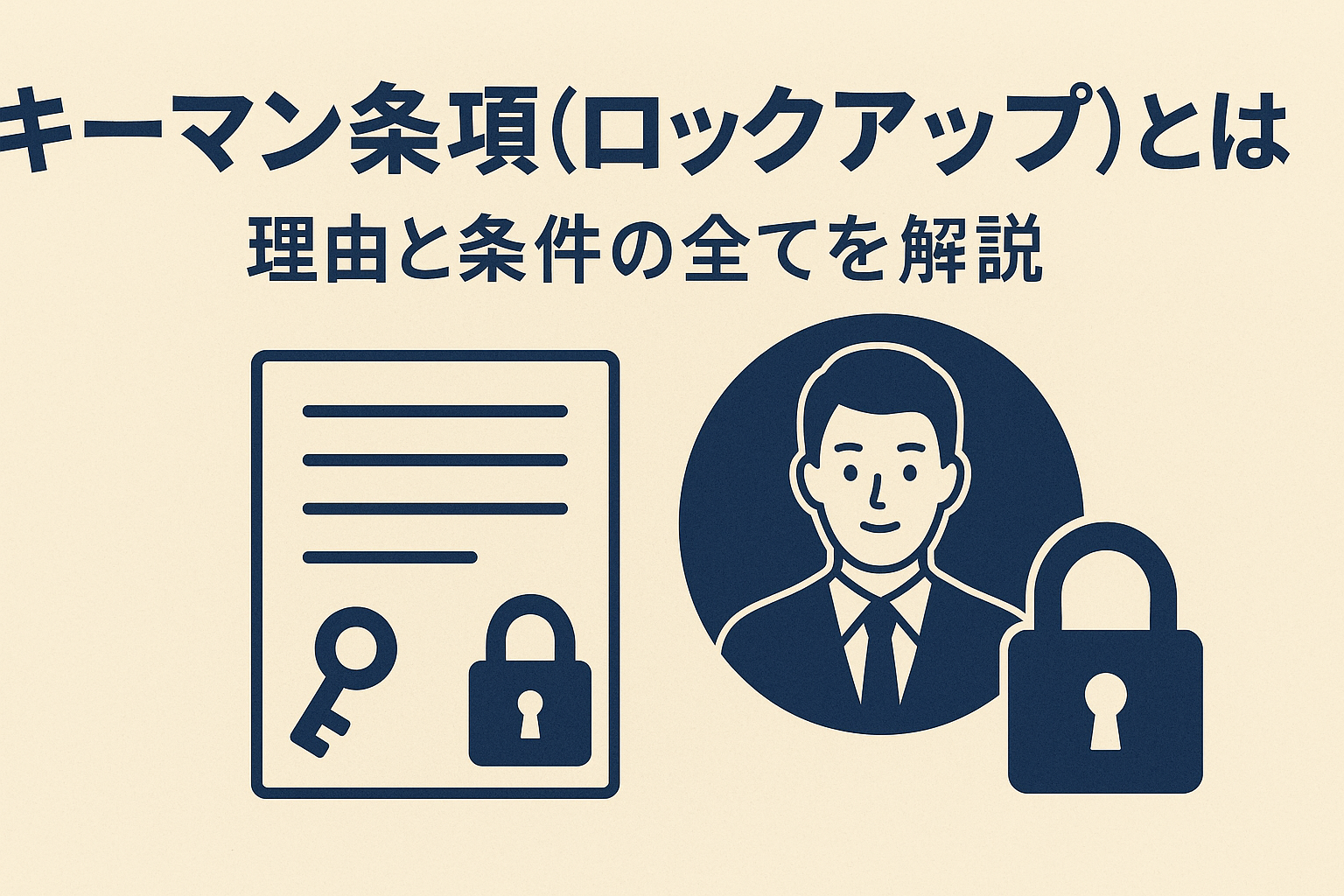



















コメント