オーナー経営者がM&A・会社売却を成約させると、多くの場合、手元にはこれまで経験したことのない規模の現金・有価証券が残ります。しかし、その瞬間から「次の戦い」が始まります。それは、
- 所得税・住民税(株式譲渡益課税など)
- 将来の相続税
- 資産運用リスク(インフレ、金利、マーケット)
との向き合いです。
とりわけ相続税は、オーナーの逝去時に一度に到来する「イベントリスク」であり、M&Aのクロージング以上にご家族の人生設計を左右します。そこで、会社売却後の資産ポートフォリオに「投資用不動産」をどう位置付けるかは、多くの富裕層にとって重要なテーマになっています。
本章では、下記について実務に即して整理していきます。なお、本章は一般的な解説であり、具体的な税務判断は必ず税理士等の専門家にご相談いただく前提でお読みください。
- 投資不動産を活用した相続税の圧縮メカニズム
- 負債(ローン)を活用した節税効果とリスク
- 2026年度税制改正を見据えた「これからの正しい設計思想」
1.会社売却と税金の全体像――どこで「相続」を意識するか
1-1. M&A・会社売却で発生する主な税金
オーナーが株式譲渡によって会社を売却した場合、原則として譲渡益に対して約20%の申告分離課税(所得税+住民税)がかかります。ここで重要なのは、
- 売却時点では「所得税の世界」
- その後の資産保有・承継は「相続税の世界」
という二段階構造になっていることです。
売却時に節税を追求するあまり、その後の相続税・資産承継の設計が歪むケースも少なくありません。M&AのFA(ファイナンシャル・アドバイザー)が本来サポートすべきは、ディールクローズだけではなく、「売却後30年」の資産設計を見据えたストラクチャリングです。
1-2. なぜ投資用不動産が相続税対策で注目されてきたのか
日本の相続税における不動産評価は、
- 土地:路線価(国税庁が公表する道路に面した土地の価格指標。一般に公示価格の約8割)
- 建物:固定資産税評価額(建築コストより低めに評価されることが多い)
をベースとします。これらは市場で実際に売買される「実勢価格」より低く算定されることがあり、特に都心部の賃貸マンションなどでは、
実勢価格:相続税評価額 ≒ 3~5:1
といった大きなギャップが生じることが珍しくありません。
この「実勢価格>相続税評価額」という構造により、
- 現金で持っていれば高く評価される
- 同額を投資用不動産に変えると評価額が低くなる
という相続税上のメリットが生じてきました。
加えて、賃貸用不動産の場合には、
- 借家権割合・貸家建付地(かしやたてつけち)の評価減
- 賃貸用であることにより、所有者が自由に利用できない制約を反映して評価を下げる仕組み
が働くため、さらに評価圧縮効果が増す構造になっています。
2. 投資不動産を活用した相続税圧縮のメカニズム
ここからは、①でご要望のあった「投資不動産を活用した相続税の圧縮効果」を、数値イメージを交えながら整理します。
2-1. 現金と不動産でどれくらい評価が変わるか
極めて単純化した例ですが、イメージとして以下のようなパターンが典型です。
- ケースA:現金10億円をそのまま相続
- 相続税評価額:10億円
- ケースB:現金10億円で都心の賃貸マンションを購入
- 実勢価格:10億円
- 相続税評価額(路線価+固定資産税評価+貸家建付地等の補正後):概ね5~7億円程度に圧縮されるケースがある
もちろん、物件の場所・築年数・賃貸状況によって大きく変わりますが、「現金=100」に比べ、不動産では「60~70程度」に評価が圧縮される構造が、従来の相続対策で広く利用されてきました。
2-2. 「借家権」と「貸家建付地」による評価減
専門用語を簡潔に整理します。
- 借家権(しゃっかけん):
賃借人(入居者)が有する権利。オーナーは自由に退去を求めにくく、その分だけ土地・建物を自由に使えないという制約があります。 - 貸家建付地:
賃貸用建物が建っている土地のこと。土地を自分の住居として自由に使えないため、その分評価を下げるルールがあります。
これらを反映した評価式により、賃貸マンションは自用(自宅)マンションより相続税評価額が下がる仕組みになっています。
2-3. 典型的なM&Aオーナーのパターン
実務でよく見るのは、次のような流れです。
- 会社売却で譲渡対価10~30億円規模の現金を取得
- 一部を上場株式・投資信託・預金で運用
- そのうち数億~十数億円を投資用不動産(賃貸マンション、一棟ビルなど)に振り向ける
- インカム(賃料収入)と相続税評価の圧縮効果を同時に狙う
ここまでは「教科書的な」相続・資産運用の組み立てです。ただし、近年はこれが行き過ぎた形で商品化され、「節税メリット」を過度に強調する販売手法が社会問題化してきました。
3.投資不動産節税スキームへの逆風――2026年度税制改正の方向性
3-1. 「路線価評価から購入価格ベースへ」の流れ
ご提示いただいたニュースのとおり、政府・与党は投資用不動産を利用した相続税節税の抑制に向け、評価基準の見直しを本格検討しています。
報道ベースでは、
- 投資用不動産の相続税評価を、従来の路線価等ではなく「購入時の価格」を基準にする
- 節税目的の駆け込み取得を抑制するため、「購入から5年以内に相続された賃貸用不動産」を対象とする
- 2026年度(令和8年度)税制改正大綱に明記する方向
とされています。
政府の調査事例として、
- 現金のまま相続すると相続税12.3億円
- 投資用不動産に組み替えることで、相続税が4.4億円まで低下
という極端なケースが紹介され、こうした行き過ぎた節税を是正することが政策目的と明言されています。
3-2. 小口化商品・不動産クラウドファンディングへの影響
少額から投資可能な「不動産小口化商品」や一部の不動産クラウドファンディング商品についても、相続税逃れとして問題視されており、
- 現行の通達評価(路線価等)ではなく、取引価格(購入価格)ベースで評価
- 購入時期にかかわらず、実勢価格を反映した評価方法に見直す
方向で議論が進んでいます。
これにより、
- 「現金を小口化商品に変えただけで評価が1/3~1/5になる」
といったスキームは、今後ほぼ成立しなくなる可能性が高いと見込まれます。
3-3. タワーマンション、一棟物への追加是正
すでにタワーマンションの相続税評価については、2024年改正で「区分所有補正率」による評価引き上げが導入されましたが、一棟賃貸マンション・一棟ビルも含め、
- 実勢価格とかけ離れた評価が出る物件の評価ルールを見直す
- 統計的手法や鑑定評価等を取り入れ、市場価格に近い評価を目指す
といった議論が進んでいます。
結論として、今後10年スパンで見れば「不動産で現金を極端に圧縮する」タイプの相続税対策は、制度上ほぼ封じられる方向にあると認識しておくべきです。
4. 負債を活用した節税術――レバレッジの本質とリスク
次に、②のテーマである「負債を活用した節税」について整理します。
4-1. 相続税における借入金の位置付け
相続税では、被相続人が負っていた借入金(ローン)は、原則として相続財産から控除できます。
- 「遺産の総額(資産)」-「債務(借入金等)」=「課税価格」
という計算式になるため、
- 借入を起こして投資用不動産を取得
- 不動産は相続税評価で「圧縮」
- 一方で借入金は額面で「満額控除」
となる場合、相続税の課税ベースを大きく下げることができます。この構造が、「レバレッジ(負債)を活用した不動産相続税対策」の中核です。
4-2. 数値イメージによる比較
非常に単純化した例を示します(税率や細かな特例は無視しています)。
- パターン1:現金10億円のみ
- 資産:現金10億
- 借入:0
- 課税価格:10億
- パターン2:自己資金2億+借入8億で10億円の賃貸マンション取得
- 資産:賃貸マンション(実勢10億、相続税評価6億と仮定)
- 借入:8億
- 課税価格:6億-8億=▲2億(マイナス部分は他の財産と通算)
現実にはここまで極端なケースは稀ですが、
「評価額が圧縮された資産」-「額面の借入金」
という構図が、負債を活用した相続税対策のキモであることはご理解いただけると思います。
4-3. 「節税」と「破綻リスク」は表裏一体
ただし、ここで誤解してはならないのは、
- 借入金は相続税評価上のマイナスだが、
- キャッシュフロー上は毎月の返済負担として重くのしかかる
という事実です。M&Aで会社を売却した後、個人として大きな借入を組んで投資用不動産を購入したケースでは、
- 金利上昇
- 賃料下落・空室増加
- 修繕費の想定外増加
- 相続人が返済を引き継げず、物件売却を余儀なくされる
といったリスクが顕在化すると、節税どころか、家族の生活基盤そのものを揺るがしかねません。
また、節税目的が前面に出過ぎたスキームは、税務調査で否認されるリスクがあります。形式上は合法であっても、実態として合理性に欠けると判断されれば、租税回避行為として指摘される可能性はゼロではありません。
4-4. プロの視点からみる「レバレッジ許容度」
実務的には、
- 不動産から得られるNet Cash Flow(税引前キャッシュフロー)
- 金利上昇のストレスシナリオ
- 相続人の年収・金融資産規模
を踏まえ、「無理なく30年持ち切れる借入水準か」を試算した上で、レバレッジの上限を決めるべきです。M&Aで数十億円の現金を得たオーナーであれば、「フルローンでレバレッジ最大化」よりも、
- 自己資金多め
- 借入比率は50%前後まで
- 金利上昇時にもキャッシュフローがマイナスにならない範囲
といった慎重な設計の方が、トータルのリスク・リターンはむしろ合理的です。
5. 事例ベースで見る「良い投資不動産活用」と「危ない節税スキーム」
ここからは、実務でよく目にするパターンを、匿名化したケースとして整理します。
5-1. ケース1:会社売却後に一棟レジを組み込んだ「王道パターン」
- オーナーAさん:IT企業を株式譲渡で売却、手取り20億円
- うち5億円を都心の一棟レジデンス(賃貸マンション)に投資
- 借入なし、もしくはLTV 30~50%程度
このケースでは、
- 賃料収入で年間2~3%程度のインカム
- 相続税評価額は実勢価格よりも低くなり、一定の圧縮効果
- レバレッジを無理にかけないため、金利・空室リスクも限定的
という、バランスの取れた「資産防衛+相続対策」として機能しやすいパターンです。
5-2. ケース2:節税メリットを前面に出したフルレバレッジ型
- オーナーBさん:会社売却後の現金は預金と金融商品で保有
- 銀行提携の不動産会社から「相続税が半分になります」と提案
- 自己資金1億円+借入9億円で、一棟賃貸マンションを購入
当初は相続税評価上のメリットが見込めても、
- その後の金利上昇
- 修繕費の増加
- 2026年度以降の評価見直し
が重なると、想定していた節税メリットが消え、借入だけが残るという事態になりかねません。
とりわけ今後は、
- 購入から5年以内の相続では購入価格ベースで評価
- 一棟物・タワーマンションの評価ルールが更に是正
される方向であるため、「今のルールが続く前提」でフルレバレッジ投資を行うのは極めて危険です。
5-3. ケース3:不動産小口化商品・クラウドファンディングを利用したスキーム
- 「3,000万円で小口化不動産を購入、評価は480万円」
- 「その後、取得価額とほぼ同額で売却し現金化」
といった事例が国税庁資料でも紹介され、過度な節税効果を生むスキームとして問題視されています。2026年度改正では、これらの小口化商品は、
- 取引価格(購入価格)ベースで評価
- 相続税・贈与税の評価額が大幅に引き上がる可能性
が高く、「小口だから安全」「少額だから税務当局も見ない」という発想は通用しなくなると考えるべきです。
6. M&Aアドバイザーの視点から見た、投資不動産活用の「設計順序」
ここで一度、「M&A後の資産設計」としての全体フレームを整理します。
6-1. ステップ1:売却前から出口後30年をシミュレーション
本来、M&AのLetter of Intent(意向表明書)や株式譲渡契約書のドラフティング段階から、
- 売却後にどの程度の生活費が必要か
- どの程度のリスク資産(株式・PE・VC等)を持てるか
- どの程度の不動産比率が妥当か
を、30年スパンでシミュレーションしておくのが理想です。
投資用不動産の取得は、「相続税を減らすため」ではなく、
- インフレ耐性
- キャッシュフローの安定性
- 他資産との相関の低さ
といったポートフォリオ上の役割から位置付けるべきであり、相続税効果はあくまで「副産物」と考えた方が、長期的には合理的な結果になりやすいと感じています。
6-2. ステップ2:税制変更リスクを前提にしたシナリオ設計
2026年度改正を含め、今後も「実勢価格に近づける方向」の見直しは続くと想定すべきです。したがって、投資不動産の相続税評価をシミュレーションする際は、
- 現行ルールベースの評価
- 改正後(購入価格ベース、補正率見直し後など)の評価
の両方を試算し、**「制度改正後でも破綻しないプランか」**をチェックしておくことが重要です。
6-3. ステップ3:レバレッジの上限と「流動性バッファ」
投資用不動産は、
- 取引コスト(仲介手数料・登録免許税・不動産取得税等)が高い
- 売却まで時間がかかり、価格もブレやすい
という意味で「流動性の低い資産」です。
M&A後のオーナー資産ポートフォリオとしては、
- 流動性の高い金融資産(預金・国債・上場株式・ETF等)
- 流動性の低いリアルアセット(投資用不動産、PE等)
の間でバランスを取り、「いざというときに不動産を売らなくても済む」だけのキャッシュバッファを確保しておくことが、結果的にご家族を守ることにつながります。
7. これからの「王道」――節税から資産承継設計へ
ここまで見てきたように、
- 投資用不動産を活用した相続税圧縮は、仕組みとしては確かに存在する
- しかし、行き過ぎたスキームは2026年度改正を中心に制度上封じられる方向
- レバレッジを過度に用いた節税は、税務リスク・破綻リスクの両面で危険
というのが、現時点での冷静な結論です。
- 「節税の多寡」ではなく、「家族が安心して使えるキャッシュフロー」と「資産の持続可能性」を軸に設計すること
- 税制改正リスクを織り込んだうえで、投資用不動産をポートフォリオの一部として適切な比率で組み入れること
- レバレッジ(負債)は、相続人の返済能力と金利シナリオを前提に「保守的に」設定すること
M&A・会社売却はゴールではなく、「資本家としての新しいスタート」です。投資用不動産は、そのスタート後の資産防衛・相続設計において有力なツールであり続けるでしょう。しかし、その使い方は、「節税商品を買う」という発想から、「家族のバランスシートをデザインする」という発想へと、確実に進化させなければなりません。
本章が、M&A後の資産設計と投資用不動産の位置付けを再考する一助となれば幸いです。なお、個別案件では、必ずM&Aアドバイザー・税理士・不動産鑑定士・弁護士等とチームを組み、法令遵守とリスク管理を前提に検討を進めていただくことを、改めて強調しておきます。
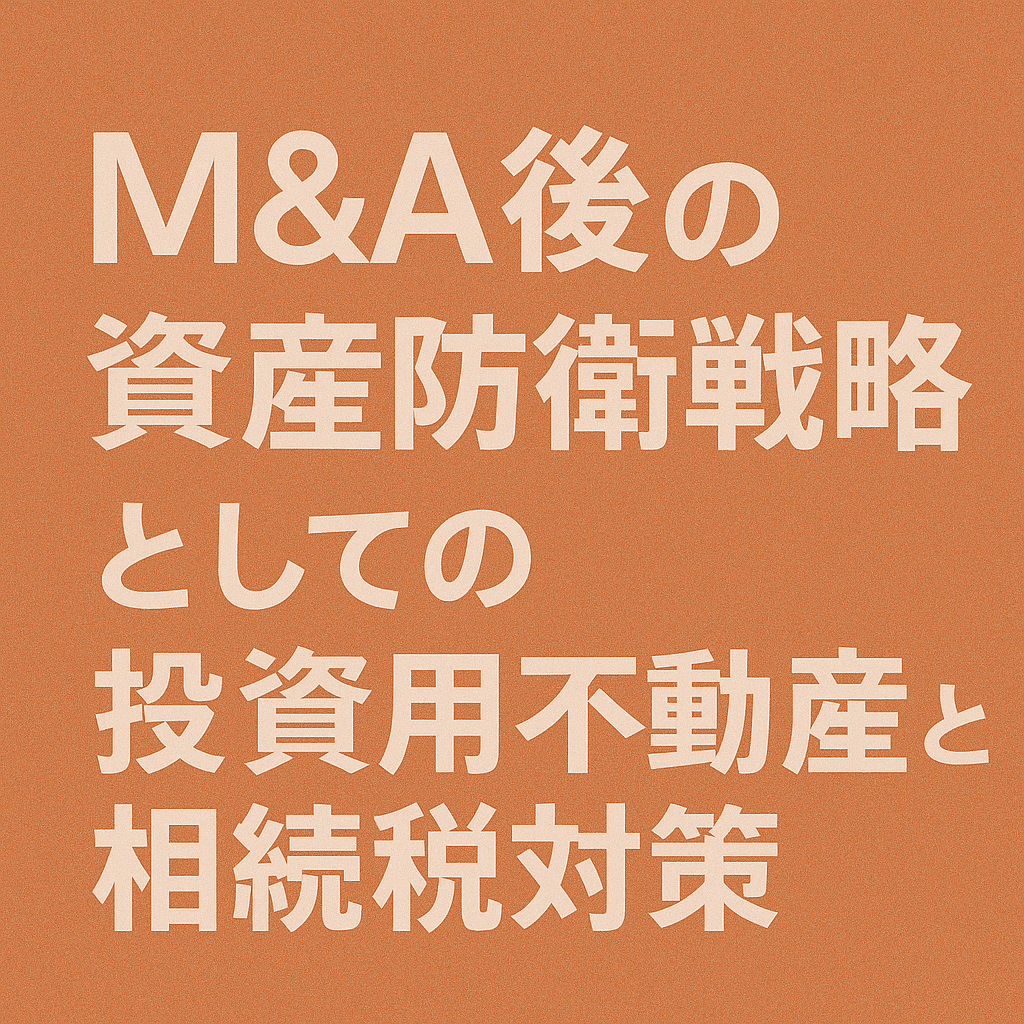



















コメント