まず、客観的な事実を確認しましょう。下図のチャート(M&Aキャピタルパートナーズ、日本M&Aセンター、ストライク、M&A総研)をご覧ください。日経平均株価がバブル後最高値を更新し、市場全体がリスクオンムードにある中で、M&A仲介セクターの株価は軒並み軟調、あるいは暴落といってよい推移を辿っています。

彼らは「高成長・高収益・高財務」の優良企業ではないのか? 市場はなぜ、彼らにこれほど低いPER(株価収益率)とPBR(株価純資産倍率)を付与しているのか?答えはシンプルです。「市場は、彼らの資本政策(Capital Allocation)を全く信用していない」からです。
仲介事業により稼ぐ力(PL:損益計算書)は一流でも、稼いだ現金をどう使うか(BS:貸借対照表)の能力が欠如している。投資家はそれを見透かしており、今回のM&Aキャピタルパートナーズ(株価コード:6080)への株主提案は、その不満が臨界点に達したことを示す象徴的なイベントなのです。
第1章:MACPへの株主提案はなぜ「極めて合理的」なのか
投資ファンドのPanah Master Fundが提出した株主提案書を拝読しましたが、その内容はファイナンス理論の教科書に載せても良いほど論理的であり、極めて正当な要求です。
1. 異常な余剰金滞留
提案書にある通り、MACPは時価総額の約41%に相当する419億円もの現預金を保有しています 。一方で、同業他社の中央値は約12%に過ぎません 。 ファイナンスにおいて、使途のない過剰な現金は「罪」です。なぜなら、現金はインフレ調整後では実質価値が目減りする資産であり、かつ株主が期待する要求収益率(コスト・オブ・エクイティ、通常8〜10%程度)を大きく下回る0.01%程度の金利しか生まないからです 。現金をただ寝かせているだけで、企業価値(ROE)は数学的に低下し続けます 。これを「キャッシュ・ドラッグ」と呼びますが、M&Aのプロを自称する企業がこの初歩的な罠に陥っているのは皮肉以外の何物でもありません。
2. 「成長投資のため」という弁解内容が非合理的
会社側は書面に記載された反対意見の中で「インオーガニック成長(M&A)のための資金が必要」と主張しています 。しかし、これは以下の2点において合理性を欠いています。
- アセットライト・モデルの矛盾: M&A仲介業は工場も在庫も不要な装置産業ではありません。運転資本はマイナスであり、巨額の設備投資は不要です 。数百億円規模の内部留保を正当化する事業上の理由は存在しません。
- トラックレコード(実績)の欠如: 過去に実施した株式会社レコフの買収(30億円)やフロンティア・マネジメントへの出資などは、株主価値を毀損していると指摘されています 。投資の実績が乏しい、あるいは失敗している経営陣に「将来のために預けておいてくれ」と言われても、株主が首を縦に振らないのは当然の理です。
第2章:上場の目的は誰のためか? ——「創業者と従業員」のためのIPO
ここで一つの問いが浮かびます。「M&A仲介会社は、一体誰のために上場したのか?」通常、上場(IPO)の主たる目的は「資金調達」です。しかし、前述の通り彼らのビジネスモデルに巨額の資金は不要です。ではなぜ上場するのか。それは以下の2点に集約されます。
- 社会的信用(コンフィデンス): オーナー社長に会社を売ってもらう際、「上場企業なら安心」と思わせるため。
- 人材採用: 激務であるM&Aアドバイザーを採用するためのブランド力とストックオプションのため。
つまり、彼らの上場は「事業運営上の信用補完」が目的であり、「投資家からの資金活用」は目的ではなかったのです。 しかし、上場企業となった瞬間から、会社は株主(投資家)のものとなります。
「上場のメリット(信用)は享受するが、上場の義務(資本コストを上回る還元)は負いたくない」 現在の株価低迷は、この「いいとこ取り」に対する市場からの痛烈なしっぺ返しです。会社側が「内部留保は安定性のため」と言えば言うほど、投資家は「それは経営陣の保身(エージェンシー・コスト)であり、株主利益の最大化ではない」と判断し、ディスカウント評価を下すのです。
第3章:「取引のプロ」と「投資のプロ」の決定的な断絶
今回の問題の核心は、M&Aアドバイザーという職業の性質そのものにあります。ここからは、ご質問にあった「アドバイザーの投資センス欠如」について深掘りします。
1. フロー脳(仲介) vs ストック脳(投資)
M&Aアドバイザーは、本質的に「ブローカー(仲介者)」です。彼らのKPI(重要業績評価指標)は「成約件数」と「手数料」であり、ディールが成立した瞬間に勝利が確定します。 その会社が買収後に成長しようが破綻しようが、アドバイザーの報酬には原則として影響しません。つまり、彼らは「PL(損益計算書)」に特化します。
一方で、投資家や経営者は「BS(貸借対照表)の住人」です。「投下した資本が、将来にわたってどれだけのリターンを生むか」という長期的な時間軸で思考します。MACPの経営陣が「現金を積み上げること」に安心感を覚えるのは、彼らが根っからの「ブローカー気質」だからです。現金を「次の利益を生むための種銭(Capital)」として見ず、「過去の取引の戦果(Cash)」として金庫にしまってしまう。この思考様式の断絶こそが、非合理な資本政策の元凶です。
2. 経歴が招く「投資センスの欠落」
大手M&A仲介会社のアドバイザーや経営陣の多くは、銀行、証券、監査法人といった厳格な規制業種の出身者です。 彼らは若手時代から、インサイダー取引防止規定により「個別株投資」を厳しく禁じられています。
- 痛みの不在: 自腹を切ってリスクを取り、株価の変動に一喜一憂し、損切りの断腸の思いを経験したことがありません。
- Excel上のバリュエーション: 彼らにとっての企業価値評価とは、DCF法などの数式を埋める「事務作業」です。「市場心理(センチメント)がどう動くか」「投資家が何を求めているか」という「相場観(相場の呼吸)」が欠落しています。
プロとして他人の企業価値(バリュエーション)を語りながら、自分の財布でリスクを取った経験がない。これは「泳いだことのない水泳コーチ」のようなものです。 結果として、自社の株価(自社のバリュエーション)が放置されていても、その痛みや危機感を肌感覚として理解できない。「業績は良いのになぜ?」と首をかしげるだけで、有効な手(大規模な自社株買いや配当性向の抜本的引き上げ)を打てないのです。
第4章:失敗した投資案件が証明するもの
MACPの株主提案において、過去の投資(Recof、フロンティア・マネジメント)の失敗が指摘されています 。これは非常に示唆に富んでいます。M&A仲介会社が「自己資金投資(プリンシパル投資)」に手を出すと、往々にして失敗します。なぜなら、彼らは「ディールを成立させるための妥協点を見つけるプロ」であって、「安く買って高く売るプロ」ではないからです。
仲介業務では「売り手と買い手の真ん中」に立つことが正義ですが、投資業務では「買い手として極限まで安く買う」ことが正義です。このマインドセットの切り替えができないまま投資を行うため、高値掴みをしたり、シナジーのない案件に手を出したりします。株主からすれば、「投資の素人であるあなたたちが運用するくらいなら、配当として返してくれ。私たちが自分で運用する(あるいはS&P500を買う)から」という主張は、100%合理的です。
第5章:結論 —— ガバナンス改革なくして株価回復なし
以上の分析から導き出される結論は明確です。
- 株主提案は「経営の正気」を取り戻すための良薬: 特別配当による資金の吐き出しは、ROEを劇的に改善させ 、資本コスト経営への回帰を促します。これは短期的な利益還元にとどまらず、経営陣に対し「資本の重み」を理解させる教育的効果も持ちます。
- 「取引屋」からの脱却: M&A仲介各社が今後、プライム市場の上場企業として評価されるためには、「案件を回す力」だけでなく、「資本を配分する力(Capital Allocation Skill)」を証明しなければなりません。
- 投資家の視点: 現状のM&A仲介セクターは、「バリュエーション・トラップ(割安の罠)」の状態にあります。PERが低いからといって安易に買い向かうのは危険です。なぜなら、その現金が有効活用されない限り、理論株価は上昇しないからです。
「 M&A仲介業が誰のために上場したのか」。 その答えを「創業者のため」から「株主を含む全ステークホルダーのため」へと再定義できた企業だけが、この株価暴落のトンネルを抜け出し、真の「投資銀行」へと進化できるでしょう。
今回のMACPへの株主提案は、日本の株式市場が「形だけのガバナンス」から「実効性のあるガバナンス」へと脱皮できるかどうかの試金石となる重要なイベントです。一人の実務家として、そして市場の規律を重んじる者として、この提案が合理的な結末を迎えることを強く支持いたします。
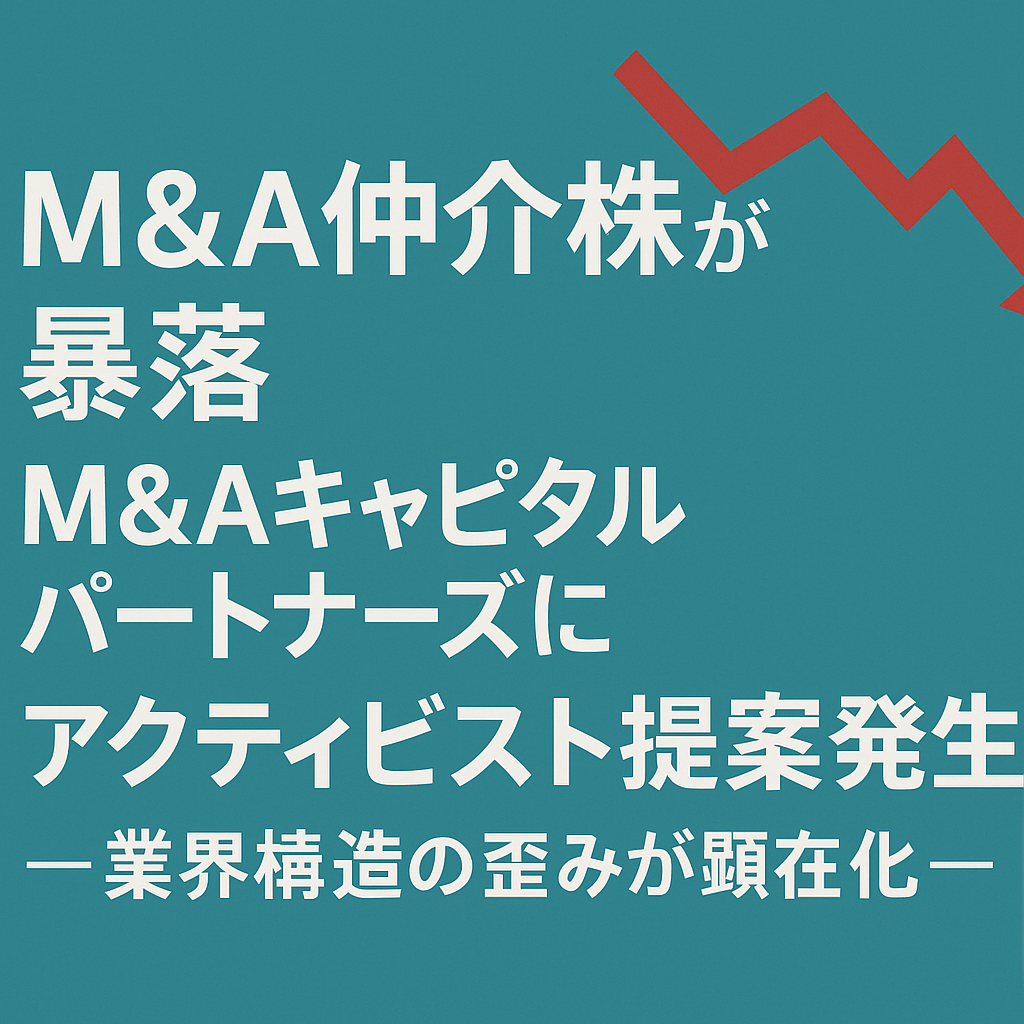





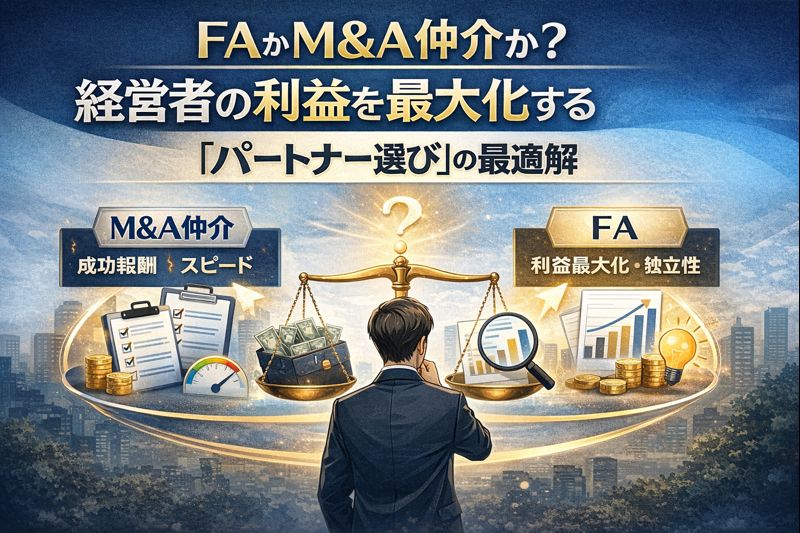
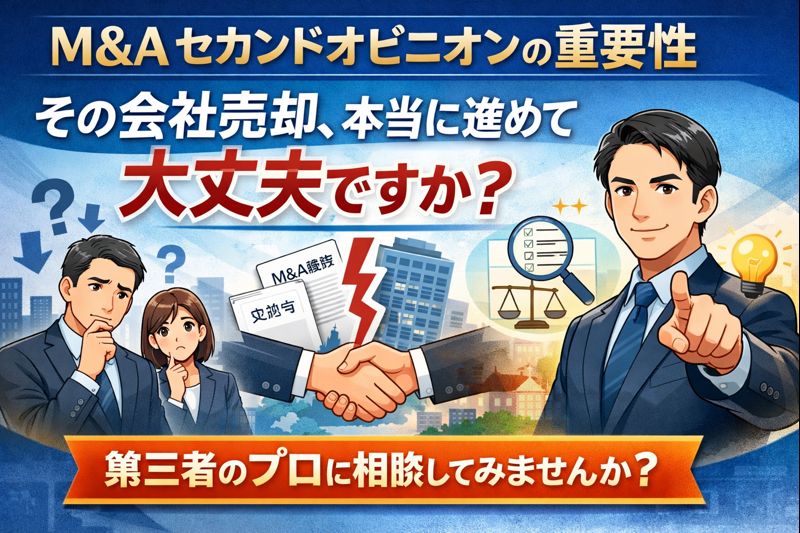

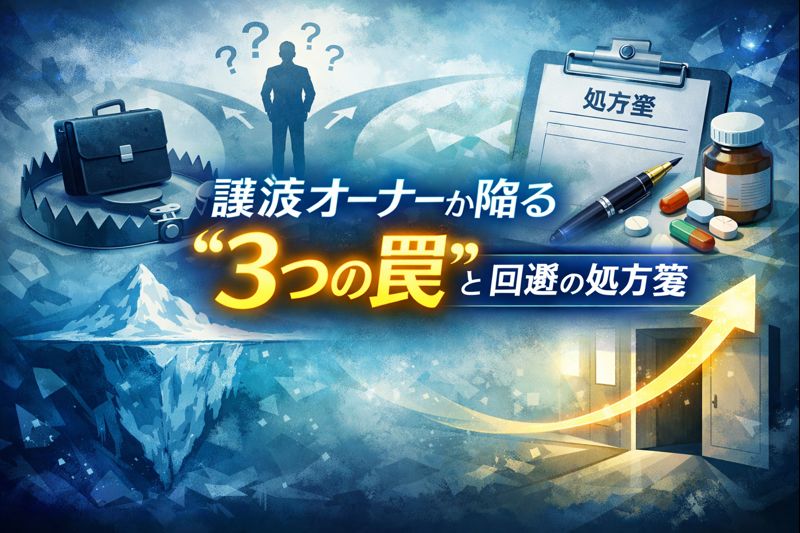

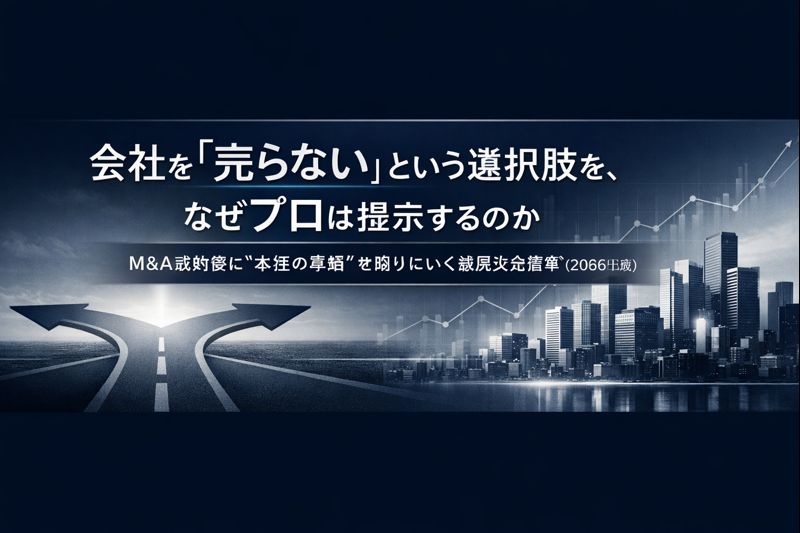


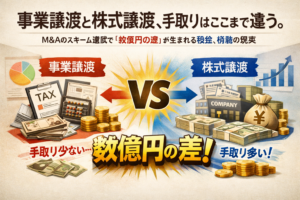

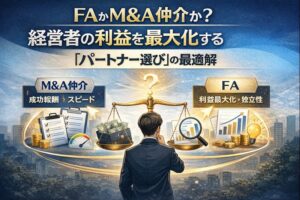


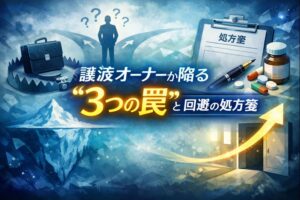
コメント