M&A(企業の合併・買収)は、単なる事業の売買に留まらず、オーナー様や企業にとって、これまでの努力を結実させ、次なるステージへと進むための重要な経営判断です。私たちM&Aアドバイザーは、その決断の瞬間に立ち会い、企業価値(バリュエーション)の算定から、最適な相手先との交渉、そして取引(ディール)の完遂までをサポートする責務を担っています。
そのプロセス全体において、私たちが最も重要視する指標の一つが、「手残り金額」です。どれほど高い価額で売却が合意に至ったとしても、最終的に手元に残る金額が想定より少なければ、そのM&Aは成功とは言えません。そして、この「手残り」に最も大きな影響を与える要素こそが、「税金」に他なりません。
M&Aの税務は、選択するスキーム(手法)、売り手と買い手の属性(個人か法人か)、そして取引の細かな条件設定によって、驚くほど複雑に、そして劇的に変化します。税率が20%で済むと思っていた取引が、スキームの選択を誤ることで50%以上の税負担になることも、実務上は珍しくありません。
この記事では、M&Aアドバイザーとして、日々バリュエーションとスキーム構築の実務に携わる立場から、M&Aにおける売却時の税率を中心とした税務の要諦を、法務・会計・税務の観点から、専門的かつ実践的に解説してまいります。
株式譲渡と事業譲渡という二大手法から、個人と法人の間での取引、さらにはM&Aの最前線とも言える「アーンアウト条件」の税務まで、皆様がM&Aという重要な航海に出る際の「羅針盤」となることを願っています。
第1章: M&Aにおける売却スキームと税務の基本原則
M&Aの税務を理解する上で、まず押さえるべきは「誰が、誰に、何を売るのか」という取引の構造です。税金は、この構造によって課税される主体と税率が根本的に変わるためです。
1-1. 主な売却スキーム:株式譲渡と事業譲渡
M&Aの売却手法は多岐にわたりますが、中小企業から大企業まで最も多用されるのが「株式譲渡」と「事業譲渡」です。
- 株式譲渡 (Stock Sale):
- 概要: 売り手(株主)が保有する対象会社の「株式」を、買い手に売却する手法です。
- 特徴: 会社の支配権(経営権)が株主から買い手へ移転します。会社自体はそのまま存続し、その「所有者」が変わるだけです。手続きが比較的簡便であり、M&Aの主流となっています。
- 税務上のポイント: 売り手である「株主」に税金が課されます。
- 事業譲渡 (Asset Sale):
- 概要: 対象会社が保有する「事業」(資産、負債、従業員、ノウハウなど)の一部または全部を、買い手に売却する手法です。
- 特徴: 会社そのものではなく、会社の「中身」である事業を選別して売買します。買い手は、必要な資産だけを引き継ぎ、不要な負債(特に簿外債務や偶発債務)を引き継がなくて済むというメリットがあります。
- 税務上のポイント: 売り手である「会社(法人)」に税金が課されます。
1-2. 課税の対象:「譲渡益(キャピタルゲイン)」
税金は、売却価額の全額に対して課されるわけではありません。原則として、「儲け」に対して課税されます。この「儲け」を、税務上「譲渡益(キャピタルゲイン)」と呼びます。
基本的な計算式は以下の通りです。
譲渡益 = 売却価額 - 取得費(簿価) - 譲渡費用
- 取得費(簿価):
- 株式譲渡の場合:その株式を「取得した時の価額」(例:創業時の出資額、他人から購入した価額)。
- 事業譲渡の場合:売却する資産・負債の「帳簿上の価額(簿価)」。
- 譲渡費用:
- M&Aアドバイザーへの手数料、デューデリジェンス費用など、売却のために直接要した費用。
この「譲渡益」に対して、選択したスキームと売り手の属性に応じた「税率」が乗じられ、納税額が確定します。
第2章: 【王道】株式譲渡の税務:個人と法人の違い
M&Aで最も一般的な株式譲渡。ここでは、売り手が「個人」の場合と「法人」の場合の税率の違いを明確に解説します。
2-1. 個人株主(オーナー経営者など)が売却する場合
非上場会社(オーナー企業)のM&Aにおいて、最も典型的なケースです。
- 課税対象: 株式の譲渡益(キャピタルゲイン)
- 税率(非上場株式):申告分離課税 20.315%
- (内訳:所得税 15% + 復興特別所得税 0.315% + 住民税 5%)
これが、M&Aの出口戦略(Exit)において株式譲渡が好まれる最大の理由です。
例えば、創業時に1,000万円出資して設立した会社の株式が、10億円で売却できた場合(取得費1,000万円、譲渡費用なしと仮定)、
- 譲渡益:10億円 - 1,000万円 = 9億9,000万円
- 税額:9億9,000万円 × 20.315% ≒ 約2億112万円
- 手残り:10億円 - 約2億112万円 ≒ 約7億9,888万円
となります。
【重要】申告分離課税とは?
給与所得や事業所得など、他の所得とは「分離」して、個別に税額を計算する方式です。日本の所得税は、合算するほど税率が上がる「累進課税」(最高税率約55%)が原則ですが、株式譲渡益は、いくら高額になっても一律20.315%の税率が適用されます。これは、投資を促進するための政策的な優遇措置と言えます。
【実務上の留意点:取得費】
創業から長い年月が経過している場合、創業時の出資額(取得費)を証明する資料が散逸しているケースがあります。取得費が不明な場合、税務上「売却価額の5%を取得費とみなす」というルール(概算取得費)がありますが、これを使うと著しく不利になります(上記例では、10億円の5%=5,000万円が取得費となり、譲渡益が9億5,000万円に膨らんでしまいます)。M&Aを検討する際は、自社の株式の取得費を明確にする書類(定款、出資証書、契約書など)を事前に確認しておくことが肝要です。
2-2. 法人株主(親会社など)が売却する場合
親会社が子会社の株式を売却するケースや、投資会社が投資先株式を売却するケースです。
- 課税対象: 株式の譲渡益(会計上の「売却益」に近い概念)
- 税率: 法人税等(実効税率 約30%前後)
個人の場合と異なり、「申告分離課税」のような優遇措置はありません。
株式譲渡益は、その法人の本業の利益や他の損失と「合算(損益通算)」され、最終的な「課税所得」に対して、法人税、地方法人税、事業税、住民税などが課されます。この合算された税率を「実効税率」と呼び、一般的に約30%前後となります。
- メリット:
- もし会社全体として赤字(欠損金)であれば、株式譲渡益が出ても、その赤字と相殺できるため、税負担が発生しない(あるいは軽減される)場合があります。
- デメリット:
- 会社全体が黒字であれば、譲渡益に対して約30%の税率が課されるため、個人の20.315%と比べて税負担が重くなります。
第3章: 事業譲渡の税務:二重課税の罠と「のれん」
次に、事業譲渡のスキームを見ていきましょう。これは株式譲渡と比べて、税務の論点が格段に複雑になります。
3-1. 売り手(法人)の税務
- 課税対象: 事業の「譲渡益」
- 事業譲渡では、売却する資産・負債を一つ一つ時価で評価し直し、その「時価(売却価額)」と「簿価」の差額の合計が譲渡益となります。
- 税率:法人税等(実効税率 約30%前後)
- これは法人株主が株式を売却した場合と同様、会社の利益として合算されます。
3-2. 最大の論点:「消費税」
事業譲渡のM&A実務において、交渉のテーブルで必ず議題となるのが「消費税」です。
- 株式譲渡: 株式(有価証券)の譲渡は、消費税法上「非課税取引」です。したがって、10億円で株式を売買しても、消費税は発生しません。
- 事業譲渡: 事業に含まれる「課税資産」の譲渡には、消費税が課税されます。
- 課税資産の例: 建物、機械設備、車両、棚卸資産(在庫)、そして「のれん(営業権)」
- 非課税資産の例: 土地、有価証券、債権
例えば、事業の売却価額が10億円で、そのうち課税資産(建物や「のれん」)の価額が6億円だった場合、
- 6億円 × 10%(消費税率) = 6,000万円
の消費税が発生します。この6,000万円は、売り手法人が買い手法人から預かり、国に納税する必要があります。
(※買い手法人は、原則としてこの6,000万円を「仕入税額控除」できるため、最終的な負担は(多くの場合)ありませんが、一時的なキャッシュフローには影響します。M&Aの契約交渉において、取引価額が「税抜(消費税別)」なのか「税込(消費税込み)」なのかは、数千万円単位の差を生むため、極めて重要な交渉項目となります。
3-3. 買い手の税務メリット:「税務上のれん」
事業譲渡は、買い手にとって大きな税務メリット(タックスシールド)を生む可能性があります。
- のれん(営業権):
- M&Aの買収価額が、対象事業の「純資産時価」を上回る場合の差額を指します。いわば、ブランド力、技術力、顧客基盤といった「目に見えない価値」の対価です。
- 税務上のれん:
- 事業譲渡において生じた「のれん」は、税務上**「5年間で均等償却(損金算入)」**が認められます。
例えば、買い手が5億円の「のれん」を計上した場合、毎年1億円(5億円÷5年)を「費用(損金)」として計上できます。法人税の実効税率を30%と仮定すると、
- 1億円 × 30% = 3,000万円
年間3,000万円、5年間で合計1億5,000万円の「節税効果」が生まれることになります。これは買い手にとって、事業譲渡を選択する強いインセンティブとなります。
3-4. オーナー経営者の「手残り」の罠:二重課税
事業譲渡は、買い手にはメリットがある一方で、売り手(特にオーナー経営者)にとっては、最終的な「手残り」において大きな罠があります。
- 【第1の課税】法人税
- 会社が事業を売却し、10億円の利益が出たとします。
- この10億円に対し、法人税等(約30%)が課税されます。
- 税引後利益:10億円 × (1 – 30%) = 7億円
- この7億円は、あくまで「会社」に残っているお金です。
- 【第2の課税】配当課税 / 給与所得課税
- オーナー経営者が、この7億円を「個人」として手にするためには、会社から「配当」または「役員報酬」として引き出す必要があります。
- 配当の場合: 非上場株式の配当は「総合課税」となり、他の所得と合算され、最大で約55%(所得税+住民税)の税率が課されます。
- (7億円 × 55% = 約3億8,500万円の税金)
【結論】
株式譲渡であれば、10億円の売却益に対する税金は約2億円(20.315%)で済みました。一方、事業譲渡を経由して個人が手にしようとすると、法人税(3億円)+配当課税(約3億8,500万円)で、合計6億8,500万円以上の税金がかかる計算となり、税率が68%を超えてしまいます。これが「二重課税」と呼ばれる現象です。もちろん、事業の一部だけを売りたい場合や、買い手が簿外債務を嫌う場合など、事業譲渡を選択せざるを得ない、あるいは選択すべきケースも多々あります。
重要なのは、この税構造の違いをM&Aアドバイザーが正確に理解し、売り手オーナーの最終的な「手残り」がいくらになるのかを、スキーム立案の初期段階でシミュレーションすることです。
第4章: 特殊な譲渡と配当の税務:時価と保有比率
M&Aの周辺、あるいはM&A後の資本政策において論点となる、特殊な取引と配当の税務について解説します。
4-1. 「個人」と「株式会社」間の取引:時価(じか)の重要性
M&Aの前段階として、オーナー(個人)が保有する株式を、自身の資産管理会社(株式会社)に移す、といった取引が行われることがあります。この「個人」と「法人」の間での株式売買において、税務当局が最も厳しく監視しているのが、「取引価額が『時価』とかけ離れていないか」という点です。
- 時価 (Market Value): 客観的な取引価額。上場株式であれば市場株価ですが、非上場株式の場合は、専門家による「株価算定(バリュエーション)」が必要となります。
【ケース1】個人から株式会社へ「時価より安く」譲渡(低額譲渡)
- 例: 時価1億円の株式を、個人(オーナー)が自分の資産管理会社に1,000万円で売却した。
- 税務上の判断:
- 個人(売り手): 「時価(1億円)」で売却したものとみなされ(みなし譲渡)、時価1億円と取得費の差額に対して譲渡所得税(20.315%)が課税されます。手元のキャッシュは1,000万円しか入っていないにも関わらず、です。
- 法人(買い手): 時価1億円のものを1,000万円で取得できたため、差額の9,000万円は「受贈益」として、法人税(約30%)の課税対象となります。
【ケース2】株式会社から個人へ「時価より安く」譲渡(低額譲渡)
- 例: 会社が保有する時価1億円の株式(または不動産など)を、オーナー個人に1,000万円で売却した。
- 税務上の判断:
- 法人(売り手): 時価1億円で売却したものとみなされ、簿価との差額に法人税が課税されます。さらに、時価と売却価額の差額9,000万円は、相手が役員であれば「役員賞与(損金不算入)」、第三者であれば「寄付金」として扱われ、税務上厳しい取り扱いを受けます。
- 個人(買い手): 9,000万円の「経済的利益」を得たとみなされ、これが給与所得(役員の場合)または一時所得として「総合課税」(最大約55%)の対象となります。
このように、個人・法人間の取引で「時価」を無視した価格設定を行うと、売り手と買い手の双方に、予期せぬ巨額の課税(しかもキャッシュの裏付けがない)が発生するリスクがあります。M&Aアドバイザー、特にバリュエーションの専門家による「時価」の算定は、税務リスクを回避するための生命線となります。
4-2. 株式保有比率毎の配当税率
M&Aで会社を売却せず、継続保有する場合、あるいはM&A後も一部の株式を保有し続ける場合の「配当」の税率も、重要な論点です。
【個人株主が受領する場合】
- 原則(非上場株式):総合課税(第3章の二重課税で触れた通り)。累進課税で最大約55%。
- ただし、配当金額の一定割合を所得税額から控除できる「配当控除」の適用があります。
- 上場株式: 「申告分離課税(20.315%)」または「総合課税(配当控除あり)」を選択できます。
【法人株主が受領する場合】
法人が他の会社から配当金を受け取る場合、その配当金は「益金(利益)」ですが、すでに法人税が課された後の利益の分配であるため、二重課税を避ける「受取配当等の益金不算入」という制度があります。
この「益金不算入」となる割合(利益としてカウントしなくてよい割合)が、株式の保有比率によって異なります。
| 保有比率 | 区分 | 益金不算入となる割合 |
| 100% | 完全子会社株式等 | 全額 (100%) |
| 1/3超 100%未満 | 関連法人株式等 | 全額 (100%) (※負債利子控除あり) |
| 5%超 1/3以下 | その他の株式等 | 50% |
| 5%以下 | 非支配目的株式等 | 20% |
例えば、A社がB社の株式を6%保有している場合、B社から1億円の配当を受け取っても、その50%(5,000万円)は益金不算入となり、残りの5,000万円にのみ法人税が課税されるイメージです。M&A後の資本政策やグループ経営において、どの程度の比率で株式を保有し続けるか(あるいは買い手が取得するか)は、配当を通じた将来のキャッシュフロー戦略に直結する重要な論点となります。
第5章: 【実務の先端】アーンアウト条件の税務
M&Aの交渉において、特にスタートアップや成長企業(グロース企業)の評価において、売り手と買い手の間で将来の業績見通しが食い違い、希望売買価額にギャップが生じることが多々あります。
- 売り手:「当社の新技術なら、3年後には売上5倍になるはずだ。」
- 買い手:「その新技術は魅力的だが、本当に市場に受け入れられるか不確実だ。」
この「バリュエーション・ギャップ」を埋めるために用いられる手法が、**「アーンアウト(Earn-out)」**です。
5-1. アーンアウト(Earn-out)とは?
アーンアウトとは、M&Aの実行時(クロージング)に支払う対価(例:10億円)とは別に、「将来の特定の業績指標(例:3年後のEBITDAや売上高)が一定の目標を達成した場合に、追加の対価(例:最大5億円)を支払う」という取り決めです。
- EBITDA (イービットディーエー): 企業が本業で生み出すキャッシュフローを示す指標の一つ。
税引前利益 + 支払利息 + 減価償却費
売り手にとっては、自社の主張する将来価値を実現するチャンスが得られ、買い手にとっては、将来の業績が未達だった場合のリスクを軽減できる(=高い買収金額を払わなくて済む)という、双方に合理的な手法です。
5-2. アーンアウトの税務(売り手:個人株主の場合)
問題は、この「将来もらえるかもしれないお金」の税務上の扱いです。
【論点】課税のタイミングはいつか?
- 原則的取り扱い:
- M&Aの実行時(クロージング時)において、「確定している対価(10億円)」だけでなく、「アーンアウト対価の見積額(時価)」も譲渡収入に含めて申告し、納税する必要があります。
【具体例】
- クロージング時の確定対価:10億円
- アーンアウト:3年後の業績達成で最大5億円
- クロージング時点での「アーンアウト見積額(時価)」:例えば、達成確率や割引率を考慮して「3億円」と算定したとします。
この場合、売り手(個人株主)は、M&Aを実行した年に、
- 譲渡収入:10億円 + 3億円(見積額) = 13億円
として譲渡所得を計算し、13億円をベースとした税金(13億円 × 20.315% ≒ 2.64億円 ※取得費ゼロの場合)を「先に」納税する必要があります。
【アーンアウト対価確定時(3年後)】
- ケースA:業績が絶好調で、5億円(最大額)もらえた場合
- 見積額(3億円)より2億円多くもらえました。
- この差額2億円は、5億円が確定した年の「譲渡所得」として、再度申告(20.315%)します。
- ケースB:業績が不振で、1億円しかもらえなかった場合
- 見積額(3億円)より2億円少なくしか もらえませんでした。
- この場合、売り手は「3億円もらえる前提で税金を先に払いすぎている」状態です。
- 差額2億円に対応する税金(2億円 × 20.315%)について、税務署に対し「更正の請求」という手続きを行い、払いすぎた税金の還付を求めることになります。
5-3. アーンアウトの実務的課題
この税務上の取り扱いは、M&Aの実務において重大な課題を突きつけます。
- 「見積額(時価)」の算定: 将来の不確実な業績を前提としたアーンアウト対価の「時価」を、M&A実行時に客観的かつ合理的に算定することは、バリュエーションの専門家にとっても極めて困難な作業です。
- キャッシュフローの問題: 売り手は、まだ手にしていない「見積額(3億円)」に対する税金(約6,100万円)を、先に自己資金で立て替えて納税しなければなりません。
- 還付の手間: 業績未達でアーンアウトが減額された場合、更正の請求(原則5年以内)という煩雑な手続きが必要となり、税務当局との折衝が発生する可能性もあります。
アーンアウトは、バリュエーション・ギャップを埋める魔法の杖のように見えますが、その設計には高度なバリュエーション技術と、この複雑な課税タイミングを熟知した税務アドバイザーとの緊密な連携が不可欠です。
第6章: スキーム選択の最適解とアドバイザーの役割
これまで見てきたように、M&Aの税務は、選択するスキームによって天国と地獄ほどの差を生み出します。
- 株式譲渡(個人): 税率 20.315%。シンプルかつ税負担が明確。
- 事業譲渡: 法人税(約30%)+消費税+配当課税(最大約55%)。二重課税のリスクがあるが、買い手には「のれん」の節税メリットがある。
- アーンアウト: 課税タイミングが前倒しになるリスクと、見積額算定の困難性を伴う。
では、どのスキームを選択すべきか?
その答えは、「売り手と買い手、双方の状況とニーズによって異なる」としか言いようがありません。
- 売り手オーナーが「手残り」の最大化を最優先するなら、株式譲渡(20.315%)が最適解に見えます。
- しかし、買い手が「簿外債務のリスクを絶対に引き継ぎたくない」と強く主張し、かつ「のれん」による節税メリットを高く評価するならば、事業譲渡でなければディールが成立しないかもしれません。その場合、二重課税をいかに回避するか(例えば、事業譲渡の対価を配当せず、会社に残して別の事業に投資するなど)を検討する必要があります。
- 個人と法人の間の取引では、M&Aアドバイザーによる客観的な「時価(バリュエーション)」の算定が、全ての税務リスクの出発点となります。
私たちM&Aアドバイザー(特にバリュエーションとスキーム構築を担う者)の真の価値は、これらの複雑怪奇な税務・法務・会計のパズルを解き明かし、法的にクリアであることは当然として、クライアント(売り手・買い手)双方のニーズを汲み取り、双方が納得できる「最適解」をテーラーメイドで設計し、提示することにあります。
結論:M&A税務の航海には、信頼できる羅針盤(アドバイザー)を
M&Aにおける売却時の税率は、オーナー様が築き上げてきた企業の価値を、最終的にいくらの「手残り」として確定させるかを決定づける、最も重要な要素の一つです。しかし、そのルールは極めて専門的かつ複雑であり、毎年のように改正される税法の影響を色濃く受けます。本記事で解説した内容は、あくまで基本的な原則であり、個別のディールにおいては、さらに詳細な事実認定と専門的な法的解釈が必要となります。
「知らなかった」「専門家に相談しなかった」ために、本来20%で済んだはずの税金が50%になってしまった、という事態は、決してあってはなりません。M&Aという、企業にとっても、オーナー様個人にとっても、一生に一度かもしれない重要な決断を下す際には、ぜひ、早期の段階で信頼できる専門家(M&Aアドバイザー、税理士、弁護士)にご相談ください。
私たちはお客様の最良のパートナーとして、あらゆる選択肢のメリットとデメリットを徹底的にシミュレーションし、お客様の「手残り」と「未来」を最大化するための羅針盤として、航海の終わりまで伴走することをお約束いたします。
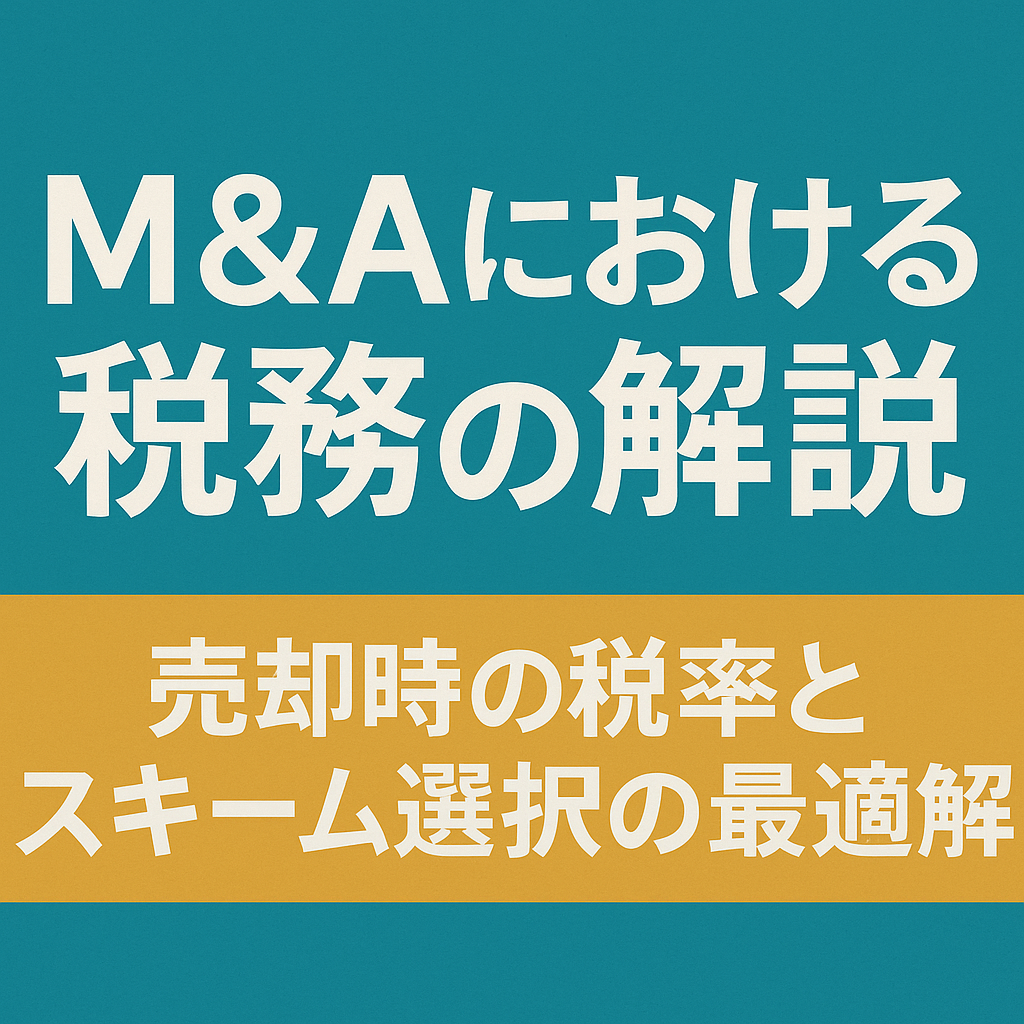



















コメント