M&Aの現場において、売り手経営者様から最も頻繁にいただくご質問があります。
「私の会社の価値はいくらでしょうか?」
この問いに対し、多くのM&A仲介会社や教科書的なアドバイザーは、EBITDA(利払い・税引き・償却前利益)の倍率や、DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)といった計算式を持ち出します。しかし、M&Aにおける買収価格は、「企業の理論的価値」では決まりません。「買い手が調達できる現金の総量」で決まります。
本稿では、特に中小企業M&Aにおいて定説となっている「EBITDAの3倍〜5倍」という相場観が、実は企業の価値とは無関係に、「銀行がLBOローンで貸せる限界値」から逆算された金融上の都合に過ぎないというメカニズムを解説します。
なぜプライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)は、一般的に事業会社(ストラテジック・バイヤー)よりも高い価格を提示できないのか。その金融構造(スキーム)を紐解くことで、貴社の真の「売り時」と「売り先」が見えてくるはずです。
第1章:バリュエーション算定の幻想
1. 「価値」と「価格」の決定的な違い
まず、M&Aにおける大前提を共有させてください。多くの経営者が、決算書を綺麗にし、事業計画を作り込めば「バリュエーション(価値)」が上がると信じています。それは間違いではありませんが、M&Aの最終局面である「価格(プライス)」決定においては、片手落ちです。
- バリュエーション(価値): その事業が将来生み出すキャッシュフローの総和(理論値)。
- プライス(価格): 買い手が実際に「用意できる」現金の上限、および競合とのセリによって決まる合意額(実務値)。
どんなに理論的な価値が100億円と算定されても、買い手のポケットと銀行からの借入枠の合計が50億円であれば、そのディールは50億円以上では成立しません。つまり、M&Aの価格決定権は、売り手の業績以上に「買い手のファイナンス能力(資金調達力)」が握っているのです。
2. 買い手の2つの種族:事業会社 vs ファンド
買い手には大きく分けて2つの種族が存在し、彼らは全く異なる「財布」と「計算式」を持っています。
- 事業会社(ストラテジック・バイヤー):自社の事業とのシナジー(相乗効果)を狙う同業種や周辺業種の企業。「永久保有」が前提。
- PEファンド(フィナンシャル・バイヤー):投資家から預かったお金で企業を買収し、価値を高めて数年後に転売(Exit)する投資のプロ。「3〜5年での売却」が前提。
結論から申し上げますと、「理論上、ファンドは事業会社よりも高い価格を提示することは難しいです。」です。その理由は、ファンドが使う「LBO(レバレッジド・バイアウト)」という魔法の杖の、”長さ”に限界があるからです。
第2章:LBOローンの正体と「EBITDA倍率」のカラクリ
1. LBO(レバレッジド・バイアウト)とは何か?
ファンドが企業を買収する際、彼らは手元の資金(エクイティ)だけで買収するわけではありません。買収対象となる企業(貴社)の将来のキャッシュフローや資産を担保にして、銀行から多額の借入(デット)を行います。これをLBOと呼びます。
【用語解説:LBO(Leveraged Buyout)】
「テコの原理(レバレッジ)」を使った買収手法。買い手は自己資金を抑え、買収資金の多くを銀行借入で賄うことで、少ない元手で大きなリターン(投資効率)を狙います。借金の返済義務を負うのは、最終的に買収された会社自身になるのが一般的です。
2. 「EBITDAの3倍〜5倍」は誰が決めたのか?
中小企業M&Aの現場では、「譲渡価格の相場はEBITDAの3倍から5倍です」とまことしやかに語られます。なぜ7倍や10倍ではないのでしょうか? それは、企業の成長性とは全く関係のない、「日本の銀行の融資審査基準」に理由があります。
ファンドが買収価格を決定する際、彼らは以下の式で計算します。
買収可能価格 = 銀行から借りられる最大額(LBOローン)+ ファンドが出せる自己資金(エクイティ)
ここで重要なのが、銀行の目線です。日本の金融機関がLBOローンを出す際、「融資金額はEBITDAの何倍まで」という厳格なガイドライン(コベナントの基準)を持っています。
- 中小企業・小規模案件: EBITDAの 2.0倍 〜 3.0倍 程度
- 中堅・優良案件: EBITDAの 3.0倍 〜 5.0倍 程度
これが現実的な上限(借入能力)です。
3. 逆算される買収価格
ファンドは投資家に対し、年率20%〜25%程度の高いリターン(IRR:内部収益率)を約束しています。そのため、買収総額のうち、自己資金(エクイティ)の割合を増やしすぎると、投資効率が下がり、目標リターンを達成できなくなります。一般的に、LBOにおける最適な資本構成は「借入6:自己資金4」が黄金比とされます。
ここで、シミュレーションをしてみましょう。
EBITDAが1億円の中小企業があるとします。
- 銀行の融資限界:中小企業向けのLBOローン審査基準(EBITDAの約3倍)を適用すると、借りられるのは3億円です。
- ファンドの自己資金:借入が3億円なら、資本構成のバランスから逆算して、出せる自己資金は2億円程度(借入6:自己資金4の比率維持)になります。
- 合計買収価格:3億円(借入) + 2億円(自己資金) = 5億円
お気づきでしょうか?
5億円 ÷ EBITDA 1億円 = 5倍(EBITDAマルチプル)
つまり、世の中で言われている「相場はEBITDAの5倍」というのは、企業の成長性を評価した結果ではなく、「銀行がEBITDAの3倍までしか貸してくれないから、ファンドのリターン計算上、オファー金額が5倍にしかならない」という金融工学上の帰結に過ぎないのです。
もし売り手が「10億円(EBITDA 10倍)で売りたい」と言った場合、ファンドは自己資金を7億円(借入3億円+自己資金7億円)入れなければなりません。これではテコの原理が効かず、ファンドの投資リターンは激減するため、彼らは「投資不適格」として検討を降ります。
第3章:事業会社が「高値」を出せる論理的根拠
一方で、事業会社(ストラテジック・バイヤー)には、このLBOの制約がありません。彼らがファンドより高く買える理由は、大きく3つあります。
1. 「シナジー効果」を価格に織り込める
ファンドはあくまで「単体での成長」と「金融テクニック」で価値を出しますが、事業会社は「自社との統合効果」を持っています。
- 売上シナジー: 貴社の商品を、買い手の大規模な販路に乗せて売る。
- コストシナジー: 物流、バックオフィス、仕入れを共通化してコストを削減する。
事業会社にとって、貴社のEBITDAが単体で1億円であっても、統合によって即座に2億円になるのであれば、「EBITDA 2億円」をベースにバリュエーション算定が可能です。ファンドは「現在の1億円」しか評価できませんが、事業会社は「未来の2億円」を買うことができるのです。
2. 調達コストと期間の概念が違う
ファンドの資金(株主資本コスト)は、投資家の期待利回りが高いため、非常に高コスト(期待リターン20%以上)です。対して、優良な事業会社は、親会社を担保として銀行から低利(1%未満など)でコーポレートローンを借りて買収資金を用意できます。
- ファンド: 「5年で2倍にしなければならないお金」を使っている。
- 事業会社: 「長期的に事業成長すればよい安いお金」を使っている。
この「資金の質」の違いが、支払える価格の差となって現れます。
3. PL(損益計算書)ヒットの許容度
ファンドはExit(出口)ありきで考えるため、EBITDA倍率を極端に気にします(高く買うと、次に高く売るのが難しくなるため)。しかし事業会社は、極端な話、「のれん(買収価格と純資産の差額)」の償却負担に耐えられ、本業の利益とかけ合わせてプラスになるなら、相場を無視した高値づかみをしてでも、戦略的に「時間を買う」という判断ができます。
【専門家の視点】
実際に私の経験した案件でも、ファンド勢がEBITDA 6倍で「これ以上は絶対に出せない」と限界を迎える中、大手事業会社が「シェア拡大の戦略的価値」を認め、EBITDA 10倍以上の価格であっさりとかっさらっていくケースは枚挙にいとまがありません。
第4章:それでも「ファンド」に売るべきケースとは?
ここまで読むと、「では常に事業会社に売るのが正解なのか?」と思われるかもしれません。しかし、M&Aは価格だけが全てではありません。あえて「安くてもファンドを選ぶ」合理的な理由が存在します。
1. 独立性の維持と「第二の創業」
事業会社に買収されると、貴社はあくまで「一部門」や「子会社」となり、親会社のサラリーマン社長が送り込まれ、社風や文化が急速に塗り替えられるリスクがあります。一方、ファンドは「経営のプロ」ではありません。彼らは経営管理やファイナンスのプロですが、現場のオペレーションは既存の経営陣(または貴社が指名する後継者)に任せるスタイルが一般的です。
「社名や屋号を残したい」「従業員の雇用と文化を守りながら、上場を目指したい」という場合、ファンドは良きパートナーとなり得ます。
2. カーブアウトや事業承継の複雑な事情
オーナー一族内の揉め事の整理、複雑に入り組んだ資本関係の解消、あるいは不採算部門の切り離し(カーブアウト)。これらのような「外科手術」が必要な案件では、ドライかつ法務・税務に精通したファンドの手腕が圧倒的に勝ります。事業会社は「綺麗な会社」を買いたがりますが、ファンドは「磨けば光る原石(少し問題を抱えた会社)」を好む傾向があります。
3. ロールアップによる「2段階Exit」
最近のトレンドとして、ファンドに株式の80%〜90%を譲渡し、オーナーが10%〜20%を持ち続ける(再出資する)スキームが増えています。ファンドの支援で会社を急成長させ、数年後にIPOや大手企業への転売(Secondary Exit)を行った際、手元に残した株式を売却することで、「初回売却益 + 成長後の売却益」という2度の果実を得ることができます。
第5章:オーナー経営者が持つべき「交渉の羅針盤」
最後に、貴社がM&Aを検討する際に持つべき心構えを提言します。
バリュエーションレポートを信じすぎない
仲介会社が持ってくる分厚い「株価算定書(バリュエーションレポート)」は、あくまで交渉の「入場券」に過ぎません。真の価格は、「誰に当てるか(事業会社かファンドか)」と「その買い手がどれだけ銀行から引けるか(ファイナンス能力)」で決まります。
「EBITDAマルチプル」を交渉カードにする
もし買い手がファンドであれば、彼らの提示額に対してこう質問してください。
「御社のLBOのレバレッジ倍率はいくつで計算していますか? シニアローンだけで組んでいますか? メザニン(劣後ローン)は検討しましたか?」
この質問が出た瞬間、相手は貴社を「素人ではない」と認識します。
「銀行評価が低いから価格が出せない」と言われたら、「では、銀行交渉に協力しましょう。事業計画の蓋然性を私が銀行に説明すれば、レバレッジはもっと効くはずだ」と切り返すことも可能です。
結論:貴社のゴールはどこか
- 最高値での売却(Cash is King)を目指すなら:シナジーのある大手事業会社一択です。時間をかけてでも、戦略的にフィットする相手を探すべきです。
- 会社の存続、独立性、あるいは急成長を目指すなら:LBOの構造的限界による「ディスカウント(価格の安さ)」を受け入れてでも、ファンドの機能を活用する価値があります。
M&Aは、単なる売買ではありません。貴社が長年育ててきた事業という「魂」を、次の時代へどう継承するかという、高度な経営判断です。
数字のマジックに惑わされず、買い手の懐事情と論理を見透かした上で、悔いのない決断をされることを切に願っており
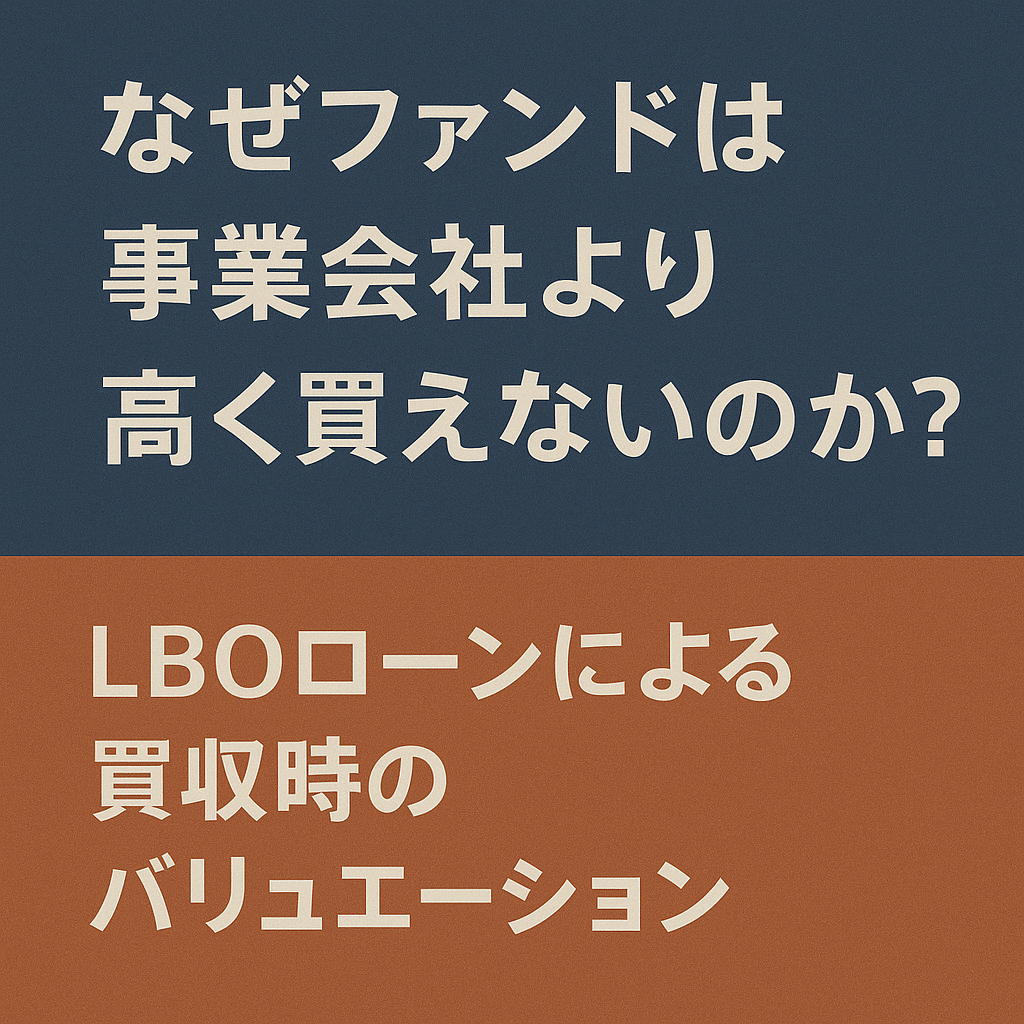




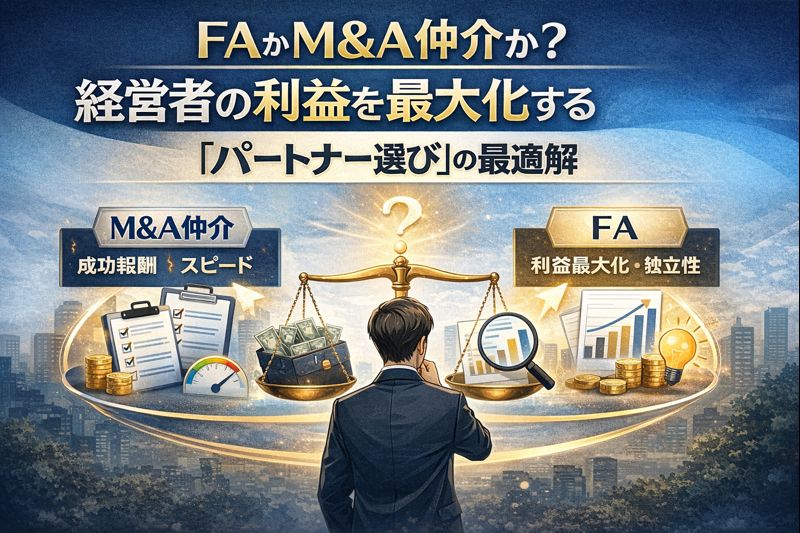
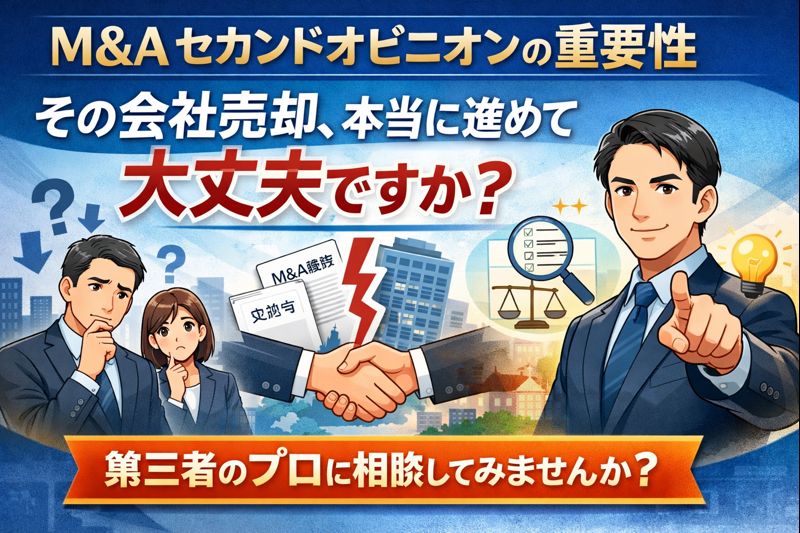

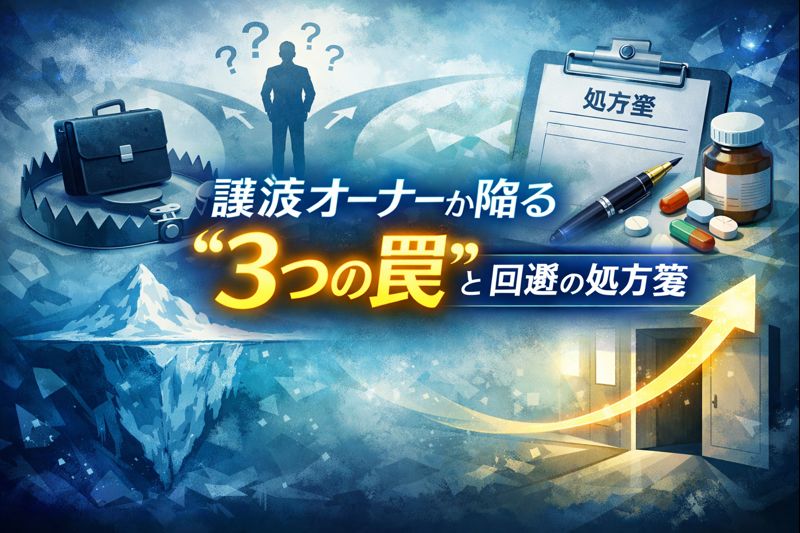

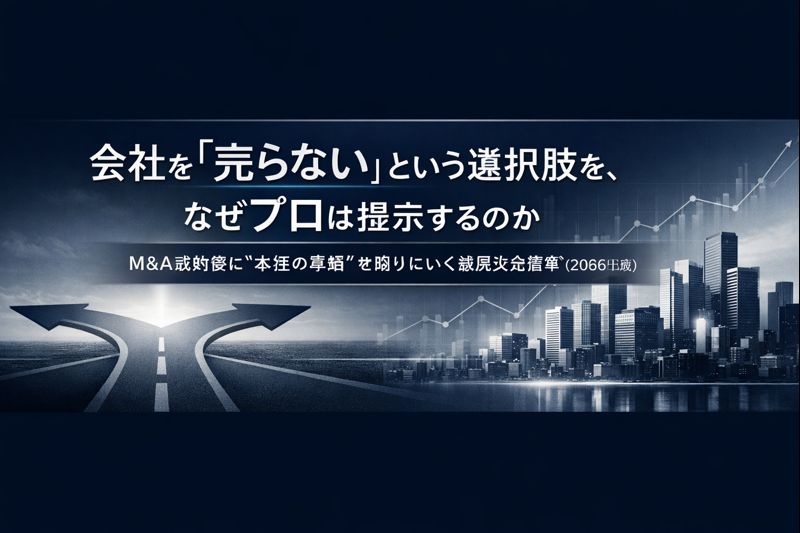


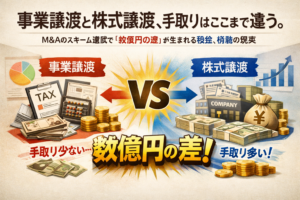

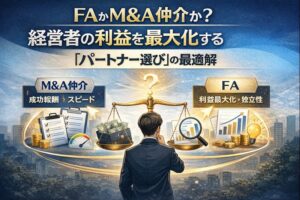


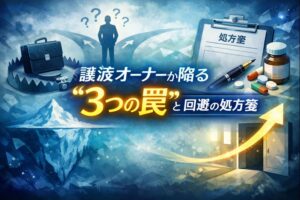

コメント