案件概要
GENDA<9166>は、全国108店舗を展開するフォトスタジオ事業のキャラットを完全子会社化することを決定しました。取引スキームは以下の通りです。
- ステップ1 : 佐野隆之氏等からキャラット株式を譲受(約142,090株)
- ステップ2 : 資産管理会社ファイブスター(キャラット株式305,700株保有)を買収
- ステップ3 : 残余株式を株式交換(比率:キャラット1株=GENDA9.884株)で取得
- 取得価額 : 総額38億円(うちキャッシュ取得約12億円、ファイブスター取得26億円)
- 日程 : 2025年10月1日効力発生予定
キャラットの直近実績は以下の通りです(2024年9月期・6か月変則決算)
- 売上高:15.21億円
- 営業利益:▲2.11億円(赤字転落)
- 純資産:8.48億円
- 総資産:32.08億円
一方、GENDAの直近業績(2025年1月期連結)は売上高1,117億円、営業利益79.6億円、純資産356.9億円と急成長を継続しています。
②バリュエーション手法の解説
本件では第三者算定機関(AGS FAS)がDCF法を基礎に株式価値を評価し、キャラットの1株当たり株式価値を7,954〜9,920円と算定。その結果、取引価格は8,500円に決定されました。以下、主要手法ごとに検討します。
(A)年買法(類似会社比較ベース)
年買法は中小企業M&Aで簡便に用いられる手法で、営業利益の数年分(2〜5倍)が目安です。
キャラットは直近赤字(営業損失▲2.1億円)であるため、年買法をそのまま適用すると理論価値はゼロ、もしくはマイナス評価となります。よって「現状収益ベースでは価値が出ない会社」であり、将来性とシナジーを前提にのみ価格が成立しているといえます。
(B)DCF法
DCF法では将来キャッシュフローを割引評価します。
- キャラットは過去3年間で黒字→黒字縮小→赤字と変動しており、単独では収益不安定。
- しかし、買収後はGENDAの送客・会員基盤(GENDA ID 240万人)との統合を前提に成長シナリオを描くことで、DCFによる正の価値が算定可能。
DCFレンジ7,954〜9,920円(中央値8,937円)に対し、実際の合意価格8,500円は妥当レンジの下位寄りであり、将来予測にある程度保守性を織り込んだ価格設定と評価できます。
(C)EV/EBITDA倍率
EV/EBITDA倍率は、エンタメ・小売業のM&Aでよく参照される指標です。キャラットの直近EBITDAは赤字のため倍率算定は困難ですが、黒字年度(2023年3月期 営業利益3.32億円、EBITDA≒4.0億円と推計)を基準にすると、取得価額38億円 ÷ EBITDA4.0億円 ≒ EV/EBITDA 9.5倍。
国内サービス業M&Aの平均5〜8倍に比べ高水準であり、赤字転落リスクを抱える企業に対してはかなりプレミアムを支払っているといえます。
買収金額とシナジー効果の織り込み
- 純資産ベース:8.48億円
- 取得価額:38億円
- プレミアム倍率:約4.5倍
つまり、GENDAは純資産額の約4.5倍を支払い、赤字企業を買収したことになります。
この差額約30億円は、のれん・シナジーの評価に相当します。
シナジー要因は以下の通りです。
- 顧客基盤統合
- GENDA ID 240万人とキャラット顧客情報を連携
- アミューズメント・カラオケとフォトスタジオ間で送客を実現
- 店舗展開効率化
- 出店立地情報を共有し、効率的な拡大を図る
- 若年層・ファミリー層のクロスユースを想定
- 新規サービス創出
- GENDA保有IPとのコラボ企画
- フォト体験のエンタメ化によるLTV向上
従来のキャラット単独の利益水準では買収価格を説明できないため、のれんの大部分はシナジー期待の資産化と位置付けられます。
主要財務指標(2024年9月期・キャラット/2025年1月期・GENDA)
| 指標 | キャラット | GENDA(連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 15.21億円 | 1,117.9億円 |
| 営業利益 | ▲2.11億円 | 79.6億円 |
| 経常利益 | ▲2.08億円 | 73.0億円 |
| 当期純利益 | ▲1.76億円 | 33.0億円 |
| 純資産 | 8.48億円 | 356.9億円 |
| 総資産 | 32.08億円 | 1,143.7億円 |
| ROE | ▲20.7%(赤字転落) | 9.3%(純利益 ÷ 期首平均純資産ベース) |
総括
本件は、赤字企業を高倍率で買収し、のれん=シナジーを強く織り込んだM&Aと評価されます。DCFによる理論レンジ内での取引ではあるものの、EV/EBITDA水準は高く、GENDAの戦略的判断が色濃く反映されています。
今後、相互送客やIPコラボによる収益化が実現できなければ、のれん減損リスクが顕在化する可能性もあり、買収効果のモニタリングが重要となります。
―この記事の監修者―
プライマリーアドバイザリー株式会社
代表取締役 内野 哲
一般社団法人 金融財政事情研究会 M&Aシニアエキスパート/東証プライム上場企業グループ会社代表取締役社長を経てM&Aアドバイザリー事業創業/自己勘定投資会社にて投資業/企業価値評価、M&Aスキーム設計に精通
[→無料相談・お問い合わせはこちら]

代表電話:03-5050-5175
免責事項(ディスクレーマー)
本稿で提供する情報は、公表されている情報や信頼できると判断した情報源に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本稿における分析、見解、将来に関する記述は、作成者個人の現時点での判断や推測に基づくものであり、将来の出来事や結果を保証するものではなく、予告なく変更されることがあります。
本稿は、読者の皆様への情報提供のみを目的としており、特定の有価証券の取得、売却、保有等を推奨または勧誘するものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願い申し上げます。
本稿の情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、作成者およびその所属組織は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
本稿の内容の無断転載、複製、転送、改変等を固く禁じます。
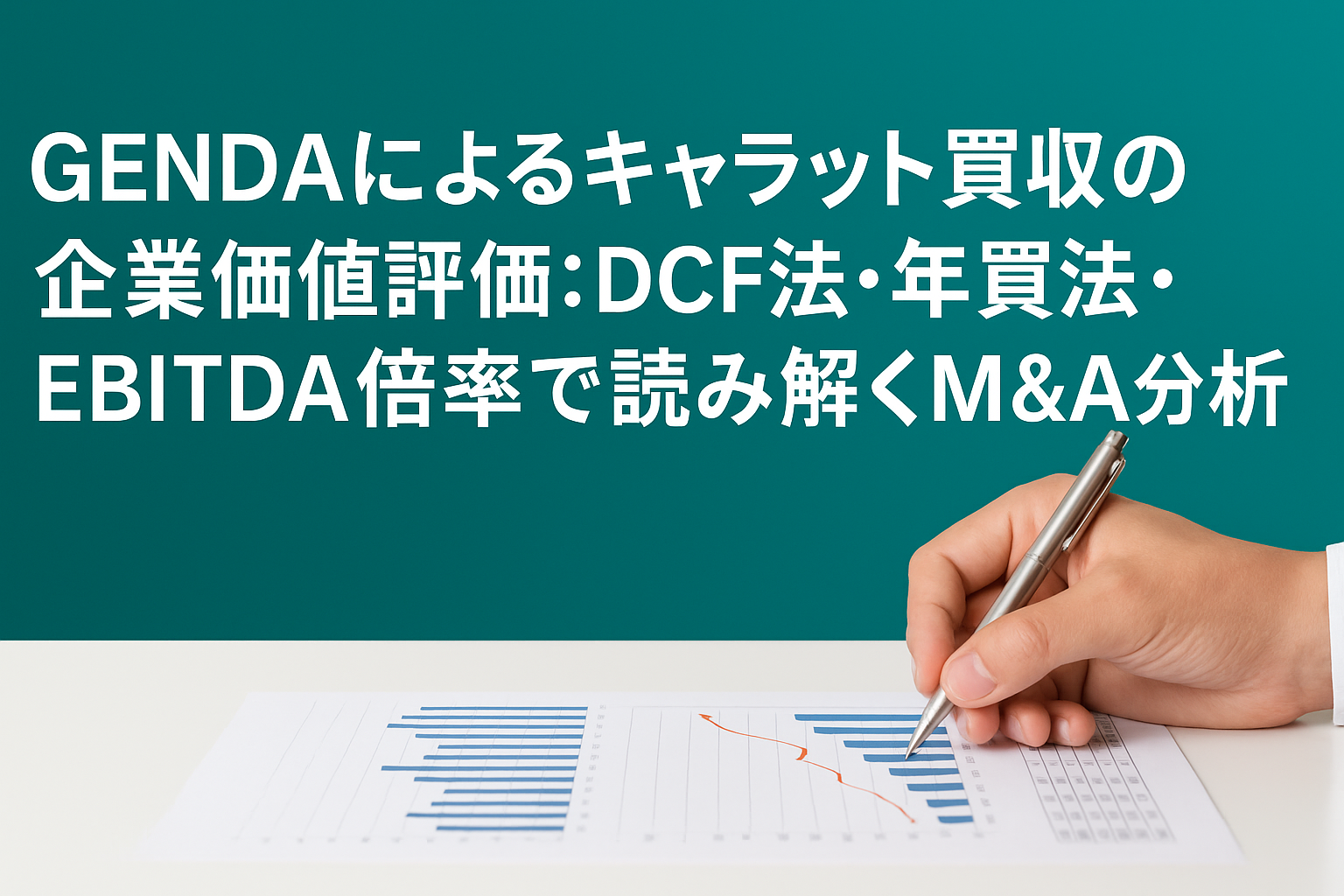



















コメント