エグゼクティブサマリー
- フライヤー(323A)はAIStepを全株式取得。取得価額は株式200百万円+アドバイザリー等4百万円、合計204百万円。決議日2025/8/15、譲渡実行予定日2025/9/1。評価はDCF法を採用。
- AIStep(2024/9期):売上高34,128千円、営業利益792千円、当期純利益688千円、総資産8,679千円、純資産1,188千円。発行株式50株。
- 取得単価は1株あたり4,000,000円で、2024/9期簿価に対しP/B約168倍、P/S約5.86倍。これは「将来成長+シナジー」前提の価格水準。
- 会社公表では2025/9期は売上2〜3倍、利益大幅増を見込み、当該前提を基に200百万円を算定と明示。フライヤーは累計会員約126万人とBtoB顧客網を活用し、生成AI研修の拡販シナジーを想定。
① 案件概要
- 買い手:株式会社フライヤー(東証グロース、323A)
- 対象会社:株式会社AIStep(オンラインAI研修、東京都港区)
- 財務実績(2024/9期)
- 売上高:34,128千円
- 営業利益:792千円
- 純資産:1,188千円
- 総資産:8,679千円
- 取得条件:普通株式50株を200百万円で取得(持分100%)。アドバイザリー費用等概算4百万円。合計概算204百万円。譲渡実行予定2025/9/1。
- 戦略的位置づけ:フライヤーは要約サービスや人材育成事業を有し、AIStep買収を通じて生成AI研修に本格参入。累計会員126万人へのクロスセル、法人向け既存ネットワークでの販売拡大を企図。
② バリュエーション手法の解説
A. DCF法(会社採用)
- DCFを用い、進行期以降の売上2〜3倍成長+マージン改善を織り込み算定。
- 仮定条件:WACC15〜20%、ターミナルg=1〜2%。逆算するとEBITDA3.5〜4.5億円規模が中期的に必要。
- 意味合い:初年度拡大だけでなく、中期的な法人・個人向け拡張と高継続率が前提。
B. EBITDA倍率法
- 実績基準:EV/EBITDA≒253倍。説明不能。
- 進行期想定基準:
- 売上0.68億、EBITDA20% → EBITDA1.36億 → EV/EBITDA≒14.7倍
- 売上0.9億、EBITDA25% → EBITDA2.25億 → EV/EBITDA≒8.9倍
- 売上1.0億、EBITDA30% → EBITDA3.06億 → EV/EBITDA≒6.5倍
- まとめ:非上場研修・教育業の取引倍率(7〜15倍)の範囲に収まり、成長前提が成立すれば妥当化可能。
③ シナジー効果の織り込み分析
1) 取得価額と実績指標の乖離
- P/B=168倍
- P/S=5.86倍
- P/OP=253倍
実績ベースでは高過ぎ、成長+シナジーが織り込まれた価格。
2) シナジードライバー
- BtoCクロスセル:126万人会員への販売。
- BtoB販売:既存法人顧客網への研修導入。
- 販管費効率:ブランド・チャネル統合でCPA低減。
- プロダクト拡張:生成AIリスキリング領域へ展開。
3) シナジー必要額の試算
- スタンドアロン(売上0.7億、P/S2.5倍):1.75億円 → シナジー0.25億円
- 中庸(売上0.9億、EV/EBITDA9倍):2.03億円 → シナジー0
- 強気(売上1.0億、EBITDA30%):2.4億円 → 買い手超過利得0.4億円
→ 実質的に、初年度売上0.9億・EBITDA25%が達成されればシナジー織り込みは0に近づき、合理的水準と評価可能。
4) リスク要因
- 継続率未達によるLTV/CAC悪化
- 講座拡張スピードと品質維持の難度
- 法人案件の季節性・更新率
- 生成AI市場の技術進化スピード
結論
実績財務では説明不可能ですが、維持可能EBITDA1.5〜3.0億円帯を近く達成できれば、年買8〜12年・EV/EBITDA7〜15倍レンジで裏付け可能。逆に未達なら評価倍率は極端に高まり、のれん毀損リスクも高い。したがって今後はLTV/CAC、解約率、法人再契約率をモニタリングし、早期にシナジー実証を図ることが極めて重要です。
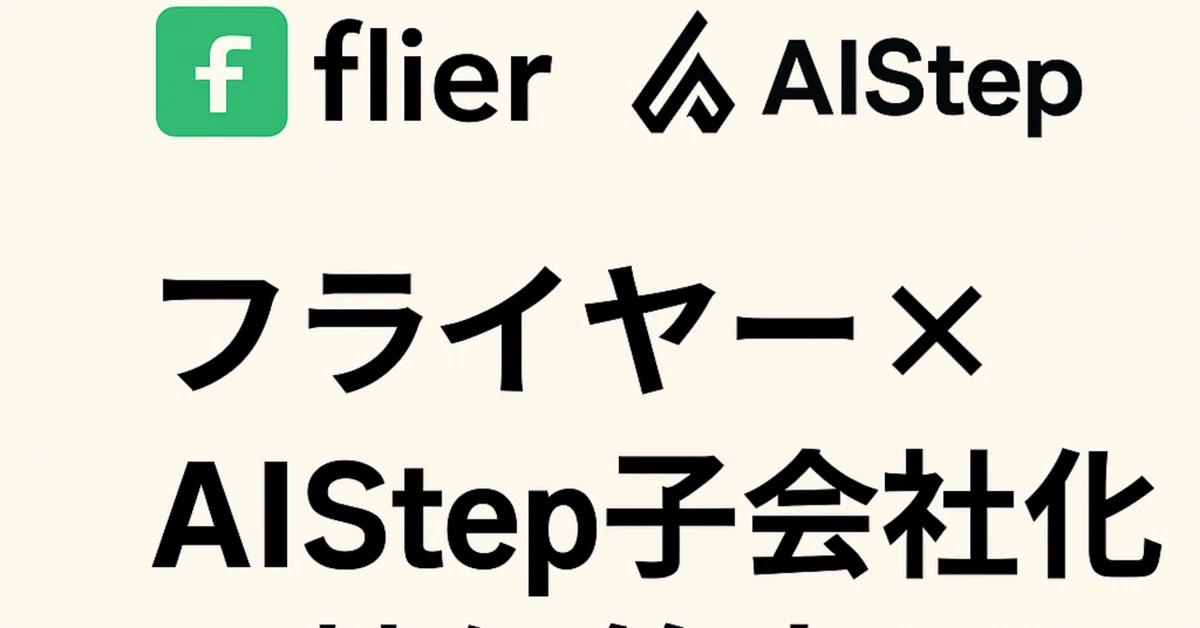



















コメント