最近、私の周りでこんなニュースが話題になりました。 「社員数30名ほどのWebサービス企業が、10億円という評価額で大手企業の傘下に入った」
創業から寝る間も惜しんで育ててきた会社。その未来を考えたとき、30代、40代の経営者であるあなたの頭に「M&A(会社売却)」という選択肢が、一度はよぎったことがあるのではないでしょうか。
「うちはまだその規模じゃない」 「M&Aなんて、業績が傾いてから考えることだ」
もしそう感じていらっしゃるなら、少しだけお時間をください。この記事は、単なる成功事例の無機質な解説ではありません。社長として事業を育て、売却の決断も経験してきた私が、あなたと同じ「経営者」の目線でこの事例を深掘りし、あなたの会社の経営に今日から活かせる実践的な学びをお届けします。
これは、遠い世界の成功物語ではありません。あなたの会社の未来を左右する、すぐ隣にあるリアルな経営戦略の話です。
エグゼクティブ・サマリー(この記事から得られる3つの学び)
- 結論: アーリーイグジットは「終わり」ではなく、創業者・従業員・事業の未来を拓く「新たな成長戦略」です。
- 学び1: IT企業の価値は「将来性」で決まります。PL(損益計算書)だけでなく、将来のキャッシュフローに繋がるKPIの可視化と改善が鍵となります。
- 学び2: M&Aは「思い立ったが吉日」ではありません。日頃からのクリーンな財務管理と、買い手の戦略に響く事業ストーリーの準備が成否を分けます。
- 学び3: 最高の交渉力は「いつでも売れる状態」から生まれます。事業が最も輝いている「タイミング」で選択肢を持つことが、経営の自由度を高めます。
案件概要(モデルケース)
今回の分析にあたり、具体的なイメージを持っていただくため、以下のようなモデルケースを想定します。
売手企業 株式会社SampleTech
事業内容 特定業界向けSaaS型Webサービスの開発・運営
企業規模 従業員30名 / 年間売上5億円 / 営業利益5,000万円
買手企業 大手IT企業A社
取得価額 10億円
M&Aの目的
A社は新規事業領域へのスピーディな参入を狙い、SampleTech社の持つ技術力、顧客基盤、そして優秀な開発チームの獲得を目指した。
企業価値評価(バリュエーション)の深掘り解説
さて、この「10億円」という価格は、どのようにして決まったのでしょうか。会社の値段の付け方(バリュエーション)について、少しだけ専門的な話にお付き合いください。
評価手法① 純資産法(年買法):会社の「土台」の価値を測る
中小企業のM&Aで最も基本的な考え方が、この純資産法です。とてもシンプルに言えば、会社の貸借対照表(BS)にある「純資産の部」の金額をベースにする方法です。
企業価値≈純資産+営業利益×数年分
これは、会社が今すぐ解散した場合に残る財産(純資産)に、将来の稼ぐ力(営業利益の数年分)を上乗せするイメージです。この「数年分」は、業界や会社の安定性によって変動します。
しかし、SampleTech社のようなIT企業の場合、この計算だけでは実態とかけ離れてしまいます。なぜなら、IT企業の本当の価値は、BS(貸借対照表)には載ってこないからです。
優秀なエンジニア組織、独自のアルゴリズム、顧客からの厚い信頼といった「目に見えない資産」。これこそが価値の源泉です。
この、帳簿上の価値(純資産)と、実際に支払われた買収価格(10億円)との大きな差額。これが、いわゆる「のれん(営業権)」です。まるで人気のお店の「信頼」や「ブランド力」のようなもので、将来もっと大きな利益を生み出すだろうという期待値に対して支払われる対価なのです。
評価手法② DCF法 / EBITDAマルチプル法:会社の「将来性」を測る
IT/Web業界のM&Aで主役となるのが、会社の「将来性」を評価する手法です。
- DCF(Discounted Cash Flow)法: 少し難しく聞こえるかもしれませんが、「将来、この会社が生み出すであろう現金の総額を、現在の価値に割り引いて計算する方法」です。まさに、事業の成長性そのものを評価する仕組みと言えます。
- EBITDAマルチプル法: これは、同業他社との比較で価値を測る、よりポピュラーな手法です。「本業の儲け(EBITDA ※)の何倍で会社が評価されているか」という倍率(マルチプル)を使って計算します。
※EBITDA ≒ 営業利益 + 減価償却費。金利や税金、減価償却の影響を排除した、事業本来の収益力を示す指標です。
今回のSampleTech社の場合、営業利益5,000万円に、仮に減価償却費が1,000万円あったとすると、EBITDAは6,000万円です。
企業価値(10億円)=EBITDA(6,000万円)×マルチプル(約16.7倍)
SaaS企業のM&Aでは、マルチプルが10倍~20倍、時にはそれ以上になることも珍しくありません。なぜなら、安定したストック収益があり、将来の予測が立てやすいからです。
【もし、あなたの会社なら?】
この話で最も重要なのは、「どうすれば、この評価を高められるか」という視点です。
- DCF評価を高めるには?:
- 解約率(チャーンレート)を下げる: 顧客が辞めないサービスは、将来のキャッシュフローが安定していると評価されます。
- 顧客単価(ARPU)を上げる: アップセル・クロスセルの仕組みはありますか?
- 高い利益率を維持する: 属人性を排し、スケールしやすいビジネスモデルを構築できていますか?
- マルチプル(倍率)を高めるには?:
- ストック収益比率を高める: 受託開発よりも、SaaSのような継続課金モデルが圧倒的に高く評価されます。
- 特定顧客への依存度を下げる: 売上が1~2社に集中していると、リスクが高いと見なされ、倍率は下がります。
- 参入障壁の高い技術を持つ: 模倣されにくい独自技術は、高い倍率の源泉です。
日々の経営判断が、未来の企業価値に直結している。この感覚を持つことが、最初の一歩になります。
【最重要】このM&Aから、IT経営者が学ぶべき「3つの教訓」
さて、ここからが本題です。私が元経営者として、この事例からあなたに最もお伝えしたい3つの教訓です。
教訓①:事業戦略の教訓:「誰に、何を、なぜ売るのか」を語れるか?
優れたプロダクトを開発し、売上を伸ばす。経営者として当然の目標です。しかし、M&Aを視野に入れるなら、もう一つ上の視点が求められます。それは、「この事業は、どのような買い手にとって魅力的か?」という視点です。
今回のSampleTech社は、大手IT企業A社の「新規事業領域への参入」という明確な戦略に、まさにピースとしてはまりました。自社の技術、顧客基盤、そして組織文化が、A社の未来の戦略とどうシナジーを生むのか。そのストーリーを明確に描けていたからこそ、高い評価に繋がったのです。
あなたの会社はいかがでしょうか。単に「良い会社です」ではなく、「私たちのこの技術は、御社のプラットフォームと組み合わせることで、市場を一変させる可能性があります」と、相手の言葉で語る準備はできていますか?日頃から業界地図を俯瞰し、自社のポジショニングを客観的に把握しておくことが極めて重要です。
教訓②:財務管理の教訓:「PL脳」から「BS・CF脳」への転換
創業期の経営者は、どうしても目先の売上や利益、つまりPL(損益計算書)に意識が集中しがちです。私もそうでした。しかし、M&Aの交渉テーブルに着くと、買い手はあなたの会社のBS(貸借対照表)とCF(キャッシュフロー計算書)を、虫眼鏡を持って精査します。
- 社長への貸付金が残っていませんか?
- 個人の支出と会社の経費が混ざっていませんか?
- 実態の不明な仮払金はありませんか?
これらは、M&Aの世界では「公私混同」と見なされ、企業価値を大きく損なう要因となります。私自身、子会社社長時代にM&Aのデューデリジェンス(買収監査)を何度も受けましたが、その厳しさは想像を絶するものです。
「いつか誰かに見せても恥ずかしくない財務諸表」。これを日常から意識することが、いざという時の交渉力を大きく左右します。専門家である税理士や会計士と密に連携し、クリーンな財務体質を維持することは、経営者の重要な責務の一つです。
教訓③:M&Aのタイミングの教訓:「最高の状態」で選択肢を持つ
経営者仲間から、「いつが会社の売り時か?」と聞かれることがよくあります。私の答えはいつも同じです。「業績が絶好調で、業界に追い風が吹いており、あなた自身が経営に最も情熱を燃やしている時」です。
多くの方が、「業績が傾いてきた」「後継者がいない」「経営に疲れた」といった理由でM&Aを考え始めます。しかし、それでは買い手から足元を見られ、買い叩かれてしまうのが現実です。
M&Aは、困った時の「最後の手段」ではありません。 事業が最も輝いている時にこそ、「このまま自分たちで成長を目指す道」と「M&Aによって、より大きな資本とリソースを得て成長を加速させる道」を対等に比較検討できるのです。
この「選択肢を持っている」という状態が、経営者に精神的な余裕と、力強い交渉力をもたらします。そのためにも、常に自社の企業価値を客観的に把握し、M&A市場の動向にアンテナを張っておくことが、現代の経営者には不可欠な素養と言えるでしょう。
総評:我が子を、より大きな舞台へ送り出すために
私自身、社長時代に何度も自社の将来について、一人で頭を抱えました。社員の生活、お客様への責任、そして何より、我が子のように育ててきた事業への想い。その未来を誰かに託すという決断は、言葉で言い尽くせるほど簡単なものではありません。
しかし、今回のSampleTech社の事例は、M&Aが単なる「売却」や「終わり」ではなく、創業者、従業員、そして事業そのものが、より大きな舞台で輝くための「成長戦略」となり得ることを力強く示唆しています。
自社のリソースだけでは越えられなかった壁を、パートナーの力を借りて乗り越える。創業者が描いた夢の続きを、より多くの仲間と共に実現していく。アーリーイグジットとは、そうした未来への扉を開く、極めてポジティブな経営判断なのです。
あなたの会社が持つ、まだ見ぬ可能性。そして、あなた自身がこれから描く新たなキャリア。一度、客観的な視点でその価値を見つめ直してみませんか?それは、想像もしていなかった未来への、確かな第一歩になるかもしれません。
Q&Aコーナー
Q1. 赤字の会社でも売却は可能ですか?
A1. はい、十分に可能です。特にIT業界では、現在の赤字は問題視されないケースも少なくありません。将来性のある独自技術、優秀なエンジニアチーム、独自の顧客データやトラフィックなど、買い手にとって魅力的な「目に見えない資産」があれば、先行投資としての赤字は許容されます。重要なのは「なぜ赤字なのか」そして「今後、どのように黒字化し、成長していくのか」というストーリーを明確に説明できることです。
Q2. 従業員には、どのタイミングでM&Aの話をすべきでしょうか?
A2. これは経営者が最も心を痛める、非常にデリケートな問題です。一般的には、基本合意契約が締結され、M&Aが後戻りできない確かな段階になってから伝えるのが望ましいとされています。あまりに早い段階で伝えてしまうと、従業員に不要な不安を与え、優秀な人材の離職に繋がるリスクがあるからです。 私が社長として最も心を砕いたのも、この点でした。伝える際には、従業員の雇用が維持されること、そしてM&Aによって生まれるキャリアの可能性や待遇改善の側面など、ポジティブなメッセージを誠心誠意、丁寧に説明することが不可欠です。
===この記事の監修者===
プライマリーアドバイザリー株式会社
[→【相談無料】自社の企業価値について、まずは話を聞いてみる]

▼免責事項(ディスクレーマー)
本稿で提供する情報は、公表されている情報や信頼できると判断した情報源に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本稿における分析、見解、将来に関する記述は、作成者個人の現時点での判断や推測に基づくものであり、将来の出来事や結果を保証するものではなく、予告なく変更されることがあります。
本稿は、読者の皆様への情報提供のみを目的としており、特定の有価証券の取得、売却、保有等を推奨または勧誘するものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願い申し上げます。
本稿の情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、作成者およびその所属組織は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
本稿の内容の無断転載、複製、転送、改変等を固く禁じます。
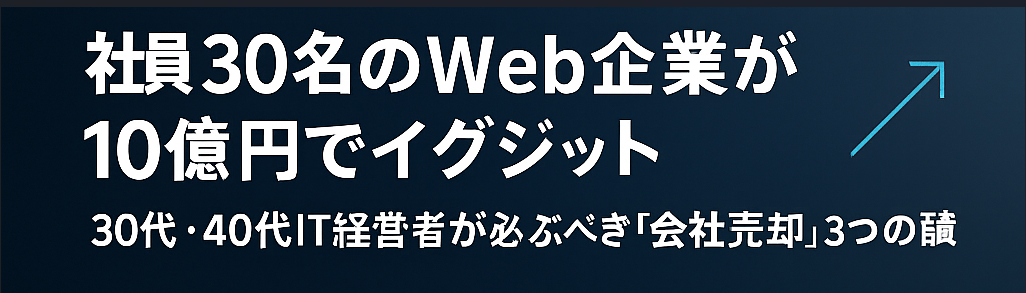



















コメント