2025年11月13日、総合旅行予約サイト「skyticket」を運営する株式会社アドベンチャー(東証グロース:6030)は、沖縄県を基盤とするホテル運営代行の雄、ファイブスターコーポレーショングループ3社(以下、ファイブスターグループ)の全株式を取得し、完全子会社化することを発表しました 。
本件M&A(Mergers and Acquisitions:企業の合併・買収)は、オンライン・トラベル・エージェント(OTA)というデジタルの領域で急成長を遂げた企業が、ホテル運営・清掃・クリエイティブといったリアルの現場オペレーションに強みを持つ企業群を傘下に収めるという、「垂直統合」型の戦略的ディールです。
開示資料によれば、取得価額(アドバイザリー費用等を含む概算)は11億2,000万円。アドベンチャー社は、これにより「ホテル契約に関する相互補完」や「ホテル運営・集客ノウハウの取得」といった強固なシナジー(相乗効果)を見込んでいます 。
第1章:本件M&Aの概要とスキーム
まず、本ディールの基本的な構造(スキーム)と当事者について整理します。
1. ディールの当事者
- 買い手(譲受企業):
- 株式会社アドベンチャー
- 東証グロース市場上場(コード番号: 6030)。
- OTAとして総合旅行予約サイト「skyticket」を運営 。今後の戦略として、国内旅行事業(ホテルサービス含む)の強化、さらに東南アジア及びグローバル進出を掲げています 。
- 対象会社(譲渡企業群):ファイブスターグループ
- ① 株式会社ファイブスターコーポレーション
- 事業内容:コンサルティング、ホテル開発、オペレーション事業 。沖縄における「ホテル運営代行業者のトッププレイヤー」と評されています 。
- ② 株式会社ファイブスターコーポレーション東京
- 事業内容:クリエイティブ事業 。ホテル運営に付随するWEB制作やマーケティング支援などを担っていると推察されます。
- ③ アイランドクリーナーズ株式会社
- 事業内容:清掃事業 。ホテル運営の根幹を支える重要な機能です。
- ① 株式会社ファイブスターコーポレーション
- 売り手(譲渡人):
- 鈴木 義浩 氏
- 上記3社の株式をすべて100%所有する個人株主(オーナー)です 。
2. M&Aスキーム:100%株式譲渡
本件は、アドベンチャー社が売り手である鈴木氏から対象3社の発行済株式すべて(100%)を買い取る「株式譲渡」というスキームを採用しています 。
専門用語解説:M&Aスキーム
M&Aを実現する手法には、主に「株式譲渡」「事業譲渡」「合併」「会社分割」などがあります。
- 株式譲渡: 会社のオーナー(株主)が保有する株式を売買する手法。会社自体はそのまま存続し、株主が変わるだけです。手続きが比較的簡便で、許認可や従業員の雇用契約なども原則としてそのまま引き継がれます。
- 事業譲渡: 会社の一部または全部の「事業」そのものを売買する手法。資産や負債、契約などを個別に移転させる必要があり、手続きが煩雑になる場合があります。
今回、株式譲渡が選ばれた理由は、M&A実務において最も一般的かつ合理的ないくつかの理由が考えられます。
- 経営権の完全な掌握: 買い手(アドベンチャー)は100%株式を取得することで、対象会社を完全子会社化し 、迅速な意思決定とグループ戦略(PMI:後述)の実行が可能となります。
- 手続きの簡便性: 事業譲渡に比べ、株主が変わるだけであるため、ホテル運営に必要な許認可や、多数の従業員との雇用契約、取引先との契約関係を個別に移転させる手間を回避できます。
- 売り手(オーナー)の税務メリット: 売り手である鈴木氏(個人)が得る株式の売却益(譲渡所得)は、原則として「申告分離課税」の対象となり、所得税・住民税合わせて約20%(2025年現在)の税率が適用されます。これは、他の所得(例えば事業所得や給与所得)と合算されて累進課税(最大約55%)となるのに比べ、税務上非常に有利です。
3. スケジュール
本件は非常にタイトなスケジュールで進行しています 。
- 取締役会決議日:2025年11月13日
- 契約締結日:2025年11月13日(予定)
- 株式譲渡実行日(クロージング):2025年11月28日(予定)
決議からクロージングまでわずか2週間強というスピード感は、本件が友好的な交渉に基づき、買収監査(デュー・ディリジェンス)を含む事前準備が水面下で周到に進められていたことを示唆しています。
第2章:買収の戦略的意義(シナジー分析)
アドベンチャー社は、なぜ11億円超の資金を投じてファイブスターグループを買収するのでしょうか。その狙いは、開示資料に示された「シナジー」にあります 24。
1. アドベンチャー(買い手)の戦略
アドベンチャー社はOTAとして「skyticket」という強力な販売チャネル(川下)を持っています。しかし、旅行商品の「仕入れ」、特にホテルサービスの領域において、競争は激化しています。同社は今後の戦略として「ホテルサービスを含めた国内旅行事業を引き続き強化」し、「東南アジア及びグローバル領域に進出」する方針を定めています 。
2. ファイブスターグループ(対象会社)の強み
一方、ファイブスターグループは「沖縄県におけるホテル運営代行業者のトッププレイヤー」であり、「宿泊施設のWEB集客コンサルティング業務やオペレーション業務等に強み」を持っています。これは、旅行商品の「製造・運営」(川上)における専門的ノウハウです。
3. 期待されるシナジー効果(垂直統合)
両社が統合することで、以下の相乗効果が期待されています 28。
- ホテル契約に関する相互補完:
- (推察)アドベンチャーは「skyticket」の集客力を背景に、ファイブスターグループが運営(またはコンサルティング)するホテルの稼働率向上に貢献できます。
- (推察)ファイブスターグループは、アドベンチャーに対し、沖縄という重要観光地における安定的なホテル在庫(客室)の供給や、有利な条件での仕入れを可能にするかもしれません。
- ノウハウの相互活用:
- ファイブスターグループが持つホテル運営や現場での集客ノウハウ。
- アドベンチャーが持つオンライン予約サービスで得た広告ノウハウやエンジニアリソース。
これは、OTA(販売)とホテル運営(製造)を結びつける「垂直統合」戦略です。これにより、単に商品を右から左へ流す「代理店」から脱却し、商品の企画・運営から販売までを一気通貫で手掛けることで、マージン(利益率)の改善、顧客体験の向上、そして他社OTAとの差別化を図る狙いがあると分析できます。
特に「沖縄」という立地は、インバウンド(訪日外国人旅行)需要が回復・成長する中で、日本国内でも最も重要なマーケットの一つです。ここでホテル運営の強固な基盤とノウハウを獲得することは、アドベンチャーが将来的に「東南アジア及びグローバル領域に進出」 する上での重要な試金石(テストマーケティング)となり得ます。
第3章:本件の核心 — バリュエーション(企業価値評価)分析
M&Aアドバイザーとして最も注目するのは、やはり「取得価額」の妥当性です。本件の価格はどのように算出されたのでしょうか。
1. 取得価額の内訳
まず、開示された価格情報を確認します 32。
- 普通株式(3社合計): 1,040百万円(10億4,000万円)
- アドバイザリー費用等(概算): 80百万円(8,000万円)
- 合計(概算): 1,120百万円(11億2,000万円)
ここで重要なのは、M&Aの「売買価格」そのもの、すなわち株主(鈴木氏)への対価は「普通株式 10億4,000万円」であるという点です。アドバイザリー費用は、アドベンチャー社がM&Aを遂行するために別途支払うコストです(詳細は第4章)。
したがって、バリュエーション分析の対象となるのは「株式価値 10億4,000万円」となります。
2. 対象会社の財務状況(単純合算)
次に、対象3社の直近の財務状況を確認します。ただし、各社の決算期は(株)ファイブスターコーポレーションが3月期、同東京が6月期、アイランドクリーナーズ(株)が1月期 と異なっています。厳密な評価(DD)では、このズレを補正(例:直近12ヶ月(LTM)の業績に引き直すなど)しますが、ここでは開示された直近決算期の数値を単純合算し、グループ全体の大まかな財務規模を把握します。
| 項目 | ① (株)ファイブスター コーポレーション (2025年3月期) | ② (株)ファイブスター コーポレーション東京 (2025年6月期) | ③ アイランド クリーナーズ(株) (2025年1月期) | 3社単純合算(概算) |
| 売上高 | 784百万円 | 58百万円 | 48百万円 | 890百万円 |
| 経常利益 | 168百万円 | 10百万円 | 3百万円 | 181百万円 |
| 当期純利益 | 120百万円 | 8百万円 | 3百万円 | 131百万円 |
| 純資産 | 207百万円 | 24百万円 | 8百万円 | 239百万円 |
| 総資産 | 461百万円 | 60百万円 | 13百万円 | 534百万円 |
3. バリュエーション手法による分析
M&Aの価値評価には、大きく分けて3つのアプローチがあります。
(1) コスト・アプローチ(純資産法)
専門用語解説:コスト・アプローチ(純資産法)
対象企業の貸借対照表(BS)に着目し、その「純資産(資産 – 負債)」を基準に株式価値を評価する手法です。帳簿上の数値を用いる「簿価純資産法」と、資産・負債を時価で評価し直す「時価純資産法(修正純資産法)」があります。
- 本件での試算:
- 3社合算の純資産(簿価ベース)は 239百万円 です。
- 取得価額(株式価値)は 1,040百万円 です 。
この差額(1,040M – 239M = 約801百万円)は、会計上「のれん(または営業権)」と呼ばれるものに相当します。
専門用語解説:のれん(営業権)
M&Aにおいて、買収価格(株式価値)が、対象企業の時価純資産額を上回る部分を指します。これは、対象企業が持つブランド力、技術力、顧客基盤、従業員のノウハウ、そして「将来生み出すであろう収益力(シナジー含む)」といった、貸借対照表には表れない無形の価値に対する対価です。
本件では、取得価額の実に約77%(801M / 1040M)が「のれん」に相当する計算となり、アドベンチャー社がファイブスターグループの「将来性」や「シナジー」を非常に高く評価していることが明確にわかります。
(2) インカム・アプローチ(DCF法)
専門用語解説:インカム・アプローチ(DCF法)
対象企業が将来生み出すと予測されるフリー・キャッシュフロー(FCF)を、一定の割引率(WACC:加重平均資本コスト)を用いて現在価値に割り引くことで、企業価値(EV)や株式価値を算出する手法です。M&Aのバリュエーションにおいて最も理論的とされ、特に「将来の成長性」や「シナジー」を評価に織り込む際に中心的な役割を果たします。
開示資料だけでは、DCF法の算定に必要な将来の事業計画や割引率を知ることはできません。しかし、買い手(アドベンチャー)の内部、および同社が起用したアドバイザーは、間違いなくこのDCF法を用いています。
その際、ファイブスターグループが単独で成長した場合(スタンドアロン価値)のキャッシュフロー予測に加え、アドベンチャーグループと統合することで生まれるシナジー(売上増加、コスト削減など)を上乗せした事業計画を作成し、それが「10億4,000万円」という価格を正当化できるか、厳密な検証が行われたはずです。
(3) マーケット・アプローチ(類似会社比較法)
専門用語解説:マーケット・アプローチ
評価対象企業と事業内容が類似する上場企業の株価や、類似するM&A取引事例と比較することで、相対的な価値を評価する手法です。客観性が高い反面、完全に類似する比較対象を見つけるのが難しい場合があります。
一般的に、このアプローチでは「マルチプル(倍率)」という指標を用います。代表的なものにPERやEV/EBITDA倍率があります。
専門用語解説:PER (Price Earnings Ratio:株価収益率)
「株式価値(株価)」が「当期純利益」の何倍かを示す指標です。
- PER = 株式価値 ÷ 当期純利益
- 本件での試算 (PER):
- 株式価値:1,040百万円
- 3社合算純利益(概算):131百万円
- PER(概算) = 1,040百万円 ÷ 131百万円 ≒ 7.94倍
4. バリュエーション評価(アドバイザーとしての見解)
「PER 7.94倍」という数値。これは高いのでしょうか、低いのでしょうか。
非上場の中小企業のM&Aにおいては、業種にもよりますがPER 5〜8倍程度が目安となるケースも多く、7.94倍という数値は一見すると「妥当な範囲の上限」のようにも見えます。しかし、この評価は「企業の成長性」を考慮して初めて意味を持ちます。
ここで、中核会社である(株)ファイブスターコーポレーションの近年の業績推移に注目します。
- 売上高の推移
- 2023年3月期:383百万円
- 2024年3月期:617百万円(対前年 +61.1%)
- 2025年3月期:784百万円(対前年 +27.1%)
- 2年間の年平均成長率(CAGR):約43.2%
- 当期純利益の推移
- 2023年3月期:27百万円
- 2024年3月期:78百万円(対前年 +188.9%)
- 2025年3月期:120百万円(対前年 +53.8%)
- 2年間の年平均成長率(CAGR):約110.6%
これは、驚異的な成長率です。(背景として、コロナ禍からのV字回復、インバウンド需要の急速な取り込み、同社の優れたオペレーション能力などが推察されます。)
年率100%を超える利益成長を遂げている企業に対し、直近利益のわずか8倍弱のPER(7.94倍)で買収できるのであれば、それは「高い」どころか、買い手にとっては「非常に魅力的な価格(割安)」と判断された可能性が極めて高いです。アドベンチャー社は、この急成長が今後も継続する、あるいは自社の「skyticket」の集客力やエンジニアリソースを投入することでさらに加速する(=シナジー) と確信し、10億4,000万円という価格を提示したと推察されます。
このバリュエーションは、過去や現在の静的な財務数値(純資産)ではなく、将来の爆発的な成長性(とシナジー)に対して支払われた、極めて戦略的な価格設定であると結論付けられます。
第4章:アドバイザリー費用(8,000万円)についての考察
本件では「アドバイザリー費用等(概算)」として 8,000万円 が計上されています 。これは取得価額合計(1,120百万円)の約7.1%に相当します。
この「費用等」には、一体何が含まれているのでしょうか。
専門用語解説:M&Aアドバイザリー費用
M&Aのディールを支援する専門家(FA:ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、会計士、税理士など)に支払う報酬の総称です。
1. FA(ファイナンシャル・アドバイザー)報酬:
M&A戦略の立案、相手先の探索・交渉、バリュエーション算定、プロセス全体の管理などを担う中核的なアドバイザー(投資銀行やM&Aブティックファームなど)への報酬。
2. デュー・ディリジェンス(DD)費用:
専門用語解説:デュー・ディリジェンス (Due Diligence, DD)
「Due(当然の)Diligence(努力・注意)」の意。M&Aにおいて、買い手が対象企業の価値やリスクを詳細に調査・分析する手続きのことです。この調査を怠って買収後に問題が発覚すると、経営陣は株主から「善管注意義務違反」を問われる可能性があります。
- 財務DD: 会計士が、対象企業の財務諸表が適正か、隠れた負債(簿外債務)はないか、収益力は本物か、などを精査します。
- 法務DD: 弁護士が、契約関係、許認可、訴訟リスク、労務問題などに法的な不備がないかを精査します。
- 税務DD: 税理士・会計士が、過去の税務申告の妥当性や、将来の税務リスク(繰越欠損金の利用可能性など)を精査します。
- その他、ビジネスDD、IT DD、人事DDなど、対象企業の特性に応じて様々な調査が行われます。
3. 契約書作成費用:
弁護士による株式譲渡契約書(SPA)や関連契約書の作成・レビュー費用。
費用の妥当性
M&AのFA成功報酬は、取引金額に応じて料率が変動する「レーマン方式」で計算されることが一般的です。
専門用語解説:レーマン方式(料率例)
取引金額(本件では株式価値10.4億円)に対し、以下の料率を乗じて算出します。
- 5億円以下の部分:5%
- 5億円超 10億円以下の部分:4%
- 10億円超 50億円以下の部分:3%
- (以下略)
本件(10.4億円)での試算(あくまで一例):
(5億 × 5%) + (5億 × 4%) + (0.4億 × 3%) = 2,500万 + 2,000万 + 120万 = 4,620万円
この試算(約4,600万円)は、あくまでFA報酬の一例です。本件の費用「8,000万円」 には、このFA報酬に加え、3社分の財務DD、法務DD、税務DDの費用、および契約書作成費用が「等」の部分に含まれていると考えるのが自然です。
3社同時のDDは1社の場合よりも工数がかかります。また、開示資料の財務諸表には「税務申告時の数値を基に記載」 との注記があります。これは、上場企業の連結決算に求められる厳密な会計基準(J-GAAPやIFRS)とは異なる可能性があることを意味し、財務DDにおいて「税務ベース」から「会計ベース」への組み替え(修正)という、より詳細な作業が必要となった可能性も示唆しています。これらを総合的に勘案すれば、ディール総額11.2億円のM&Aをクロージングさせるための専門家コストとして、8,000万円という金額は実務的な観点から妥当な範囲内であると考えられます。
第5章:今後の展望とPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)の課題
M&Aは、「株式譲渡実行日(クロージング)」 で終わりではありません。むしろ、そこからが本番です。買収後に、両社の経営資源や業務プロセスをいかに効果的に統合し、期待したシナジーを実現するかというプロセス — PMI(Post Merger Integration)— が、M&Aの成否を最終的に決定づけます。
アドベンチャー社は「本件による 2026年6月期の当社連結業績に与える影響は、現在精査中」 としていますが、水面下では以下のPMIが急ピッチで進められることになります。
1. 会計・管理体制の統合
- 決算期の統一: アドベンチャー社(6月期決算)と、ファイブスターグループ3社(1月、3月、6月期) のバラバラな決算期は、速やかに親会社(アドベンチャー)の6月期に統一される必要があります。
- 会計基準の統一: 前述の通り、「税務ベース」で作成されていた財務諸表を、アドベンチャー社の連結財務諸表に取り込むため、上場企業水準の会計基準に準拠させる必要があります。
- 内部統制(J-SOX)の構築: 上場企業の子会社として、適切な内部統制システムの構築・運用が求められます。
2. システム・業務プロセスの統合
本件シナジーの核となる部分です。「skyticket」のオンライン予約システム(アドベンチャー側)と、ファイブスターグループが持つホテル運営の現場(在庫管理、清掃管理、集客コンサル)のシステムや業務フローを、いかにシームレスに連携させるか。アドベンチャー社の「エンジニアリソース」 の活用が鍵となります。
3. 組織・人事・企業文化の統合
最も難易度が高いのが「人」の統合です。IT企業であるアドベンチャーと、ホテル運営というリアルなオペレーションを担うファイブスターグループとでは、企業文化や仕事の進め方が大きく異なる可能性があります。
また、売り手であり、3社の代表取締役(または大株主)であった鈴木義浩氏 が、買収後どのような立場で経営に関与し続けるのか(キーマン・ロック)も、PMIの重要な論点となります。
結論:成長性への投資とPMIの挑戦
本件、アドベンチャー社によるファイブスターグループのM&Aは、単なる規模拡大ではなく、OTAがホテル運営という川上領域のノウハウと資産を獲得し、バリューチェーン全体での競争力強化を図る「垂直統合」型の戦略的買収です。
そのバリュエーション(株式価値10億4,000万円)は、対象会社(特に中核)の年率100%超という驚異的な利益成長性と、アドベンチャーグループとの強固なシナジーへの期待を反映した、合理的かつ未来志向の価格設定であると我々は分析します。簿価純資産(2.4億円)の約4.3倍、直近利益(1.3億円)の約8倍という価格は、この「将来価値」への対価に他なりません。
アドベンチャー社は、合計11億2,000万円の投資(うち約8億円は「のれん」という将来への期待)を回収するため、今後、困難ではありますが極めて重要なPMI(経営統合プロセス)に挑むことになります。
「skyticket」という空のチケットから始まったアドベンチャーが、沖縄の地でリアルのホテル運営という新たな翼を手に入れ、インバウンド需要の風を掴み、グローバルという大空へどう羽ばたいていくのか。引き続き注視してまいります。






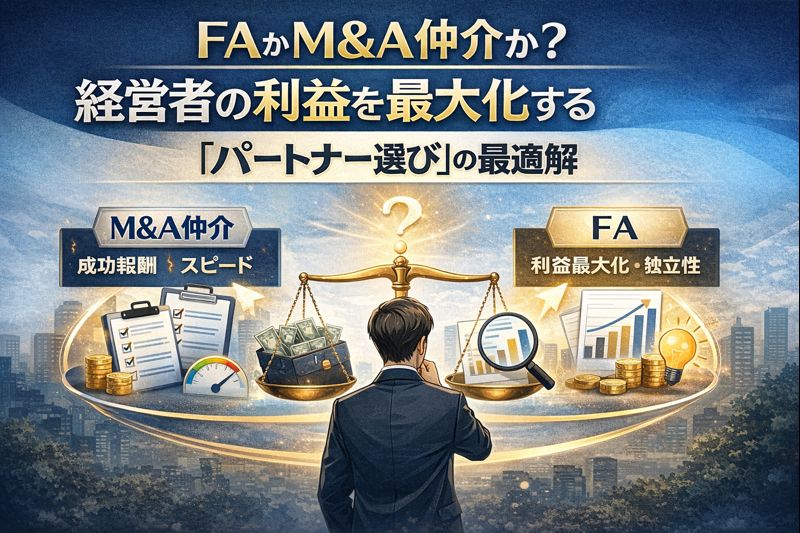
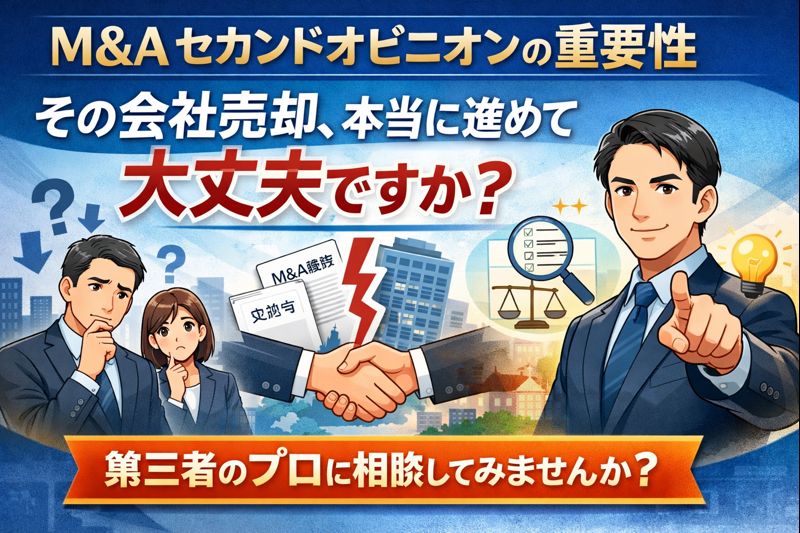

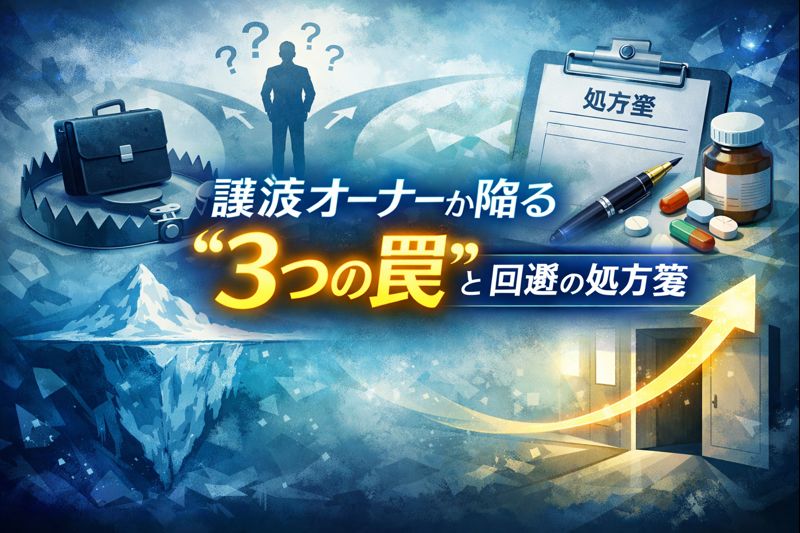

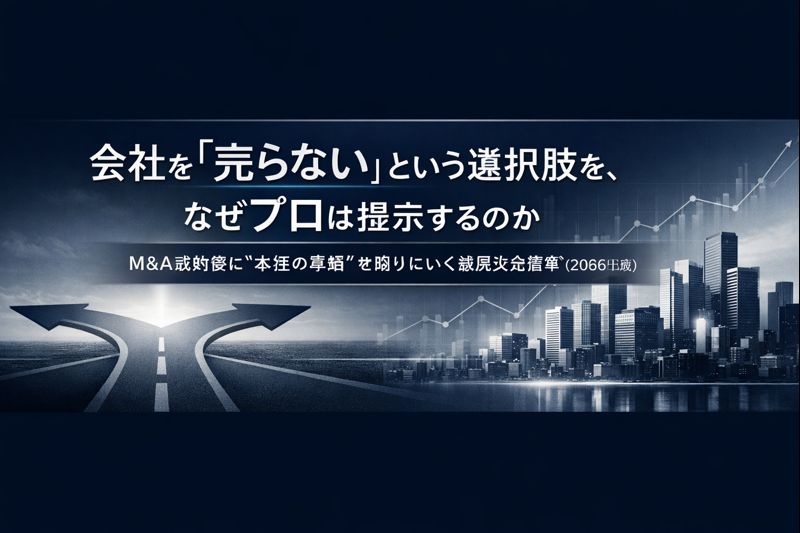


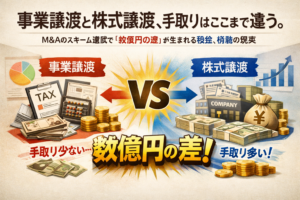

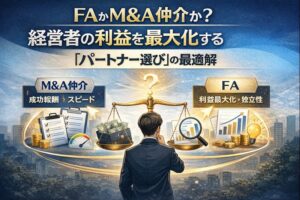


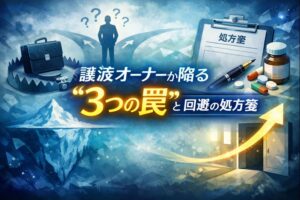
コメント