「価格(Price)とはあなたが支払うものであり、価値(Value)とはあなたが得るものである」。 これは投資の神様ウォーレン・バフェットの言葉です。
「なぜ、私が手塩にかけて育てたこの会社はEBITDAの5倍でしか評価されないのに、上場した瞬間にPER20倍、あるいはそれ以上の値段がつくのでしょうか?」
この問いは、単なる計算式の違いではありません。そこには「非上場」と「上場」という二つの異なる世界を隔てる、リスク、流動性、そして情報の非対称性という深い河が流れているのです。
本稿では、プロフェッショナルファンドが駆使する「マルチプル・アービトラージ(倍率の裁定取引)」の正体と、なぜそのような価格差が合理的に正当化されるのかについて、法務・税務・会計の視点を交えながら詳解します。
第1章:二つの物差し 〜「回収期間」と「永続価値」〜
まず、非上場企業(中小企業含む)と上場企業の評価手法が根本的に異なる背景を理解する必要があります。
1. 非上場企業の評価:EBITDA倍率法の正体
実務上、多くの中小企業や非上場企業のM&Aでは、EV/EBITDA倍率(イーブイ・イービッター倍率)**が共通言語として使われます。
【用語解説】EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 日本語では「利払い・税引き・償却前利益」と訳されます。ざっくり言えば「会社が本業で稼ぎ出すキャッシュフローの力」です。
- 計算式: 営業利益 + 減価償却費
- なぜ使うのか? 国によって税率や金利が違うため、それらを差し引く前の「生の稼ぐ力」で比較するため。また、設備投資額(減価償却)の影響を排除してキャッシュの創出力を測るためです。
非上場企業の世界で「EBITDAの3倍〜5倍」が相場と言われるのには、極めて泥臭い、しかし合理的な理由があります。それは「投資回収期間(Payback Period)」の発想です。
中小企業のオーナーや買い手(個人や事業会社)は、「この会社を買ったら、何年で元が取れるか?」を直感的に重視します。
- EBITDA × 3倍 ≒ 3年で投資額に相当するキャッシュが生まれる
- EBITDA × 5倍 ≒ 5年で投資額に相当するキャッシュが生まれる
非上場企業は、オーナーへの依存度が高く、事業基盤が盤石でないケースも多いため、5年先、10年先の未来を精緻に予測することは困難です。したがって、買い手は「5年程度で回収できる価格」を上限として設定する力学が働きます。これが「5倍の壁」の一つの正体です。
2. 上場企業の評価:PER(株価収益率)の論理
一方、上場株の世界ではPER(Price Earnings Ratio)が主役となります。
【用語解説】PER(株価収益率) 株価が1株当たり純利益(Net Income)の何倍かを示す指標。
- 計算式: 株価 ÷ 1株当たり当期純利益
- 意味: 投資家がその企業の「将来の成長」に対してどれだけのプレミアム(上乗せ)を支払う気があるか。
上場企業の場合、投資家は「5年で元を取りたい」とは考えません。「ゴーイング・コンサーン(継続企業の前提)」に基づき、その企業が半永久的に成長し続けることを前提に、将来のキャッシュフローを現在の価値に割り引いて評価します。上場市場には世界中の投資マネーが集まるため、リスクが分散され、許容されるリターン(資本コスト)が低くなります。その結果、高い倍率(PER 15倍〜20倍以上)が許容されるのです。
第2章:ファンドの錬金術 〜EBITDA 5倍からPER 20倍への架け橋〜
さて、ここからが本題です。 プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)は、非上場企業をEBITDA倍率(例えば5倍)で買収し、数年後に上場(IPO)させてPER倍率(例えば20倍)で売却することを目指します。一見すると「安く買い叩いて高く売りつける」だけの濡れ手粟に見えるかもしれませんが、投資家の視点では、ここには「リスクの縮小」と「異次元への変換」という明確なロジックが存在します。
このメカニズムを、数値を交えて解剖しましょう。
1. 比較の罠:「5倍」と「20倍」は比較対象が違う
まず、多くの人が誤解している算術的なトリックを解き明かします。
- EBITDA倍率は、「企業価値(Enterprise Value = EV)」に対する倍率です。
- PERは、「株式価値(Equity Value)」に対する倍率です。
【プロの視点】企業価値(EV)と株式価値(EqV)の違い
- 企業価値(EV): 事業そのものの価値。借金を返す前の価値。
- 株式価値(EqV): 企業価値から銀行への借金(有利子負債)を返し、現金を足した後の、株主の手取り分。
式: 株式価値 = 企業価値(EV) - 純有利子負債(Net Debt)
この違いがなぜ重要か。シミュレーションしてみましょう。
【モデルケース】
- EBITDA:10億円
- 減価償却費:2億円
- 営業利益:8億円
- 支払利息・税金等を引いた最終利益(Net Income):5億円(EBITDAの約50%と仮定)
- 純有利子負債:なし(借金ゼロ)
A. 非上場時の評価(EBITDA × 5倍)
- 企業価値(EV) = 10億円 × 5倍 = 50億円
- 借金ゼロなので、株式価値も50億円
- この時、最終利益(5億円)に対するPERを逆算すると?
- 50億円 ÷ 5億円 = PER 10倍
B. 上場時の評価(PER × 20倍)
- 上場市場で、同業他社がPER20倍で取引されているとします。
- 株式価値 = 最終利益 5億円 × 20倍 = 100億円
【結果】 EBITDA 5倍(50億円)で買ったものが、上場市場ではPER 20倍(100億円)になる。 ここで注目すべきは、「5倍→20倍(4倍)」になったのではなく、実質的には「PER 10倍→PER 20倍(2倍)」への評価替え(マルチプル・エクスパンション)が起きたということです。
それでも「価値が2倍になる」というのは劇的です。なぜ市場は、上場した瞬間にその会社の価値を2倍と認めるのでしょうか?
第3章:バリュエーション・ギャップの正体 〜なぜ市場は「上場」を高く評価するのか?〜
投資家が、非上場企業には低い倍率しか適用せず、上場企業には高い倍率を適用するのには、法務・会計・市場流動性の観点から、以下の3つの合理的な理由があります。これこそが「価値の源泉」です。
1. 流動性ディスカウント(Illiquidity Discount)の解消
これが最大の要因です。
- 非上場株: 売りたくてもすぐに売れません。買い手を見つけるのに半年以上かかり、DD(デューデリジェンス)を受け、契約交渉をするコストがかかります。現金化できないリスクに対し、投資家は20%〜30%程度のディスカウント(割引)を要求します。
- 上場株: スマートフォン一つで、秒単位で現金化できます。「いつでも逃げられる」という安心感(流動性)には、巨大なプレミアムがつきます。
ファンドが上場させるということは、「換金できない資産」を「現金同等物」に変える機能を提供したことになり、その対価としてバリュエーションが跳ね上がるのです。
2. ガバナンスと情報の信頼性(Information Asymmetry)
- 非上場企業: 多くのオーナー企業では、「公私混同」が見られます。社長の車、交際費、家族への給与などが経費に含まれている場合があります。また、会計監査を受けていないため、財務諸表の数字が本当に正しいか、外部からは不透明です(情報の非対称性)。この「怪しさ」が割引要因となります。
- 上場企業: 監査法人の厳格な監査を受け、内部統制(J-SOX)が整備されています。ガラス張りの経営であり、数字の信頼性が担保されています。
ファンドは買収後、CFOを送り込み、監査法人を入れ、管理会計を導入し、「誰が見ても透明な会社」に磨き上げます。この「安心感」が、PERの向上(マルチプルの拡大)に直結します。
3. 少数株主の保護と支配権プレミアム
- 非上場企業(少数持分): 非上場会社の株を10%だけ持っていても、配当が出る保証もなく、経営に口も出せず、売ることもできないため、価値は極めて低く見積もられます。
- 上場企業: 少数株主であっても法的に強く保護されており(会社法、金商法)、市場で適正価格で売却可能です。
ファンドは通常100%(あるいは過半数)を取得し、経営を完全にコントロールできる「支配権(Control Premium)」を持っています。上場によって、支配権を持たない一般投資家にも「安心して保有できる権利」として切り売りするため、流動性と相まって高い総額評価が得られます。
第4章:投資家(買い手)の視点 〜合理的な判断基準〜
では、あなたが投資家だとして、この「歪み」をどう捉えるべきでしょうか。
プロ投資家の思考回路
プロの投資家(機関投資家やファンド)は、EBITDA倍率やPERを単なる「割安・割高のシグナル」としては見ていません。彼らが見ているのは「リスク調整後リターン」です。
- 非上場への投資: 「流動性がなく、情報も不透明で、経営者がワンマンかもしれない」というハイリスクな案件。だからこそ、年率20%〜30%のリターン(IRR)が見込めない限り投資しません。逆算すると、入り口の価格はEBITDA 3〜5倍に抑える必要があります。
- 上場株への投資: 「いつでも売れて、情報は正確で、コンプライアンスも守られている」というミドルリスクな案件。年率5%〜8%程度のリターンが得られれば十分合理的です。そのため、PER 20倍(益利回り5%)でも喜んで購入します。
結論: ファンドが5倍で買い、20倍で売る行為は、単なる転売ではありません。 「ハイリスク・ハイリターン」の商品を、経営改善とガバナンス強化によって「ローリスク・ミドルリターン」の商品に作り変え、リスク許容度の低い一般投資家(市場)に適合させたという、付加価値の創出なのです。
第5章:実務家としてのアドバイス 〜バリュエーションを高めるために〜
最後に、上場・非上場を問わず、企業価値を高めたい経営者、あるいは賢明な投資家への実務的な示唆をお伝えします。
1. 「EBITDA」の質を上げる
単に利益が出ているだけでは不十分です。「社長の属人性がないか」「特定の取引先に依存していないか」「一過性の利益ではないか」。利益の**「質(Quality of Earnings)」が高まれば、非上場であっても7倍、8倍、あるいは10倍以上の評価がつくことは珍しくありません(特にSaaSやヘルスケア業界など)。
2. 会計と法務の「磨き上げ」は早めに
将来的なExit(売却や上場)を考えるなら、早急に「資産の分別(個人と会社)」、「労務リスク(未払い残業代)の解消」、「契約書の整備」を行うべきです。これらはDD(デューデリジェンス)における減額要因(Debt-like items)となり、最終的な手取り額を大きく毀損します。
3. 資本コストの意識を持つ
自社の株価がPER何倍か、というのは「市場があなたに期待する成長率」と「市場があなたに感じるリスク」の通信簿です。 PERが低いということは、「成長しないと思われている」か「リスクが高いと思われている」かのどちらかです。IR(投資家向け広報)を通じて、この認識ギャップを埋める作業こそが、CFOや経営者の最重要課題です。
結び:価格の向こう側にあるもの
M&Aや株式投資の世界において、絶対的な「正解の価格」は存在しません。あるのは、買い手と売り手の双方が納得する「合意点」だけです。しかし、その合意点を形成するロジック——流動性、ガバナンス、情報の透明性——を理解していれば、あなたは市場の波に翻弄されることなく、本質的な価値を見極めることができるようになります。
ファンドが享受する「EBITDA 5倍からPER 20倍」への利ざやは、不透明な原石を、誰もが安心して取引できる宝石へと研磨する「加工賃」とも言えるでしょう。
投資家としての皆様には、単なる倍率の数字に惑わされず、その背後にある「リスクの所在」と「キャッシュフローの確からしさ」を見抜く眼を持っていただければ、これに勝る喜びはありません。
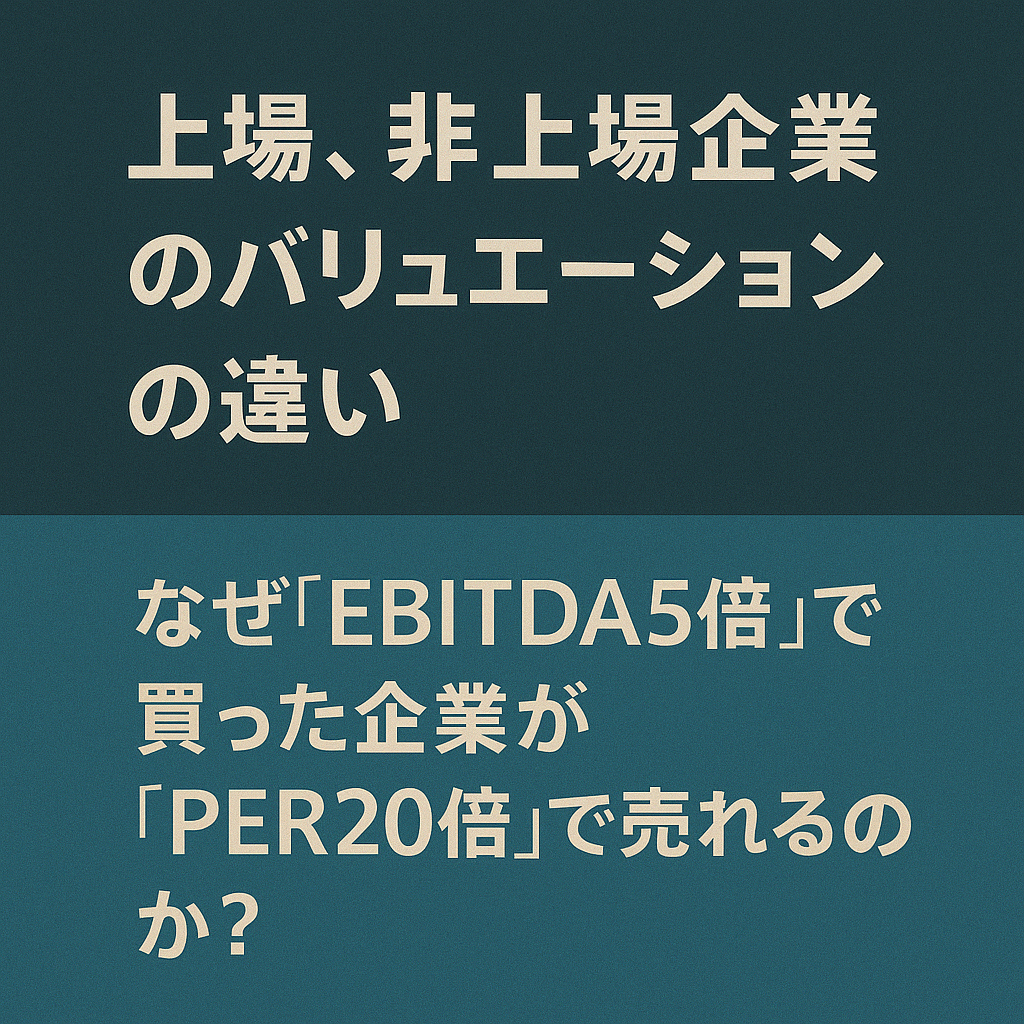




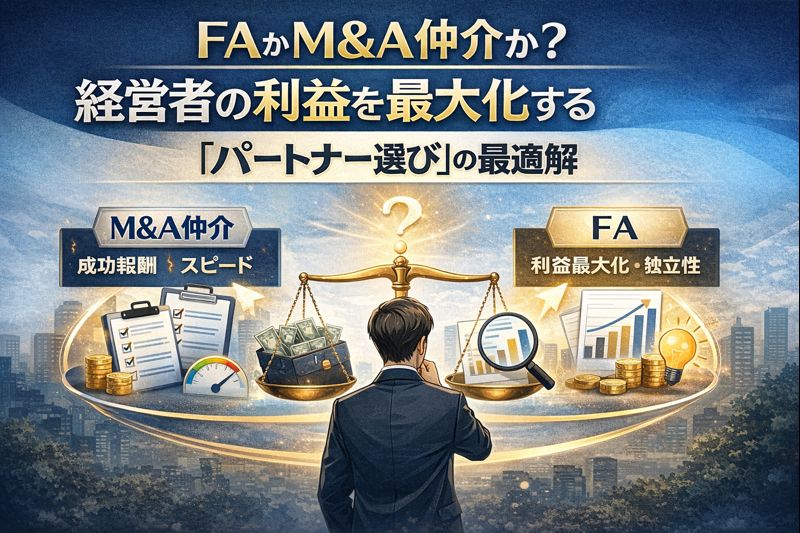
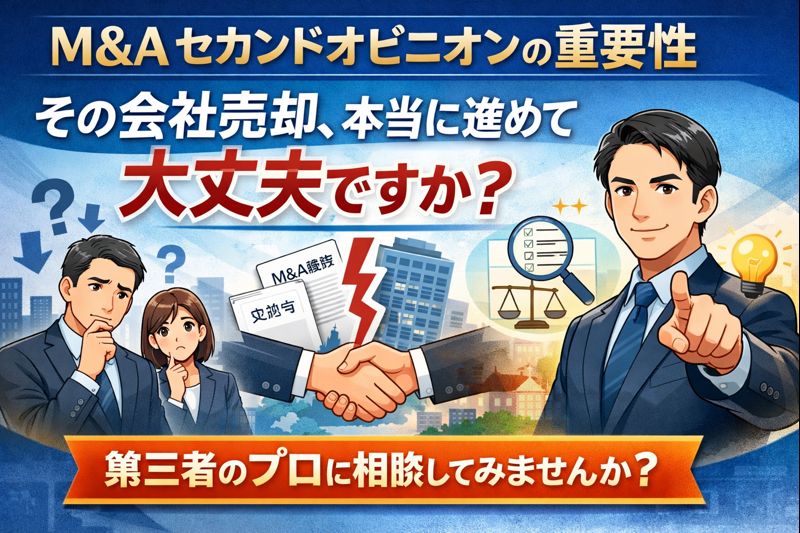

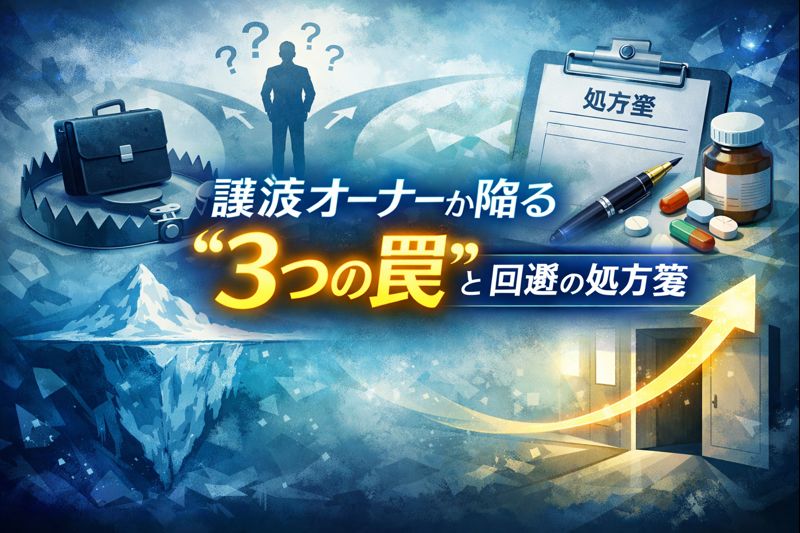

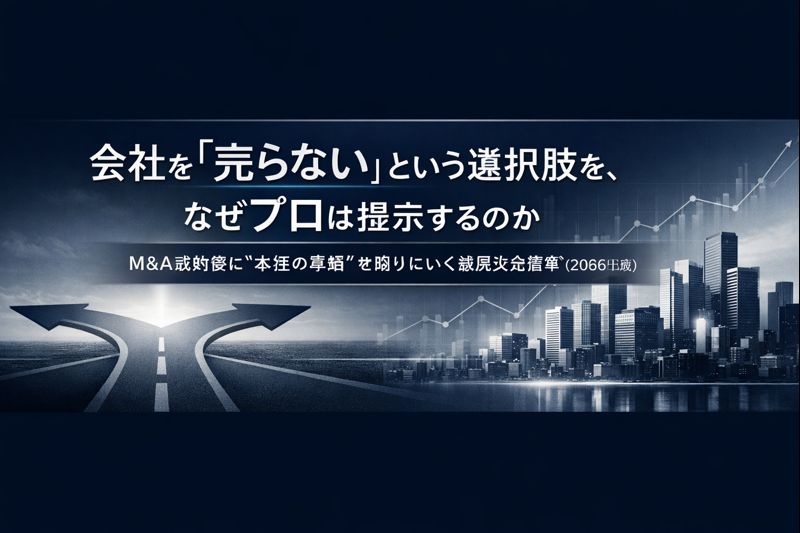


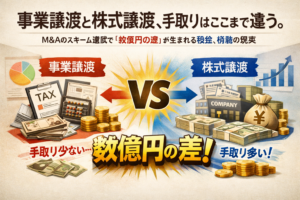

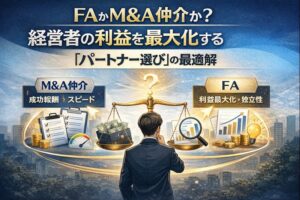


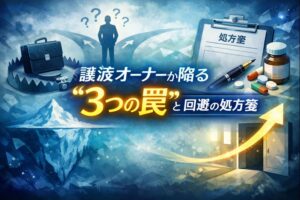

コメント