2025年11月6日、みずほリース株式会社(以下、みずほリース)は、その完全子会社が組成するMMパワー合同会社(以下、公開買付者)を通じて、東京証券取引所インフラファンド市場に上場するジャパン・インフラファンド投資法人(以下、JIF)の投資口に対する公開買付け(TOB)を開始すると発表しました 。本取引は、JIFを非公開化(完全子法人化)することを目的としています 。ディールは単なる一件のTOBに留まりません。これは、日本のインフラファンド市場が直面する構造的な課題、特に再生可能エネルギー分野における事業環境の劇的な変化に対し、スポンサー企業がいかにしてM&Aと高度な法務・財務スキームを駆使して能動的に価値創造を追求するか、その最適解の一つを示す象徴的な事例と言えます。
本稿では、みずほリースによるJIF非公開化の背景にある市場環境の分析から、その核心であるM&Aスキーム、バリュエーション(価格算定)の妥当性、そして公正性を担保するために講じられた精緻なプロセスについて、専門的かつ実務的な視点から詳説します。
1. 取引の背景:上場インフラファンド市場が直面する「三重苦」
本取引の背景を理解するには、JIFをはじめとする上場インフラファンドが置かれた厳しい事業環境を認識する必要があります。特に太陽光発電アセットを主軸とするファンドは、制度変更と市場環境の変化という「三重苦」に直面しています。
① FIT制度からFIP/Post-FITへの移行
JIFが保有する資産の多くは、固定価格買取制度(FIT制度)の適用を受ける太陽光発電設備です 。この制度は長期安定収益の基盤でしたが、近年、FITの買取価格は低下傾向にあります 。さらに、FIT期間が満了(Post-FIT)した後や、新たに主流となりつつあるFIP制度(市場価格にプレミアムを上乗せする制度)への移行後は、収益の予測可能性が低下し、市場価格の変動リスクに晒されます 。
② 資本市場の機能不全(NAV割れ)
インフラファンドやREIT(不動産投資信託)は、公募増資によって新たな資産を取得し、ポートフォリオを拡大する「外部成長」が重要な成長戦略の一つです。しかし、資料によれば、JIFの投資口価格は、その保有資産の時価(鑑定評価額)に基づく1口当たり純資産価値(NAV)を下回る水準で低迷していました 。「NAV割れ」の状態では、公募増資を行うと既存投資主の価値を希薄化(希釈化)させてしまうため、新たな資産取得(外部成長)が事実上困難な状況に陥っていました 。
③ 導管性要件の時限性
インフラファンドが投資家への分配金を損金算入できる(事実上、法人税が免除される)ための税務上の要件を「導管性要件」と呼びます。現行税制では、再生可能エネルギー発電設備を主たる資産とするインフラファンドがこの特例を享受できる期間は、最初の資産取得から20年間に限定されています 。この期限を過ぎると、投資法人レベルで法人税が課税され、投資主への分配金が大幅に減少する可能性が指摘されています 9。
これら「三重苦」を背景に、JIFは上場を維持したままでは機動的な資産入替や、リパワリング(設備の高性能化)、蓄電池の併設といった積極的な設備投資(内部成長)の意思決定が難しく、将来的な成長戦略を描きにくい状況にあったと推察されます 。
2. M&Aスキームの徹底解説:三段階で進める「資産の解放」
みずほリースが選択したスキームは、これら上場の制約からJIFの資産を「解放」し、非公開の枠組み下で柔軟かつ大胆な価値向上策を実行するための、極めて精緻な三段階のプロセスで構成されています。
第一段階:TOBと「アセットマネージャー(AM会社)」の同時再編
まず、みずほリースは100%子会社(エムエル・パワー)経由で設立したMMパワー合同会社を公開買付者として、JIF投資口のTOBを実施します 。ここで注目すべきは、TOBと並行して、JIFの資産運用会社であるジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社(JIA)の資本構成を再編する点です 。
- TOB前: JIAは丸紅が90.0%、みずほ銀行とみずほ信託銀行が各5.0%を保有する、丸紅主導のAM会社でした 。
- TOB実施後: みずほリースは、丸紅から39.0%、みずほ銀行・信託から全株式(計10.0%)を取得します 。
- 結果: JIAは「丸紅 51.0%、みずほリース 49.0%」の共同運営体制に移行します 。
これは、単にJIF(投資法人=資産の器)を取得するだけでなく、その資産運用を担うJIA(AM会社=運用の頭脳)の経営権を丸紅と共有する体制を構築することを意味します。非公開化後のアセットの価値向上(バリューアップ)を、両社の知見を融合して実行する(みずほリースは顧客基盤やPPA、丸紅はインフラ運営ノウハウ)という強い意志の表れです 。
第二段階:スクイーズアウト(完全子法人化)
TOBは、買付予定数の下限を「66.67%(発行済投資口の3分の2)」に設定しています 。これは、TOBで全投資口を取得できなかった場合に、残存する少数投資主から投資口を取得し完全子法人化する「スクイーズアウト」手続を見据えたものです。
- 専門用語解説:投信法における投資口併合
- 本件で用いられるのは、投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)第81条の2に基づく「投資口併合」スキームです 。
- 株式会社のM&Aで用いられる株式併合(会社法)と同様に、複数の投資口をより少数の投資口に併合します。
- この決議には、投資主総会において、出席した投資主の議決権の「3分の2以上」の賛成(特別決議)が必要です。
- みずほリースがTOBで66.67%(≒3分の2)以上を取得すれば、この特別決議を単独で可決できます。これが、下限値を66.67%に設定した法的な理由です。
- 実務上の論点:株式買取請求権の不存在
- 会社法の株式併合では、反対株主に「株式買取請求権」が認められていますが、投信法にはこれに相当する制度が存在しません 。
- その代わり、投資口併合によって1口未満の「端数」が生じた投資主には、その端数の合計数を売却して得た金銭が交付されます 。
- このため、投資主の利益保護の観点から、TOBに応募しなかった投資主に交付される金銭の額が、TOB価格(65,000円)と同額になるよう設定することが、手続の公正性を担保する上で極めて重要となります 。
第三段階:非公開化後の「資産移管」と「投資法人の清算」
最も重要なのが、非公開化後の戦略です。JIFは上場廃止により、前述の「導管性要件」を満たさなくなります。そこで、みずほリースは、税務上の非効率が生じるJIF(投資法人)を「器」として使い続けるのではなく、JIFが保有する太陽光発電設備等の資産を、みずほリースがスポンサーとなる別ファンド(おそらく私募ファンド)に移管することを計画しています 。そして、資産の移管が完了した後、資産(中身)がなくなったJIF(器)は清算される予定です 。
これは、上場インフラファンドという「器」の制約(特に導管性要件の時限性)から優良な発電資産を「解放」し、より柔軟な運営(FIP転換、リパワリング、蓄電池併設など)が可能な私募ファンドの枠組みで、資産価値の最大化を図るという、極めて合理的かつ大胆な再編戦略です。
3. バリュエーション(価格算定)の妥当性
本TOB価格は1口当たり65,000円です 。この価格の妥当性を検証します。
① プレミアムの水準
65,000円という価格は、公表前営業日(2025年11月5日)の終値53,600円に対し、21.27%のプレミアムを付与した水準です。対象者(JIF)の特別委員会も指摘している通り、これは過去の上場インフラファンドの非公開化事例におけるプレミアム水準(10.34%~13.92%)と比較して、有意に高い水準です。
② 第三者算定機関の算定結果
M&Aの実務では、複数の評価手法を用いて価格レンジを算定します。本件では、買付者側(SMBC日興証券)、対象者側(PwCアドバイザリー)双方が独立した算定機関に評価を依頼しており、その結果は価格の妥当性を強く裏付けています。
■ 1口当たり投資口価値の算定結果(両社比較)
| 算定手法 | 買付者側 (SMBC日興証券) | 対象者側 (PwCアドバイザリー) |
| 市場価格法 | 49,043円~53,933円 | 49,043円~53,933円 |
| 類似法人比較法 | 50,639円~61,892円 | 48,668円~62,870円 |
| DCF法 | 56,138円~70,786円 | 57,426円~70,193円 |
| 修正純資産法 (NAV) | 64,076円~75,701円 | 64,076円~75,701円 |
- 専門用語解説:修正純資産法(NAV法)
- これは、インフラファンドやREITの評価において最も重視される手法の一つです。貸借対照表上の純資産額に、保有する発電所等の資産の「含み損益(時価評価額と簿価の差額)」を反映させて、実態の純資産価値を算出します 。
- 分析:
- TOB価格(65,000円)は、両社が算定した修正純資産法(NAV)のレンジ(64,076円~75,701円)の範囲内にあります。
- また、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引くDCF法のレンジに対しても、概ね中央値近辺に位置しており、合理的な価格設定であると評価できます。
③ 価格交渉の経緯
本価格は、みずほリースが当初提示したものではありません。対象者(JIF)側が設置した独立した「特別委員会」が、複数回にわたる粘り強い交渉を行いました 。当初2025年6月に提示された価格(56,000円)から、最終的に65,000円まで、実に9,000円(約16%)もの価格引き上げが実現しています 。この「真摯な交渉プロセス」こそが、本価格が一般投資主の利益に配慮した公正なものであることを示す強力な証左となります 。
4. ディールの公正性を担保する「防護壁」
本件のように、実質的なスポンサー(みずほリースはJIAのスポンサーであるみずほ銀行のグループ企業であり、取引後はJIAの主要株主となる)が主導する非公開化は、構造的な利益相反(買付者=安く買いたい vs 一般投資主=高く売りたい)の問題を内包します。この問題を回避し、手続の公正性を担保するため、本ディールでは経済産業省の「公正なM&Aの在り方に関する指針」に準拠した、幾重もの「防護壁」が設けられています。
- 独立した特別委員会の設置と権限付与対象者(JIF)は、買付者から独立した監督役員2名と外部有識者1名からなる「特別委員会」を設置しました。重要なのは、この委員会が単なる「お飾り」ではなく、価格交渉を実質的に主導し、FAの選任を承認するなど、強力な権限を与えられていた点です 。
- 独立したアドバイザーの起用特別委員会は、独立したファイナンシャル・アドバイザー(PwCアドバイザリー) 及びリーガル・アドバイザー(長島・大野・常松法律事務所) を起用し、専門的な助言に基づき買付者と交渉を行いました。
- MOM(マジョリティ・オブ・マイノリティ)条件買付下限(66.67%)は、応募契約を締結している丸紅(1.34%) を除いた、利害関係のない一般投資主の「過半数」の応募がなければTOBが不成立となるよう設定されています 。これにより、一般投資主の意思が取引の成否に反映される仕組み(実質的なMOM)を確保しています。
- 対抗的買収機会の確保(マーケット・チェック)買付者は、対象者が他の買収提案者と接触することを禁止するような「取引保護条項」を設けていません 。さらに、公開買付期間を法定最短の20営業日より長い30営業日に設定することで 、投資家に十分な判断期間を与えると同時に、対抗的な買収提案者(いわゆる「ホワイトナイト」)が登場する機会も間接的に担保しています。
6. 本取引の意義と今後の展望
みずほリースによるJIFの非公開化は、岐路に立つ日本の上場インフラファンド市場にとって、重要な試金石となるディールです。本取引が示すのは、「上場による成長」が困難になったインフラファンドを、豊富な資金力と事業シナジーを持つスポンサーが「非公開化」というM&A手法を用いて取得し、上場の制約から解放された私募ファンドの枠組みで再生・価値向上を図るという、新たな戦略的選択肢です 。FIT制度という安定期が終わり、FIP制度やPPA(電力購入契約)といった、より事業運営能力(アセットマネジメント能力)が問われる変動期に突入した今、発電資産の価値を最大化するには、機動的な設備投資やリパワリングが不可欠です。
みずほリースは、JIFの資産を非公開化し、丸紅との共同運営体制(JIA)のもとで自社の顧客基盤(PPA需要家など)と結びつけることで 、まさにその価値最大化を目指しています。
本ディールは、同様の課題を抱える他の上場インフラファンドやそのスポンサー企業に対し、M&Aを通じた事業再編の可能性を強く示唆するものであり、今後のインフラ市場におけるM&Aの活性化を促す先駆的な事例となることは間違いないでしょう。
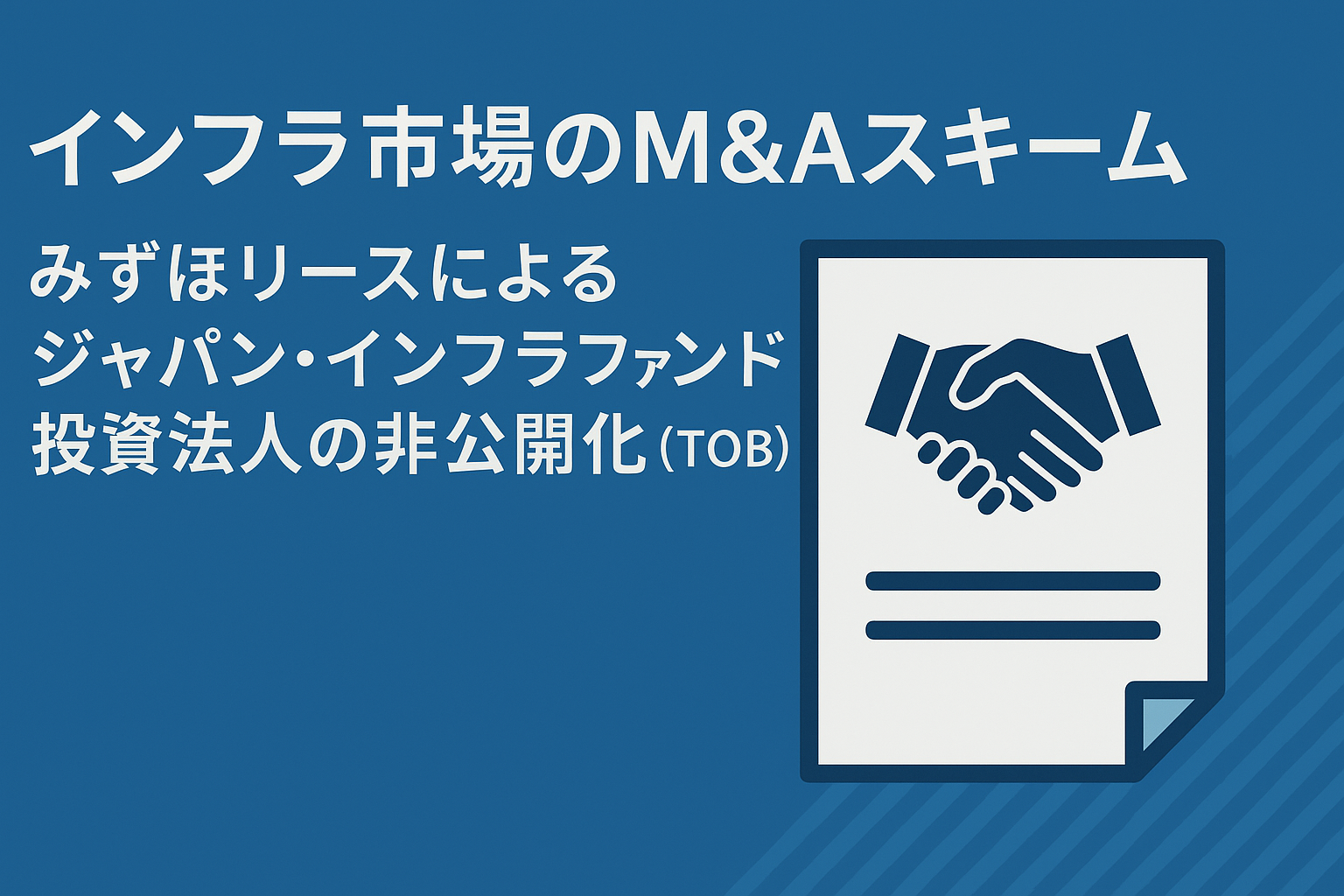



















コメント