M&A契約書(株式譲渡契約書など)において、最も交渉が熱を帯びるパートの一つが「表明保証(Representations and Warranties)」であり、それとセットで議論されるのが今回のテーマである「サンドバッキング(Sandbagging)」の問題です。一見すると法的なテクニカルターム(専門用語)に見えますが、これは「買収価格(バリュエーション)の正当性をどう守るか」というファイナンスの問題そのものです。
- 買い手(譲り受け側): デュー・デリジェンス(DD/買収監査)でリスクを見つけたが、ディールを止めるほどではない。しかし、将来損害が出たら補償してほしい。
- 売り手(譲り渡し側): DDでリスクを開示したのだから、それを知って買ったのなら後から文句を言うのは筋違いだ。
この両者の利害が鋭く対立するポイントを調整するのが、以下の2つの条項です。
- プロ・サンドバッキング条項(買い手有利)
- アンチ・サンドバッキング条項(売り手有利)
1. サンドバッキング条項(プロ・サンドバッキング)とは
~買い手の「資産価値」を守る盾~
「サンドバッキング(Sandbagging)」とは、元来ポーカー用語などで「強い手を隠し持っておき、相手を油断させて勝つ」という意味合いがあります。M&Aにおける「プロ・サンドバッキング条項(単にサンドバッキング条項とも呼びます)」とは、以下の取り決めを指します。
「買い手が、売り手の表明保証違反の事実を契約前に(DDなどで)知っていたとしても、クロージング(決済)後にその違反について損害賠償請求ができる」
実務的な解説
多くの買い手はこの条項を希望します。なぜなら、M&Aにおける表明保証は「売り手が情報の正確性を担保する」ものであり、一種の「価格形成の前提条件」だからです。例えば、ある機械メーカーを買収するとします。売り手が「工場は法令を遵守しています」と表明保証しました。しかし、買い手のDDによって「実は一部の排水設備が基準を満たしていない」ことが発覚したとします。
この場合、プロ・サンドバッキング条項があれば、買い手は以下の戦略を取れます。
- とりあえずそのまま契約・クロージングする。
- 買収完了後、売り手に対して「表明保証違反」として、排水設備の改修費用を請求する。
買い手の論理としては、「欠陥がある商品を、欠陥がないという前提の価格(あるいは条件)で買うのだから、知っていたとしてもその分の補償を求めるのは経済合理性がある」というものです。
サンドバッキング条項契約書例
乙(買い手)が、甲(売り手)の表明保証違反を知り、または知り得た場合であっても、そのことは甲の責任の有無や内容にいかなる影響も与えないものとする。
2. アンチ・サンドバッキング条項とは
~売り手の「開示インセンティブ」を守る防波堤~
対して「アンチ・サンドバッキング条項」は、売り手を保護するための規定です。
「買い手が契約前に知っていた(あるいはDDで知り得た)事実については、クロージング後に表明保証違反として責任追及できない」
実務的な解説
売り手(特に創業オーナーなど)からすれば、プロ・サンドバッキング条項は「罠」のように感じられます。「DDですべて資料を出して説明したじゃないか。それを知った上で買ったのに、後からお金を請求するなんて不誠実だ(サンドバッグにする気か)」という感情です。アンチ・サンドバッキング条項を入れることで、売り手には「積極的に情報を開示するインセンティブ」が働きます。「隠すと後で訴えられるが、DDで正直に出して買い手が認識すれば、免責される」という構造になるからです。
アンチ・サンドバッキング条項契約書例
以下の事実は、甲(売り手)の表明保証違反とはならない。
(1) 乙(買い手)が契約締結時に認識し、または認識し得た事実
(2) DDにおいて提供された情報に含まれる事実
3. 実務における深い論点:中小M&A特有の「認識」の曖昧さ
ここからは、教科書的な解説を超えて、添付資料2枚目に示されているような**「現場で本当に起きるトラブル」**について深掘りします。
「DDで開示した」の認識ギャップ
大手企業同士のM&Aであれば、VDR(バーチャルデータルーム)というクラウド上の保管庫ですべての資料がログ管理され、「いつ誰が何を見たか」が証拠として残ります。しかし、中小規模やカーブアウト(事業切り出し)案件では、資料が不十分なケースが多々あります。
- 売り手の主張: 「マネジメント・インタビュー(経営陣への聴取)の時に、口頭で『ちょっと未払い残業代があるかもしれない』とニュアンスを伝えたはずだ。だから買い手は知っていた(アンチ・サンドバッキングにより免責だ)。」
- 買い手の主張: 「『労務管理はこれから整備が必要です』とは聞いたが、具体的な未払い額があるとは聞いていない。これは明確な認識とは言えない。」
このように、「どの程度の情報提供があれば『知っていた(認識し得た)』と言えるのか」が最大の争点になります。
リスクへの処方箋:特別補償(Specific Indemnity)の活用
私たちアドバイザーがこのような膠着状態(プロ vs アンチの対立)に直面した場合、どちらか一方の条項を押し通すのではなく、「特別補償(Specific Indemnity)」という解決策を提案することがあります。これは、DDで見つかった「特定のリスク(例:未払い残業代、許認可の不備)」についてのみ、サンドバッキングの議論から切り離し、以下のように個別具体的に合意する方法です。
- 「未払い残業代のリスクについては買い手も認識しているが、もし将来請求が発生した場合は、上限〇〇万円まで売り手が負担する」
これにより、抽象的な「知っていた/知らない」の水掛け論を避け、金銭的なリスク分担を明確にすることができます。
4. 法的な潮流とグローバルスタンダード
※ここでは法的な確定判断ではなく、ビジネス慣行としての解説を行います。
日本の民法や商法の原則、および過去の判例(東京地判平成18年など)を見ると、明示的な特約がない限り、「買い手が悪意(知っていた)の場合、売り手の責任を問うのは難しい(=アンチ・サンドバッキング的な解釈)」に傾きやすい傾向があります。一方で、欧米(特に米国)のM&A契約実務では、プロ・サンドバッキング条項(買い手保護)が盛り込まれるケースが非常に多いです。「表明保証は『事実の保証』であり、買い手の知識に左右されるべきではない」という考え方が強いためです。
日本でも近年、クロスボーダー案件やファンドが関与する案件が増加しており、契約書に明示的に「プロ・サンドバッキング条項」を入れる交渉が増えています。したがって、「契約書に何も書かなければ売り手有利になりやすいが、買い手としてはプロ・サンドバッキング条項を明記することでリスクヘッジを図る」というのが、現代M&Aの定石となっています。
5. まとめ:賢明なM&A当事者であるために
- 買い手の方へ:DDで見つけたリスクがあってもディールを進めたい場合、「プロ・サンドバッキング条項」を入れるか、個別の「特別補償」を設けることで、将来の損失を防いでください。知っていたからと言って泣き寝入りする必要はありません。
- 売り手の方へ:後出しジャンケンで責任を追及されないよう、「アンチ・サンドバッキング条項」を主張しつつ、DDでは「不利な情報ほど書面で明確に」開示してください。それがあなたの身を守る最大の防御となります。
M&Aは結婚に例えられますが、契約書は離婚条件まで定めた婚前契約のようなものです。感情的な対立を避け、論理的かつ品位ある交渉を行うこと。そして、双方のリスク許容度を正しく契約書に落とし込むこと。それが、成功するM&Aの条件です。
私たちアドバイザーは、その複雑なパズルを解き、双方にとって納得感のある「握手」を実現するために存在しています。






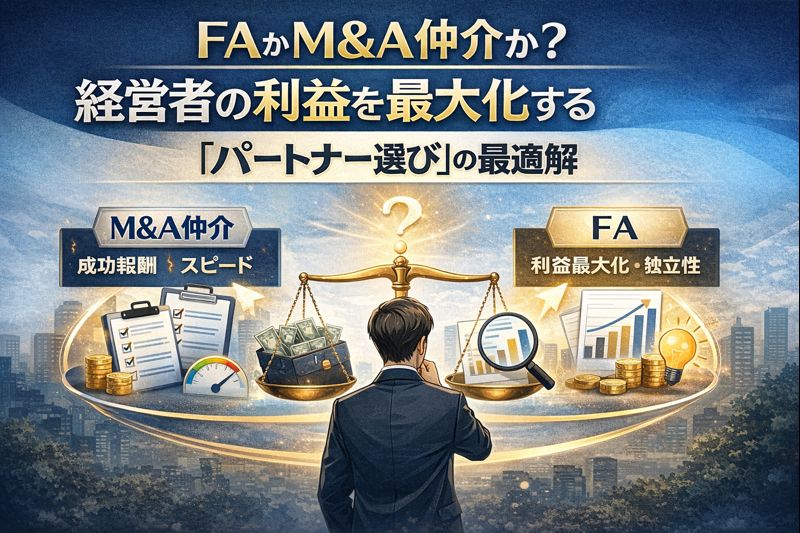
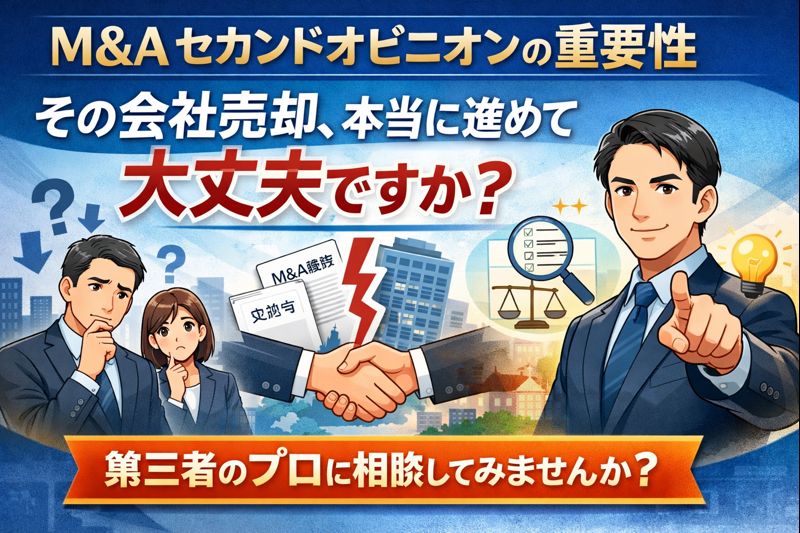

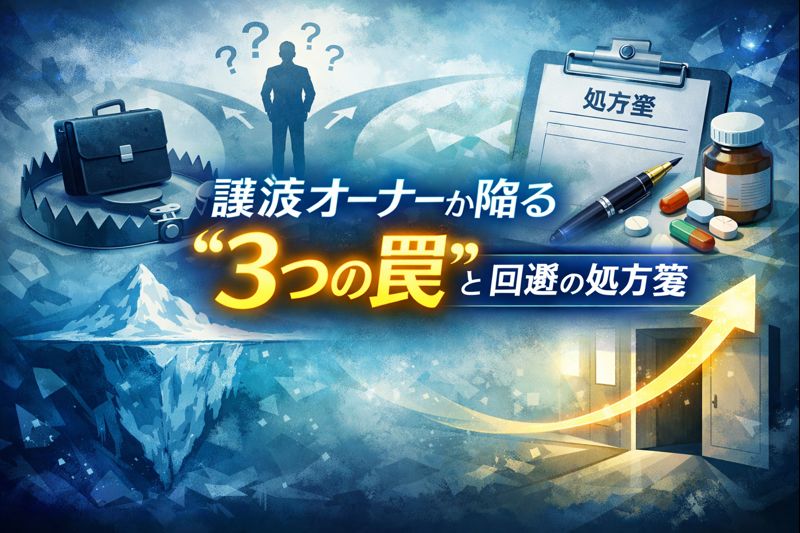

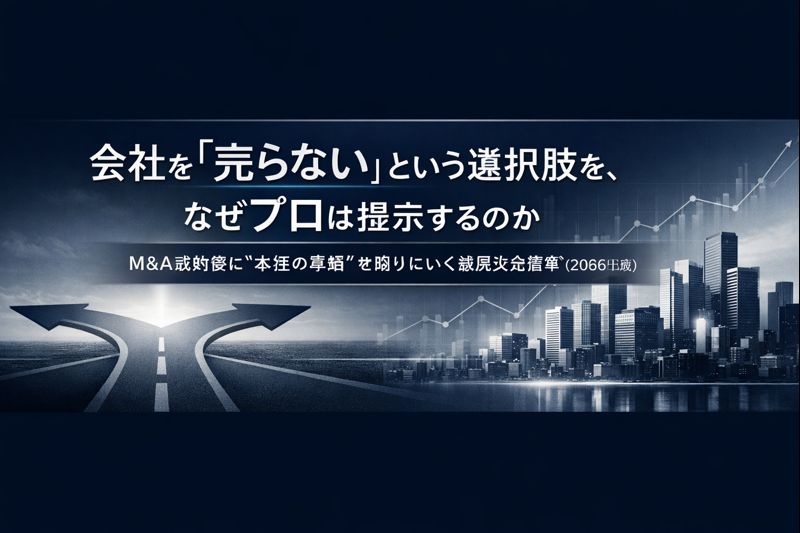


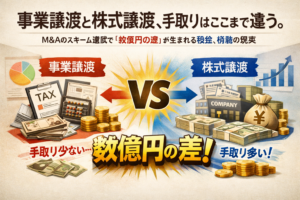

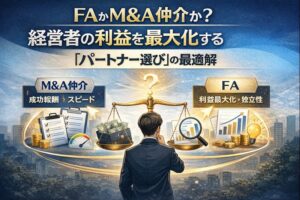


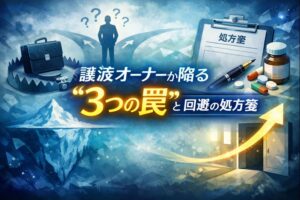
コメント